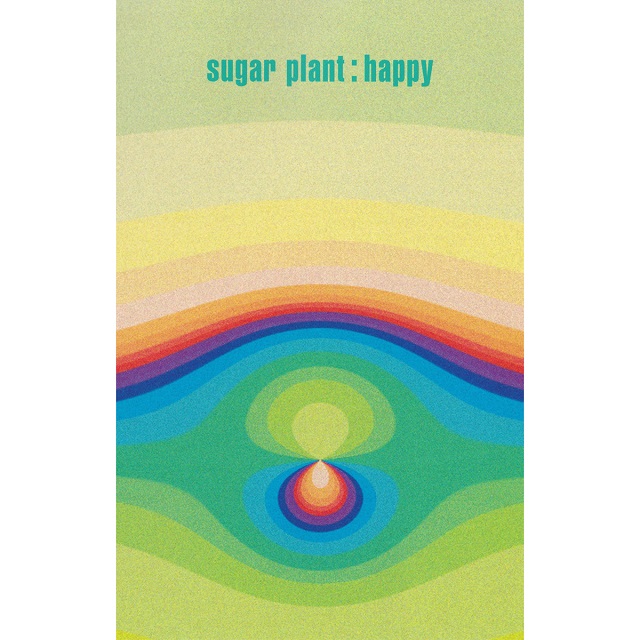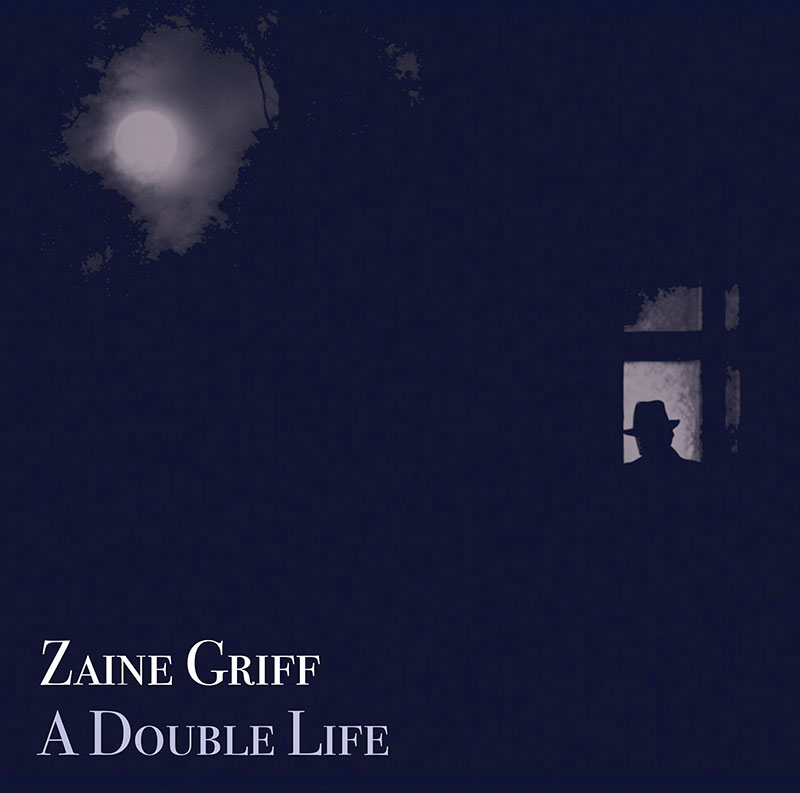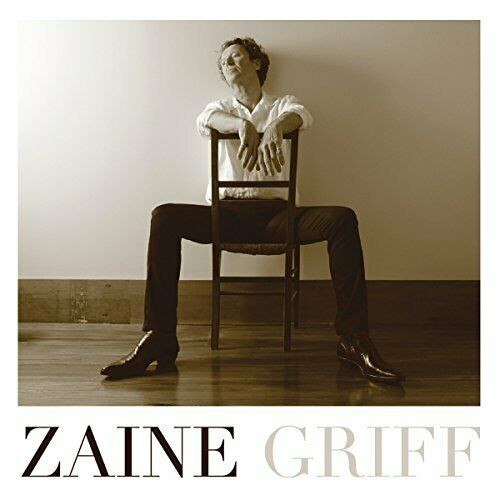ファット・ホワイト・ファミリーのことがなぜ好きかと訊かれたら答えは簡単。UKインディ・ロックの、とくにパンク以降から受け継がれている良き反骨精神があるからです。せこいことは言わずに巨悪に立ち向かいましょう。〈ドミノ〉のプレスリリースがいつになく、熱い。「活動初期から、ファット・ホワイト・ファミリーは、ロックンロールにおいて長い間軽視されてきた神話の力、人々に何か信じるものを与えること (あるいは何も与えないこと) の必要性を本能的に理解していた。無機質で無難なポップ・キャリア主義者のモノカルチャーの中で、ファット・ホワイト・ファミリーは聖なる炎を秘めている。聴く者たちを鼓舞する特別な力を持ったバンドである彼らは、その精神において激しくパンクだ」
エレキング的にも同意します。もちろんです。だから、ぼくたちの頭が吹っ飛ぶような新作を期待しています。発売は4月26日。
公開されたばかりの新曲「Bullet Of Dignity」のMV
こちらは昨年12月に公開されている「Religion For One」

Fat White Family
Forgiveness Is Yours
Domino / ビート