日本を代表するテクノDJのひとり GONNO(4/28には GONNO × MASUMURA として CONTACT でもプレイ)による新作2タイトル『Waft』『Wander Other Worlds』と、菊地晴夏を中心とする新プロジェクト HAL ca によるデビュー作『ANIMA』、計3タイトルが〈813 Records〉からリリースされる。いずれも立体音響技術「360 Reality Audio」を用いた作品とのことで、どんなサウンドに仕上がっているのか、自身の耳で確かめてみてほしい。
GONNO と HAL ca による立体音響作品が 813 Records より3タイトル同時リリース!
ヨーロッパを中心にテクノ/ハウスシーンでも活躍してきたDJ/プロデューサー Gonno 音響作品『Waft』『Wander Other Worlds』と、様々なサウンド・インスタレーションを手がけてきたコンポーザー菊地晴夏を中心とした新プロジェクト HAL ca によるデビュー作『ANIMA』が一挙リリース。
これまでpeechboyやXTALなど国内の気鋭エレクトロニック・アーティストの作品を発表してきたレーベル813が、立体音響技術360 Reality Audio に特化したスタジオ「山麓丸スタジオ」の協力を得て、 新たな音響快感を追求したアンビエント、テクノミュージック作品にアプローチする。
まずGonnoによる2作品は、後日に発表されるEP『Loom』と合わせた立体音響三部作の一環。『Waft』は、ニューエイジ~アンビエントへと接近し新たなイマーシヴ体験を追求した4曲入りEP。そして1トラック20分強の大作シングルとなる『Wander Other Worlds』は、リコーの開発するRICOH PRISMの体験プログラムとして制作された楽曲から発展。同プログラムのビジュアル演出を手掛けた画家、Akiko Nakayamaがアートワークを提供している。
同様にRICOH PRISMのプログラムとして、デジタル・アーティスト村上裕佑のディレクションで制作された同名作品のサウンドトラックでもある、HAL ca『ANIMA』にも注目してほしい。中心人物となる菊地晴夏は、パリのエコールノルマル音楽院の映画音楽作曲科を首席で卒業という才媛。配信作品としては今作がデビュー作となる。HAL caでは今後、空間音響を軸としたプロジェクトとして活動していく。

Gonno / Waft
Label: 813
2022年3月30日発売
※Amazon Music Unlimited、Deezerなど360 Reality Audio対応プラットフォームにて先行リリース。ステレオ版のリリースは4月6日予定。
[収録曲]
1. Warbly FM
2. Nikita
3. 550 Drums
4. A Long Way

Gonno / Wander Other Worlds
Label: 813
2022年3月30日発売
※Amazon Music Unlimited、Deezerなど360 Reality Audio対応プラットフォームにて先行リリース。ステレオ版のリリースは4月6日予定。
[収録曲]
1. Wander Other Worlds
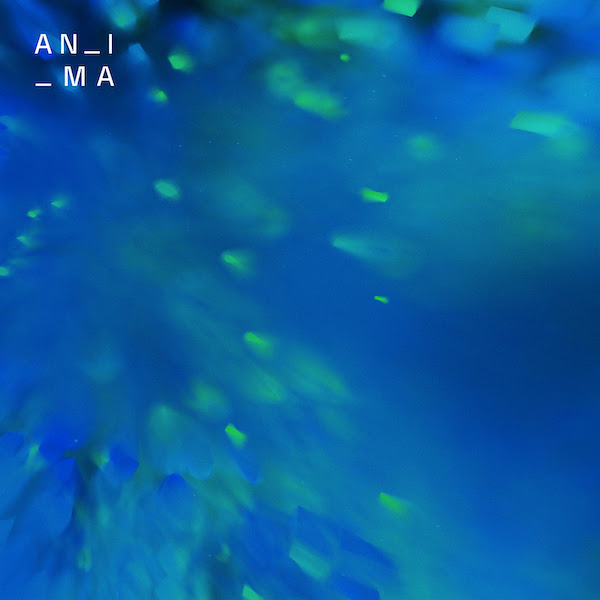
HAL ca / ANIMA
Label: 813
2022年3月30日発売
※Amazon Music Unlimited、Deezerなど360 Reality Audio対応プラットフォームにて先行リリース。ステレオ版のリリースは4月6日予定。
[収録曲]
1. MononooN
2. roTaTe
3. MeMory
4. NoVa

















