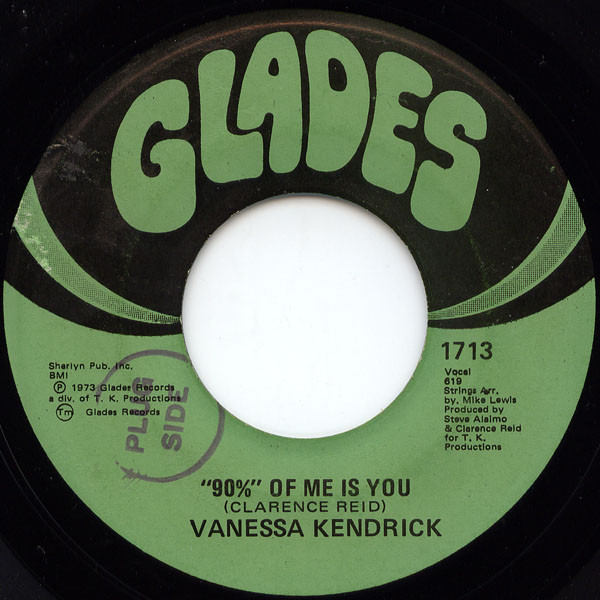生まれて初めてNHKの朝ドラを観ている。笠置シズ子にも興味はあったけれど、塚本晋也の新作で主人公を演じる趣里が朝ドラでも主役を張っていると知り、その振り幅にまずは興味が湧いた(ついでに『東京貧困女子』も最初だけ観た)。内覧会で一足先に『ほかげ』を観ていたので、朝ドラで歌劇団のルーキーを演じる趣里がとても幼く感じられ、『ほかげ』では生活に疲れて先の見えない人物像がしっかりと造形されていたのだなと改めて趣里の演技力に感心した。『ほかげ』は戦後の闇市を舞台にした作品で、居場所のなくなった人々が暗中模索を続ける群像劇。前半と後半で異なる主題を扱い、戦争によって滅茶苦茶になった日本の心象を様々な視点から洗い出す。誰もが無表情のままで、喜怒哀楽のどこにも触れないのは塚本作品の本質が剥き出しになっている気がする。

©2023 SHINYA TSUKAMOTO/KAIJYU THEATER
『鉄男』シリーズや『六月の蛇』といったカルト作品のイメージが強かった塚本晋也が8年前に『野火』でいきなり政治的な話題に首を突っ込んだ時はけっこう驚かされた。とはいえ、政治的なテーマばかり撮り続ける「専門家」よりもアレックス・コックスやアダム・マッケイのようにアホなことばかりやっていた人が自分たちの領域を政治に侵された途端、一気に作風が変わり、自分たちがやっていたことを守るために政治的になるという姿勢が僕はとても好きなので『野火』には喝采を叫んだし、同じ衝動に突き動かされている『ほかげ』にも同じように拍手を送りたい。そして、ブレインフィーダー別冊で取材した際に「塚本晋也に会いたい!」と吠えていたフライング・ロータスのCDをごっそり携えた野田努と共に塚本晋也が待つユーロ・スペースに向かうのであった。渋谷の街はそろそろハロウィンの気運が高まっていた頃である。
戦争が終わったら「終わったー」といってみんな伸び伸びするというイメージがあったんですけど、『野火』をつくってから、戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね。
■(フライング・ロータスについて少し説明してから)40年前に1週間ほど熊野の山のなかで水木しげるさんとご一緒する機会があったんですね。
塚本:おう、おう。
■『ゲゲゲの鬼太郎』を描いた人だということぐらいしか僕は知らなかったので、水木さんに片腕がないことも知らなくて。驚いてしまって。その1週間で、戦争の話をたくさん聞かせてくれたんですね。で、東京に戻って水木さんの戦記物を全部読んだんです。変わった話もいろいろあったんですけど、それまで考えてもみなかったのが復員兵の話で。戦争に行った兵士が日本に帰ってきて居場所がないなんてことがあるとは想像もしなかったんですね。で、日本の映画をいろいろ思い出して見たんですけど、復員兵の話なんてあったかなあと思って。スケキヨぐらいしか思い当たらなかったんです。(*スケキヨ=『犬神家の一族』の登場人物)
塚本:(笑)ツボにはまりますね。世代が似てる。
■『ほかげ』には大雑把に言って3パターンの復員兵が出てきますけど、どうしてあの3パターンにしようと思ったんですか?
塚本:子どもの主観でそれぞれの復員兵には出喰わしてるから、ひとりひとりの背景はわからないんですね。その3つが合わさると何があったかということが浮き彫りになって、どうしてみんなこんなことになってるんだろうと、みんなに共通の歴史があったんだということがわかるようになっています。確かに、その3つを関係づけないで観ちゃうと「なんで?」となっちゃいますよね。でも、どうしても結びつけるとは思うんですよ。最初の復員兵が夜中にわめき散らして、どうしてあんなことになってるのか、最初はわからないと思うんだけど、彼に何があったかは最後でわかると思うんです。最初にあの3パターンを考えたわけではなくて、頭から脚本を書いていって、自分で納得がいくように進めていった結果なんです。シンプルな構造が最初にできたので、自然にああなったんですね。
■座敷牢に閉じ込められていた復員兵はどの段階で?
塚本:わりと最初からいましたね。
■短いですけど、強烈な印象が残りました。
塚本:そうですね。俳優さんが素晴らしく演じてくれて。セリフがないわけですから、演技にかかってるところがありますよね。とても存在感を感じさせてくれました。
■彼らはみな『野火』の戦場から生きて戻ってきた人たちと考えていいんですよね?
塚本:そうですね、僕はそのつもりです。
■戦争の後始末というか、戦争が起きた後のことをどうするんだという意識ですよね?
塚本:それはありました。戦争が終わったら「終わったー」といってみんな伸び伸びするというイメージがあったんですけど、『野火』をつくってから、戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね。
■高齢の方にたくさん取材をされたと聞いたんですが。
塚本:それは『野火』の時ですね。皆さん、80歳を越えられてたんで。資料も少ないし、実際の声を聞いとかなきゃと思って。今回は資料がかなりあったので、そこまではしませんでした。
■そうなんですね。
塚本:戦争孤児の資料はかなりあったんですよ。でも、復員兵の話はほぼないんです。本当の「加害性」について書いてあるのは。ベトナム戦争に比べるとほんのちょっとだけしかない。
■ベトナム戦争だと『ディア・ハンター』だとか『シザーハンズ』だとか映画もわりとありますよね。ストレートなのはウイリアム・ワイラーの『我が生涯の最良の時』ですか。
塚本:ああ、それ、観てないです。
■え、意外ですね。それこそ3人の帰還兵の話でPTSDに苦しめられる話です。タイトルも皮肉です。
塚本:それは観よう(と、タイトルをメモする)。
■『我が生涯の最良の時』はリアリズムで、『ほかげ』もそれに近いし、『野火』もそうですけれど、塚本作品に期待する荒唐無稽さとは違いますよね。
塚本:前は戦争が迫ってるとか、そういった危機感を感じないでつくってたし、それどころか『マトリックス』が出た時に、ああ、先にやられちゃったと思ったぐらいで(笑)。
■あー(笑)。
塚本:どちらかというとヴァーチャル・リアリティの世の中に生きている自分がいて、暴力もファンタジーとして描いてたんです。人間のなかには暴力性があるんだし、観たいんだから、観ればいいし、それがガス抜きになって、実際に(暴力を)やる人も減るだろうという方便をつけていたんですけど、『野火』の3年ぐらい前から戦争を身近に感じるようになっちゃって。ファンタジーとして描くには暴力があまりに近づいてきたと思って、むしろ近づきたくないという思いがあったんですね。こんなに嫌なものに近づきたくないよっていう表現なんです。
■逆の印象ですけどね、『野火』は。
塚本:どっちにしろ暴力描写は出てきちゃうんですけど(笑)。以前とは使い方が違います。
[[SplitPage]]
©2023 SHINYA TSUKAMOTO/KAIJYU THEATER
いまは変態性がなくなっちゃったんです(笑)。変態の時は、人間の肌は鉄みたいな硬いものに接している時にフェティシズムが香り立ってエロが際立っていたんですけど。
■なるほど。黒沢清さんの『トウキョウソナタ』は、当時観た時、最後に天才的なピアニストが出てきて問題が全部解決しちゃうという安易な終わり方に思えちゃったんですけど、安倍政権になってから見直したら、ぜんぜん印象が変わって、日本人がそんな奇跡みたいなものにしかすがるものがなくなっているという皮肉に観えたんですよ。息子がアメリカ軍に入隊するというエピソードも安倍政権が安保法制を強行採決した後だと、もはや予言みたいだったなと。実際にいま、自衛隊は米軍の傘下にいるようなものですからね。黒沢さんは早かったのかなって。
塚本:黒澤監督はそこまでお考えになってつくったんですね。
■……と、思いましたけど。塚本監督が『野火』を撮らなくちゃと感じたのも同じ流れだったということですよね?
塚本:時期は合いますよね。急に近づいた気がして。安倍政権がもう一回、戻ってきちゃった時ですね。前の内閣の時も嗅覚的にはあったんですが、心配な感じは。きっと一回、引っ込んでいる間に設計図をしっかりつくったんでしょうね。早く憲法を変えてとか。どういう段取りでやるか決めて、復活してから着実にやってたんでしょう。『野火』をつくった時も、世の中的にはまだそれほどの危機感はなかったんですよ。だから、つくってはみたものの響かない可能性もあるかなとか、すぐ(上映も)終わっちゃうかもなとは思ってたんですよ。でも、公開してる時に、その時は戦後70年の年だったんですけど、その年にちょうどキナ臭さを感じる人が大勢出てきたので、その人たちの琴線に引っかかったと思うんです。『野火』を上映してる時に、いろんな法案が強行採決されていって。
■僕は日本は本気で戦争をやる気はないと思いますけど、それこそ中国軍200万人に対して自衛隊は18万しかいないし、いますぐに10倍にしようという気配もないし。ただ、戦争が近づいてくるというムードだけで塚本作品のようなエロ・グロ・ナンセンスは最初に取り締まられると思うんですよね(笑)。
塚本:そうですよね、気配はありますよね(笑)。そうなったらめちゃくちゃやられるんじゃないですかね。
■『野火』で作風を変えたにしても、塚本作品には武器に対するオブセッションがずっとありますよね?
塚本:そうですね、(武器に対する興味が)もっとあれば、もっと複雑で映画も面白くなると思うんですけど、これが案外、嫌いだったんです(笑)。こんなにヤなものなのに、武器が大好きで、頬ずりしたいというのだったら、映画がもっと複雑になると思うんですけど、案外嫌いなんで、どっかあっさりしちゃうんですよ。
■なるほど。
塚本:でも、僕の映画で武器をペロペロしたりすると喜ぶ人がいるんで、実感としてちょっと薄い癖に、そのテーマに惹きつけられているという感じがあって。『鉄男』は当時、僕は変態だったので……
■いまは違うんですか?(笑)
塚本:いまは変態性がなくなっちゃったんです(笑)。変態の時は、人間の肌は鉄みたいな硬いものに接している時にフェティシズムが香り立ってエロが際立っていたんですけど。
■実感を込めて『鉄男』はつくっていたわけですね(笑)。でも、『斬、』の刀も同じじゃないですか?
塚本:あの頃になると、そうですね、あれも『鉄男』なんですけどね、SFじゃないだけで。
■そうですよね。
塚本:刀という鉄と一体化するまでの話ですからね。武器はもうヤだと思っているのに、自分でも変態性を思い出すために奮い立たせたんですよ。
■そういう感じだったんですか。なるほど。そのヤだと思っているものを今回の『ほかげ』では子どもに持たせましたよね? いまの話の流れでいくとロクなことをしてませんよね(笑)。
塚本:そうですね、いま、あまりに大事なことなので、どこからいえばいいかな。たとえば宮崎駿さんとかも戦争大っ嫌いだと言ってるのに零戦の映画つくったり、けっこう皆さん、戦争は嫌いなのに武器が好きな人は多いから、難しいところなんですけど。えーと、『2001年宇宙の旅』の最初で、猿が木の棒で別な猿を叩き殺して欲しいものを勝ち取った時に人類の夜明けが始まって、その木を空に投げると宇宙船になってピューっと落っこってくるというシーンが全部を物語っているというか、あれは木でしたけれど、人って、こう、鉄と出くわした時に、恋愛がそこから始まっているので、いくらそこから鉄とか武器が憎いものになっても別れようとはならないんですね。憎くても切り離せない。人間と武器はどうしても切り離せないというのが自分のテーマにはなっています。
■世界中のあらゆる国家が捨てませんよね。どうしても武器は持ってる。
塚本:そう、みんな鉄が大好きだから、交通事故が多くても自動車を止めようとはならないし、機械と恋愛しているというのがまずはあります。『鉄男』もそうだし、『斬、』の刀をピュッと空に投げると『野火』の世界になって戦車やらなにやら爆発的な量の鉄になるんです。自分の映画では自分というものと鉄の歴史を描いていたんですけど、自分と都市やテクノロジーの関係が、『野火』をつくった頃から、年齢のせいもあると思うんですけど、ついに自分よりも次の世代のことが心配になって、心配で心配でたまらなくなって、あえて子どもに一番恐ろしい武器をもたせちゃったんだなって、いま、言われて気づいたので、それを子どもがどう扱うのかなという話を無意識につくっていたんだなと思いました。
■『トウキョウソナタ』で息子がアメリカ軍に入る話と少し重なるのかもしれませんね。『斬、』の時には核武装の話も出ていたので、一般の人にも刀を持つ気持ちになれますかというメッセージに受け取れたんですよ。
塚本:はい、そういう話ですね。
■武装する覚悟はありますかと。選挙権を持つような人には『斬、』の問いも有効だと思うんですけど、でも、もっと小さな子どもが武器を持ってしまうと、そのレベルではないですよね。いままでの武器と見せ方も違うし、『ほかげ』の子どもも隠して持っていたし。
塚本:そうですね。無意識ですね。最後に趣里さんが自分の映画にしては珍しくストレートなことを子どもに言うんですけど、すごいじわっと来るのは、やっぱりそういうことがあったからなんですね。また趣里さんがすごいはっきり言うんですよ。あれは感動しましたよ。
■確かに。
塚本:趣里さん、ありがとうって。よくぞそこまではっきり言ってくれたって。
■塚本監督が書いたセリフなんですよね。
塚本:そうなんですけどね。
[[SplitPage]]
©2023 SHINYA TSUKAMOTO/KAIJYU THEATER
前は映画をつくるのは楽しくてやってたんですけど、戦争映画はやらなきゃいけないという感じなんです。あと1本でやめますけど。そのあとは変態に戻りたい。変態が生きられる世の中にしないといけませんよ(笑)。
■現場ではアドリブなんかもあったんですか?
塚本:あんまりないですね。遊んでるシーンぐらいかな。遠足ごっこで。
■上官の家に向かっている時に男の子が鼻を啜り上げるシーンがすごくよかったんですけど、不思議な感動があって。
塚本:観てますね(笑)。あれは演出ではないです。自然な成り行きで、そのまま使わせてもらいました。
■あの子は動きだけで表現しますよね。感情がすり切れちゃってるというか。
塚本:親が死んでるところから始まってますからね。
■とはいえ、あの子が報酬を受け取らないのはさすがに大人っぽすぎると思ったんですけど。
塚本:あの年代になると、もう自意識はあるので、人を撃った行為でお金を受け取ることはできないと思いますよ。
■そうですか。
塚本:あるいは直感的にイヤだと思ったか。
■塚本監督の視点はあの子に一番近いんですか? 銃だけ持っていて、どうやって生きていくのかなとか考えちゃうんですけど。
塚本:あの子に近いのかもしれないですね。戦争孤児のエピソードにもすごい共感があったんですよ。
■戦後、実際に見かけたわけではないですよね。
塚本:そうですね。資料から浮かび上がって来るものです。自分が戦争孤児だったことは、皆さん、隠してるんですよ。戦争孤児だというといじめられたみたいで。

©2023 SHINYA TSUKAMOTO/KAIJYU THEATER
■ああ。国というのは、戦争はするけど、まったくケツを拭いてないというか、後ろにいろんなものを残したまんまなんですね。
塚本:本当にそうなんですよ。戦争後遺症になった人はいなかったということにしたみたいなんです、日本は。大和魂で片づけられちゃったみたいで。戦争で気分が悪くなるような奴は日本にはいないと。いないって言われると家族は隠さないといけないし、国は実際には後遺症の研究はしてたみたいで、資料もたくさん残ってるんですけど、戦争が終わった途端に研究もやめちゃったんですね。
■研究をしてたこと自体は最低限の良心があったように感じますけど。
塚本:いや、良心というよりヤベエっていう感じじゃないですか。みんな、こんなんなっちゃってるよーとか。でも、そういう人がいると認めたら賠償もしなくちゃいけなくなるから、なかったことにしたんでしょうね。
■そうか。
塚本:そういう人たちは、その後、高度成長期の時は仕事をしていて忘れられたんだけど、定年になってから、夜、悪夢が蘇ってきて死ぬまで続いたそうです。
■『野火』と『ほかげ』を足すと、やっぱり『ゆきゆきて神軍』を思い出しますよね。
塚本:戦争は調べれば調べるほど人間のどうしようもなさが露呈してくるんですよ。あともう一発は作らないといけないと思うんですけど、調べているとうんざりしますよ。
■やらなきゃいけないって(笑)。
塚本:前は映画をつくるのは楽しくてやってたんですけど、戦争映画はやらなきゃいけないという感じなんです。あと1本でやめますけど。そのあとは変態に戻りたい。
■(笑)。
塚本:変態が生きられる世の中にしないといけませんよ(笑)。
■どうして高校生の時に『野火』を読もうと思ったんですか?
塚本:偶然なんですよ。日本の文学に目覚めてあれこれ読んだんです。薄いわりに濃密そうだなと思って。『野火』とか『黒い雨』とか『砂の女』とかシンプルなタイトルで、濃密そうだと惹かれるんです(笑)。
■『万延元年のフットボール』とかダメなんですね。
塚本:それは未読でした。外国の本も読めなかった。登場人物の名前が長いのもダメだったんです(笑)。
■『ほかげ』はそれ以前に誰にも名前がついてないですよね。「女」とか「復員兵」とかもはや記号ですよね。
塚本:僕ね、3人以上出るとダメなんです。4人、5人になると、もう分かんなくなるんです(笑)。
■『ほかげ』は前半と後半で視点が変わるし、人数が多いというほどではないですけど、塚本作品にしては複雑ですよね。
塚本:複雑ではないけど、パタッと様変わりするのは珍しいですね。
■最近は都市よりも自然を撮りたいということでしたし、後半はほとんど自然の風景でしたね。
塚本:前半のシチュエーションで行くのもストイックでいいんですけど、自分のなかでは黒澤明監督の『天国と地獄』のパロディの気分があるんですよ。
■ああ。でも、塚本監督は自然を撮っていても、『斬、』なんか密室みたいでした。
塚本:そうですね。
■開放感がまったくない。武器と同じで塚本監督には抜け出られないものがあるというか。
塚本:ああ。密室も嫌いなんだけど好きというか。『HAZE』とか撮ってますから。(*『HAZE』=狭い空間に男が閉じ込められた短編)
■閉所恐怖症でしたよね、そういえば。僕もそうなんですけど。
塚本:僕は金縛りにしょっちゅう会うんですけど、あれが閉所の極限です。
■いまでも?
塚本:いまでもしょっちゅうですね。子どもの時からずっと恐怖です。
『ほかげ』にちらっと出てくる傷痍軍人は僕も当時、見たことがある。大島渚『日本春歌考』の冒頭にもちょっと出てくる。しかし、戦後すぐの闇市はさすがに見たことがない。塚本監督も実際に体験したわけではないものの、その痕跡に惹かれて、最初は短編のつもりで撮り始めたのが『ほかげ』だったそうである。それが思いの外、長い作品になってしまったと。「(闇市は)憧れだったんですね。ヤクザとか愚連隊とかテキ屋とかパンパンとかオカマとか、そういう人たちが活躍していて、もうカオスで」と塚本監督は話していた。『ほかげ』が闇市だけの作品にならなかったのは、やはり『野火』のインパクトがまだ監督のなかで衰えていなかったからだろう。そして、もう一本、戦争映画を撮るつもりだとは本文中にあった通り。これも覚悟して待つこととしたい。『ほかげ』の試写を観た夜、帰りに渋谷の道玄坂を下りながらメイド服の女の子がズラっと並んでいるのを目にして、闇市のエネルギーはまだ続いているのかもしれないと僕は思った。

『ほかげ』
11月25日(土)よりユーロスペースほか全国順次公開
監督・脚本・撮影・編集・製作:塚本晋也
出演:趣⾥、森⼭未來、塚尾桜雅、河野宏紀、利重剛、⼤森⽴嗣
助監督:林啓史/照明:中⻄克之/⾳楽:⽯川忠
⾳響演出:北⽥雅也/ロケーションコーディネート:強瀬誠
美術:中嶋義明/美術デザイン:MASAKO/⾐装:佐々⽊翔/ヘアメイク:⼤橋茉冬
製作:海獣シアター/配給:新⽇本映画社
2023年/⽇本/95 分/ビスタ/5.1ch/カラー
配給:新日本映画社
©2023 SHINYA TSUKAMOTO/KAIJYU THEATER
https://hokage-movie.com/#about