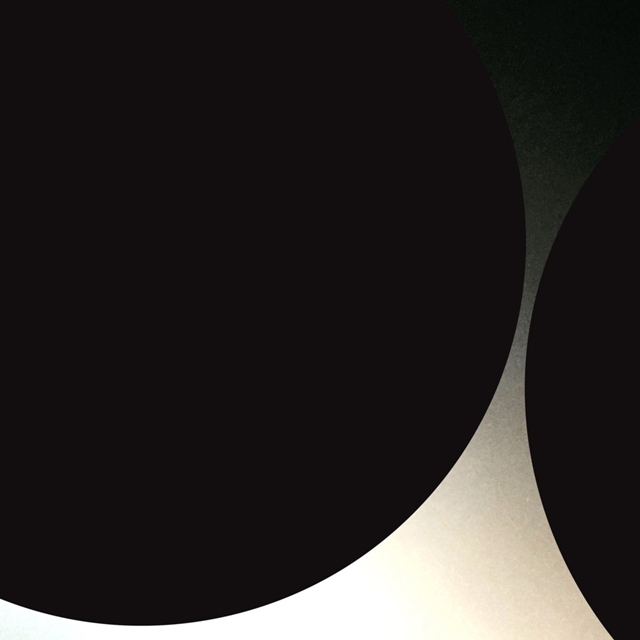ニコラス・ジャーが新たにコンピを編纂している。20世紀後半のポーランドの前衛音楽/実験音楽を集めたもので、2枚に分散してのリリース。1959年から2001年まであったワルシャワのスタジオで録音されたもの。マトモスが先日発表した新作でもとりあげていたボグスワフ・シェッフェルはじめ、クシシュトフ・クニッテルやボフダン・マズレク、ヴォジミエシュ・コトニスキやエルジュビェタ・シコラなど、ポーランドの前衛音楽家/実験音楽家が多数ピックアップされている。これはチェックしておきたい。

artist: Various
title: Would It Sound Just As Bad If You Played It Backwards? A Collection of Sounds from the Studio Eksperymentalne Polskiego Radia (1959-2001) Vol. I
label: Other People
release: 20th May, 2022
tracklist:
01. Krzysztof Knittel - Lapis (1985)
02. Bohdan Mazurek - Canti (1973)
03. Magdalena Dàugosz - Yes and No (1990)
04. Barbara Zawadzka - Greya III (1991)
05. Barbara Zawadzka - Greya IV (1990)
06. Barbara Zawadzka - Greya II (1987)
07. Rudnik - Epitaph of Stones (1984)
08. Bogusław Shaeffer - Symphony. Electronic Music for Tape (perf. by Wolfram) (1964-66) - I
09. Bogusław Shaeffer - Symphony. Electronic Music for Tape (perf. by Wolfram) (1964-66) - II
10. Bogusław Shaeffer - Symphony. Electronic Music for Tape (perf. by Wolfram) (1964-66) - III
11. Bogusław Shaeffer - Symphony. Electronic Music for Tape (perf. by Wolfram) (1964-66) - IV

artist: Various
title: Would It Sound Just As Bad If You Played It Backwards? A Collection of Sounds from the Studio Eksperymentalne Polskiego Radia (1959-2001) Vol. II
label: Other People
release: 20th May, 2022
tracklist:
01. Wlodzimierz Kotoński - Study For One Cymbal Stroke (1951)
02. Symphony. Electronic Music For Tape Part I (performed by Bohdan Mazurek) (1966)
03. Elżbieta Sikora – Letters to M. (1980)
04. Bernadetta Matuszczak – Libera me (1991)
05. Elżbieta Sikora - View From the Window (1978)
06. Magdalena Długosz - Mictlan I (1987)
07. Barbara Zawadzka - Greya part V (1991)
08. Krzysztof Knittel - Poko (1986)