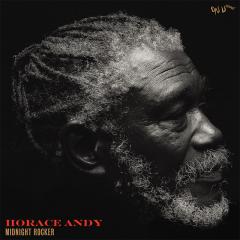クラブ・ミュージックは労働者階級から生まれたものだから、そういう街にいたことが自分に影響を与えているんだと思う。
ハウスかと思えばテクノへ、テクノかと思えばトランスへ、トランスかと思えばハーフ・テンポのビートへ、あるいはジャングル~ハードコア、ガラージ、フットワーク、ポップスへ。紙一重でグルーヴを保持しつつもDJセットのなかで絶えずジャンルを横断するようなプレイングはクラブ・ミュージックのスタンダード・スタイルとすら言い切れる。特定のジャンルやスタイルへと身を捧ぐ美学も依然としてクラブ・カルチャーに欠かせない重要な要素のひとつだけれど、私たちの普段のリスニング態度というのはもっと気ままに、さまざまなサウンドやビートをコラージュするようなものであることは間違いないし、その自由さをクラブに持ち込むということはごく自然な動きでもあるだろう。
そして、多くの若い人びとがクラブ・ミュージックを横断的に聴く、ということを強く意識したのはコロナ禍の、あのクラブの扉に鍵がかかってしまった時期のことではないだろうか? ホーム・リスニングを強いられた時代を経て、私たちは配信プログラムやウェブ上のDJミックス、動画コンテンツ、あるいはストリーミング・サーヴィスに星の数ほど広がるプレイリストの数々を絶えず渡り歩いてきた。その蓄積はけっして無意味なものではなかったし、むしろダンス・ミュージック受容の可能性を拡張したのではないか、とも考えられる。そんな感覚を(時代の要請とは無関係に)持ち合わせているアーティストたちに、いま光が当たりはじめている気配がする。
今回インタヴューをおこなった〈Ninja Tune〉所属のアイ・ジョーダンもそのひとりだろう。北イングランドの郊外、労働者の街ドンカスターで生まれ育ち、現在はロンドンを拠点とするノンバイナリーのアーティストだ。階級差別と静かに闘いつつ、物心がつくころから変わらないピュアな音楽愛をもとに多彩なジャンルを横断するプレイヤーで、約10年にわたるアンダーグラウンドでのDJ活動を経て、2019年以降〈Local Action〉からシングルをリリース、2020年にはヒット曲 “For You” を送り出している。のちにコラボするフレッド・アゲイン同様、パンデミック時代が生んだプロデューサーと言えるだろう。その後〈Ninja Tune〉と契約、21年の “Watch Out!” であらためてその存在感を見せつけたアイ・ジョーダンの、ファースト・アルバムがついに完成した。現在流行のトランシーな感覚を維持しつつも、さまざまなスタイルに挑むこの新星にUKダンス・ミュージックの現在地を訊く。
音楽業界には労働者階級の人はあまりいないから、成功するために自分の訛りをなるべく消すように努めてきたけど、歳を重ねたいまは自分がどこから来たのかってことにプライドを持てるようになったし、出自への感謝も湧いてきたんだ。
■いまはロンドンが拠点なんですよね。育ったドンカスターという街はどんなところですか?
IJ:ドンカスターが日本でよく知られてないのは、そんなに素敵なところじゃないからかな(笑)。基本的には労働者階級の街で、わたしが好きな音楽のシーンはなかった。だから16歳のときにドンカスターを出たんだけど、あそこは自分にインスピレーションを与えてくれる場所でもあったんだ。クラブ・ミュージックは労働者階級から生まれたものだから、そういう街にいたことが自分に影響を与えているんだと思う。ドンカスターはベースラインが生まれたシェフィールドとそう遠くないしね。ドンカスター・ウェアハウスっていうヴェニューがあるんだけど、そこは90年代初頭のUKレイヴやハードコア・テクノのパーティにとって重要な場所だった。
■労働者階級であるということは、音楽をやるうえでもご自身にとって大きいですか?
IJ:そうだね。イギリスっていうのはすごく階級意識の高い国で、たとえば自分にはヨークシャーや北イングランドあたりの訛りがあるんだけど、そうした要素から、その人の階級をすぐに判断されてしまうような風土があって。わたしは、そういったものと闘ってきたところもあるかな。音楽業界には労働者階級の人はあまりいないから、成功するために自分の訛りをなるべく消すように努めてきたけど、歳を重ねたいまは自分がどこから来たのかってことにプライドを持てるようになったし、出自への感謝も湧いてきたんだ。ただ、自分は労働者階級のダンス・ミュージックをつくっているし、そうしたものに影響を受けてはいるんだけど、やっぱり音楽をつくるにはお金も練習するための時間も必要で、でも労働者階級だとそうした余裕は持てない。実際、自分の家族のなかでドンカスターを出たのはわたしだけだしね。もちろん、音楽の道に進んでいったのも。
■最初に音楽を聴くようになったのはいつごろで、どういうものに惹かれていましたか?
IJ:人生をとおしてずっと音楽に影響を受けつづけてるよ。最初にギターを手にしたのが3歳ぐらいのころで、母がジョージ・マイケルやプリンス、フィル・コリンズ、シンプリー・レッドとか、そういう音楽を聴いていたから影響を受けたかな。10歳のころには本格的にギターを練習するようになって、そのときはロックに夢中だった。16歳ごろから徐々にダンス・ミュージックに興味を持つようになって、トランスやミニストリー・オブ・サウンド、イビザ的なサウンドを聴くようになったんだ。そのあともっとハードな音を求めてペンデュラムやハッピー・ハードコア、ドラムンベースなんかを聴くようになった20歳ごろからDJをはじめて、テクノ、ハウス、ドラムンベース、ガラージ、そういったものをプレイするようになっていった。

ノスタルジアというか、郷愁のようなものをトランスに感じとっている人が多いんじゃないかな。
■あなたの音楽の特徴のひとつに、トランシーな感覚があります。いまトランスが流行しているのはなぜだと思いますか?
IJ:UKだけじゃなく、いまヨーロッパ全体でトランス・ミュージックが流行っていると思う。とくに90年代から00年代初頭のサウンド、ユーロ・ダンスのようなトランスがね。わたしもその時期の音楽には影響を受けていて、デビューEPの「DNT STP MY LV」にもトランスを入れてる。トランスの浮遊感や多幸感に触れる体験が好きだから、自分もつくってるんだ。そして、いまはトランスと同時にテクノ・エディットしたものがブームになっていて、たとえば自分もつくった曲を違うヴァージョンでテクノ・エディットにしたりしてる。全体的にノスタルジアというか、郷愁のようなものをトランスに感じとっている人が多いんじゃないかな。
■現在トランスを受容している層はおそらくリアルタイム世代ではないですよね。
IJ:当時流行ってたトランスは聴いてたよ。7歳ぐらいのころに(笑)。労働者階級の住む街、とくに北イングランドだと、子どものころからダンス・ミュージックに触れる機会がすごく多いんだ。昔は中古のトランスのコンピレーション・アルバムなんかが簡単に、安く手に入りやすかったし、海賊盤もたくさん売ってたから。
■UKではいまやはりレイヴも勢いがあるのでしょうか。
IJ:レイヴやクラブはすごく流行っていると思う。というか、それらはイギリスの一部だから、流行りつづけていると言ったほうがいいかな。とくにコロナ以降はこういったものをみんなすごくありがたがっていると思うし。
■スクウォット式のレイヴもいまだ根強い?
IJ:いまでもフリー・パーティやスクウォット・レイヴはけっこうあるよ。とくに夏場は野外でおこなわれるものが多くて、たとえばロンドンのハックニー・マーシーズって公園だと、昼も夜もそういったパーティをやってるかな。
■あなたが躍進していったのはコロナ禍のタイミングでしたが、トランスやレイヴといったカルチャーが盛り上がるようになったのは、やはりパンデミックの影響だと思いますか?
IJ:そうだと思う。パンデミックがあったことで音楽の聴き方や音楽への向き合い方が人びとの間で大きく変わっていったと思うけど、パンデミックが終わって友だちと一緒にクラブで音楽を聴けるようになったことを祝うムードはすごく大きくなったと思う。同時に、ダンス・ミュージックというものが違った方向でも聴かれるようになったと思ってる。クラブが閉鎖されているからこそ、その枠を飛び越えるようなダンス・ミュージックの新たな可能性をロックダウンが示してくれたんじゃないかな。
■ちょうどパンデミックの起こった2020年に、あなたの代表曲ともいえる “For You” がリリースされました。2023年の現時点から振り返ってみたとき、どういう印象を抱きますか?
IJ:3年経って、この曲のことを考えることはよくあるけど、いまクラブではプレイしてないかな。今回の東京や上海は初めてプレイする場所だったから今回はかけたけどね(註:取材は昨年12月、来日公演のタイミングでおこなわれた)。3年間で自分は大きく成長できたと思うし、そのなかでこの曲はたくさんプレイしてきたから。いまは “For You” のことを誇りに思っているよ。

当時流行ってたトランスは聴いてたよ。7歳ぐらいのころに(笑)。労働者階級の住む街、とくに北イングランドだと、子どものころからダンス・ミュージックに触れる機会がすごく多いんだ。
■〈Local Action〉のあと、〈Ninja Tune〉と契約に至った経緯を教えてください。
IJ:“For You” をリリースしたあとオファーをもらって、2枚のEPと1枚のアルバムを出すという内容の契約を結んだんだ。〈Ninja Tune〉はすごくいいレーベルで、できれば条件を達成したあとも契約を更新していきたいなと思ってるよ。
■移籍した2021年にEP「Watch Out!」をリリースしていますが、それまで以上にハードコアなブレイクビーツが披露されている印象を受けました。
IJ:いや、そういうわけではなくて、わたしはハードコアなサウンドをずっとつくりつづけているつもりなんだ。「Watch Out!」には2曲ぐらいハードコアが入っているけど、ディスコ・エディットのハウス・トラックがあったりするし。ハードコア・テクノは自分の一部だから、その時期はとくに熱中してつくってたかな。いまは少し変わってきてて、テクノやトランスを中心につくるようになった。アーティストとして、いろんなプロダクションにアプローチしていきたい気持ちが強くて、たとえばアルバムはテクノやトランスもあるし、ガラージや実験的な要素も含まれている。なるべく多くのジャンルを横断的につくっていきたいと思ってる。
■ふだんの制作において、なにかコンセプトを考えたうえでつくることはありますか?
IJ:EPや曲単体にかんしては内省的で自分自身を見つめ直すようなものが多いんだけど、明確なコンセプトはないかな。ただ、やっぱりアルバムを制作するとなると客観的な視点やコンセプトが必要になってくるから、ある程度ぼんやりとは考えている。
■現在制作中のアルバムはどのような内容になっているのか、教えてください。
IJ:このアルバムは、自分の人生のなかでいちばん重要なプロジェクトで、誇りに思える大切な作品になった。わたしの尊敬するアーティストや友人たちともたくさんコラボレーションしていて、UKのクラブ・ミュージックをベースにエクスペリメンタルやハウス、トランス、ドンク、ガラージのような多彩な方向性を持つ音楽が混ざりあった内容で。それぞれ違ったセッティングや環境でも楽しんで聴いてもらえるアルバムだと思うよ。