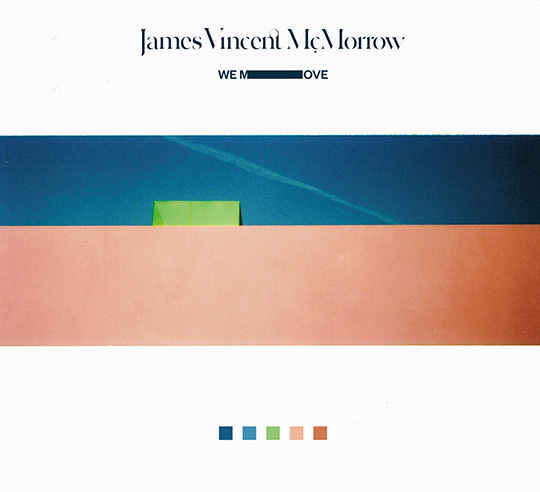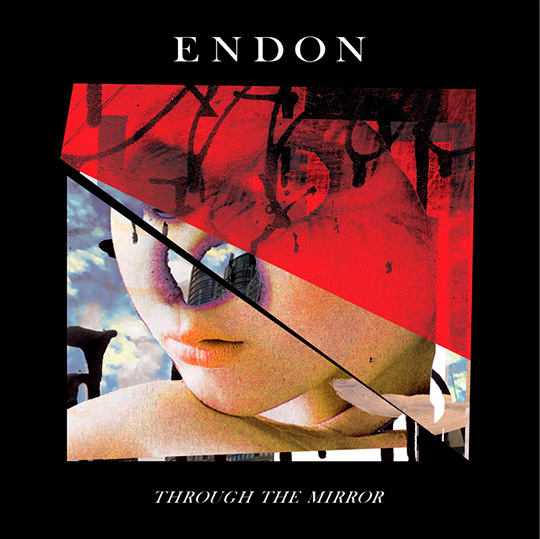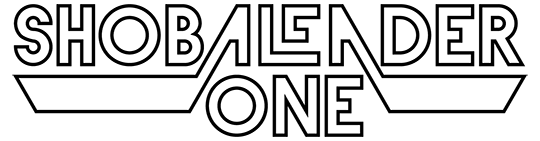「世界」が終わりつつある。より正確には「20世紀的な世界」が終わりつつある、というべきか。われわれにとって所与の概念・世界観・倫理観・思考の大枠となっていた時代・世紀が、なし崩し的に消失していく。歴史の継続性が軽視され、失われていく。それは全体主義の萌芽でもある。波打ち際の砂粒のように消え去っていく20世紀(後半?)の痕跡。後世の歴史家たちも「21世紀の真の始まりは2017年だった」を記すようになるのではないか。新・全体主義の誕生にむけて?
このような時代において芸術は、「20世紀的な概念で形成された人間」の「終わり」を強く意識することになるだろう。死。消失。ゆえにこの時代において、音楽は20世紀(後半)へのレクイエムとなる。
テープ・ループ・レクイエム。ウィリアム・バジンスキーの新譜『ア・シャドウ・イン・タイム』を聴き終えたとき、そのような言葉が脳裏に浮かんだ。本アルバムは、昨年(2016年)1月に亡くなったデヴィッド・ボウイへの追悼でもあるという。じじつ1曲め“フォー・デヴィッド・ロバート・ジョーンズ”はボウイの本名からつけられている。
音楽的には、あのバジンスキーのサウンドである。霞み、傷つけられた、しかし柔らかい音の連鎖、生成、変化。記憶が崩壊していくようなムード、アンビエンス。本作の雰囲気は、どことなく名作『ザ・ディスインテグレーション・ループス』を思わせる。『ザ・ディスインテグレーション・ループス』は映像作品でもあり、2001年9月11日、倒壊していくワールド・トレード・センターを映したものであった。そこに乗るバジンスキーによる霞んだ色彩のテープ・ループ・アンビエント。その時が止まるような美しさ。だが、その美には、20世紀の死と終焉が刻印されているのだ。
本作『ア・シャドウ・イン・タイム』もまた、そのような終末/崩壊の感覚を継承している。むろん違う点もある。ボウイへ追悼作であることからも分かるように、本作は「世界の終わり」と「個人の死」が、不思議な説得力で結びついている。
そう、昨年から続く20世紀偉人的音楽家たちの死は、20世紀の終わりを強く意識させることになった。20世紀の終わり。21世紀のはじまり。それは歴史の継続性の終焉でもある。それがわれわれに強い不安(と高揚感?)をもたらしている。世界は、どうも良くなってはいない。20世紀を変革した偉人たちは、相次いで世を去った。となれば私たちが今、生きている現在=この世界は、どうやら、あの「20世紀」ではないらしい。この根拠が剥奪された感覚は、根拠を希求し、その結果、誤った高揚感を求めるだろう。
本作は、ボウイという20世紀後半のイコンの死=消失の向こうから鳴らす20世紀へのレクイエム/アンビエントである。その音は死の不穏さに彩られているが、同時に死の華のように儚く、最後の生の発露のように美しい。終わりはいつも甘美であり、同時に不穏な色彩に彩られているものだ。そう、ウィリアム・バジンスキーはアンビエントの「黒い星」を作出したのだ。