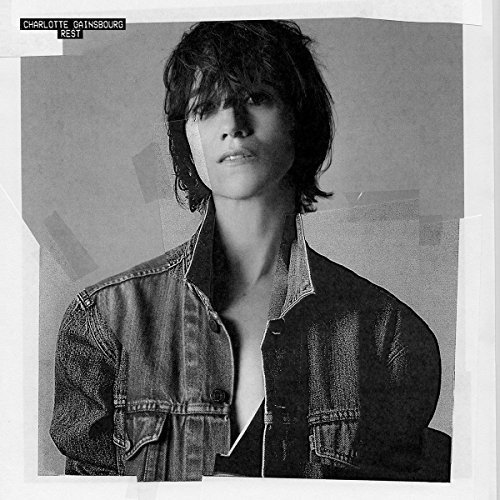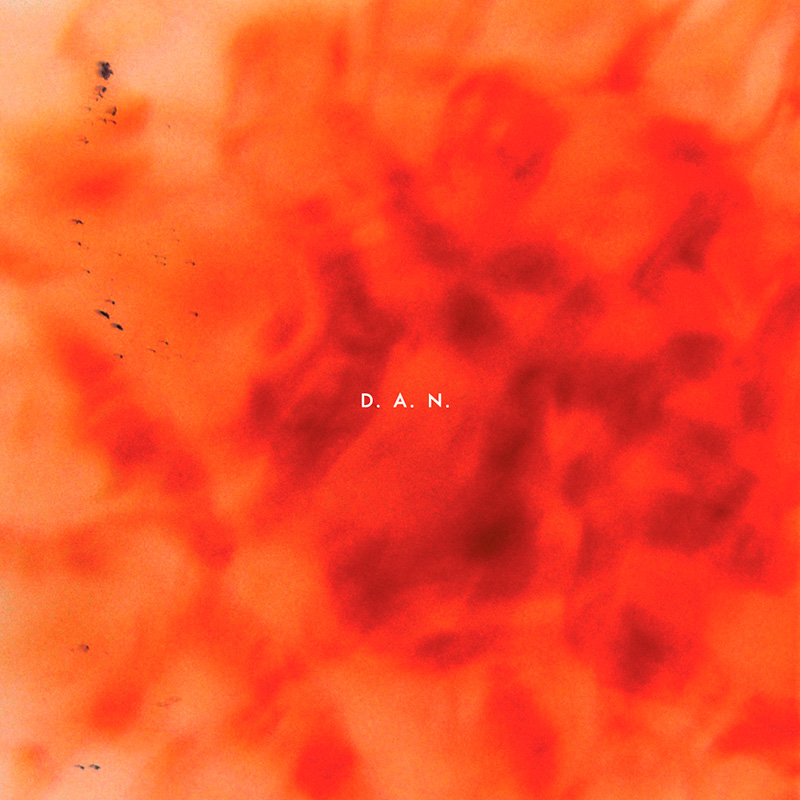〈φonon (フォノン)〉は、EP-4の佐藤薫の〈SKATING PEARS〉のサブレーベルとして2018年に始動した、という話はすでに書いた。いまのところEP-4 [fn.ψ]『OBLIQUES』、A.Mizukiのソロ・ユニットで、ラヂオ ensembles アイーダ『From ASIA (Radio Of The Day #2)』という2枚のリリースがある。
で、このたび第二弾のリリースありとの情報。
そのひとつは、家口成樹セレクトのエレクトロ・コンピレーション、『Allopoietic factor』。いま最高にクールなエレクトロニック・ミュージック/ノイズが収録されている。そして、もう1枚は森田潤の初ソロCD『LʼARTE DEI RUMORI DI MORTE。美しくも不気味な音を巧みにコラージュさせる音響センスは秀逸で、ユーモアもある。
ぜひ、チェックしてくれ。
https://www.slogan.co.jp/skatingpears/
6月15日(金) 2タイトル同時発売!!
アーティスト:Various Artists
アルバムタイトル:Allopoietic factor
発売日:2018年6月15日(金)
定価:¥2,000(税別)
品番:SPF-003
発売元:φonon (フォノン) div. of SKATING PEARS
01. Bark & Pulse / ZVIZMO
02. Suna No Onna / Turtle Yama
03. Fuzzy mood for backpackers / bonnounomukuro
04. Crepuscular rays / Singū-IEGUTI
05. Exocytosis / Yuki Hasegawa
06. Boiling Point / 4TLTD
07. Armor / Natiho Toyota
08. Sairei No Odori / Black root(s) crew
09. IN A ROOM / Radio ensembles Aiida
10. Proto-Enantiomorphous / EP-4[fn.ψ]

アーティスト:Jun Morita
タイトル:LʼARTE DEI RUMORI DI MORTE
発売日: 2018年6月15日(金)
定価:¥2,000(税別)
品番:SPF-004
発売元:φonon (フォノン) div. of SKATING PEARS
トラックリスト
01. Le Pli II
02. Poesia I
03. L'Arte Dei Rumori Di Morte
04. Corpus Delicti
05. Acephale Extravaganza
06. Poesia II
07. Live at Forestlimit,Tokyo 20-Jan-2018