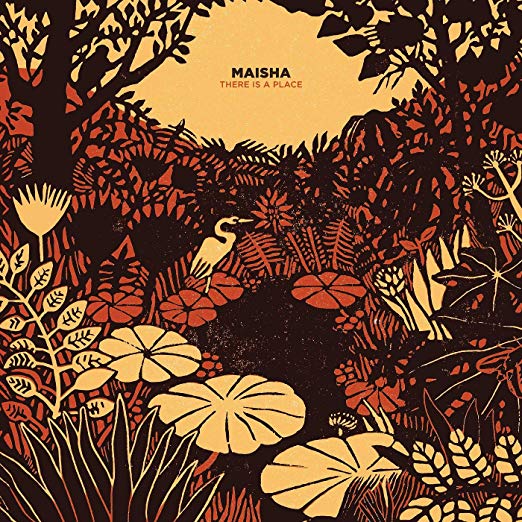ポルトガルの〈プリンシペ〉というレーベルがクゥドロをリリースしはじめたとき、それは本当に斬新でモダンなダンス・ミュージックであった。正直、〈プリンシペ〉よりも10年前にクゥドロを先導していたDJアモリムやDKカドゥはまったく垢抜けず、ワールドワイドに知れ渡ることがなかったのも当たり前だと思えた(筆者は2008年にブラカ・ソム・システマのデビュー・アルバムで初めてクゥドロを知ることになった。だから、それ以前のものは遡って聴いただけ)。旧世代ではDJネルヴォソだけが〈プリンシペ〉にサルヴェージされ、作風もアップデートされたものになっている。〈プリンシペ〉はごく初期にフォトンズというポルトガルでは2006年からレコードをリリースしていた中堅のハウス系プロデューサーをレーベルに迎え入れていたので、クゥドロを土着サウンドとして温存するのではなく、ハウスというフォーマットの中で都会的な洗練を施そうという意志を持っていたことは明らかだったと思う。そして、DJニガ・フォックスやB.N.M、あるいはパリのニディア・ミナージュがそのラインで流れ出していったのである。しかし、その中にレーベル番号で言えば3番という早い時期のリリースにもかかわらず、なかなか意図不明なリリースが含まれていた。ナイアガラである。アルベルト・アルルーダ、アントニオ・アルルーダ、サラ・エッカーソンからなり、ノヴォ・ムンドの名義では普通にハウスもやっている3人組が2013年にリリースした事実上のデビュー・シングル「Ouro Oeste」はクゥドロとはまったくかけ離れ、ハウス・ミュージックとしてもどこかしっくりとこないものであった。僕はしばらくすればナイアガラは〈プリンシペ〉を離れ、同じポルトガルの〈エンチュファーダ〉辺りに移るだろうと思うほど〈プリンシペ〉の路線ではないと思っていたぐらいで、それが〈プリンシペ〉における3枚目のアーティスト・アルバムはDJニガ・フォックスでもなければCDMでもなく、まさかのナイアガラだったのである。そして案の定というか、これがやはりダンス・アルバムではなく、初めて9月に聴いてからすでに1ヶ月、いったいこれはなんだろうと思いながら何度も聴き返してしまうことになった。何度聴いても過去の引き出しのどこにも収まってくれない。もう一度、もう一度……
ポップでもなければ、実験音楽でもない。最初はスフィアン・スティーヴンスやコス/メスがシリーズ化しているライブラリー・ミュージックを狙ったものかなと考えた。冒頭から変調させた声がミニマルというか、循環コードに絡みつき、アンビエント・ミュージックにしては賑やかな情景描写が展開される。このパターンが何曲か続き、ダンス・ミュージックでないことははっきりしてくる。いわゆるヒプノティックな効果は期待されているようで、メンタルに訴えかけようとはしているものの、トリップ・サウンドの要素はなく、特異な世界観に引きずり込まれることはない。なんというか、抽象的でとても醒めている。調べてみるとアルベルト・アルルーダは〈プリンシペ〉と出会う前にノイズやポスト・ロックのバンドで活動していた過去があり、それがどんな音楽だったのかということまではわからなかったものの、実験音楽やアヴァンギャルドにありがちな理性的で酩酊感のない音楽であろうとする感覚は残っているということなのだろう。ノイズやポスト・ロックにありがちな攻撃的要素をすべてスタティックなパーツに置き換えて全体像を組み立て直したという感じかもしれない。それでいてミュジーク・コンクレートに通じる面はまったくないのだから独創的としか言えない。何度も聴いているうちにどこにもなかった扉が開いて自分の中に新たな引き出しが生まれたような気になってきた。違和感が既視感にすり替わったというか。
後半になると控えめながら、ほとんど曲でパーカッションがフィーチャーされる。催眠的であることに変わりはなく、ポップでも実験的でもないことは変わらないのに、どことなく理性的ではなくなり、知らず識らずのうちにトリップ・サウンドに紛れ込んでいるような体験になっている。“Damasco”“Siena”、そしてポルトガルなのになぜかイタリア全土を統一に導いた“Via Garibaldi”と続く流れは実に素晴らしく、“Matriz”であっさりとアルバムが閉じられてしまうと、え、ちょっと待ってよ、もう一度という気持ちになってしまう(出来の良くないハウスを追加したボーナス・トラックは興ざめ)。ここでやはり今年前半の白眉だったと言えるドゥ・レオンのミニ・アルバム『De Leon』を思い出すのが順当だろう。ナイアガラに比べてテクノのフォーマットにすんなりと順応しているドゥ・レオンは絶対に正体を明かさないユニットとして登場し、ガムランとカポエラにダブを取り入れたサウンドでテクノとワールド・ミュージックの垣根を完全に取り払ってしまった(“A3 Untitled”は確実にベーシック・チャンネルの先をいっている。1年以内に必ずマーク・エルネスタスがリミックスか何かで関わろうとするだろう)。2本のカセットに続いてリリースされたデビュー・アルバムは〈オネスト・ジョン〉傘下の〈マナ〉からリリースされ、その瞑想的なダンス・サウンドはナイアガラ『Apologia』で「それ以上、先に行ってはいけない」と釘を刺されていた領域にズンズンと突き進んでいく。この2枚を続けて聴くことは、結末を読むのが怖い昔話を読むような体験に似ているような気がする。