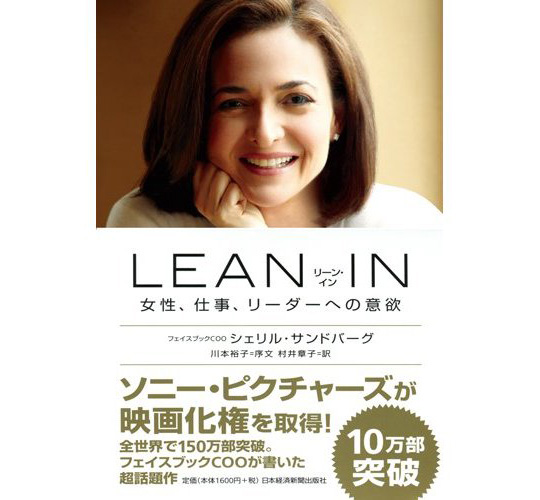JINTANA & EMERALDS - Destiny |
どこかにありそうでどこにもないベイエリア〈エメラルド・シティ〉から、極上のメロウ・ミュージックが届けられた! 横浜を拠点とする〈PAN PACIFIC PLAYA〉から、JINTANAが中心となって結成されたネオ・ドゥーワップ・バンド(!?)、JINTANA & EMERALDS。彼らがこのたびリリースするアルバムがそれだ。すでに7インチ盤「Honey/Runaway」を発表し、そのとてつもなくユニークなサウンドを国外にまで知らしめた彼らが、ついに『Destiny』という10曲入りアルバムをリリースすることになった。
本作ではドゥーワップにとどまらず、フィル・スペクターを連想させるような、オールディーズの雰囲気がつめこまれている。ロネッツ風あり、モータウン風あり、プラターズ風あり、そしてジョー・ミークのカヴァーもあり。現代の音響技術を駆使してアップデートされた、21世紀版のウォール・オブ・サウンドが聴こえてきたら、そこはもう、青い海と青い空に囲まれた架空の都市〈エメラルド・シティ〉である。
そんな本作の世界観を支えるのは、スティール・ギターを弾くJINTANAである。彼が抱いていたオールディーズの世界にメンバーは運命(destiny!)のように集まった。このユニークで、どこか大瀧詠一やYMOのノベルティ盤を思わせる本作を追求すべく、主要メンバーであるJINTANA EmeraldsとTOI Emeralds(一十三十一)にインタヴューをおこなった。

JINTANA & EMERALDS
横浜発、アーバン&メロウ集団PPPことPAN PACIFIC PLAYA所属のスティールギタリスト、JINTANA率いるネオ・ドゥーワップバンド、JINTANA&EMERALDS。リーダーのJINTANA、同じくPPP所属で、最近ではあらゆるところで引っ張りだこのギタリスト、Kashif a.k.a. STRINGSBURN、媚薬系シンガー、一十三十一、女優としても活躍するMAMI、黒木メイサなど幅広くダンス・ミュージックのプロデュースをする行うカミカオルという3人の歌姫たちに加え、ミキサーにはTRAKS BOYSの半身としても知られる実力派DJ、CRYSTALを擁する6人組。
「声が個性的でカッコいい唄物」をやりたいと思ったとき、愛聴しているドゥーワップと〈PPP?のノリが僕の中で繋がったんです。それで一十三十一に電話して…… (JINTANA)
■『Destiny』、聴かせていただきました。この作品はかなりコンセプチュアルですよね。クラブなどでみんなで話しているうちにノリで作っちゃったような印象を受けて、そこが楽しいのですが、実際の制作の経緯はどのようなものだったのですか?
JINTANA:もともと〈Pan Pacific Playa?(※以下PPP)があって、僕もそのメンバーなんです。それで、ブラックミュージック的なものを掘り下げていきたいなと思っているうちにオールディーズが好きになって、すごく聴くようになったんです。〈PPP?には、LUVRAW & BTBっていうトークボックスをやっているグループがあるのですが、そのトークボックス声がすごくカッコよくて、そういう「声が個性的でカッコいい唄物」をやりたいと思ったとき、愛聴しているドゥーワップと〈PPP?のノリが僕の中で繋がったんです。それで一十三十一に電話して、「誰かまわりにオールディーズ好きでやりたそうな人いる?」って訊いたら……。
■むしろ、一十三十一さんがノッてきたんですね。
JINTANA:そう(笑)。「いやいや、わたしがやりたい!」って。
■一十三十一さんはやはり、「おもしろそう!」って思ったわけですか?
一十三十一:そうですね。わたしはコーラスを付けるのが好きなんです。それで、全員歌うドゥーワップ・バンドというのはおもしろいなと思って、「わたしが参加したい!」って言ったんです。そこで決まりました。
■じゃあ、ドゥーワップとかオールディーズというものが、先立ったコンセプトとして強くあって、その上でおもしろそうな人を集めた感じなんですね。
JINTANA:そうですね。ただ、もともとみんなそういうのが好きということがベースにはありました。KASHIFくんと〈PPP〉のKESくんと一十三十一なんか、それぞれ達郎フリークで「達郎フリークの会」みたいな感じでしたし(笑)。
■なるほど、山下達郎ならコーラスものは重要ですよね。JINTANA & EMERALDSは、「悪ふざけ感」がとてもいいですよね。僕が聴いときは、細野晴臣のトロピカル三部作やティン・パン・アレーの『イエロー・マジック・カーニヴァル』を思い出しました。最初に波の音が聞こえて、ナレーションのようなものが入る。細野さんなんかは、自分の音楽を「レバニラミュージック」と呼んで、インチキなエキゾチック音楽をやっていましたが、『Destiny』も、そういう「インチキなベイエリア」のような感じがとてもよかったです。制作時に聴いていたバンドなんかはあるのですか?
JINTANA:個別にはいろいろあるのですが、フィル・スペクターはすごく聴きまくっていました。
■なるほど。アルバムでも、“Emeralds Lovers”なんかは完全にロネッツのようなイントロですよね。一十三十一さんは、自身のアルバムで大瀧詠一のジャケットを引用していましたが、そのへんの音楽はいつから好きだったんですか?
一十三十一:自分のルーツとして、両親がわたしの生まれた78年から14年のあいだ北海道で営んでいたレストランがあるんです。その名も「トロピカル・アーバン・リゾート・レストラン ビッグ・サン」といって、まさに大瀧詠一さんや山下達郎さんのような世界観のお店なんです。国道沿いにハリボテのヤシの木がドーン! と立っていて、北海道なのにうちはいつも常夏で、西海岸の風が吹いている(笑)。アロハシャツとアーバンが混ざっているようなお店です。そこでかかっている音楽や雰囲気が、わたしのルーツなんです。店の選曲も両親がしていて、達郎さんやユーミンや大瀧詠一さん、あるいはビーチボーイズなんかがずっとかかっていました。オシャレな店だったので、80年代は着飾った大人たちのデート・スポットとして流行っていました。
国道沿いにハリボテのヤシの木がドーン! と立っていて、北海道なのにうちはいつも常夏で、西海岸の風が吹いている(笑)。 (一十三十一)
■鈴木英人の世界ですね。
一十三十一:まさにあの感じです。
■フィル・スペクターのサウンドは特徴的ですが、『Destiny』もかなりミックスにこだわっているように思いました。ミックスを担当したクリスタルさんには、なにか注文を付けたりはしたんですか?
JINTANA:いや、最初にサウンドのアイデアを話したときにクリスタルくんともすぐに意気投合したので、あとはクリスタルくんのノリでやってもらっています。トラックを送ってクリスタル君にミックスしてもらい戻してもらう流れなのですが、いつも曲がそこで最終的に磨き上げられて輝く感じです。
■『Destiny』ではドラムも特徴的だと思いました。生で叩いている躍動感もあり、一方で打ち込みのようなサウンドの厚さもあり、懐かしいんだけど古臭くもない絶妙なバランスです。ドラムは打ち込みですよね。
JINTANA:ドラムは全部打ち込みです。フィル・スペクターは、オールディーズ的な気持ちいいメロディーに加えて、サウンドもすごく気持ちよくさせようとした人だと思います。大瀧詠一さんも同じことをした。俺らもその現代版をやりたいなと思ったので、いまの音楽的な技術でいちばん気持ちいいと思うサウンドを追求しました。それは、やはり昔の音とは違いますよね。音響的な心地良さを追求しているうちにこういう音づかいになりました。
■僕も大瀧詠一さんなど好きでよく聴きますが、サウンドもさることながら、ノリも大瀧詠一っぽいですよね。JINTANA & EMERALDSには、JINTANAさんと一十三十一さんが北海道出身なのに「西海岸」という共通体験をでっちあげちゃうような遊び心があります。
一十三十一:さっき、メンバーのKASHIFくんとLINEで「祝フラゲ日」みたいなことをやっていたんです。「本当に出るんだね」って(笑)。
JINTANA:ふざけているうちに出た感じはあるよね。
■7インチのシングルを出したときはどうでしたか。
JINTANA:『Tiny Mix Tapes』とかにも取り上げていただいて話題になり、好評で嬉しかったです。
■7インチ・シングルはDJとかで買う人も多いと思います。僕もDJをやっているんですが、現代の潮流からするとこの作品はBPMが極端に遅いんですよね。それがすごく新鮮です。とくに後半はずっとゆったりしていて、その遅さとコーラス・ワークにドゥーワップっぽさを感じました。本人たちとしては、JINTANA & EMERALDSのドゥーワップっぽさはどこにありますか。
JINTANA:仲良さそうなところかな(笑)。昔のジャケットを見ていると、他のメンバーと顔がくっついちゃうようなキャッキャした写真があって、それが僕のドゥーワップのイメージです。
一十三十一:リア充感ね(笑)。
[[SplitPage]]
昔のジャケットを見ていると、他のメンバーと顔がくっついちゃうようなキャッキャした写真があって、それが僕のドゥーワップのイメージです。 (JINTANA)
■なるほど、そういうところなんですね(笑)。たしかに、そういう楽しい感じがよく出ているので、リスナーも仲間に入りたくなりますね。イニシアチブを取っていたのは、やはりJINTANAさんですか?
JINTANA:イニシアチブというか、JINTANA&EMERALDSという世界のきっかけをつくったのは僕ですが、その後はみんなで自由に遊んでいる感じですね。
一十三十一:歌詞の世界は「EMERLDS CITY」での物語なんです。デトロイト・ベイビーちゃんという歌詞専門の帰国子女の女性がいて、その子がメンバーの実話をもとに歌詞を書いているんです。だいぶエメラルド・エフェクトがかかっていますけど(笑)。
■その世界観はすぐ共有されたんですか。
JINTANA:「いまの音響で気持ちいいドゥーワップがやりたい」という想いが最初にあって。その後、〈PPP?の脳くんが、ドゥーワップには宝石の名前からとったバンド名が多いからという理由で、JINTANA & EMERALDSという名前を付けてくれたんです。
■一十三十一さんは、そのような立ち上げの経緯をどう見ていましたか。
一十三十一:その頃、わたしは出産して音楽活動から少し離れていて、5年ぶりに『CITY DIVE』を作っていました。JINTANA & EMERALDSは、そのあいだくらいのタイミングだったんです。子育ても落ち着いてきたし、新しい活動もしたいと思ったときだったので、「あたしやる!」と思って、すぐ参加しました。バンド活動は地味に2年くらいやっていて、今回ついにリリースということになったのですが、ずっと遊んでいるうちにここまで来た感じです。
〈PPP〉の脳くんが、ドゥーワップには宝石の名前からとったバンド名が多いからという理由で、JINTANA & EMERALDSという名前を付けてくれたんです。
■ジャケット・デザインやPVなどを見ても、みんなイメージが共有できている感じがしますよね。“18 Karat Days”という曲名も、オールディーズのセンスが最高です。
JINTANA:50年代のスラングとか言い回しを深堀りしてみようと思って、いろいろ調べていたんです。そしたら「すげーヤバい」みたいな意味で「18 Karat」という言葉が使われていた例を知って、曲名はそこから付けています。この曲は、50年代の言葉使いをかなり使っています。
■“Runaway”は出だしがプラターズの“オンリー・ユー”みたいですが、そこから外していく感じがおもしろいです。本作はとてもポップなので、誰が聴いてもいい曲だと思えると思いますが、一方でコアなリスナーが聴いたら、いろいろな先行する音楽を思い浮かべて楽しむかもしれませんね。制作にあたっては、「誰々っぽくしよう」とか話したりするんですか?
JINTANA:そういうのはあまりないですね。それよりも、メンバーの誰に向かって作るかということのほうを意識していました。「この曲はカミカオルちゃんの世界観で作ろう」とか。あとはライヴをしていくなかで細かく調整することもありましたね。
■活動していくうちに洗練していったんですね。アルバムでは“アイ・ヒア・ア・ニュー・ワールド”と“レット・イット・ビー・ミー”をカヴァーしていましたが、今後カヴァーしてみたい曲とかありますか。
一十三十一:本当はもっと入れようと思って、候補曲もたくさんあったんですよ。でも、今回は2曲だけ。日本語でやろうという話も出ていました。
JINTANA:ビージーズもやりたいと言っていたんですよ。
みんなで力を合わせてやっていく感じに、「バンドっていいな」と思いました(笑)。 (一十三十一)
やっぱり男女一緒にやっていることですかね。ライヴするときも着替えがあるから、控室が女子部屋と男子部屋に分かれていて、修学旅行みたいだと思いましたね(笑)。 (JINTANA)
■まだまだ、いろんな方向に広がっていきそうですよね。一十三十一さんは、どのように音楽制作に関わっていたんですか?
一十三十一:JINTANA & EMERALDSのなかで、わたしの担当は歌だけなので、それが自分のソロ活動とは全然ちがうんです。曲ができていく様子を客観的に見れたのが、楽しかったですね。みんなで力を合わせてやっていく感じに、「バンドっていいな」と思いました(笑)。
ソロのときは守備範囲が広くて緊張感も高かったりするのですが、バンドではみんながサポートしながら作るので心強いです。JINTANA本人も地元の仲のいい友だちとして出会っているし、KASIFくんも一十三十一でもいっしょに曲を作ったりして仲がよくて、カミカオルちゃんもデビューのときから仲良し。そんななかで撮影なども進んでいくので、本当に楽しい活動ですね。このジャケットの笑顔のとおりです(笑)。
■JINTANAさんは、いままでの音楽活動と今回で違ったこととかありましたか。
JINTANA:やっぱり男女一緒にやっていることですかね(笑)。ライヴするときも着替えがあるから、控室が女子部屋と男子部屋に分かれていて、修学旅行みたいだと思いましたね(笑)。
■それは大きなちがいですね(笑)。LUBRAW&BTBさんが参加していたり、おなじみのメンバーで楽しくやっている感じがあります。
JINTANA:“Destiny”は、「いま、このめんつメンツでこの瞬間にいっしょに音楽やパーティをしているのは、とても幸せな運命の導きで、その幸福な瞬間を心から味わいたい」という気持ちで作った曲なので、ふたりは入れたいなと思いました。
■なるほど。ドゥーワップ~オールディーズということですが、お気に入りのミュージシャンなどいますか。
JINTANA:モーリス・ウィリアムス&ザ・ゾディアックス“ステイ”とかは、すごく好きです。普通に歌がはじまったのに、次の瞬間にめちゃくちゃ高い声になるのが──ほとばしっている感じがヤバいんです(笑)。この曲は『僕の彼女を紹介します』っていう韓国映画での甘すぎるシーンのBGMにもなってます。
モーリス・ウィリアムス&ザ・ゾディアックス“ステイ”とかは、すごく好きです。普通に歌がはじまったのに、次の瞬間にめちゃくちゃ高い声になるのが──ほとばしっている感じがヤバいんです(笑)。 (JINTANA)
■コーラスに凝っている曲って、最近は意外と少ないかもしれませんね。
JINTANA:少ないですよね。ただ、声で気持ちよくするような曲はある気はします。全部機械ではなく最終的に声で聴かせる曲というのはやっぱりいいし、そういうものが好きな人は多いと思います。
■最近はエレクトロ・サウンドが流行っていますが、JINTANA & EMERALDSのように、BPMが遅めでしっかり歌を聴かせられるようなバンドは貴重です。対バンしてみたい相手とかいますか。
JINTANA:対バンというのはあまりに恐れ多いのですが、夢としていつかご一緒したいのは、横山剣さんですね。
■今後はどのような予定になっていますか。
JINTANA:7月19日に京都メトロ、21日に代官山〈UNIT〉でレコ発ライヴをします。そこでエメラルドの世界に連れていくような非日常的な体験を楽しんでもらいたいですね。観ただけでトリップするような。
■クリスタルさんに音響的な部分をまかせて、どうでしたか。
JINTANA:ミックスが終わってファイルが戻ってくるといつも見違えるように鮮やかになっているのですが、個人的に、いちばん気持ちよかったのは“Moon”ですね。聴いた瞬間、別の世界に誘われましたね。
■個人的に思い入れがある曲とかはありますか。
一十三十一:最初の出会いが“Honey”だったので、それは思い入れがありますね。でも、全部びっくりするほど名曲ですけどね(笑)。毎回デモのクオリティがすごく低いんですよ(笑)。どの曲も、全然音程とかわからないところからはじまっているという物語があるので、それぞれおもしろかったです。
JINTANA:僕の声で歌っているデモは、解釈の余地がかなり多いという(笑)。
一十三十一:そうそう。自分なりの解釈で楽しめるところがありました。だから、だんだんデモのクオリティの低さも安心して受け入れられるようになってくるんです(笑)。とんでもないデモが送られてきても、「これもきっとあのレベルまで行くんだな」ということがわかるようになる。そういう、ゴールに向けての成長のストーリーがありました。
■一十三十一さんの立ち位置がいいですよね。「わたしは歌を歌うだけなんだ」と。
一十三十一:すごく客観的に見ていました。でも、みんなそれぞれのセンスが光っているので、とんでもないものが送られてきても安心感がありました。いろんな人の手が加わっていくことによって、着地点はいつもdestinyなんですよ(笑)。毎回そのストーリーを追いつつ完成に向かうのが楽しいです。だから、どの曲もいろんな物語があるんです。







 ハウス、ブレイクビーツの影響を受け、89年からDJ活動を開始。海賊放送やレイヴで活躍、ハードコア~ジャングル/ドラム&ベースの制作をはじめる。95年にGanjaから"Super Sharp Shooter"の大ヒットを放ち、96年にはDJ HYPE、PASCALと共にレーベル、True Playazを設立、ファンキービーツとバウンシーかつディープなベースラインで独自のスタイルを築く。00年の“138 Trek"は自己のレーベル、Bingo Beatsに発展、ブレイクステップの新領域を開き、2ステップ~グライムやブレイクス・シーンに多大な影響を与える。03年にはPolydorから1st.アルバム『 FASTER』を発表。09年以降、“Crack House”と銘打ったZINC自身が提唱する新型サウンドを布教。“Crack House”はBasslineサウンドを主体として、エレクトロ、ダブステップ、フィジェットハウス、ブレイクス、ジャングル等をミクスチャーした最先鋭のエレクトロ・ダンスミュージック。MS DYNAMITEをフィーチャーした10年の"Wile Out"はアンセムとなる。近年はA-TRAKとの共作をはじめ、自身のSoundcloudで新曲を続々とフリー・ダウンロードで挙げ、多大な支持を得ている。毎週金曜にRinse FMでオンエア。
ハウス、ブレイクビーツの影響を受け、89年からDJ活動を開始。海賊放送やレイヴで活躍、ハードコア~ジャングル/ドラム&ベースの制作をはじめる。95年にGanjaから"Super Sharp Shooter"の大ヒットを放ち、96年にはDJ HYPE、PASCALと共にレーベル、True Playazを設立、ファンキービーツとバウンシーかつディープなベースラインで独自のスタイルを築く。00年の“138 Trek"は自己のレーベル、Bingo Beatsに発展、ブレイクステップの新領域を開き、2ステップ~グライムやブレイクス・シーンに多大な影響を与える。03年にはPolydorから1st.アルバム『 FASTER』を発表。09年以降、“Crack House”と銘打ったZINC自身が提唱する新型サウンドを布教。“Crack House”はBasslineサウンドを主体として、エレクトロ、ダブステップ、フィジェットハウス、ブレイクス、ジャングル等をミクスチャーした最先鋭のエレクトロ・ダンスミュージック。MS DYNAMITEをフィーチャーした10年の"Wile Out"はアンセムとなる。近年はA-TRAKとの共作をはじめ、自身のSoundcloudで新曲を続々とフリー・ダウンロードで挙げ、多大な支持を得ている。毎週金曜にRinse FMでオンエア。 ディープ&ドープな最重量ベース・サウンドでダブステップの真髄を表現する"King of Wobble Bass"、LOEFAH。90年代ロンドンのレイヴ・シーンでハードコア~ジャングル/ドラム&ベースを体感し、4HEROのReinforced、GOLDIEのMetalheadzからの作品群にインスパイアされる。2000年頃には古いダブ、レアグルーヴ、ソウル、ヒップホップを再発見し、音楽的基礎を広げる。やがて友人のDIGITAL MYSTIKZのMALA&COKIと音を作り始め、138bpmでダビーなトラックを作る等、様々な実験を繰り返す。04年にはDIGITAL MYSTIKZとレーベル、DMZを旗揚げし、"Dubsession"、"Twisup"を発表。またBig Appleから"Jungle Infiltrator"、Tempaから"Truly Dread"、Rephlexからのコンピ『GRIME 2』では3曲フィーチャーされる等、彼の存在がダブステップと共に脚光を浴びる。その後もDMZを始め、Tectonic等からフロアーフィラーを連発する。09年からは自己のレーベル、Swamp 81を設立、ポスト・ダブステップの潮流を開き、エレクトロ、ハウス、テクノ、ガラージ、ゲットー等を奔放にmix。BODDIKA、JOY ORBISON、ZED BIASらを擁し、UKベース・シーンの要塞となっている。
ディープ&ドープな最重量ベース・サウンドでダブステップの真髄を表現する"King of Wobble Bass"、LOEFAH。90年代ロンドンのレイヴ・シーンでハードコア~ジャングル/ドラム&ベースを体感し、4HEROのReinforced、GOLDIEのMetalheadzからの作品群にインスパイアされる。2000年頃には古いダブ、レアグルーヴ、ソウル、ヒップホップを再発見し、音楽的基礎を広げる。やがて友人のDIGITAL MYSTIKZのMALA&COKIと音を作り始め、138bpmでダビーなトラックを作る等、様々な実験を繰り返す。04年にはDIGITAL MYSTIKZとレーベル、DMZを旗揚げし、"Dubsession"、"Twisup"を発表。またBig Appleから"Jungle Infiltrator"、Tempaから"Truly Dread"、Rephlexからのコンピ『GRIME 2』では3曲フィーチャーされる等、彼の存在がダブステップと共に脚光を浴びる。その後もDMZを始め、Tectonic等からフロアーフィラーを連発する。09年からは自己のレーベル、Swamp 81を設立、ポスト・ダブステップの潮流を開き、エレクトロ、ハウス、テクノ、ガラージ、ゲットー等を奔放にmix。BODDIKA、JOY ORBISON、ZED BIASらを擁し、UKベース・シーンの要塞となっている。 ミキシングを自在に操り、様々なアプローチで ダンスミュージックを生み出すサウンド・オ リジネイター。03年に1st.アルバム『GOTH-TRAD』を発表。国内、ヨーロッパを中心に海外ツアーを始める。05年には 2nd.アルバム『THE INVERTED PERSPECTIVE』をリリース。また同年"Mad Rave"と称した新たなダンスミュージックへのアプローチを打ち出し、3rd.アルバム『MAD RAVER'S DANCE FLOOR』を発表。06年には自身のパーティー「Back To Chill」を開始する。『MAD RAVER'S~』収録曲"Back To Chill"が本場ロンドンの DUBSTEP シーンで話題となり、07年にUKのレーベル、SKUD BEATから『Back To Chill EP』、MALAが主宰するDEEP MEDi MUSIKから"Cut End/Flags"をリリース。12年2月、DEEP MEDiから待望のニューアルバム『NEW EPOCH』を発表、斬新かつルーツに根差した音楽性に世界が驚愕し、精力的なツアーで各地を席巻している。
ミキシングを自在に操り、様々なアプローチで ダンスミュージックを生み出すサウンド・オ リジネイター。03年に1st.アルバム『GOTH-TRAD』を発表。国内、ヨーロッパを中心に海外ツアーを始める。05年には 2nd.アルバム『THE INVERTED PERSPECTIVE』をリリース。また同年"Mad Rave"と称した新たなダンスミュージックへのアプローチを打ち出し、3rd.アルバム『MAD RAVER'S DANCE FLOOR』を発表。06年には自身のパーティー「Back To Chill」を開始する。『MAD RAVER'S~』収録曲"Back To Chill"が本場ロンドンの DUBSTEP シーンで話題となり、07年にUKのレーベル、SKUD BEATから『Back To Chill EP』、MALAが主宰するDEEP MEDi MUSIKから"Cut End/Flags"をリリース。12年2月、DEEP MEDiから待望のニューアルバム『NEW EPOCH』を発表、斬新かつルーツに根差した音楽性に世界が驚愕し、精力的なツアーで各地を席巻している。