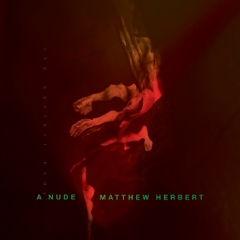テクノに関して言えば、ぼくには問題点がひとつある。ぼくがもうすでに良いテクノをたくさん知っているということだ。みんなより早く生まれたお陰で、オウテカやベーシック・チャンネルの時代から聴いてきた。IDMというタームが出てきた時代も経験している。ぼくはいまでも日常的にエレクトロニック・ミュージックを聴いているけれど、新作に関しては年々おっくうになってる。すでに自分の日常には、魅力的なテクノがたくさんあるからだ。とはいえ、やはりどうしても飽きる。その多くに関して言えば、高尚なアートなんぞではなく、そして取り立てて言うほどの感情移入もない、ある種の刺激物として消費しているのだから無理もない。それはこの音楽の出自を考えればすぐにわかることだ。
で、だったら新しいのを聴こうという気になり、本作のように情報としての共有に値する秀作に手を出すハメになる。こちら〈エディションズ・メゴ〉のサブレーベルからリリースされた、BelongのメンバーとTelefon Tel Avivのメンバーのふたりによるプロジェクトで、文句なしに素晴らしい最新エレクトロニカである。
ミニマルであってミニマルでない。反復されるが不規則で、複数のレイヤーがそれぞれずれていく。単純な快楽主義ではないのだが、彼らはそこを〝聴かせる〟次元にまで押し上げている。オウテカがミニマルをやったと喩えてもいいな。音響体験としてのスリルがあるのだ。
昔からぼくはエディットが細かいものが好きなので、気が滅入るほどの細かいチョップも心地良く、スラップスティック風に耳を刺激するし、ベーシック・チャンネル以降、マーク・フェル以降にも対応している。
オウテカの新作も良さそうだし、テクノ(IDM寄りのほう)が盛り上がっているのは確実だ。20年前にエレクトロニカが好きだった人も、いままたこのサブジャンルに注目してもいいかもよ。まあ、ある種の刺激物として。

 ボトムの効いたキックとおぼろげなハイハットによるビートに神々しく降り注ぐパッドが印象的。スネアやクラップが使われていないので、浮遊感が際立っている。それに対して重厚なベースラインがコントラストとなっていて心地よい。
ボトムの効いたキックとおぼろげなハイハットによるビートに神々しく降り注ぐパッドが印象的。スネアやクラップが使われていないので、浮遊感が際立っている。それに対して重厚なベースラインがコントラストとなっていて心地よい。 深淵へゆっくりと下降していくかのようなディープな1曲。異なる周期で揺らぐパッドが重なり合うことで徐々に大きなうねりを生み出していく。擦り付けるようなハイハットが鼓膜と意識をかきむしる。
深淵へゆっくりと下降していくかのようなディープな1曲。異なる周期で揺らぐパッドが重なり合うことで徐々に大きなうねりを生み出していく。擦り付けるようなハイハットが鼓膜と意識をかきむしる。
 タイトに打ち込まれるエレクトロ・ビートの間をパッドがシンセベースと連動しながら吹き抜けていく。中盤のブレイク部ではメロディ素材と絡み合いながら程よくノスタルジックな空気をもたらしてくれる。
タイトに打ち込まれるエレクトロ・ビートの間をパッドがシンセベースと連動しながら吹き抜けていく。中盤のブレイク部ではメロディ素材と絡み合いながら程よくノスタルジックな空気をもたらしてくれる。
 いつまでも漂っていられる浮遊感がたまらない。その肝は、じわじわと解放されていくバックグラウンド・パッドの爽快なテクスチャー変化と、アシッドサウンドになりそうでならないベース・シーケンスの焦らしだ。
いつまでも漂っていられる浮遊感がたまらない。その肝は、じわじわと解放されていくバックグラウンド・パッドの爽快なテクスチャー変化と、アシッドサウンドになりそうでならないベース・シーケンスの焦らしだ。
 長く減衰する残響音がパッド代わりとなって大きく起伏するベースラインと共に鼓動する壮大なトラック。アクセントとしてホイッスルのように吹き付けられるシンセにハッとさせられる。
長く減衰する残響音がパッド代わりとなって大きく起伏するベースラインと共に鼓動する壮大なトラック。アクセントとしてホイッスルのように吹き付けられるシンセにハッとさせられる。