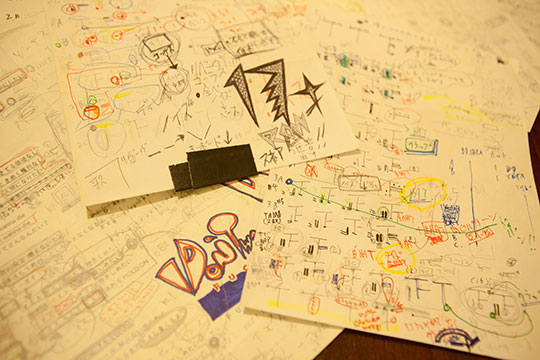「日本で現在、ゲイネスを作中に潜ませたエッセンスやくすぐりとしてでなく、ナラティヴを作り続けているのは、我田引水ながら自分らの他には思い当たりません」というのは、今泉監督とのパートナーシップで映画を作り続けておられる音楽担当の岩佐浩樹さんの言葉だ。彼らの作品は海外の映画祭を中心に上映されており、新作『すべすべの秘法』(“The Secret to My Silky Skin”)のワールドプレミアも日本ではなく、2013年ベルリン・ポルノ映画祭だった。
真正なるゲイ映画というのは、確かに現代の日本で市場が成立するのかは不明だし、発表の場もごくごく狭い箱の中になるのだろうが、例えば昨年。今泉監督がピンクのバナーを掲げて反韓デモにカウンターをかけに行っておられる写真を見た時には、勇ましげに中指を突き立てる人びとや、白地に黒文字のプラカを手にした人びとが並んだ新大久保の街に、ピンクのバナーがひっそりと、力強く存在しているイメージが頭に浮かび、彼らの映画も日本映画界のピンクのバナーだ。と思った。
********
『すべすべの秘法』はゲイ漫画家、たかさきけいいち原作のコミックの映画化だ。そのせいか、日本におけるカミングアウトや同性婚、「社会改革がリアリティになるのは、よその国の話よね」みたいな日本人の当事者意識の無さ、といったポリティカルな問題をやんわり微笑しながらナイフで斬ってみせた『初戀』(拙著収録の書き下ろしレヴュー参照)とは違う。もっと王道のゲイ日常記というか、京都から東京のヤリ友(ファック・バディー)に会いに来たあるゲイの数日間をまったりと描いている。
今泉監督は1990年からピンク映画の俳優としても活躍しておられ、2013年ベルリン・ポルノ映画祭では、彼の過去の出演作品と『すべすべの秘法』の上映を合わせた特集プログラム「RETRO : KOICHI IMAIZUMI」が組まれた。ポルノ映画祭で上映されたからには、セックスシーンがばんばん出て来て描写が露骨なんだろう。と思ったが、実はセックスシーンは少ない。露骨。という点でも、そのものズバリを見せているという点ではそうだろうが、そういう派手な言葉は似合わない。
にも拘わらず、今回の今泉作品でもっとも印象に残っているのは性描写である。
なぜだろう。
ゲイ映画をストレート(とくに女子)が見る場合、「いったい男どうしが褥で何を、どうやって致しているの?」的な好奇心があるのは当然であり、BLとかやおいとかの存在もそこに無関係であろう筈がない。わからないもの、自分ではけっして経験で征服することができないものには人間は必要以上にそそられ、ファンタジーすら抱くものだからだ。
が、そうした映像消費者のBL的期待や、それを満足させようとする市場の常識を打ち砕くかの如くに、『すべすべの秘法』の性描写は日常的で当たり前だ。
なんかこう、炬燵で蜜柑を食べているようなセックスシーンなのである。
が、一部のフェティッシュ好きの方々がプロに金を払って行うスペシャル・セッションでもない限り、人間が営んでいる性行為などというものはやはり炬燵で蜜柑を食べているようなものだ。生活の一部であるセックスで、いちいち大袈裟なエロスが毎回展開されることはない。それは性的指向がどうであれ、同じことだろう。
だのにゲイのセックス描写となると、何か特別なもののようにいやらしく美しく演出されたり、激しいもののように描かれがちなのは、それは作り手(&受け手)の意識にそれが「倒錯したもの」だという前提的感覚があるからではないか。
そこへいくと『すべすべの秘法』の性描写は見事なまでに倒錯感がない。ったく人間ってやつは、男女だろうと男男だろうとやることは同じなのねー。と微笑ましくさえなる。この日常的で健康的な性描写は、「倒錯したもの」という暗黙の了解の上に成り立つゲイの性描写へのアンチテーゼではないか。何かそこには、ピンクのバナーを掲げて新大久保の街角に立つ今泉監督の姿が透けて見える気がするのだ。
今日も勤務先の保育園で、子供たちを相手に、「ダディとマミイがいる人、手をあげてー」「はーい」「じゃ、ダディとダディがいる人ー」「はーい」「マミイとマミイがいる人ー」「はーい」「うちのマミイは服を脱いでシャワーする時はダディになるから、どっちなのかわかんない」「うーん、そりゃ微妙だね」みたいな話をしたばかりだ。
わたしの住むブライトンは同性愛者が多い地域ではあるが、英国では、同性愛者の存在はもはや炬燵の上の蜜柑のようなものになりつつある。
日本もそのうち、ある日気がついたらそうなっている。
『すべすべの秘法』の風呂場のラストシーンからはそんな声も聞こえたような気がする。
※第8回ベルリンポルノ映画祭特集プログラム凱旋上映
RETRO 今泉浩一×佐藤寿保
2014年2月5日(水)から8日(土)まで渋谷UPLINKで行われます。
『すべすべの秘法』を含めた4作品に『家族コンプリート』を加えた特別凱旋上映です。
2月8日(土)15:00〜上映後には田亀源五郎×今泉浩一のトークショーがあります。
https://www.uplink.co.jp/event/2013/21607