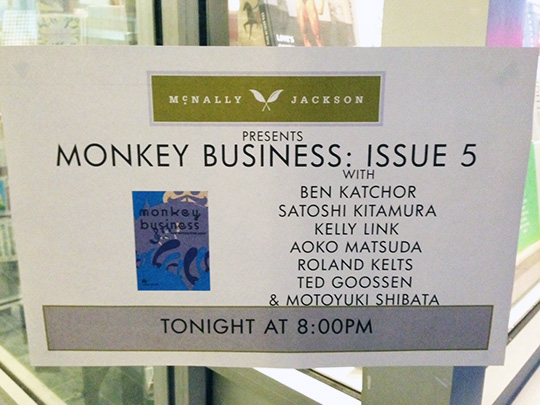Downtown boys ダウンタウン・ボーイズ

photo by Y.Sawai
ダウンタウン・ボーイズは、プロヴィデンス出身のバイリンガル、ポリティカル・サックス・パンク・パーティ・バンドだ。ここ2、3年の間、プロヴィデンスのバンドに関わらず、ブルックリンのローカル・バンドのように、ブルックリンで絶えずライブをやっている。サックス2人、ギター、ベース、ドラム編成で、英語、スペイン語を織り交ぜ、音楽的にはパンク、ロック、ジャズなどをミックス、最高のエネルギーを、純粋な楽しさを、ダンスフロアにぶちまける。
DIY会場から、ラテン・レストラン、ハウス・パーティからSXSWなどのフェスにも出演。真のDIYの彼らが、スクリーミング・フィメールズと同レーベル〈Don giovanni Records〉から、デビュー・アルバム『フル・コミュニズム(完全共産主義)』をリリースした。アメリカや世界での現在の批判的瞬間、産獄複合体、人種差別、同性愛偏見、国家資本主義、ファシズムなど、自分の精神、目、心を閉ざそうとする全ての物を破壊するためのレコードである。
5月15日、レコードリリースを記念し、ダウンタウン・ボーイズのレコ発に行った。ブシュウィックのパリセーズ(https://palisadesbk.com)というDIY会場で、数ヶ前にはダスティン・オングと嶺川貴子やパーケット・コーツなどの新鋭のインディ・バンドがプレイしている会場である。
かれこれ10回ほど見ているダウンタウンボーイズだが、今回のショーは今まで見た中で一番人が多かった。一緒にプレイしたバンドにもよるが、パンク・キッズが多いクラウドで、目の周りを黒く塗っている女の子や、顔中にピアスをしている男の子(タンクトップ率高し)、キスしまくっている女の子たちなど、むせ返った会場の雰囲気に圧倒された。以前、ダウンタウン・ボーイズの別バンド、マルポータド・キッズを見た時と同じ雰囲気、それがさらに倍である。
シンガー、ヴィクトリア・ルイズが、語り(叫び)はじめながらショーはスタート。パンクを注入したギター・ラインとコーラス、伝染性の強いサックス・ライン、ファンキーで不吉なホーン・ラインなど。ダウンタウン・ボーイズの曲は、エネルギーの塊だ。この世代が、時代に風穴を開ける力があることを証明する。彼らこそ、現在の声明である。
ヴォーカルのヴィクトリアは、種差別やその他の差別、政治的なトピックを持ち出し、歌っているのと同じくらい喋ってる(叫んでいる)し、オーディエンスはそれに答え、前の方ではモッシュも起こり、会場全体が彼らのサポーターであるかのようだ。
私自身は政治的な解説を加えるほどの知識を持たないが、この辺りは、アメリカのバンドを色濃く表しているように思える。レコードでこの熱気が伝わるかわからない。彼らが命を懸けているのは、そのパフォーマンスに、そして声を大にして叫びたいメッセージなのは間違いない。
現在の音楽に対して、政治に対して、そして世の中に対する革命を主張する。いちどライヴ体験をすると、頭の中をスカッと風が吹く。彼らは何処でも100%だ。
ダウンタウン・ボーイズのダニエルとノーランは、ホワット・チアー・ブリゲイドという19人バンドでもプレイしている。(https://www.whatcheerbrigade.com)
彼らはビルディング16という会場を運営していたのだが、場所が取り壊されることになった。ラストショーに招待されたのだが、いつ見ても、彼らのストリート・バンドたる精神にど肝を抜かれる。
人数が多いので(19人!)、ステージには入りきらない。フロアはもちろん、天井に通っているパイプによじ登ったり、手狭なステージから降り、マーチングをはじめ、会場の外で演奏を始めたり、お祭り騒ぎがオーディエンスを自然に巻き込むパフォーマンスになっている。
●ビルディング16でのダウンタウン・ボーイズのショーが含まれたプロモ・ヴィデオ:
オフィサーが引張叩かれる度に、裸にされ、最後はバンドで歌ってる。
●Wave of History:アメリカの小学校の社会の教科書に使われるべきだと思う。
さらに、ヴィクトリアとジョーイは、マルポータド・キッズというラテン、エレクトロな別バンドもやっていて、6月全般はイースト・コーストからミッド・ウエストをツアーする。
https://www.facebook.com/MalportadoKids
ダウンタウン・ボーイズと同郷プロヴィデンス出身の、ライトニング・ボルトは偶然にも、ダウンタウン・ボーイズのレコ発パーティの日に、ブルックリンの別会場のウィックでショーをやっていた。悩んで、ダウンタウン・ボーイズのショーに来たのだが、考えてみればダウンタウン・ボーイズとライトニング・ボルトには、たくさんの共通点がある。お互い自分たちの場所を持っていたし(ダウンタウン・ボーイズはビルディング16、ライトニング・ボルトはフォート・サンダー)、レコードよりライヴが一番、現場主義だし、とてつもないエネルギーを発散させるし、ビルディング16のラスト・ライブの時は、ライトニング・ボルトのメンバーも遊びにきていて、彼ら同士も交流がある。プロヴィデンスーブルックリンの関係も踏まえて、ダウンタウン・ボーイズが、彼らの直継承者であることは間違いない。