 MOURN |
この感覚、かつて体験したことがある、と過去の記憶をめぐらしてみて、あ、と思い出した。「僕はペイヴメントとかピクシーズが好きなだけ。ペイヴメントの歌詞をちゃんと理解できたらどんなにハッピーなんだろう! そんな気持ちで曲を作ってバンドで歌って……気がついたらいまここにいる。ほんとにそれだけなんだ」。1995年、最初のアルバム『グランポー・ウッド』を発表したベン・リーに最初に取材をしたときのことだ。彼は当時17歳、どんなにやんちゃな青年なんだろう、と想像して訊ねてみると、好きなバンドの影響を受けて、好きなように自分もギターを手にしてみただけなんだ、というあっけらかんとした回答。そのときの、肩すかしを食らいつつもどこか晴れ晴れとした感覚を、いま、このスペインの若き4人組を聴きながら思い出している。
いや、もしかするとベン・リー以上に冷めているかもしれない。まだ全員10代というスペインはバルセロナを拠点にするモーン。結成からわずか2年でワールド・ワイド・デビュー、さらにはピッチフォークなどのメディアで高い評価を得るにいたった彼らにはたちまちのうちに注目が集まることとなった。パンクやオルタナティヴ・ロックに触発されたというそのスタイルだけ取り出せばたしかに稚拙ではある。成熟という言葉からはほど遠く、演奏を動画などで見るかぎりはあどけない様子も伝わってはくる。だが、どこまでむき出しにするのかと不安にさえなる荒削りな演奏、感情を闇雲に発露させる場所というより、感情を淡々と刻みつける場所といった感じで、不気味なまでに薄暗い表情を時折見せるヴォーカル、どこか冴えない生活や風景をひたすらに言葉に置き換えたような歌詞……これが果たして10代の姿か、と思えるほどに醒めた表情をうかがわせるのも事実。「ペイヴメントの歌詞を理解できるアイツはカッコいいな」と無邪気かつアイロニカルに歌っていたあの頃のベン・リーを部分的に思い出させるが、モーンは根底にもっと切実な何かを抱えている印象さえあるのだ。
とはいえ、今回メールで取材をした際の下記回答を読んでもらえばわかるように、ほとんど難しいことを語らない、語りたがらない。その素っ気ない対応はモラトリアムとも思えるもので、この自我を包み隠したような態度がその成長と同時にどう崩壊し、再構築されていくのかを静かに見守っていたい、と、彼らの親世代である筆者は思うのだった。
■Mourn / モーン
バルセロナを拠点として活動する4人組バンド。〈キャプチャード・トラックス〉とサインし、2015年にファースト・アルバム『モーン』をリリース。デビュー前からメディアの高い評価を受けるなど注目を集めている。
ソニック・ユース、スーパーチャンク、アーチャーズ・オブ・ローフ、サニー・デイ・リアル・エステイト、カーシヴとかみたいな90年代のアメリカのバンドに浸かってたわね。
■あなたがたはまだ15~18歳とのことですが、幼馴染みや学校の仲間同士なのでしょうか? いつ、どのようないきさつでバンドが結成されたのか教えてください。
カーラとジャズ(以下C&J):カーラとジャズは3年前から同じ学校で人文科学を学んでいたの。レイアとジャズは姉妹だからいっしょに育ってきたし、アントニオとジャズは11歳のときからの友だちなのよ。
■あなたがたのホームタウンのバルセロナでは、あなたがたと同じ世代の友だちはどういう音楽をおもに聴いているのですか? スペインのドメスティックな音楽シーンはどういう状況なのでしょう?
C&J:うーん、地元のガレージ・ロックをたくさん聴いたけど、他にも商業的なものとか カタラン・ルンバ(catalan rumba)とかも聴いた……けどやっぱり、わたしたちはソニック・ユース、スーパーチャンク、アーチャーズ・オブ・ローフ、サニー・デイ・リアル・エステイト、カーシヴとかみたいな90年代のアメリカのバンドに浸かってたわね。他にもイギリス、スウェーデン、ベルギー、オランダのバンドも大好き。いまはインターネットがあるから、世界のどこにいてもそういう他国のバンドのレコードやニュースを簡単に見つけることができるでしょ。もちろん、スペインのミュージック・シーンもおもしろい。とくにバルセロナにはたくさんのクールなバンドがいるのよ。なかでもアニミック(Anímic)とBeach Beach(ビーチ・ビーチ)が好きだな。
■わたしがある程度知っているかぎり、スペインには80年代頃から独自のインディ・シーン、インディ・レーベルがあり、日本でも古くは〈エレファント〉や〈マンスター(Munster)〉などがインディ・ロック・ファンの間で人気でした。最近では、〈マッシュルーム・ピロー(Mushroom Pillow)〉というレーベルや、デロレアン(Delorean)、ポロック(Polock)、エル・コルンピオ・アセシノ(El Columpio Asesino)、チャイニーズ・クリスマス・カーズ(Chinese Christmas Cards)などのバンドを個人的にはチェックしています。あなたがたはこうした他のスペインのインディ・ミュージック・シーンの中でどういうポジションにいるのでしょうか?
C&J:私たちは自分たちがバルセロナのインディ・ロック・シーンにいると思っているわ。私たち、町の小さなパブや会場で演奏をはじめたからね。マデイ(Madee)、オハイオス(Ohios)、レッド・ベアズ(Red Bears)、ザ・サワーズ(The Saurs)、ダ・サウザ(Da Souza)などとも共演したのよ。

私たちは自分たちがバルセロナのインディ・ロック・シーンにいると思っているわ。
■スペインには「インディ・ミュージック・アウォード」という賞があるようですが、あなたがたの世代にとってもこうしたアウォードは一つの通過点、目標だったりするのですか? もしくは、もっと現場でホットなヴェニューやギグ、イヴェントやフェスなどがあれば教えてください。
C&J:賞は私たちにとってゴールではないわね。ただ曲を書いて演奏しているときに楽しみたいだけなの。ただ、〈アポロ(Apolo)〉という私たちのお気に入りの会場で演奏するのが本当に好きで、そこで演奏するときは気楽でいられるわ。前回そこで演奏したとき、本当にすばらしく魔法のようで、次にまたあそこで演奏するのが待ちきれないの。あと、〈プリマヴェラ・サウンド(Primavera Sound)〉っていう私たちが 好きなフェスの一つで演奏したときも興奮したわ。バルセロナには他にも〈ソナー〉っていうかっこいいフェスがあるんだけど、こっちはエレクトロ・ミュージック寄りね。
■では、具体的にはどういうバンド、音楽にシンパシーを感じて楽器を手にしたりバンドを組もうと思ったのでしょうか?
C&J:初めてわたしたちをギターを手に取って音楽を作るように駆り立てたのは、パンク・バンド。ラモーンズ、クラッシュ、セックス・ピストルズ……みたいな。私たちは本当にパンク・ミュージックが好きなの。わたしたちがいっしょに演奏をはじめたときは、PJハーヴェイ、ローリング・ストーンズ、ラナウェイズ、クラッシュ、エリオット・スミスなどのカバーをいくつかやっていたわね。でも、最終的に彼らのどういうところにインスパイアされたかっていうと、音と詩の力強さ、彼らが生きていた瞬間、彼らの働き方についての好奇心、彼らのいろいろな考え方、メッセージや彼らの感じ方、わたしたちができる見方、記憶に深く残って、素晴らしい! と思わせるいくつかのコード……それこそさまざまなの。それらのすべてがわたしたちを突き動かし、毎日楽器を弾かせつづけているんだと思うわ。
初めてわたしたちをギターを手に取って音楽を作るように駆り立てたのは、パンク・バンド。ラモーンズ、クラッシュ、セックス・ピストルズ……
■あなたがたが実際にオリジナルの曲を作りはじめたとき、お手本にしたソングライターはいましたか? そして、いまのあなた方が最高と思えるソングライター、コンポーザーは誰ですか?
C&J:そうね、わたしたちはエリオット・スミスのようなリリックや、そしてパティ・スミスのパンク調のポエトリーが本当に大好きなのよ。後は、デヴィッド・ベイザン(ペドロ・ザ・ライオン)やマーク・コズレク(サン・キル・ムーン)なんかも本当にクールなリリックで大好きよ。私たちは物語を作るのが好きで、言葉で生活に対しての感じ方、不安感、いらだたせるものや話したいものについて表現しているの。もちろん、好きな映画や本、写真など影響されたものはなんでも曲にしたいけど、生活の中から感じることを歌にすることが好きなのよ。
■それは、あなたがたの場合、スペインという国、バルセロナという町に暮らす一員としての社会への意識が活動のバネになっているということでしょうか?
C&J:そう。わたしたちはスペインのいまの状況に憤りを感じているわ。でも、政府に代わって主張しているつもりはないし、曲を書き演奏しているときはそういったことは避けているの。ただ、それが好きだからそうしているし、少なくともいままではそれが衝動的だったのは間違いないところ。私たちの必要性が評価されているとして、それがすべて社会に対してのそういう憤りの反映ではないとは思うけど、やっぱり社会に対して何かを感じてしまうのよ。おそらく、いつかわたしたちは音楽とこういう考え方、社会への見方を関わらせていくつもりよ。いままでは私たちはライヴではそういうことをとりあえずいっさい忘れて、演奏を楽しみたかったけど、いつかはちゃんとカタチにしたいわね。
僕たちは偽ることなしに誰よりもいいと思っているし、自分たちの音楽が好き、世界には好きなバンドも多くいるから演奏しているってだけなんだ。
■あなたがたが〈キャプチャード・トラックス〉と契約することになったきっかけをおしえてください。マック・デマルコなど新たな世代のヒーローへのシンパシーもきっかけになりましたか?
C&J:きっかけはブランク・ドッグスのマイク・スナイパー(レーベル・オーナー)がニュースレターで私たちのスタジオでの映像を見てくれてね。興味を持ってくれてたらしいの。で、アルバムが出たときにわたしたちのスパニッシュ・レーベルである〈ソーンズ(sones)〉が連絡してくれたのよ。何が起こるかわからないわ。もし、彼が映像を見てくれてなかったらいまこうやって話せてないわね(笑)。
■そのマック・デマルコには1月に日本に来たときに取材したのですが、そのときに彼はこのように話していました。「チープでロウ・ファイなサウンドにしているのには狙いがある。ウェルメイドな音作りに飽き飽きしてしまったのと、どこか“Weird”な音を出すことそのものが刺激的だから」。では、あなたがたの場合、たった2日間でアルバムを録音してしまうというようなその姿勢に、何か確信犯的な意識はありますか?
C&J:なるほどね。そうね、わたしたちの場合は多くの資金を持っていなかったからっていうのがまず一つめの理由。それとライヴを録音したかったからというのもあるわ。おかげでより楽しく、本当に新鮮で信頼のできるものができた。それはわたしたちのオリジナルなやり方であって、そこにいっさいの策略はないの。たしかにレコーディングはたった2日間だったんだけど充実していたし過不足もなくて。録音はバルセロナと私たちの町に近いアレニス・デ・マルという町の〈ノーチラス(Nautilus)〉というスタジオでしたわ。そこはとても美しくてたくさんのカーペットがあって、本当に高い天井の部屋で。ジャズの父親のバンドのドラマーでもある ルイース・コッツ(Lluís Cots)にプロデュースしてもらって、わたしたちはとても快適な雰囲気の中、作業をしたの。安心していられたわ。
■ピッチフォークでも高い評価を得て、世界規模であなたがたのエネルギーが注目されるようになりましたが、そうした状況の変化についてどう受け止めていますか?
C&J:いやあ、そんな実感もまだわからないし、野望とかを抱くような感情もまだ持っていないんだよ。高い評価をもらってどうですか? って訊ねられることもあるけど……本当にまだ何もわからないんだ。そういうことを考えて活動しているわけじゃないからなあ。ただ、僕たちは偽ることなしに誰よりもいいと思っているし、自分たちの音楽が好き、世界には好きなバンドも多くいるから演奏しているってだけなんだ。






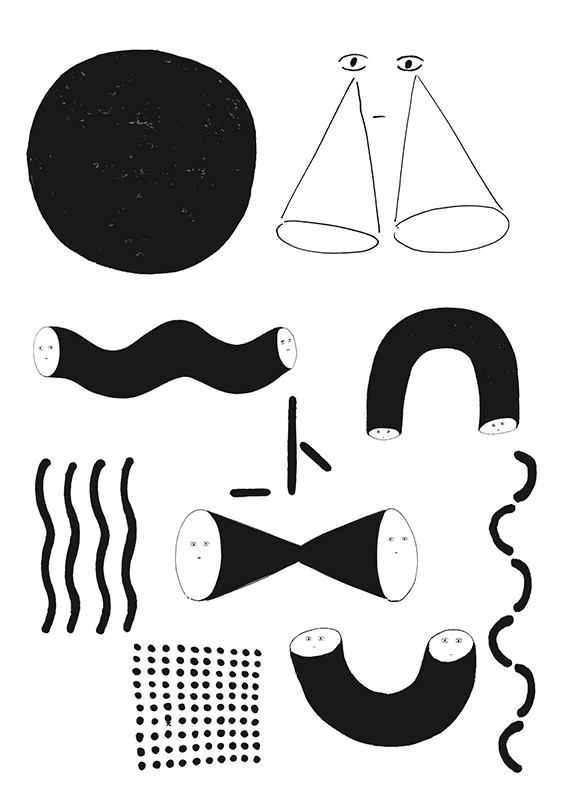
 東京ベルリンを拠点に活躍するアーティスト。写真家、芸妓、ミュージシャン、モデルなど多彩な顔を持つ。自身の日常を幻想的な色彩で切り取る写真やコラージュ、またこうした要素に音楽や立体表現を加えたインスタレーションを発表する。パレ・ド・トーキョーなどの個展、展覧会多数。ボーカルとしてdaisy chainsaw、Panacea、Kai Althoff、Mayo Thompson、Jonathan Bepler、Terre Thaemlitz、秋田昌美、中原昌也となどとコラボレーションする。tony conrad と舞台音楽で共演したり、bernhard willhelmのショウでライブパフォーマンス、そしてJürgen Paapeとカバーしたjoe le taxiはSoulwaxの2ManyDjsに使われ大ヒットした。写真作品集に『ハナヨメ』『MAGMA』『berlin』、音楽アルバム『 Gift /献上』『wooden veil』などがある。ギャラリー小柳所属。
東京ベルリンを拠点に活躍するアーティスト。写真家、芸妓、ミュージシャン、モデルなど多彩な顔を持つ。自身の日常を幻想的な色彩で切り取る写真やコラージュ、またこうした要素に音楽や立体表現を加えたインスタレーションを発表する。パレ・ド・トーキョーなどの個展、展覧会多数。ボーカルとしてdaisy chainsaw、Panacea、Kai Althoff、Mayo Thompson、Jonathan Bepler、Terre Thaemlitz、秋田昌美、中原昌也となどとコラボレーションする。tony conrad と舞台音楽で共演したり、bernhard willhelmのショウでライブパフォーマンス、そしてJürgen Paapeとカバーしたjoe le taxiはSoulwaxの2ManyDjsに使われ大ヒットした。写真作品集に『ハナヨメ』『MAGMA』『berlin』、音楽アルバム『 Gift /献上』『wooden veil』などがある。ギャラリー小柳所属。 音楽家。1990年生まれ。2010年アルバム『剃刀乙女』でデビュー。
音楽家。1990年生まれ。2010年アルバム『剃刀乙女』でデビュー。 tomoyoshi date, hiroki ono, takeshi tsubakiからなるアンビエントバンド。数多の諸概念・主義主張を融解する中庸思想を共有しながら、所作と無為を心がけ活動中。
tomoyoshi date, hiroki ono, takeshi tsubakiからなるアンビエントバンド。数多の諸概念・主義主張を融解する中庸思想を共有しながら、所作と無為を心がけ活動中。 1977年ブラジル・サンパウロ生まれ。3歳の時に日本へ移住。 ロック、ジャズ、ポスト・ロックなどを経て90年代後半より電子音楽を開始。 ソロ作品に加え、Opitope、ILLUHA、Melodiaとして活動するほか、中村としまる、KenIkeda、坂本龍一、TaylorDeupreeとも共作を重ね、世界各国のレーベルから14枚のフルアルバムをリリース。 西洋医学・東洋医学を併用する医師でもあり、2014年10月にアンビエント・クリニック「つゆくさ医院」を開院 (
1977年ブラジル・サンパウロ生まれ。3歳の時に日本へ移住。 ロック、ジャズ、ポスト・ロックなどを経て90年代後半より電子音楽を開始。 ソロ作品に加え、Opitope、ILLUHA、Melodiaとして活動するほか、中村としまる、KenIkeda、坂本龍一、TaylorDeupreeとも共作を重ね、世界各国のレーベルから14枚のフルアルバムをリリース。 西洋医学・東洋医学を併用する医師でもあり、2014年10月にアンビエント・クリニック「つゆくさ医院」を開院 ( イラストレーター。風景やモノを中心に、パターンワークやシンプルな形を使用したミニマルでリズミカルな作画で書籍や雑誌、CDジャケットを中心に活動。また音楽制作会社での勤務経験をもとに、ミュージックガイド「5X5ZINE」の制作/刊行を定期的におこなっている。
イラストレーター。風景やモノを中心に、パターンワークやシンプルな形を使用したミニマルでリズミカルな作画で書籍や雑誌、CDジャケットを中心に活動。また音楽制作会社での勤務経験をもとに、ミュージックガイド「5X5ZINE」の制作/刊行を定期的におこなっている。 餡子作りという限られた材料を元に独自の配合を研究し、日々理想の餡子を模索し続ける小豆研究家、池谷一樹によるケータリング餡子屋。一丁焼きたい焼き屋を目指し日々試行錯誤を繰り返している。今回は最中をまた同時にadzuki名義で活動する音楽家でもある。
餡子作りという限られた材料を元に独自の配合を研究し、日々理想の餡子を模索し続ける小豆研究家、池谷一樹によるケータリング餡子屋。一丁焼きたい焼き屋を目指し日々試行錯誤を繰り返している。今回は最中をまた同時にadzuki名義で活動する音楽家でもある。 手造りどぶろく屋。
手造りどぶろく屋。





