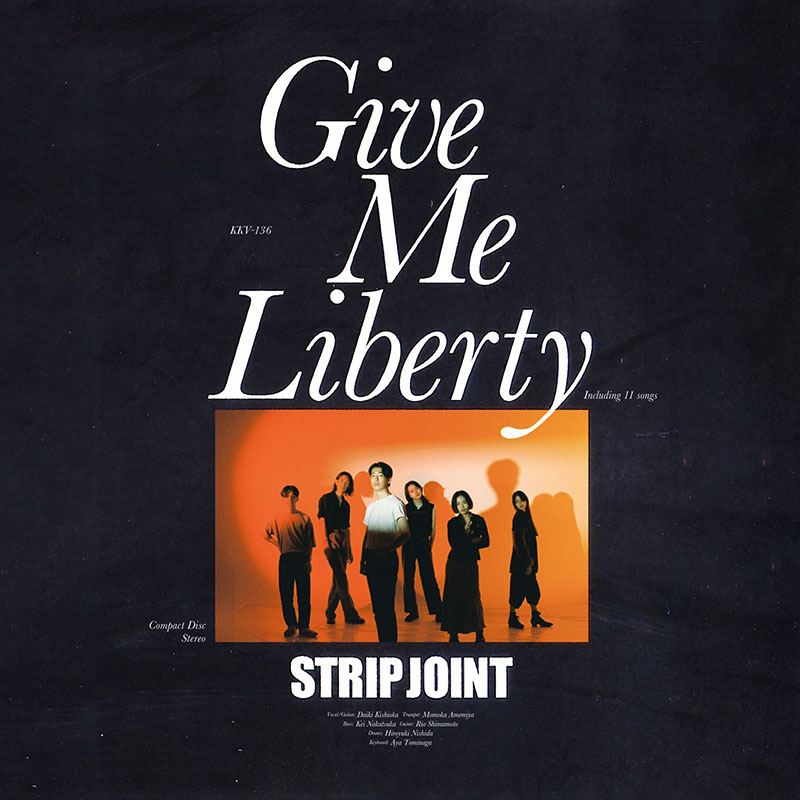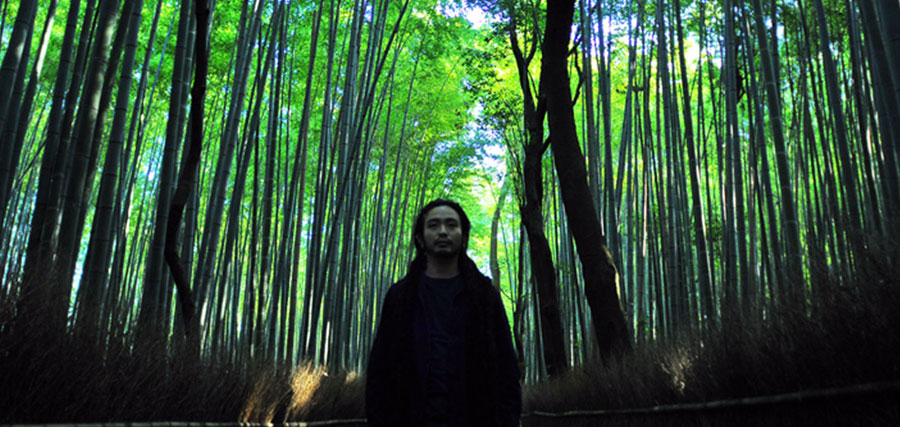現役看護師がコロナ禍で見つめた葛藤の日々
「新興感染症はいつも、医療従事者への差別とセットだ」
平穏だった日常はやがて逼迫する状況に押し流される──ささくれ立つ心、SNSや報道へのとまどいと動揺、恋人や家族への不安、医療現場の崩壊、そして自身も感染
Covid-19、通称新型コロナウイルス感染症、その最前線を経験した現役の医療従事者が思いを綴った手記!
目次
はじめに
第1章 差別
第2章 恋愛
第3章 組織
第4章 感染
第5章 医療崩壊
第6章 記憶
終章
あとがき
著者
1992年生まれ。日本赤十字看護大学卒。
2015年より看護師として急性期病棟に勤務。
手術や抗癌剤治療など、病気や怪我の集中的な治療を必要とする患者のケアに携わる。
2018年に医学書院「看護教育」にて、「学生なら誰でも知っている看護コトバのダイバーシティ」というタイトルで1年間連載を行う。
2020年に晶文社より『医療の外れで──看護師のわたしが考えたマイノリティと差別のこと』を刊行。
本書は2冊目の著書となる。
【オンラインにてお買い求めいただける店舗一覧】
◆amazon
◆TSUTAYAオンライン
◆Rakuten ブックス
◆7net(セブンネットショッピング)
◆ヨドバシ・ドット・コム
◆Yahoo!ショッピング
◆HMV
◆TOWER RECORDS
◆紀伊國屋書店
◆honto
◆e-hon
◆Honya Club
◆mibon本の通販(未来屋書店)
【P-VINE OFFICIAL SHOP】
◆SPECIAL DELIVERY
【全国実店舗の在庫状況】
◆三省堂書店
◆紀伊國屋書店
◆丸善/ジュンク堂書店/文教堂/戸田書店/啓林堂書店/ブックスモア
◆旭屋書店
◆有隣堂
◆TSUTAYA
◆未来屋書店/アシーネ
◆くまざわ書店