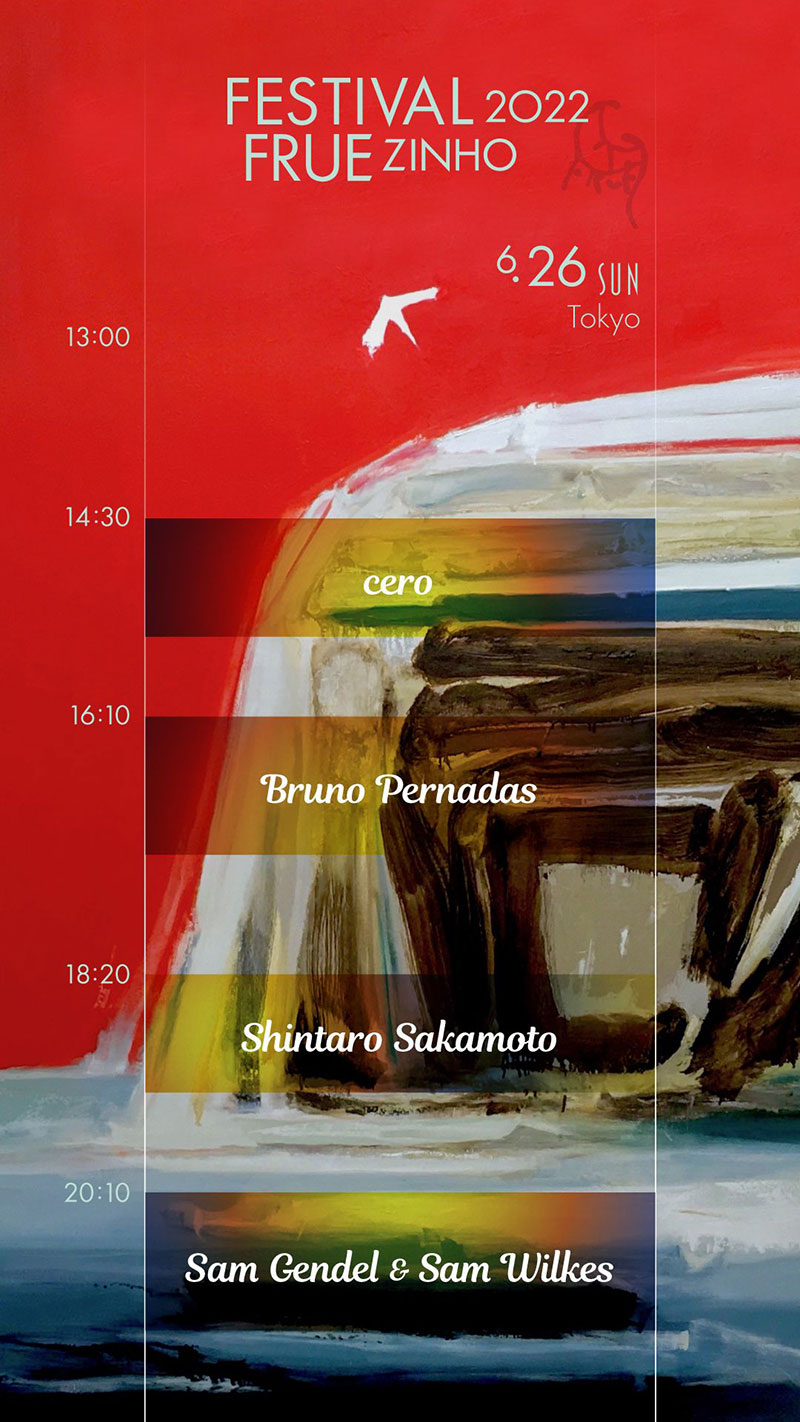近代科学の進歩や哲学は人類のプライドを打ち砕くプロセスでもあった。大きなところだけを言っても宇宙の中心だと思っていた地球は太陽の周りを回っている周辺へと格下げされ、人類も生物の頂点からサルの子孫に降格、主体も歴史も虚妄と退けられ、人類は遺伝子の乗り物に過ぎず、意識はただの錯覚、最近は物理的化学的電気的反応の集合体というところまで転げ落ちてきた。惨憺たるものだけれど、こうしたダウングレードはダーウィンから数えてもたかだか160年の間に起きたことで、短くとって250万年の人類史と比べてもいささか急すぎるし、トランプの支持層が科学を受け入れないのもむべなるかなという気もしてくる。これに追い討ちをかけるようにシオランやショーペンハウアーの思想を再構成してトレンド化しているのが反出生主義で、仏教の一切皆苦ではないけれど、人が生きることは苦しみを伴うとわかっている以上、新たに人類を産むのは悪ではないかという主張につながっていく。反出生主義について、この程度の簡単な説明を聞いたEXIT兼近がアベマプライムで「誰かがひとりでも嫌な思いをするなら人類は存在しない方がいいという考えはリベラル思想の究極(大意)」と咄嗟に解釈し、これはなかなか鋭いと思い、功利主義(最大多数の最大幸福)を理念としている新自由主義に対して全体の平等を理想とするリベラルが底辺にものさしを置くしかないとしているプリンシプルにはやはり考えさせられるものがあった。『ベビー・ブローカー』はそんな世界にまた1人望まれない赤ちゃんが生まれたところから始まる。大雨が降りしきるなか、自分では育てられないと判断した若い母親(イ・ジウン演じるムン・ソヨン)が教会の「ベイビーボックス(赤ちゃんポスト)」に赤ちゃんを置き去りにする。韓国映画でよく見かける急な坂道の上に位置する教会。この「見上げる」という感覚は置き去りにされる赤ちゃんをとても小さなものに感じさせ、ものさしが底辺にあることをそこはかとなく意識させる。印象的なオープニングである。

赤ちゃんが置き去りにされる様子を暗がりで見守っていた2人の女性は1人が母親を追跡し、もう1人は地面に置かれた赤ちゃんを「ベイビーボックス」に入れる。視点は教会の内側に移動し、「ベイビーボックス」から赤ちゃんを取り出したソン・ガンホ演じるハ・サンヒョンと教会でバイトとして働くユン・ドンス(カン・ドンウォン)は監視カメラの映像を消去して赤ちゃんがいた痕跡を消し、そのまま赤ちゃんを連れ去っていく。赤ちゃんを「ベイビーボックス」に入れた女性は車で2人の跡をつけていく。(以下、設定バレ)2人の女性は刑事で、2人の男たちが赤ちゃんを誰かに売り飛ばす現場を現行犯で抑えようとしているのだということがだんだんとわかってくる。翌日になって気が変わったムン・ソヨンは赤ちゃんを返せと2人に詰め寄るが、売れば大金になるし、山分けしようという提案に説得されて一緒に赤ちゃんの買い手のところへ行くことにする。そして、これが思いのほか長い旅となってしまう。是枝裕和という才能が海外に流出した作品である『ベイビー・ブローカー』はゆっくりとした変化に重きを置いたロード・ムーヴィーで、そのせいか、韓国映画として観るとやはり薄い。韓国映画に特有の畳み掛けるようなエピソード群とは異なり、「空気」や「間」が多くの時間を占め、押しつけらるよりも察することで成り立つ場面が多いからである。ぺ・ドゥナ演じるアン・スジン刑事が張込みを続けながら車のウインドウについた花びらを指先で移動させ、車のなかに落とす場面などはとても印象的で、そうした部分はそれこそ邦画を観ているようだし、なんというか、ユニクロの韓国支店で高機能ウェアを買っているような気分というのか、店内の会話はすべて韓国語だし(日本語字幕ということ)、入れ物と中身がズレたままの感じは最後まで持続する。

是枝作品の多くはこれまで社会から隔離された集団性を描くことに何度か関心を示してきた。『Distance』のカルト集団、『誰も知らない』の放置された兄弟たち、『万引き家族』の疑似家族(この言い方は家族が正統で、そのイミテーションのような響きを帯びてしまうけれど、ほかにわかりやすい表現が思いつかないのでこのまま使う)。『ベイビー・ブローカー』の主役たちもやはり社会からは隔離された存在であり、ローソン・マーシャル・サーバー監督『なんちゃって家族』(13)と同じように意味もなく過ごしていた時間のなかで奇妙な紐帯が生じていく。そして、その関係性が家族性を帯びてくるという意味で『ベイビー・ブローカー』は『万引き家族』の前日譚のようであり、国家の下部組織にはならない集団性のあり方が通底している。『ベイビー・ブローカー』に疑似家族という性格を発生させる大きな要因は集団で赤ちゃんの面倒を見ることにあり、そのなかでシングルマザーの子育てがどれだけ孤独な作業であったかが切実に浮かび上がってくる。表向きはクリーニング店を営むハ・サンヒョンがいつもの習慣で、ボタンの取れていたムン・ソヨンの服を繕い、ほいっと気軽に手渡すシーンは象徴的である。たったそれだけのことも他人からしてもらうことがなかったムン・ソヨンは予期せぬことに動揺し、イ・ジウンはそうした心の動きを1ミリも体を動かさない演技で観客に伝える。これは名演だった。

是枝作品はまた複数の家族構成を組み替えるというアプローチもこれまでに何度か繰り返している。『そして父になる』や『海街Diary』はそのヴァリエーションで、家族の組み換えがそんなに簡単なことではないことを主題化してきた。『ベイビー・ブローカー』が飛躍するのは、こうした組み換えを同じ時間軸ではなく、異なる時間軸で試みたことにある。(以下、ネタバレ)赤ちゃんを売ることに失敗したユン・ドンスは自分がいた孤児院に車を向け、自らも孤児院の門前に捨てられていたことをムン・ソヨンに明かす。ユン・ドンスは作品の冒頭で教会に赤ちゃんを置いていく母親たちに強い怒りを示し、おそらくはその怒りが赤ちゃんを売り飛ばすモチヴェーションへと転化されていたのである。作品のクライマックスでユン・ドンスは捨てられた赤ちゃんの立場からムン・ソヨンの行為を許すと告げる。いくらシングル・マザーやシングル・ファーザーが1人で子どもを育てられず、それを国家のせいにしたとしても、やはり捨てられた子どもの気持ちが捨てた親へと向かうのは必定である。そして、捨てられた子どもと捨てた親の連鎖をメリーゴーラウンドという無限ループとダブらせて表現する是枝も残酷である。「許す」というひと言でユン・ドンスはメリーゴーラウンドから降りられる糸口をつかめたのかもしれない。しかし、ムン・ソヨンはどうしたって取り残される。ムン・ソヨンは警察と通じて赤ちゃんの取引現場にアン・スジン刑事たちを踏み込ませる。

是枝作品にはいつも最後のところでしっくりこないところが残ってしまう。『ベイビー・ブローカー』では部屋を暗くするシーンが説明的過ぎて(邦画として観るなら)くどいと思ってしまったし、ハ・サンヒョンたちは金遣いが荒すぎてシングル・マザーの苦境がどこか薄まって見えてしまった。リサーチ不足なのか是枝の金銭感覚はどうもリアリティがなく、『万引き家族』も、西友なら48円で買えるコロッケを冒頭で90円も出して買うので、なかなか貧困マインドには入り込めなかったし、『万引き家族』が「函館3部作」など若手の問題意識にのっかってつくられたと言われても仕方がない面はある。『三度目の殺人』は音楽がこの場面はこういう感情で観ろと命令されているみたいでどうしても抵抗があり、『歩いても 歩いても』も最後のナレーションさえなければ……等々。『ベイビー・ブローカー』も決定的なのはムン・ソヨンはヤクザの親分を殺してその妻に殺害を指示されていたにもかかわらず、3年の刑期を終えて外に出てきても復讐されるどころかガソリンスタンドで働いていたりして、その間にヤクザの組織が壊滅したとか、なにかヤクザに狙われる理由がなくなったという説明がないこと。そのせいで、そもそもあの話にヤクザを絡める必要はあったんだろうかとさえ思ってしまった。それこそエンディングをハッピー・エンドと取るかバッド・エンドと取るか、それは観客の自由だという流れにする布石だったのだろうけれど、僕としてはその直前でつまづいてしまった感じ。アン・スジン刑事が浜辺で成長した子どもと遊ぶシーンは前述した花びらのシーンとうまく呼応していてとてもよかっただけに、そういうところが、なんというか、いつももったいない。

反出生主義はそれなりに体系化された思想であり、キリスト教が苦しみを肯定してきた思想だと思うと、信仰心が薄れてきた時代には相応の説得力があるし、この60年間で30億から78億人に倍増してしまった人類に「生まれてくる」ことがそれだけで祝福されるという感覚が今後も維持されるかどうかは未知数だと思う。生まれたことを肯定するのはそう思いたいだけではないかと言われれば、どんな反論が期待できるというのか? 地球はそろそろ人間が住むには適さなくなってきたし、次の生物に地球を譲った方がいいんじゃないかと考えている人だって少なからずいることだろう。反出生主義が宗教的なものの考え方と入れ替わりかねない時代に『ベイビー・ブローカー』はひとつの問いであり、誰かと言い争うには格好の材料である。是非、自分とは意見の違いそうな人を誘い、内容について議論をしてみて欲しい。「時間」が「異なる立場」を結びつけるという意味ではとても良い作品だから。なお、同作品からソン・ガンホがカンヌの最優秀男優賞を受賞していたけれど、どう見てもユン・ドンス役を演じたカン・ドンウォンの方が熱演ではなかったかと思う。また、本職はシンガーソングライターだというイ・ジウンはどうしても『万引き家族』の松岡茉優に見えて仕方がなかった(素朴な疑問だけれど、闇で赤ちゃんを買った夫婦って、その子どもの戸籍とかはどうするのかな?)。








 在りし日のタンツムジークのふたり。左にアキヲ。右にオキヒデ。アトム・ハートが好きだったから〈ライジング・ハイ〉に決めたという、その頃のアーティスト写真。
在りし日のタンツムジークのふたり。左にアキヲ。右にオキヒデ。アトム・ハートが好きだったから〈ライジング・ハイ〉に決めたという、その頃のアーティスト写真。 フェリーに乗って大阪から福岡に向かうふたり。「オッキー、今度せっかく九州行くから、フェリーのらへん? 楽しいやん」
フェリーに乗って大阪から福岡に向かうふたり。「オッキー、今度せっかく九州行くから、フェリーのらへん? 楽しいやん」 2019年ぐらいのふたり。
2019年ぐらいのふたり。