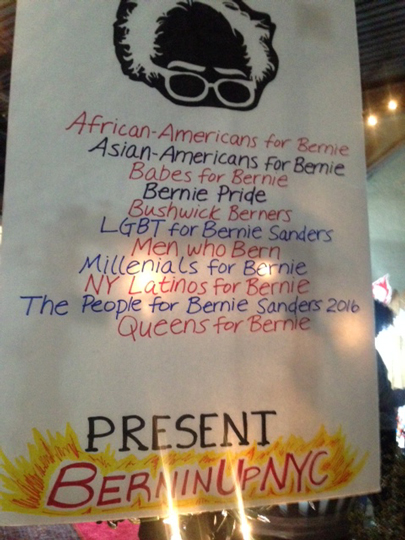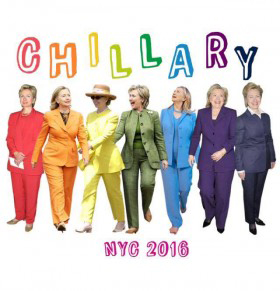3月末に首相官邸で行われたアベとムガベの握手がまるで独裁政権の契り合いに見えてしまったからではないけれど、ムガベ大統領が30年以上も牛耳るジンバブエにルーツを持ち、父親がンビラ(親指ピアノ)奏者としてマリンバ・アンサンブルを率いていたテンダイ・マレーアと、コンゴに起源を持つらしきフセイン・カロンの2作目を。マレーアはディゲブル・プラネッツのシュマエル・バトラーとスター・ウォーズ由来らしきシャバズ・パレシィズとして〈サブ・ポップ〉からも2枚のアルバムをリリースしてきた成長株。ユニット名に使われているチムレンガとは戦いとか抵抗といった意味らしく、近年は人権や社会正義を示すようにもなっているという(タイトルの「銃を持った女たち」とは橋元さんのことだろうか?)。
2年前のデビュー・アルバムはそれこそシャバズ・パレシィズに作風も近く、マルカム・マクラーレンを思わせるシャンガーンなどもありつつ全体としてはヒップホップの範疇に留まるものではあった(映像も楽しめる→https://www.youtube.com/watch?v=2ChY5_uSR-8)。それが、ここではジャケットに貼られたステッカーでも強調しているようにジンバブエのビートとコンゴのギター奏法が前面に押し出され、US風のヒップホップはかろうじて殻を残しているだけに過ぎない。セネガルのヒップホップなどはあまりにもアメリカのコピーでしかなく、アフリカの遺伝子がむしろ移民先で花開くという図はダンス・ミュージック全体に見通せることとはいえ、これだけ面白い例はなかなかないかもしれない。レーベル・サイドはこれに「アフロ-フューチャリスト・ヒップホップ」というレッテルを与えている。
透明度の高いギター・サウンドが終始、明るいムードを呼び込むのに対し、歌詞はかなり政治的らしく(それはムガベに対するもの? それともアメリカ?)、「およげ!対訳くん」とかで取り上げてくれないかなーと。前作同様、宇多田ヒカルが絶賛していたジーサティスファクションからサッシー・ブラックもMCで参加。アナログ・オンリーのようで、ダウンロード・コードが付いてます。
アフリカついでに、ドミューンでもけっこう受けたゴールデン・ティーチャーのメンバーが参加したグリーン・ドアー・オールスターズのデビュー作も。これはグラスゴーとガーナ、そして、ベリーズ(旧英領ホンデュラス)から複数のグループが混在としたセッション・バンドで、どうやら主導権を握っているのはグラスゴーのグリーン・ドアーというスタジオ(〈ZEレコーズ〉からマイケル・ドラキュラの名義でアルバムをリリースしていたエミリー・マクラーレンがプロデュース)であり、同じくグラスゴーのハントリーズ&パーマーズ(『クラブ/インディレーベル・ガイドブック』p.55)から主宰のアウンティ・フローやオプティモのJ・D・トウィッチが最終的に宅で仕上げているという過程はどうしてもエイドリアン・シャーウッドのニュー・エイジ・ステッパーズを想起させる。ただし、レゲエではなくアフリカ。アリ・アップの役回りはやはりゴールデン・ティーチャーのキャシー・オージでしょうか。
オープニングからしばらくはイメージ通りのアフリカ音楽が続き、だんだんダブを多用したり、クラブ的なスキルが比重を増してくる。エンディング近くになってくると、パーカッションの刻み方だけでアフリカ音楽を感じさせるだけで、チムレンガ・ルネッサンス同様、形式性はどんどん希薄になっていく。どこまでやったらレゲエとは呼ばれなくなるかという問いがニュー・エイジ・ステッパーズに存在していたとしたら、同じことがここではアフリカ音楽によって行われていることは間違いない。時にハンドクラップだけ、ハットとコーラスだけでアフリカがそこに立ち現れてくる。
ハドソン・モホークやラスティといったベース系だけでなく、グラスゴーといえばメアリ・スチュワート人気といい、スコットランドの独立騒ぎであれだけ高揚したんだから、面白い音楽が出てこないほうがおかしいともいえるけれど。