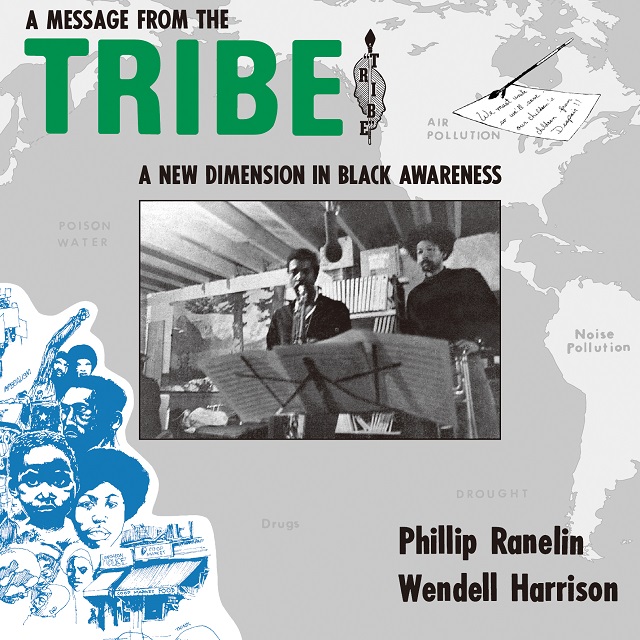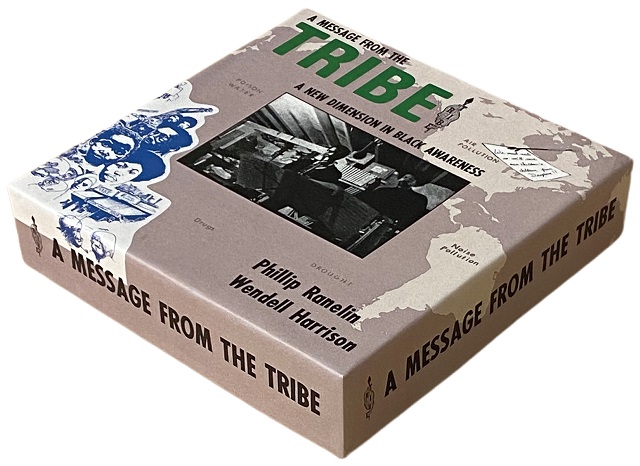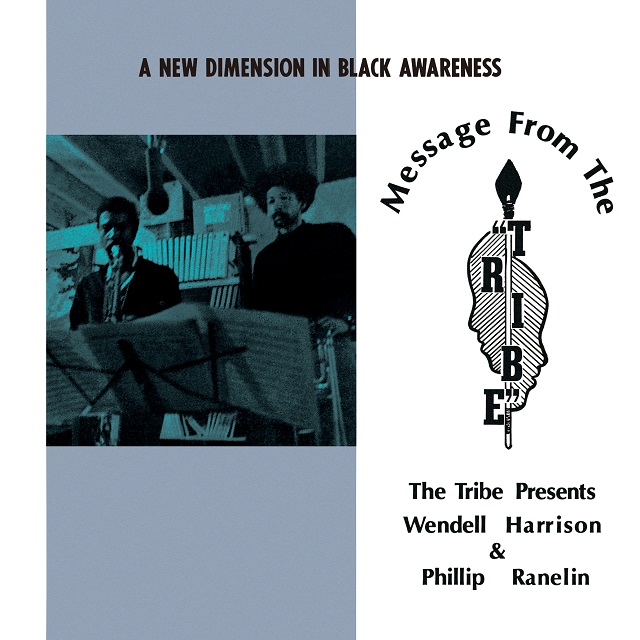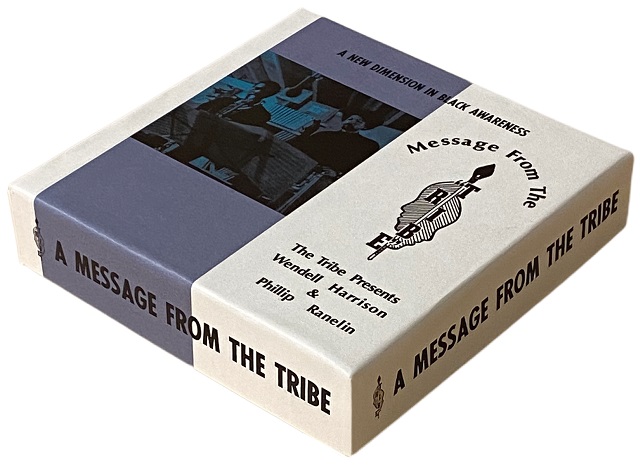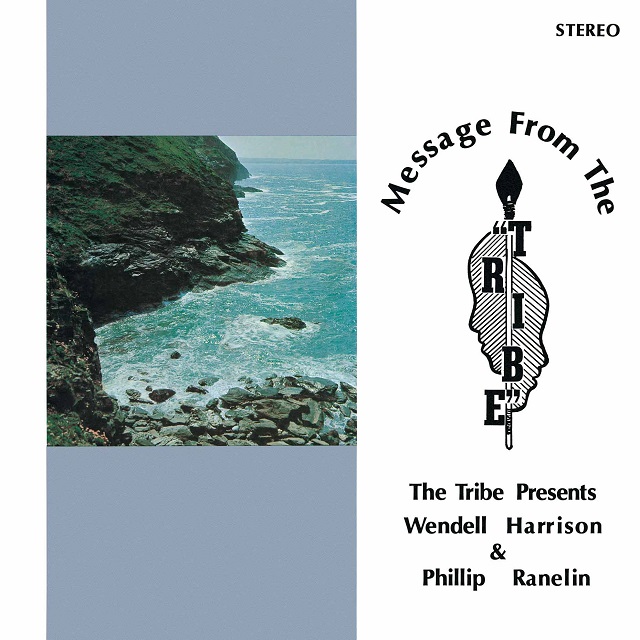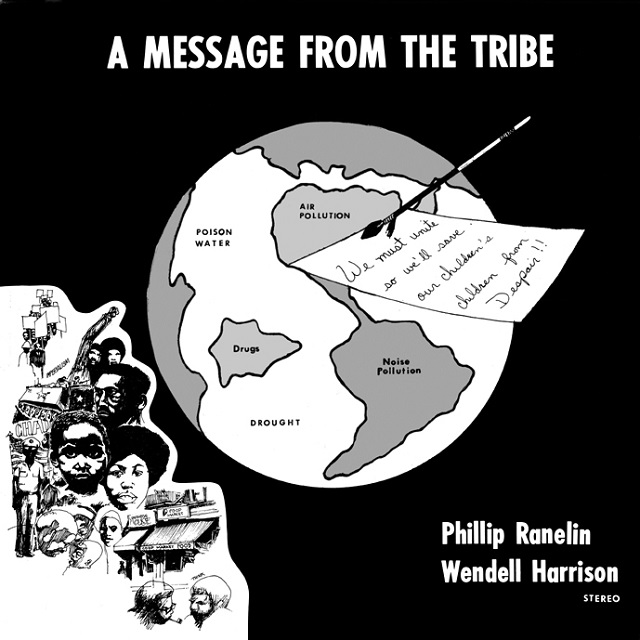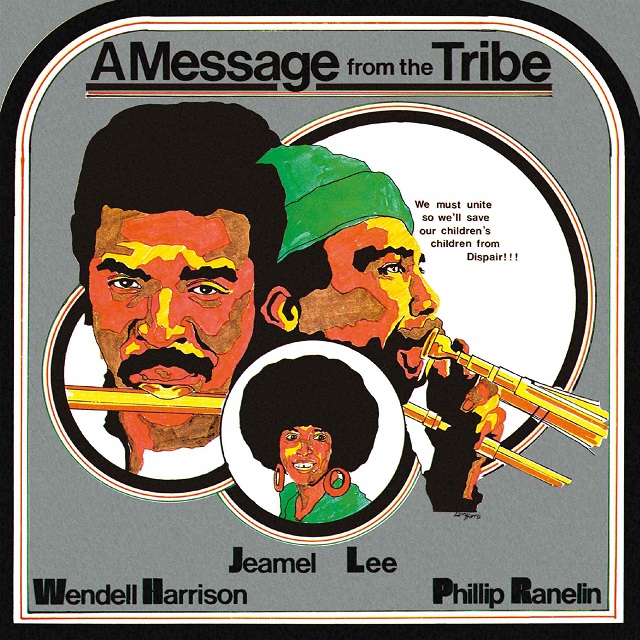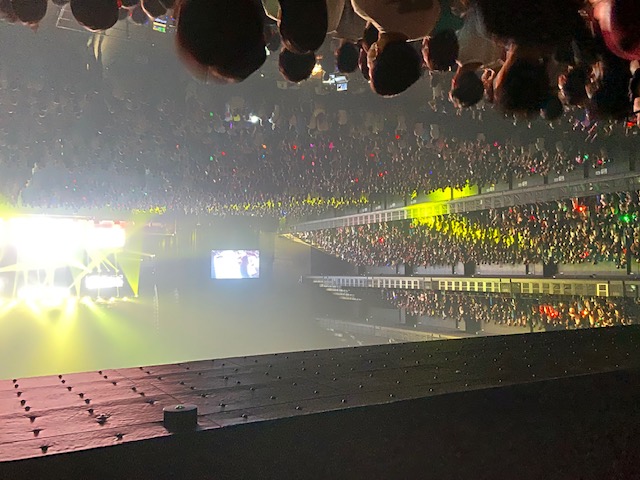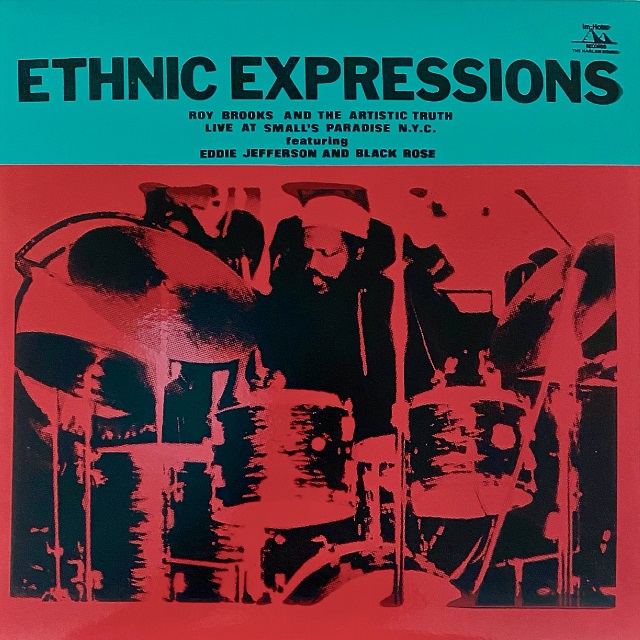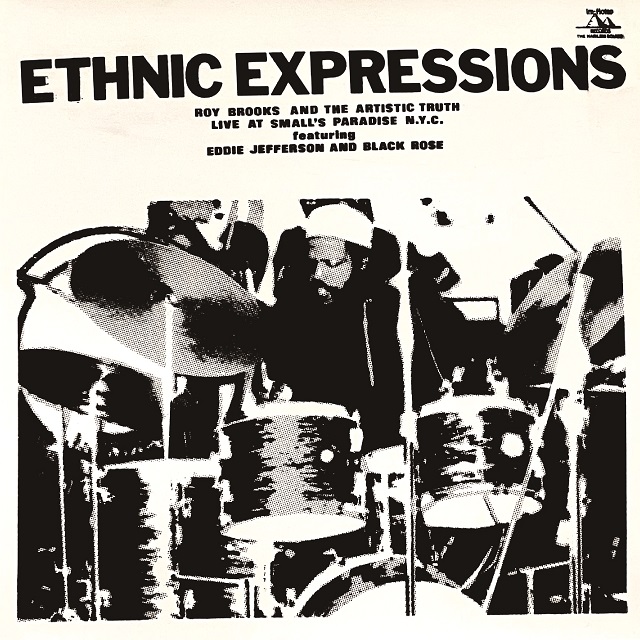今年頭、ひさびさの長尺作品となる「Antidawn」をリリースし話題をさらったベリアル。本日10月21日、また新たな音楽が発表されている。「Streetlands」と題された3曲入りのEPで、レーベルはおなじみの〈ハイパーダブ〉。ビートはほとんどなく、どうやら「Antidawn」の続編的な位置づけの作品のようだ。年明け1月27日にはヴァイナルも予定されているとのこと。

artist: Burial
title: Streetlands
label: Hyperdub
release: 21st October, 2022
tracklist
1. Hospital Chapel
2. Streetlands
3. Exokind