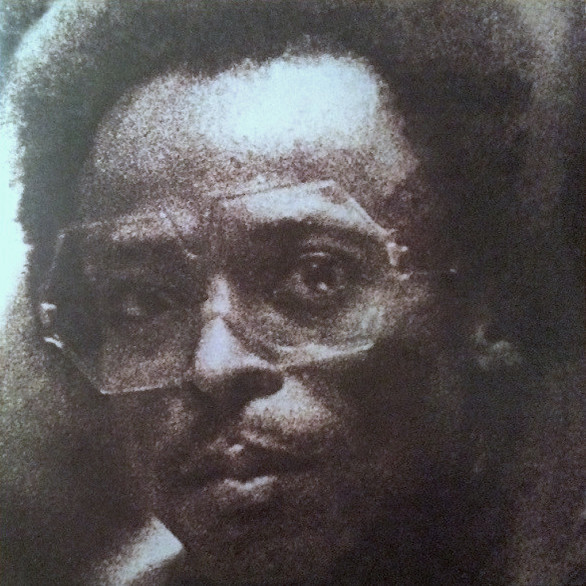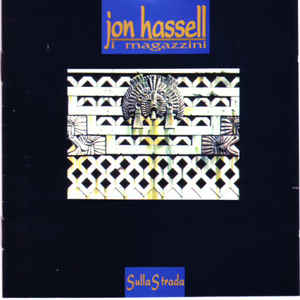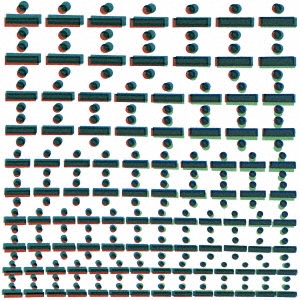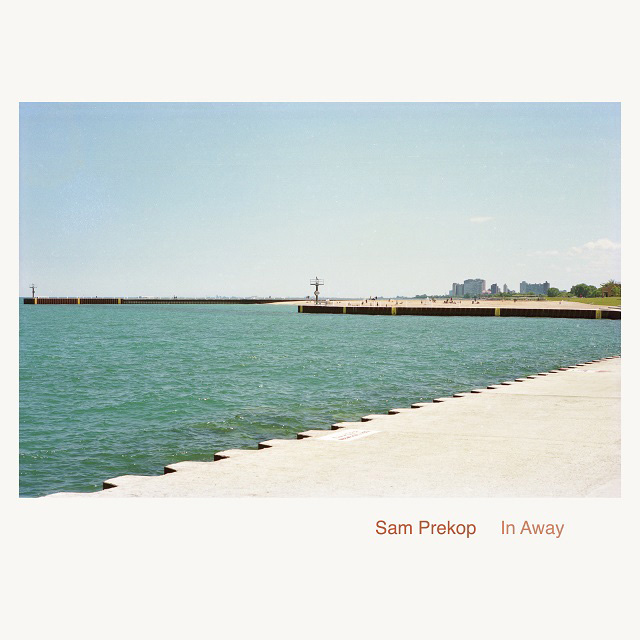ベルリンの〈PAN〉と、ウガンダはカンパラの〈Hakuna Kulala〉(〈Nyege Nyege〉のサブレーベル)が手を組んだ。『KIKOMMANDO』と題された新プロジェクトは、カンパラのシーンを新たな角度から切りとるもので、音源に加え写真やMVもその一環に含まれる模様。
8月6日にリリースされるミックステープには Blaq Bandana や Ecko Bazz、Swordman Kitala や Biga Yut といった〈Hakuna Kulala〉のアーティストが参加。〈PAN〉の STILL が全曲のプロデュースを担当している。STILL ことシモーネ・トラブッキは、かつてザ・バグが先鞭をつけたエレクトロニック・ミュージックとダンスホールの折衷を継承する音楽家で、2017年の『I』が話題となった人物だ。
それは対話だった、とトラブッキは今回のプロジェクトについて述べている。「シンガーたちに自信を持ってもらえるような音楽的土台をつくると同時に、わたしは彼らに挑戦もした。一緒に仕事をすることはアイディアを加速させ、発明というものがひとりだけでできるものではないことを明らかにする。それこそ『KIKOMMANDO』がわたしにとってアルバムでなく、ミックステープである理由だ」とのこと。
現在 Ecko Bazz の “Ntabala (Rolex Riddim)” が公開中。他の曲も楽しみです。

V/A (Prod. by STILL)
Title: KIKOMMANDO
Format: Digital mixtape / Book
Label: PAN / Hakuna Kulala
Cat. No: PAN 124 / HK029
Release date: 6 August 2021
01. Blaq Bandana – Nkwaata (Prod. by STILL)
02. Ecko Bazz – Ntabala (Rolex Riddim) (Prod. by STILL)
03. Swordman Kitala – Rollacosta feat. Omutaba (Prod. by STILL)
04. Biga Yut feat. Florence – Ntwala (Prod. by STILL)
05. Biga Yut – Tukoona Nalo (Prod. by STILL)
06. High Cry Interlude (Prod. by STILL)
07. Jahcity – Njagala Kubela Nawe (Prod. by STILL)
08. Biga Yut – Plupawa (Prod. by STILL)
09. Winnie Lado – The Race (Prod. by STILL)
10. Florence – Bae Tasanze (Prod. by STILL)
11. Jahcity – Tukikole Nawe feat. Omutaba (Prod. by STILL)
12. Winnie Lado – Ahlam Wa Ish السماء هي الحد (Prod. by STILL)