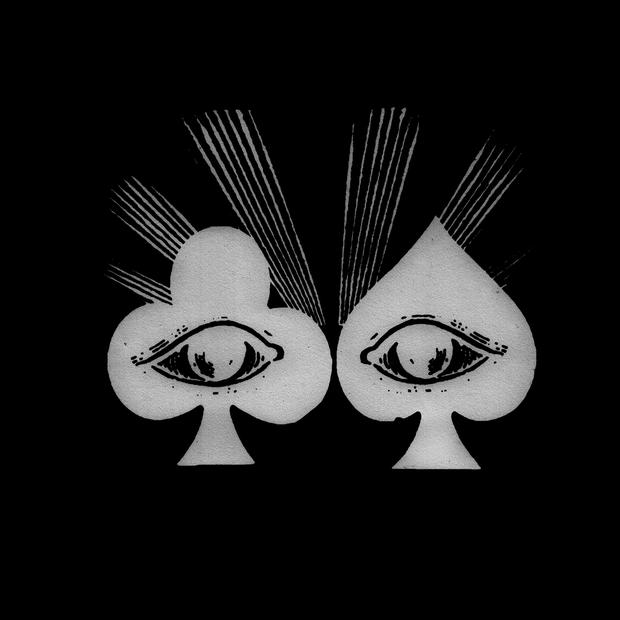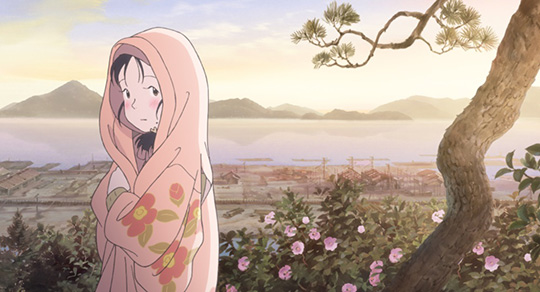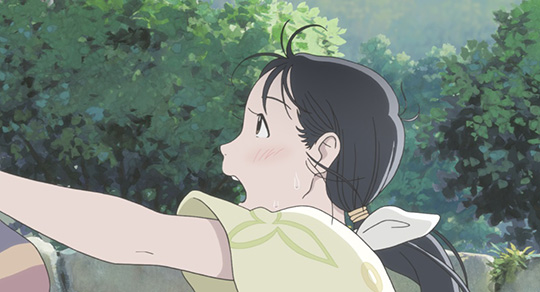いよいよ迫ってきました。昨秋ジェフ・ミルズにジャックされていたele-king編集部ですが、ふたたび彼の周囲が騒がしくなってきています。2月22日にポルト・カサダムジカ交響楽団との新作『Planets』をリリースするジェフ・ミルズですが、それとほぼ同じタイミングで来日公演もおこなわれます。同公演はイタリアの若き指揮者アンドレア・バッティストーニ、そして東京フィルハーモニー交響楽団とのコラボレイションで、2月22日に大阪フェスティバルホール、2月25日に東京Bunkamura オーチャードホールにて開催されます。
そしてこのたび、公演当日の演目が発表されました。ジェフ・ミルズ自身の新曲に加え、ジョン・アダムス、ドビュッシー、リゲティ、黛敏郎、となかなか挑戦的な名前が並んでおります。以下、湯山玲子さんによる楽曲解説とともに、詳細をご確認ください。
ジェフ・ミルズ×東フィル×バッティストーニ来日公演、演奏演目を発表!
2月に大阪・東京で開催されるジェフ・ミルズと東京フィルハーモニー交響楽団とのコラボレーション・コンサートの演奏曲目が明らかにされた。
同公演では2月22日にリリースされるジェフが初めてオーケストラのために書きおろした新作“Planets”の世界初披露が既にアナウンスされている。この新作に加え、公演テーマである「体感・宇宙・時間」を大いに感じさせてくれ以下の4曲が追加発表された。
“Short Ride in a Fast Machine”(ジョン・アダムス)
テクノの得意分野であるミニマルに、クラシックの世界でアプローチを続けている近代作曲家、ジョン・アダムスの作品。オーケストラにおけるミニマル・ミュージックの音響が堪能できる。リズム感覚、速度など演奏者にとっては難易度が高いと言われるこの難曲を指揮者のバッディストーニがどう対峙するかが注目される。
“月の光”(ドビュッシー)
印象派ならではの浮遊感と映像的な美しさに溢れた、誰もが一度は耳にしたことがあるピアノの名曲。今公演ではオーケストラ編曲ヴァージョンで披露。
“ポエム・サンフォニック(100台のメトロノームのための)”(リゲティ)
作年の公演では4分33秒間無音が続くジョン・ケージ“4分33秒”が披露され大いに話題となった。爆クラ! presentsならではの「問題作」実演コーナーは今回も健在。演奏されるのはハンガリーの作曲家リゲティ・ジェルジュの100台のメトロノームを使った「問題作」。
“BUGAKU(舞楽)より第二部”(黛敏郎)
声明や雅楽など、日本の伝統的音楽の響きとテクスチャーを交響曲に意欲的に取り組んだ黛敏郎の代表的作品のひとつ。イタリアの若き天才指揮者バッティストーニと、デトロイト・テクノDJのジェフ・ミルズふたりの感性が、日本の音楽が持つ独特のタイム感や響きをどう捉えていくか。本公演のハイライトともいうべき作品だ。
ジェフ・ミルズ×東京フィルハーモニー交響楽団×バッティストーニ。3者のスリリングなコラボレーションは2月22日(水)に国内屈指の音響空間でもある大阪・フェスティバルホールで、東京公演は2月25日(土)に渋谷・Bunkamura オーチャードホールで開催される。
【公演概要】
『爆クラ! presents ジェフ・ミルズ×東京フィルハーモニー交響楽団×バッティストーニ クラシック体感系Ⅱ -宇宙と時間編』
大阪公演(会場:フェスティバルホール)
日時:2017年2月22日(水) 18:00開場/19:00開演
東京公演(会場:Bunkamura オーチャードホール)
日時:2017年2月25日(土) 17:30開場/18:00開演
チケット価格(税込/大阪・東京共通):SS席8,800円/S席7,800円/A席6,800円
出演(大阪・東京共通):
DJ:ジェフ・ミルズ
指揮:アンドレア・バッティストーニ/オーケストラ:東京フィルハーモニー交響楽団/ナビゲーター:湯山玲子
演奏予定曲目(順不同):
※ Planets / ジェフ・ミルズ
※ Short Ride in a Fast Machine / ジョン・アダムス
※ 月の光 / ドビュッシー
※ ポエム・サンフォニック(100台のメトロノームのための) / リゲティ
※ BUGAKU(舞楽)より第二部 / 黛敏郎
【公演オフィシャルサイト】
www.promax.co.jp/bakucla/02
【ジェフ・ミルズ / CD『Planets』】
https://www.umaa.net/what/planets.html
【ジェフ・ミルズ / “Planets”Playlist】
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOvRZEHpi-uYHbnM_tIam0QKs_ameLSlt