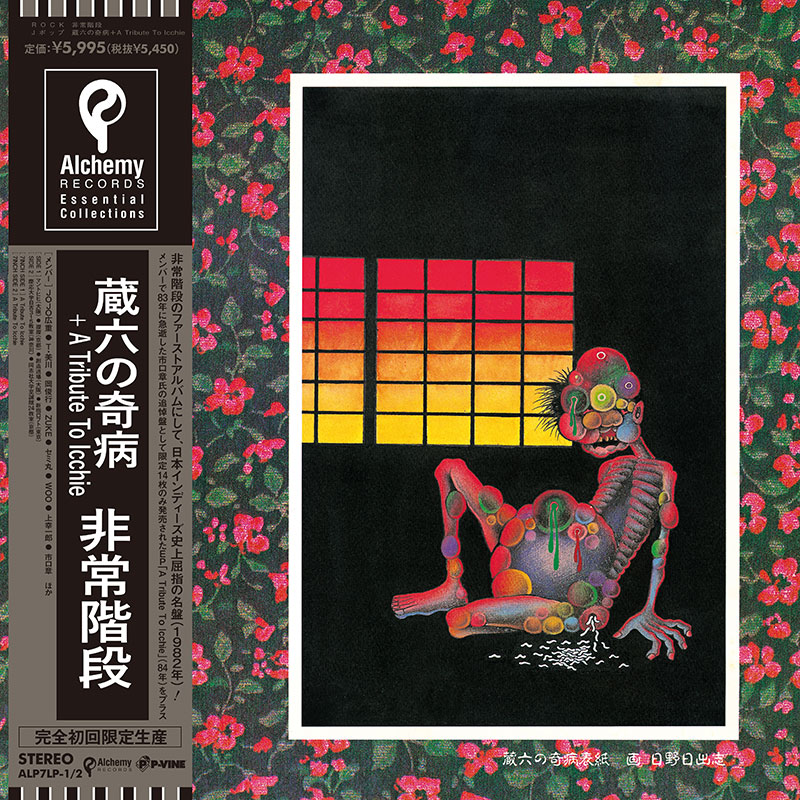ジェフ・ミルズが『メトロポリス』をリリースしたのは2000年のこと。ダンスフロアに近しいテクノ・アーティストが “コンセプト・アルバム” をリリースすることがまだ珍しかった時代で、その後立て続けにアルバムを発表するジェフ・ミルズだが、じつは4枚目のアルバムだった。またそれは、1927年のドイツで制作されたSF映画の古典に新たな音楽を加えるという、じつに大胆な試みでもあった。
リリース当時、ジェフの音楽付きの上映会が青山CAYで行われたことを思い出す。テクノロジーとロボット、メトロポリスの支配者、そして上流階級と労働者たちに階層化された社会を描いたこの映画にジェフのエレクトロニック・サウンドが重なると、それはたしかに現代のメタファーとなりうる。
2000年にリリースされ、2010年にいちどリイシューされたこの『メトロポリス』が、この度『メトロポリス・メトロポリス』としてまったく新しく制作され、3月3日に〈アクシス〉よりリリースされる。
『メトロポリス』は、オリジナルは147分の大作だったが、フリッツ・ラングの意思とは関係なく、商業的な理由でこれまで勝手に縮められて(エディットされて)、上映されてきている。が、しかし、2010年に失われたフィルムが見つかり、完全復刻したのだった。それで、シネミックスのイベントを依頼されたことをきっかけに、ジェフがあらたに作り直すことになったという。なので、じっさいに制作した音源は147分あるそうだが、リリース用に収録曲は編集されている。それでもアナログ盤で3枚組だが。また、ブックレットではTerry Matthewというシカゴのジャーナリストが素晴らしい文章を寄せている。いま混乱し、階層化され、映画のようにいつ労働者たちの反乱が起きてもおかしくないこの世界で、なぜ『メトロポリス』なのかを、みごとに理論づけている。そう、これは注目のリリースなのだ。
(ちなみに同古典SF映画はテクノ・アーティストに人気で、ジョルジオ・モロダーはリメイク版『メトロポリス』の音楽を手がけ、クラフトワークは “Metropolis” 、クラスターのメビウスは『Musik für Metropolis』を作っている)

Jeff Mills
Metropolis Metropolis
Axis Records
日本のレコード店には、3月下旬にアナログ盤、CDが発売される