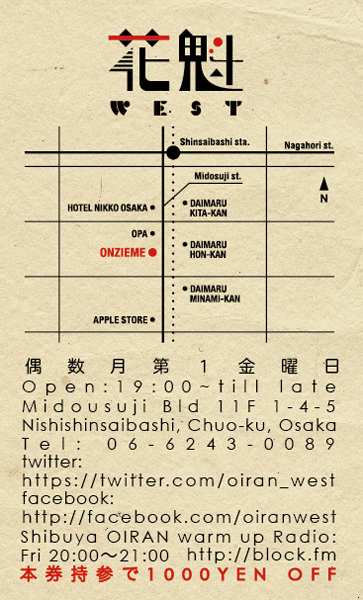Daphni - Jiaolong Merge/ホステス |
『スイム』で感心したことは、それがダンス・ミュージックであること以上にエクスペリメンタル・ミュージックとしての面白味があったことだ。
ジミ・ヘンドリックスはその昔、水中で音がどのように響くのかに興味をふくらませたあまりアンプごとバケツのなかに沈めたというが、水中の音体験を空想して作ったという『スイム』は、録音も凝っていて、身軽で心地よい体験だった。僭越ながら言わしてもらうと僕は水泳も好きで、昨年はwhy sheep?と50メートル自由形で勝負して勝った(まあ、どちらも遅いということでもある)。『スイム』は真剣勝負というよりも水遊びに近い。アーサー・ラッセルの歴史的名曲"レッツ・ゴー・スウィミング"の現代版である。
カリブー名義で昨年発表したその『スイム』は、2011年、ほぼすべてのメディアから賛辞された。カリブーは、そして、リミキサーとしてもレディオヘッド、ジュニア・ボーイズ、それからジャイルス・ピーターソンにまで引っ張られている。かつてマニトバ名義でIDMもしくはサイケデリック・ロックにアプローチしていたダン・スナイスにとって、ダンスを意識した『スイム』は出世作となった。
『スイム』は、彼に取材したときに聞いた話では、ロンドンのクラブ・カルチャーの活気に影響を受けて生まれている。セオ・パリッシュやポスト・ダブステップの面白さにうながされて、彼(ダン・スナイス)と盟友フォー・テット(キエラン・ヘブデン)はダンス・ミュージックにアプローチした。
『スイム』が徹底徹尾のダンスだったわけではない。彼らしいIDM的なアプローチがところどころにあった。そこへいくと今回彼がダフニ名義でリリースするアルバム『ジャオロン』は、完全なダンス・ミュージックである。
夜遊びに出かける前のワクワクした感覚さ。そうやって作った曲をクラブでためしにプレイしてみたあとは、それ以上曲をいじることはしなかった。その時点でできたものを気に入ればそのままキープして、そうじゃなければ曲を消してしまったんだ。
■『ジャオロン』は、あなたがダフニ名義で発表した作品やあなた自身のレーベル〈ジャオロン〉から発売されたシングルの編集盤+新曲ですが、エメラルズのダフニ・リミックスをなぜ入れなかったんですか? 正直入れてほしかったです!
ダン:ありがとう、リミックスを気に入ってくれてうれしいよ。アルバムに入れなかった理由は、あれは実際エメラルズの曲だし、それにリミックスの曲はすでにデジタル・フォーマットで手に入るからさ。アルバムには1曲だけリミックスとして収録されている曲("ネ・ノヤ")があるけど、あれはリミックスとして制作したわけじゃなくて、コス・ベル・ザムのトラックをサンプリングした僕自身の曲として作ったんだ。でもコス・ベル・ザムのトラックの権利上の理由で、サンプルの使用権をクリアするためにはリミックスとして表示しなきゃいけなかった。
■東京には〈テキスト〉や〈ジャオロン〉の固定ファンがいるので、わりとすぐに売り切れてしまうんですよ。ところで、通して聴いていて、あなたが楽しんでダンス・トラックを作っているのが伝わってくるようなCDになったと思います。まずはダフニ名義での活動と〈ジャオロン〉レーベルのポリシーみたいなものを教えてください。
ダン:僕にとってキーとなっているのは、どの曲もすばやく、そして僕自身がDJをするときに使うための新しい曲を作るっていう具体的な目的のためってことかな。曲の多くは、金曜か土曜の午後、DJのために飛行機でヨーロッパのどこかへ行く前に作っていたから、短い時間でいっきに完成させなきゃいけなかった。いまでも聴き返すと、ちょっとした間違いがあっても戻ってやり直したりせずに、急いでいっきに曲を書いているときの熱狂的なエネルギーが感じられるよ。
曲がそういうエネルギーをうまくとらえてくれているといいなと思っているんだ、夜遊びに出かける前のワクワクした感覚さ。そうやって作った曲をクラブでためしにプレイしてみたあとは、それ以上曲をいじることはしなかった。その時点でできたものを気に入ればそのままキープして、そうじゃなければ曲を消してしまったんだ。
■"パリス"みたいな曲には、ちょっとかわいらしい感覚が打ち出されていますよね。ある種のかわいらしさはこのコンピレーション全体にも言える感覚ですが、あなた自身は意識されましたか?
ダン:いや、意識してそうなったわけじゃないよ。でもまちがいなく、カリブーのレコードよりも楽しい感じのする要素が多くなっていると思う。あまり高尚なコンセプトにこだわったりしたものを作るよりも、 人びとが楽しんでくれるような要素を残したものを作りたかったんだ。
■音数が少なくスペースがあって、80年代のシカゴ・ハウスやデトロイト・テクノみたいなファンキーな感覚もありつつ、あなたらしいIDM的なアプローチある、とてもユニークなトラック集だと思いました。たとえば"スプリングス"のような曲もユーモラスでお茶目な曲ですが、同時に即興的で、ライヴ感のある曲です。あなたのダンス・トラックにおいて、即興性は高いんでしょうか?
ダン:かなりあるね。曲の多くは、サンプリングやプログラミングされた音に対応してモジュラー・シンセサイザーを僕が演奏するっていう形で作ったんだ。"スプリングス"はそのいい例さ。トラックを流しながら、シンセサイザーのつまみをいじって作った。だからベース・ドラムのピッチが上がったり下がったりしているんだよ。その予測不能さがクラブで作り出すエキサイティングな感覚が好きだね。
■即興性について訊いておいてこんなこと言うのもなんですが、"ライツ"みたいな曲を聴くと、本当にリズミックな感覚を楽しんでいるなと思います。注意深く聴いていくと、曲の展開に関しては、なにげにかなり工夫されていると思いました。あなたがダンス・トラックを作るさい、どんなところに力を注いでるんでしょうか?
ダン:そういうもの(展開やアレンジ)の重要性は低いよ。カリブーの曲を作っているときにはそういうことを長い時間をかけて考えるけどね。"ライツ"の展開がうまくできていると思ってくれてうれしいけど、あれもすごくすばやくジャムをして作ったんだ。とくに途中のアシッドっぽい部分とかにそれが表れているんじゃないかな。
[[SplitPage]]グローバルな音楽の再発見が進んでいるいまの状態にワクワクしているよ。僕自身レコードを収集していて、こういうオリジナルのレコードを何年も買い続けているけど、リイシューされないかぎり聴く機会のない音楽もたくさんある。
 Daphni - Jiaolong Merge/ホステス |
■カリブーの『スイム』以来、急速にダンス・ミュージックにアプローチしていますね。リミキサーとしてもずいぶん活躍しています。あなたにとってダンス・ミュージックのどこが魅力なんでしょうか?
ダン:ロンドンに住んでいるんだけど、ここではいまは明らかにバンドよりダンス・ミュージックに勢いがあるから、僕自身もそういう方向にエネルギーが向くのは自然なことだと思う。それに僕は飽きっぽいから、『アンドラ』みたいなもっとサイケ・ロックの影響を受けたアルバムを作ったあとには、なにか違ったものを作る必要があったんだ。じつは僕が10代のときに音楽をはじめたのはダンス・ミュージックを通してだったから、僕にとって新しいものってわけじゃないんだ。ただ、自然にまたそこに戻ってきたっていうだけさ。
■コス・ベル・ザムの"ネ・ノヤ"のようなアフリカ音楽との出会いと、あなたにとってのこうした音楽の魅力を教えてください。ここ数年、UKやヨーロッパではアフリカ音楽の再発や発掘が拡大していますが、あなた自身もこうした現代のワールド・ミュージックの動きに興味を持っているんですか?
ダン:そうだね、グローバルな音楽の再発見が進んでいるいまの状態にワクワクしているよ。僕自身レコードを収集していて、こういうオリジナルのレコードを何年も買い続けているけど、リイシューされないかぎり聴く機会のない音楽もたくさんある。たとえばコス・ベル・ザムのトラックはアナログのアフリカン・ミュージックのコンピレーションで聴いたんだけど、(コンピレーションを制作した)彼らがバンドに連絡をとってリイシューする権利を得たってことは、僕が自分の曲でサンプルを使うときにも、バンドと連絡を取ってちゃんともとの曲のミュージシャンにもお金が渡るようにするのが容易だってことでもあった。最近はすごく多様で、しかもまったく知られていないような音楽までリイシューされているのにはびっくりするよ。音楽ファンにとってはこの上ない贅沢だね。
■ライク・ア・ティムやフューチャーみたいな昔のアシッド・ハウス、初期の〈リフレックス〉なんかを参照することはありましたか?
ダン:じつをいえば、僕の最初のレコードやEP(『ギバー』や『イフ・アスホールズ・クド・フライ・ディス・プレイス・ウド・ビー・アン・エアポート』など)の頃は、自分ではダンス・ミュージックを作っているつもりだったんだ。その頃僕はUKガラージやトッド・エドワーズ、エイフェックス・ツイン、ダフト・パンクなんかをよく聴いていて、そういう音楽と、大好きなスピリチュアル・ジャズの混ざったような音楽を作りたかったんだけど、最終的にそのふたつの中間みたいなところで落ちついたと思う。『スイム』がダンスの世界とインディの世界の中間みたいになったのとどこか似ているよ。
■もともとはクラブで汗かいて踊っていたようなタイプじゃないですよね?
ダン:そういうタイプだったし、いまでもいい音楽がかかっていればそうするよ!
■うぉ。あなたが最初に夢中になった踊ったDJって誰でしたか?
ダン:僕にとって最初のDJで、僕にDJのやり方を教えてくれたのはクーシク(Koushik)っていう僕のふるい友人だよ。彼は何年か前に〈ストーンズ・スロー〉からいくつかリリースもしている。いまでも彼は僕がいままで見たなかで最高のDJのひとりだし、誰よりも音楽をよく知っているよ。すばらしい人間さ、彼の音楽がもっと知られていたら、彼がもっといろいろリリースしていたらと願うね。
■あなたにとってのオールタイム・フェイヴァリットのダンス・トラックをいくつか挙げてください。
ダン:たくさんありすぎて、選ぶのが難しいな。
■いつから、どんな経緯でDJプレイが楽しくなっていったのでしょうか? 多くのダンスのプロデューサーはDJからはじまっていますが、あなたは違った出自を持っています。
ダン:高校のときにDJのまねごとみたいなことをしていて、まだ自分の音楽をリリースしたりするようになる前、僕はトロントで〈ソーシャル・ワーク〉って名前のクラブナイトをやっていたんだ。じつはフォー・テットのキエランと本当に知り合ったのもそこでだよ。いちどイギリスのフェスティヴァルで会ったことがあったけど、ちゃんと知り合って友だちになったのは彼を僕らのクラブナイトでDJしてくれるよう招待したときさ。僕がジャズ・レコードとかをかけていたら、彼がやってきてビースティー・ボーイズやアーマンド・ヴァン・ヘルデンなんかをプレイしはじめたんだ。すばらしいサプライズだったね!
■ちなみにDJはどのくらいの頻度でやっているのですか?
ダン:いまはほぼ毎週末だよ。
[[SplitPage]]高校のときにDJのまねごとみたいなことをしていて、まだ自分の音楽をリリースしたりするようになる前、僕はトロントで〈ソーシャル・ワーク〉って名前のクラブナイトをやっていたんだ。じつはフォー・テットと本当に知り合ったのもそこでだよ。
 Daphni - Jiaolong Merge/ホステス |
■ここ数年で、mp3にうんざりした連中がまたアナログ盤にこだわりを見せていますが、〈ジャオロン〉がアナログ盤にこだわる理由を教えてください。
ダン:僕はちょっと矛盾しているんだ。レコード収集家としてレコードという媒体や、それが作り出すデジタル・ファイルにはない所有感が好きなんだけど、レコードのほうが音がいいっていう意見にはまったく賛成できないね。すごく高価なハイファイ・システムでなら少なくとも同じくらいいい音質になり得ることはあるけど、普通のクラブや家で聴くときの環境ならデジタルの24ビット・ファイルのほうがはるかにいい音がするよ。サーフェス・ノイズやクラブで発生しやすいフィードバック・ノイズ、平均的なカートリッジの性能の問題による信号の歪みといった、懐古主義者が忘れがちなごくあたりまえな理由からさ。
だから、今回も自分の音楽がデジタルやCDでもリリースされてうれしいよ。どうしてもアナログ媒体では届かない層の人たちにも聴いてもらえるからね。
■DJでもターンテーブルを使うんですか?
ダン:いや、先に言ったような理由から、CDJとオーディオ・ファイルを使っているよ。
■あなたやフォー・テットのような人が作ったダンス・トラックで踊るのとスクリレックスのダンス・トラックで踊るのとでは、同じダンスという経験においては等価でしょうか? それとも違いがあると思いますか? あるとしたらどんな違いでしょうか?
ダン:たぶん違いがあるとすれば、踊っている人たちの平均年齢かな......いや、でもそれも必ずしも違わないな、僕はいつも僕のライヴやDJに来てくれる人たちの年齢の若さに驚いているんだ。もちろんなかには僕みたいに年金生活者みたいな年齢の人たちもいるけど、僕が思うほど多くはないね。
■クラブ・ミュージックには音楽的におもしろいものもありますが、実際のクラバーのなかには、もっとメトロノーミックなミニマルでも、あるいは馬鹿みたいなレイヴでも、楽しいひと晩を過ごせるなら何でもいいって人が少なくないと思いますが、そういうなかであなたの作るクラブ・ミュージックには、シーンに対する批評的な態度が含まれていると思いますか? それとも純粋な楽しみ、快楽として作ったものなのでしょうか?
ダン:音楽のどのジャンルにもつまらない音楽は存在しているし、むしろそれが大多数だと思うよ。だからつまらないダンス・ミュージックの存在は僕にとっては驚きでもないし興味もないね。興味があるのはその例外さ、新しくておもしろいレコードだよ。それが僕が音楽を作っている理由でもあるんだ、自分自身のためや、他の人たちとシェアするためにそういうおもしろい音楽を作ろうとしているんだ。
■マシュー・ハーバートがやっていることについてはどう思いますか?
ダン:彼のことは好きだよ、ただ僕があまりコンセプトを高く持っていないのに対して、彼はとてもはっきりしたコンセプトを持っているよね。
■エメラルズのリミックスは、アメリカのアンダーグラウンドのシーンとロンドンのクラブ・シーンが出会った新しい試みでしたが、他にこうした企画は控えているのでしょうか? あるいはいま〈ジャオロン〉から出してみたいアーティストがいたら教えてください。
ダン:何も計画はしていないよ。僕はエメラルズとツアーをしたことがあるから、彼らとは近い友人なんだ。彼らはすばらしい人間だし、エクスペリメンタル・ミュージックについてすごくよく知っている。僕らはカナダを横断するリムジンの後部座席で、 ニック・レイスヴィク(Nic Raicevik)やモートン・スボトニックについて語り合ったりしたね。
■〈ジャオロン〉からは、トロ・イ・モワの別プロジェクトも出してますが、クラブ・シーン以外へのアプローチにも気を遣っているんですか?
ダン:いや、彼もいっしょにツアーした近い友人のひとりなんだ。彼がそのトラックを送ってきて、僕がそれを気に入ったからリリースすることにした、ってだけのシンプルなことさ。
■このダフニ名義での活動はまだ続きそうですが、カリブーのほうは逆に言えば、ダンスにとらわれない作品になっていくということでしょうか?
ダン:必ずしもそうとは言えないな、次のカリブーのレコードがどんなサウンドになるかはまだはっきり分からないけど、恐らく『スイム』の後に続くようなものになると思うよ。