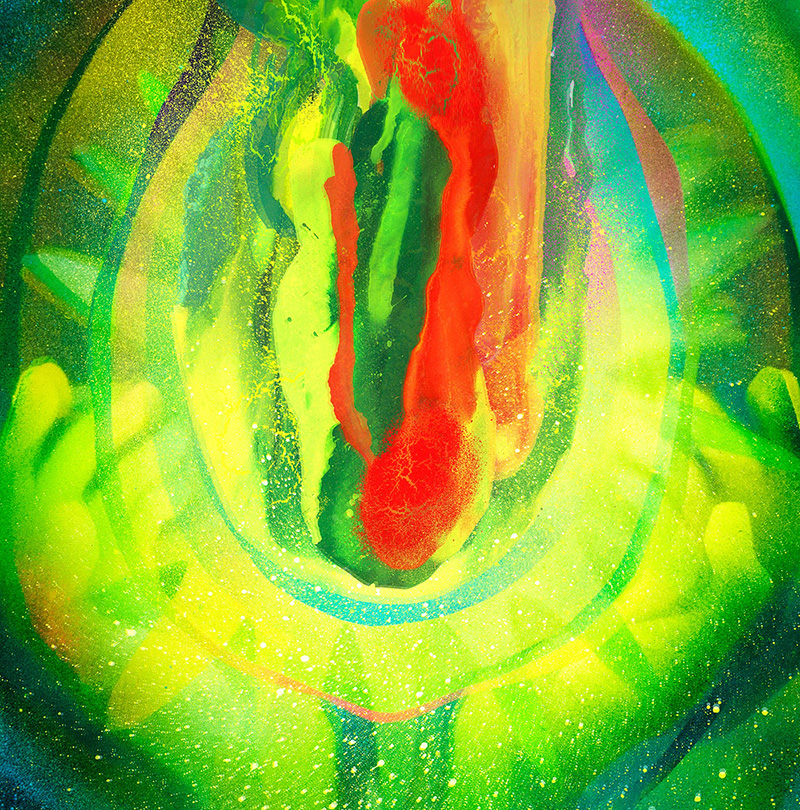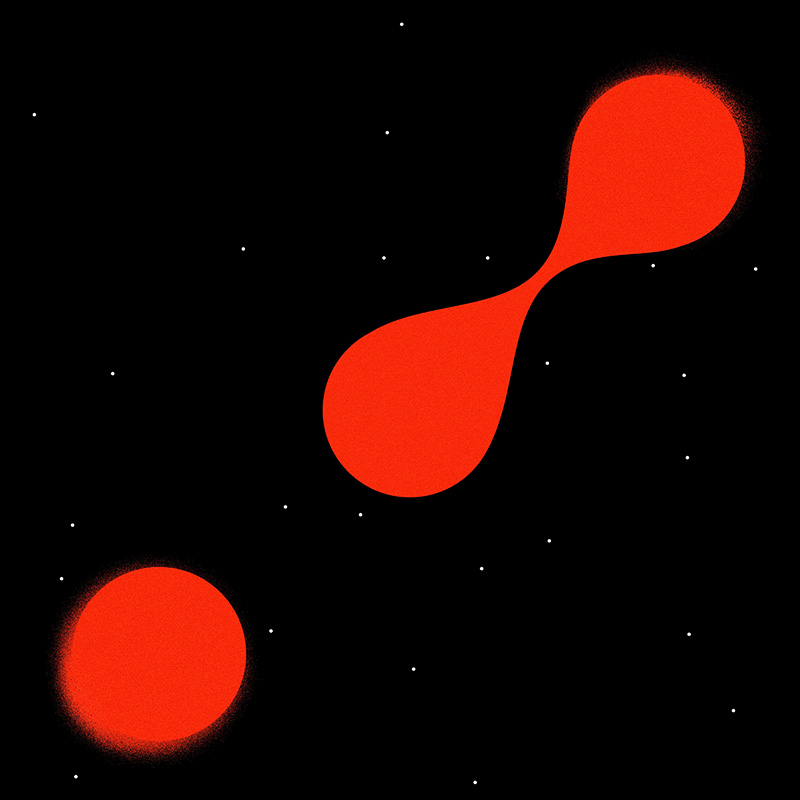長くジャズを聴いてきた者としては、いま現在の注目の若手アーティストを聴くことからはもちろん新たな興奮を得られるのだが、一方でかつて素晴らしい作品を残してきたベテラン・アーティストの新作が出れば、やはりチェックせずにはいられない。そして、そんな新旧アーティストが共演したとなれば黙ってはいられないものだ。こうした新旧アーティストの共演は、たとえばロザンゼルスなどで結構盛んに行なわれており、ハーヴィー・メイソンのバンドにカマシ・ワシントンやマーク・ド・クライヴ・ロウが参加したことがあったし、昨年のフィリップ・ベイリーの『ラヴ・ウィル・ファインド・ア・ウェイ』もそうした新旧の力が組み合わさって作られたアルバムだ。最近ではエイドリアン・ヤングとアリ・シャヒード・ムハマドの『ジャズ・イズ・デッド 001』で、ロイ・エアーズ、ダグ・カーン、アジムス、マルコス・ヴァーリらレジェンド級ミュージシャンとのコラボも実現した。
その『ジャズ・イズ・デッド 001』に参加したひとりのゲイリー・バーツは、以前にもザ・ロンゲッツ・ファウンデーションの『キッス・キッス・ダブル・ジャブ』(2015年)に参加するなど、若手ミュージシャンとのセッションに積極的なアーティストのひとりである。1960年代にアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズでプロ・デビューし、マイルス・デイヴィスのグループへ参加したほか、マックス・ローチ、スタンリー・カウエル、マッコイ・タイナー、アリス・コルトレーンらと共演してきたゲイリー・バーツは、ポスト・コルトレーン的なスピリチュアル・ジャズから、マイゼル・ブラザーズをプロデューサーに迎えたジャズ・ファンク、さらにはルーカス=エムトゥーメイによるブギー~フュージョン路線と、長きに渡って活躍してきたサックス奏者だ。レア・グルーヴやクラブ・ジャズ世代からも人気が高く、ザ・ロンゲッツ・ファウンデーションやエイドリアン・ヤングもそんなところからラヴ・コールし、共演へと繋がったのだろう。
そして、今回はロンドンのジェイク・ロング率いるマイシャがラヴ・コールを送って共演が実現した。マイシャはアフリカ色の強いスピリチュアル・ジャズを指向していて、ちょうどバーツの〈マイルストーン〉や〈プレスティッジ〉時代のサウンドやコンセプトと共通項がある。バーツは1970年にウントゥー・トゥループというグループを率いて、『タイファ』と『ウフル』という連作からなる『ハーレム・ブッシュ・ミュージック』を発表している。マルコムXとコルトレーンに捧げられたアフロ・フューチャリズムに富む『ハーレム・ブッシュ・ミュージック』は、現在のブラック・ライヴズ・マター運動にも繋がる作品なのだが、その中の “ウフル・ササ” を取り上げている。原曲はアンディ・ベイが歌うジャズ・ファンク調のナンバーだが、今回はヴォーカルが入らないぶんバーツ本人のサックス・ソロがより引き立てられるものとなっている。もう1曲バーツのナンバーをやっていて、“ドクター・フォローズ・ダンス” は『フォロー・ザ・メディシン・マン』(1973年)の収録曲。こちらもジャズ・ファンクだが、アフロ・リズムにブロークンビーツのエッセンスを加えたジェイク・ロングのドラムと楽曲が見事に合致している。そのほかの “ハーレム・トゥ・ハーレム” や “ザ・スタンク” は今回のセッションのための新曲だが、どちらも『ハーレム・ブッシュ・ミュージック』あたりに入っていても違和感のない楽曲で、マイシャがバーツの音楽をいかに研究し、理解してきたかがわかる。“レッツ・ダンス” はマイシャのカラーが強いアフロ・ジャズで、ダンサブルなリズムと牧歌性に満ちたバーツのサックスが素晴らしいコンビネーションを見せる。
ゲイリー・バーツと同時期にデビューして活躍してきたアーチー・シェップも、コルトレーンとの共演を経て開花していったサックス奏者である。ドン・チェリーやセシル・テイラーなどとのフリー・ジャズから、ゴスペルやソウルなどを取り入れたジャズ・ファンク~スピリチュアル・ジャズなど幅広く演奏し、1980年代以降はバラード奏者としても高い評価を得ている。ジャズ・ファンク期の作品はバーツ同様にクラブ・ジャズ・ファンから人気が高く、『アッティカ・ブルース』(1972年)はじめカヴァーやサンプリング・ソースとしても愛されてきた。そんなアーチー・シェップが、ワシントンDCのヒップホップ・プロデューサーであるダム・ザ・ファッジマンクの新作にフィーチャーされている。ロウ・ポエティックとK・マードックとのデュオであるパナセアをトラックメイカーとして支え、MCインサイトとのユニットのY・ソサエティでの活動やMFドゥームやブルーなどとのコラボにより、ジャジーでソウルフルなトラック作りに定評のあったダム・ザ・ファッジマンク。今回のアルバムは彼にとって初めてのジャズ・プロジェクトとのことで、自身でドラムスやヴィブラフォンを演奏し、ミュージシャンと組んだバンド形態のプロジェクトとなっている。エイドリアン・ヤングとのコラボでア・トライブ・コールド・クエストが完全にミュージシャンとして組んでいるのと同じことだろう。そしてアーチー・シェップはサックスのほかにピアノ演奏でも参加し、ロウ・ポエティックがシンガー/ラッパーとして加わっている。
基本的にジャズの即興演奏にヒップホップのエッセンスやラップ・パフォーマンスを交えたもので、“ラーニング・トゥ・ブレス” や “チューリップ” のようにクールでソリッドな楽曲が収められている。1970年前後のエッジの立ったシェップの諸作に通じる匂いを感じさせるもので、ジャズとヒップホップが底辺で繋がっていることを改めて感じさせる。そしてバーツとマイシャの場合もそうだが、このコラボもダム・ザ・ファッジマンクからのシェップに対するリスペクトの念が滲み出たものとなっている。