巷では天才か、奇人か、魔人か、などと噂され、ここ1~2年で着実に関心を高めている期待のアシッド・ローファイ・フォーク・ロッカー、リキヒダカ情報です。
6月上旬、広島と愛媛でジム・オルーク × 石橋英子との共演あります。これは見たい、聴きたい。行ける人羨ましいです。
もうひとつ、Giorgio Givvnのレーベルから、2014年に制作された幻のアルバムの発売となりました。2枚組の透明紫色のヴァイナル。ジャケも音もヤヴァイです。
日時:6月6日 (火)
会場:広島クラブクアトロ
OPEN:18:00
START:19:00
料金:前売¥4.000 / 当日¥4.500 (+1drink order)
出演:ジム・オルーク × 石橋英子 × 日高理樹
*取り扱い:ローソンチケット、チケットぴあ、e+(イープラス)、エディオン広島本店プレイガイド、タワーレコード広島店、STEREO RECORDS
日時:6月8日 (木)
会場:愛媛どうごや
OPEN:18:00
START:19:00
料金:前売¥4.000 / 当日¥4.500 (+1drink order)
出演:ジム・オルーク × 石橋英子 × 日高理樹
*取り扱い:どうごや 089-934-0661、more music 089-932-3344、まるいレコード 089-945-0132、RICO SWEETS & SUPLLY CO.089-947-0125、ふるぎやきっかけや”肉”
★問い合わせ
STEREO RECORDS
info@stereo-records.com

Riki Hidaka
Lucky Purple Mystery Circle
QQQQQQQQQ
9QLP-0001
2LP (PURPLE VINYL)
2017年5月17日(水)発売
【組曲ゲノム】
https://www.youtube.com/watch?v=wrqhrv0C41k
【夜の街】
https://www.youtube.com/watch?v=Ey6J7eBRfE0
【私の頭の中のロックンロール音楽】
https://www.youtube.com/watch?v=G3e6Cm8JG08



 〈workshop〉からのリリースによりブレイクしたライプツィヒが誇る若手プロデューサー、グナー・ヴェンデル aka カッセム・モッセは、いまドイツで最も熱い実力派アーティストのひとりである。オマー・S の〈FXHE〉、ドイツの〈Laid〉や〈Mikrodisko〉、UKの〈nonplus+〉などからもアヴァンギャルドながら、ファンキーな魅力も併せ持つエレクトロ~ディープ・ハウス~テクノの傑作トラックを多数発表、カルト的人気を得ているアンダーグラウンド・ヒーローだ。同郷の盟友 Mix Mup とのユニット、MM/KM として〈The Trilogy Tapes〉からのリリースも評判になっており、自身のレーベル〈Ominira〉からも多様なスタイルの作品を発表、昨年は名門〈Honest Jon’s〉から実験的なアルバムを出し話題になるなど、非常に精力的ながら独自のスタンスで活動を続けているユニークな存在。また、パフォーマンスにおいても一点に留まることがない。つねにセッティングや内容を変え、2回と同じことはしない、まさに「ライヴ」感満点なセットだ。特に Kassem Mosse 名義ではヒップホップにも通じるラフなビート感、自然と身体が動いてしまうグルーヴを備え、何度見ても新しさを発見させてくれる。
〈workshop〉からのリリースによりブレイクしたライプツィヒが誇る若手プロデューサー、グナー・ヴェンデル aka カッセム・モッセは、いまドイツで最も熱い実力派アーティストのひとりである。オマー・S の〈FXHE〉、ドイツの〈Laid〉や〈Mikrodisko〉、UKの〈nonplus+〉などからもアヴァンギャルドながら、ファンキーな魅力も併せ持つエレクトロ~ディープ・ハウス~テクノの傑作トラックを多数発表、カルト的人気を得ているアンダーグラウンド・ヒーローだ。同郷の盟友 Mix Mup とのユニット、MM/KM として〈The Trilogy Tapes〉からのリリースも評判になっており、自身のレーベル〈Ominira〉からも多様なスタイルの作品を発表、昨年は名門〈Honest Jon’s〉から実験的なアルバムを出し話題になるなど、非常に精力的ながら独自のスタンスで活動を続けているユニークな存在。また、パフォーマンスにおいても一点に留まることがない。つねにセッティングや内容を変え、2回と同じことはしない、まさに「ライヴ」感満点なセットだ。特に Kassem Mosse 名義ではヒップホップにも通じるラフなビート感、自然と身体が動いてしまうグルーヴを備え、何度見ても新しさを発見させてくれる。 この1~2年で急に頭角を現してきたように見える(かもしれない) Resom (レゾム)は、ベルリンではよく知られた存在だ。反ナショナリズム、反差別主義を掲げる、ベルリンの中でも特にリベラルなスタンスのクラブ、〈:// about bank〉のレジデントDJを長年務め、ライプツィヒでの学生時代からの友人であるカッセム・モッセや Mix Mup (ミックス・マップ)らを陰で支えるブッキング・エージェントとしての顔も持ち、それ以外にもつねに様々なイベントのオーガナイズや、制作に関わってきた。音楽業界における女性の地位向上のためにも行動する、フェミニストでありアクティヴィストでもある。そのDJスタイルは一言では形容しがたい、非常に独特なもので、ジャンルで言えばアンビエントからエレクトロ、歌物からミニマルまで非常に幅広く縦横無尽にミックスしていくのだが、ただ色々かけているというのではなく、彼女の中で明確なイメージやテーマがあり、それをもっともオブスキュアでレフトフィールドな選曲によって紡ぎ出していくような、まったく予測不可能ながら、いつも彼女らしいちょっぴりストレンジな高揚感に到達させてくれるのである。Ben UFO や DJ NOBU も絶賛する彼女の個性を、ぜひ一度体験してみて欲しい。
この1~2年で急に頭角を現してきたように見える(かもしれない) Resom (レゾム)は、ベルリンではよく知られた存在だ。反ナショナリズム、反差別主義を掲げる、ベルリンの中でも特にリベラルなスタンスのクラブ、〈:// about bank〉のレジデントDJを長年務め、ライプツィヒでの学生時代からの友人であるカッセム・モッセや Mix Mup (ミックス・マップ)らを陰で支えるブッキング・エージェントとしての顔も持ち、それ以外にもつねに様々なイベントのオーガナイズや、制作に関わってきた。音楽業界における女性の地位向上のためにも行動する、フェミニストでありアクティヴィストでもある。そのDJスタイルは一言では形容しがたい、非常に独特なもので、ジャンルで言えばアンビエントからエレクトロ、歌物からミニマルまで非常に幅広く縦横無尽にミックスしていくのだが、ただ色々かけているというのではなく、彼女の中で明確なイメージやテーマがあり、それをもっともオブスキュアでレフトフィールドな選曲によって紡ぎ出していくような、まったく予測不可能ながら、いつも彼女らしいちょっぴりストレンジな高揚感に到達させてくれるのである。Ben UFO や DJ NOBU も絶賛する彼女の個性を、ぜひ一度体験してみて欲しい。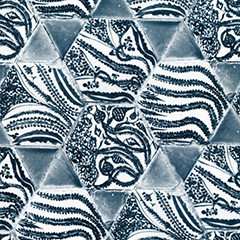
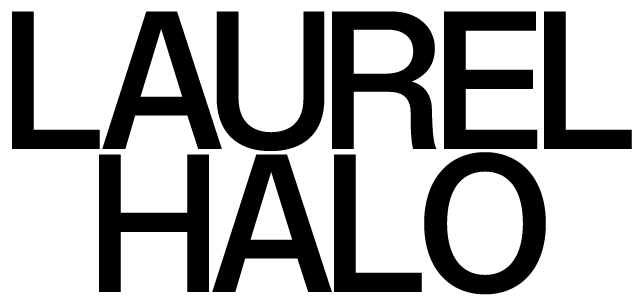
 label: HYPERDUB / BEAT RECORDS
label: HYPERDUB / BEAT RECORDS
 アーティスト: Jeff Parker / ジェフ・パーカー
アーティスト: Jeff Parker / ジェフ・パーカー アーティスト: Jamire Williams / ジャマイア・ウィリアムス
アーティスト: Jamire Williams / ジャマイア・ウィリアムス

