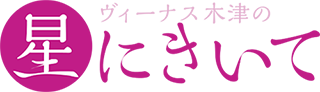フラング・ロータス、さもなければシカゴのディープ・ハウスおける最重要プロデューサー、90年代後半のロン・トレント──、アフリカン・サイエンスのアルバム『Circuitous』を聴いたとき、そのように感じました。アフロで、コズミックで、スピっているようです。
とはいえ、こちらは、ベルリンのもっともクールなレーベル〈PAN〉からのリリースです。アフリカン・サイエンスはよりモダンで、実験的で、フリーキーです。音楽の向こう側には、ブラック・サイエンス・フィクションが広がっているかもしれません。ケオティックです。何かが起きているようです。アクトレスを思い出して下さい。この音楽は、どきどきします。
まったく……これは注目の初来日です。
AFRIKAN SCIENCES Japan Tour 2015
Afrikan Sciences x DE DE MOUSE
4.24 fri @ 大阪 心斎橋 CONPASS
Live Acts: Afrikan Sciences(PAN, Deepblak - New York), DE DE MOUSE
DJs: T.B.A.
Open/ Start 19:00
¥ 3,000(Advance), ¥ 3,500(Door)plus 1 drink charged @ door
前売りメール予約: https://www.conpass.jp/mail/contact_ticket/
Ticket Outlets: PIA, LAWSON, e+(eplus.jp)
Information: 06-6243-1666(CONPASS)
www.conpass.jp
UBIK
4.25 sat @ 東京 代官山 UNIT
Live Acts: Afrikan Sciences(PAN, Deepblak - New York), N'gaho Ta'quia a.k.a. sauce81(disques corde)
DJs: Shhhhh(SUNHOUSE), MAMAZU(HOLE AND HOLLAND)
Open/ Start 23:30
¥3,000(Advance), ¥3,500(Door)
Ticket Outlets: LAWSON(L: 76745), e+(eplus.jp), disk union CMS(渋谷, 新宿, 下北沢), TECHNIQUE, Clubberia Store, RA Japan and UNIT.
Information: 03-5459-8630(UNIT)
www.unit-tokyo.com
Afrikan Sciences(PAN, Deepblak - New York) https://soundcloud.com/afrikan-sciences
オークランド出身、 NY拠点のエリック・ポーター・ダグラスのソロ・プロジェクト。DJとして80年代のヒップホップをルーツに持ち、90年代後期の電子音楽のプロダクションに自身のサウンドを見い出し、2007年にオークランドの盟友 Aybee主宰の〈Deepblak〉からデビュー、同レーベルからEPとアルバムをリリース、 Gilles Peterson主宰の〈Brownswood〉のコンピレーションにも参加。Afrika Bambaataaの私生児、SF作家Octavia Butler、 Sun Raの孫息子とも言及され、90年代の東海岸のハウス、40年代のジャズ、 西ロンドンのブロークン・ビーツ、土着的なアフリカやラテンのリズムから掻き集め、蓄積されたビートの感性は様々な音楽のフォームとサイファイ・ビジョンと結びつきながら独創的なプロダクションへと発展。AybeeとのMile Davisトリビュート・プロジェクト『Sketches Of Space』ではアシッド・ハウス先駆者Ron Hardyとアフロ・ビートかけあわせたような作品を披露。 長年先人達によって育まれ、更新されて来たアフロ・フューチャリズムの前衛としても異彩を放つ電子音楽家である。
N'gaho Ta'quia a.k.a. sauce81(disques corde) https://soundcloud.com/sauce81
プロデューサーsauce81の変名プロジェクト。sauce81としては、2008年、バルセロナにて開催されたRed Bull Music Academyに招待され、Sonar Sound Tokyoなどの国内フェス、海外でのライヴパフォーマンスも行っている。生々しいマシン・グルーヴとラフで温かみのあるシンセ使い。雑味たっぷりの楽器演奏と時折表すファジーでメローなボーカルワーク。ディープなソウルとファンクネスをマシンに宿すプロダクション・スタイルで、数々のリミックス、コンピへの楽曲提供を重ねてきた。これまでに『Fade Away』EP、『All In Line / I See It』EP、77 Karat Gold(grooveman Spot & sauce81)『Love / Memories In The Rain』7inch、『It's About Time』EP などのオリジナル作に加え、Shing02脚本・監督のショートフィルム『BUSTIN’』のために書き下ろした楽曲が、UKの〈Eglo Records〉から『Natural Thing / Bustin'』7inch レコードとしてリリース。N'gaho Ta'quia(ンガホ・タキーア)では、自身のルーツである 70's ジャズ、ファンク、ソウル・ミュージックをヒップホップ/ビート・ミュージックのフィルターを通してアウトプットすると共に、アルバム制作へと繋がるコンセプチュアルな世界観を表現している。
Shhhhh(SUNHOUSE) https://twitter.com/shhhhhsunhouse https://shhhhhsunhouse.tumblr.com/
DJ/東京出身。オリジナルなワールドミュージック/伝統伝承の発掘活動。フロアでは民族音楽から最新の電子音楽全般を操るフリースタイル・グルーヴを発明。オフィシャルミックスCD、『EL FOLCLORE PARADOX』のほかに『ウニコリスモ』ら2作品のアルゼンチン音楽を中心とした、DJ視点での南米音楽コンピレーションの編集/監修。ライナーノーツ、ディスクレビューなど執筆活動やジャンルを跨いだ海外アーティストとの共演や招聘活動のサポート。 全国各地のカルト野外パーティー/奇祭からフェス。はたまた町の酒場で幅広く活動中。
Mamazu(HOLE AND HOLLAND)https://mamazu.tumblr.com/
SUPER X 主催。90年代中期頃からDJとして活動を始める。今は無きclub青山MIXの洗礼を浴び、音と人、空間に触発され多種多様な音を吸収。小箱から大箱、野外まで独自の視点で形成される有機的なプレイを続け、国内外数多くのDJ、アーティストとの共演を果たす。トラック制作ではSkateDVDの『007』や『LIGHT HILL ISM』、雑誌『TRANSWORLDJAPAN』付録DVD、代々木公園にて行われる伝統ダンスパーティー『春風』のPVなどに楽曲を提供。2011年HOLE AND HOLLANDから発売されたV.A『RIDE MUSIC』の収録曲「ANTENA」ではInterFMなどでも放送され、日本が宇宙に誇るALTZもPLAY!、BOREDOMSのEYEもMETAMORPHOSE 2012でPLAYし、REDBULL主宰の RBMA RADIO にて公開され大きな話題となる。2012年5月には『RIDE MUSIC』から待望のアナログ・カット、MAMAZU - ANTENA - YO.AN EP EDITをリリースしこちらもALTZ、INSIDEMAN aka Q(Grassroots)、箭内健一(Slow Motion Replay)、YAZI(Blacksmoker)などなど様々なDJがPLAY中!2013年は自身初となるMIXCD『BREATH』をリリースし、最近ではアパレルブランドSON OF THE CHEESEの2015F/WのイメージMIXを提供。HOLE AND HOLLANDからリリースが予定されている。またCOGEEとのB2Bユニット『COZU』やSUNGAを加えたライヴユニット『DELTA THREE』ではBLACK SHEEPによるコンピレーションLP『ANTHOLOGY』に曲を提供するなど、活動は多義に渡る。