昨年のウインブルドンではニック・キリオスが大活躍だった。全身に刺青が入った黒人のテニス・プレイヤーで、ショットが決まるたびに客席の誰かに大声で話しかけ、勝っても負けてもオーストラリア本国に戻ればレイプ疑惑で裁判が待っていた(精神障害を理由にいまだに裁判からは逃げている)。大坂なおみが開いたエージェント・オフィスが初めて契約した選手であり、日本に来た時はポケモンセンターの前に座り込んで「絶対にここから離れない」とSNSに投稿していた。僕の推しはカルロス・アルカラスだったんだけれど、昨年は早々とキリオスに負けてしまったので、そのまま惰性でキリオスを追っていた。そうなんだよ、危うくカルロス・アルカラスのことを忘れてしまうところだった。それだけインパクトの強い選手だった。僕がカルロス・アルカラスを応援し始めたのはピート・サンプラスに顔が似ていたから。90年代のプレースタイルを象徴するテニス・プレイヤーで、あまりにもプレーが完璧すぎて「退屈の王者」とまで言われた男。W杯のカタール大会でエンバペがゴールするたびにマクロンが飛び跳ねていたようにサンプラスが00年の全米オープンで4大大会最多優勝記録を打ち立てた時はクリントンも思わず立ち上がっていた。試合でリードしていても苦々しい表情だったサンプラス。内向的で1人が好きだったサンプラス。僕がピート・サンプラスを応援し始めたのはアラン・ランキンに顔が似ていたから。僕はアラン・ランキンの顔が大好きだった。セクシーでガッツに満ち、野獣に寄せたアラン・ドロンとでもいえばいいか。初めて『Fourth Drawer Down』のジャケット・デザインを見た時、この人たちは何者なんだろうと思い、どんな音楽なのかまったく想像がつかなかった。
 The Associates – The Affectionate Punch(1980年)
The Associates – The Affectionate Punch(1980年)
なんだかわからないままに聴き始めた『Fourth Drawer Down』はなんだかわからないままに聴き終わった。朗々と歌い上げるビリー・マッケンジーのヴォーカルと実験的なのかポップなのかもわからないサウンドは現在進行形の音楽だと感じられたと同時に「現在」がどこに向かっているかをわからなくするサウンドでもあった。その年、1981年はヒューマン・リーグがシンセ~ポップをオルタナティヴからポップ・ミュージックに昇格させた年で、シンセ~ポップのゴッドファーザーたるクラフトワークが『Computerwelt』で自ら応用編に挑むと同時にソフト・セル『Non-Stop Erotic Cabaret』からプリンス『Controversy』まで一気にヴァリエーションが増え、一方でギャング・オブ・フォー『Solid Gold』やタキシードムーン『Desire』がポスト・パンクにはまだ開けていない扉があることを指し示した年でもあった(タキシードムーンはとくにベースがアソシエイツと酷似し、アラン・ランキンは後にウインストン・トンのソロ作を何作もプロデュースする)。『Fourth Drawer Down』はそうした2種類の勢いにまたがって、両方の可能性を一気に試していたようなところがあった。それだけでなく、グレース・ジョーンズ『Nightclubbing』に顕著なファッション性やジャパン『Tin Drum』から受け継ぐ耽美性も共有し、オープニングの“White Car In Germany”では早くもDAF『Alles Ist Gut』を意識している感じもあった。混沌としていながら端正なテンポを崩さない“The Associate”を筆頭に、PILそのままの“A Girl Named Property”、物悲しい“Q Quarters”には咳をする音が延々とミックスされ、あとから知ったところでは“Kitchen Person”は掃除機のホースを使って歌い、“Message Oblique Speech”のカップリングだった“Blue Soap”は公園のようなところにバスタブを置いて、その中で反響させた声を使っているという。まるでジョー・ミークだけれど、ジョー・ミークにはない重いベースと破裂するようなキーボードが彼らをペダンチックな存在には見せていない。
これらが、しかし、すべて助走であり、アラン・ランキンとビリー・マッケンジーが次に手掛けた『Sulk』はとんでない方向に向かって華開く。昨年、同作の40周年記念盤がリリースされ、全46曲というヴォリウムに圧倒されながらレビューを書いたので詳細はそちらを参照していただくとして、ここではスネアをメタル仕様に、タムを銅性の素材に変えたことで、インダストリアルとは言わないまでも、全体に金属的なドラム・サウンドが支配するアルバムだということを繰り返しておきたい。『Sulk』はパンク・ロックのパワーを持ったグラム・ロック・リヴァイヴァルであり、ニューウェイヴの爛熟期に最も退廃を恐れなかった作品でもある。あるいは15歳のビョークが夢中で聴いたアルバムであり、彼女のヴォーカル・スタイルに決定的な影響を与え、イギリスのアルバム・チャートでは最高10位に食い込んだサイケデリック・ポップの玉手箱になった。『Sulk』はちなみにイギリス盤と日本盤が同内容。アメリカ盤とドイツ盤がベスト盤的な内容になっていた。ジャケットの印刷技術もバラバラで、リイシューされるたびに緑色が青に近づき、裏ジャケットのトリミングも違う。オリジナル・プリントはイギリスのどこかの美術館に収蔵されているらしい。
ビリー・マッケンジーが『Sulk』の北米ツアーを前にして喉に支障をきたし、アメリカで売れるチャンスを逃したとして怒ったアラン・ランキンはアソシエイツから脱退、『Sulk』に続いてリリースされたダブルAサイド・シングル「18 Carat Love Affair / Love Hangover」(後者はダイアナ・ロスのカヴァー)がデュオとしては最後の作品となってしまうも、『Fourth Drawer Down』以前にリリースされていたデビュー・アルバム『The Affectionate Punch』のミックス・ダウンをやり直して、同じ年の12月には再リリースされる。元々の『The Affectionate Punch』はなかなか手に入らず、その後、イギリスでようやく見つけたものと聴き比べてみると、ミックス・ダウンでこんなに変わってしまうものかと驚いたことはいうまでもない。たった2年でアラン・ランキンが音響技術の腕を確かなものにした自信が『The Affectionate Punch』の再リリースには漲っていた。同作からは“A Matter Of Gender”が先行カットされ、結局、デビュー・シングル“Boys Keep Swinging”(デヴィッド・ボウイの無許可カヴァー)などを加えて元のミックス盤も05年にはCD化される。『Sulk』に続く道も感じられはするけれど、オリジナル・ミックスはまだシンプルなニューウェイヴ・アルバムで、この時期は〈Fiction Records〉のレーベル・メイトだったキュアーとヨーロッパ・ツアーなどを行なっていたことからロバート・スミスがギターとバック・コーラスで参加、ベースのマイケル・デンプシーはその後もアソシエイツとキュアーを掛け持っていた。ロバート・スミスは後にビリー・マッケンジーが自殺する直前、キュアーのライヴを観に来てくれたのに声をかけ損なったことを悔やんで「Five Swing Live」をリリースしたり、“Cut Here”をつくったりしている。
 The Associates – Sulk(1982年)
The Associates – Sulk(1982年)
バンドを脱退したとはいえ、『Sulk』の名声はアラン・ランキンにプロデュース業の仕事を舞い込ませる。ペイル・ファウンテインズ“Palm Of My Hand”は“Club Country”で用いたストリング・アレンジを流用しながら彼らのアコースティックな持ち味を存分に活かし、反対にコクトー・ツインズ“Peppermint Pig”はあまりにもアソシエイツそのままで、これは派手な失敗作となった。彼らのイメージからは程遠いインダストリアル・ドラムに加えて近くと遠くで2本のギターが同時に鳴り続けるだけでアソシエイツに聞こえてしまい、ノイジーなサウンドに尖ったリズ・フレイザーのヴォーカルが入るともはやスージー&ザ・バンシーズにしか聞こえなかった。そして、アンナ・ドミノやポール・ヘイグのプロデュースから縁ができたのか、アラン・ランキンのソロ・ワークも以後は〈Les Disques Du Crépuscule〉からとなる。アソシエイツ脱退から4年後となったソロ・デビュー・シングル“The Sandman”は幼児虐待をテーマにした静かな曲で、カップリングは戦争を取り上げた暗いインストゥルメンタル。続いてリリースされたファースト・ソロ・アルバム『The World Begins To Look Her Age』はアソシエイツのようなエッジは持たず、80年代中盤のニューウェイヴによくあるAOR風のシンセ~ポップに仕上がっていた。これはランキンを失ったマッケンジー単独のアソシエイツも同じくで、マッケンジーもまた気の抜けたアソシイツ・サウンドを鳴らすだけで、2人が離れてしまうと緊張感もないし、いずれもメローな部分ばかりが際立つ自らのエピゴーネンに成り下がってしまったことは誰の耳にも明らかだった。2人がそろった時の化学反応はやはり1+1が3にも100にもなるというマジックそのものだったのである。しかし、2人は93年まで再結成に意欲を示さず、とくにビリー・マッケンジーはイエロやモーリツ・フォン・オズワルドといったユーロ・テクノの才能と組んでサウンドの更新に勤め、それなりに意地は見せていた。アラン・ランキンは『The World Begins To Look Her Age』の曲を半分入れ替えて〈Virgin〉から『She Loves Me Not』として再リリースした後、〈Crépuscule〉から89年に『The Big Picture Sucks』を出して、まとまった音源はこれが最後となる。
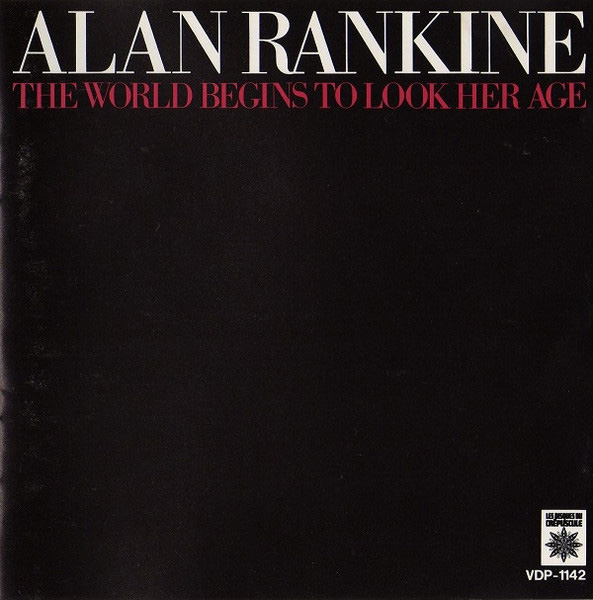 Alan Rankine – The World Begins To Look Her Age(1986年)
Alan Rankine – The World Begins To Look Her Age(1986年)
93年に再結成を果たしたアソシエイツは6曲のデモ・テープを製作するも94年からアラン・ランキンは地元グラスゴーのストウ・カレッジで教鞭に立ち、それほど頻繁に作業ができなくなった上にビリー・マッケンジーが97年1月に自殺、新しいアルバムが完成されるには至らなかった。そのうちの1曲となる“Edge Of The World”はその年の10月にリリースされたビリー・マッケンジーのソロ名義2作目『Beyond The Sun』に“At Edge Of The World”としてポスト・プロダクションを加えて収録され、さらに3年後、キャバレー・バンド時代のデモ・テープなどレア曲を37曲集めた『Double Hipness』には6曲とも再録されている。6曲のデモ・テープは『The Affectionate Punch』に戻ったような曲もあれば、新境地を感じさせる“Mama Used To Say”にドラムンベースを取り入れた“Gun Talk”など完成されていれば……などといっても、まあ、しょうがないか。ザ・スミスがビリー・マッケンジーを題材にした“William, It Was Really Nothing”に対する10年越しのアンサー・ソング、“Stephen, You're Really Something”も週刊誌的な興味を引くことになった。アラン・ランキンが残した音源は少ない。ビリー・マッケンジーと組んだアソシエイツとその変名プロジェクトにソロ・アルバム2.5枚とソロ・シングル3枚、クリス・イエイツらと組んだプレジャー・グラウンド名義でシングル2枚のみである。また、2010年まで大学教員を続けたランキンは大学内に〈Electric Honey〉を設け、ベル&セバスチャンのデビュー・アルバム『Tigermilk』など多くのリリースにも尽力している。
ビリー・マッケンジーがソロでつくった曲は間延びした印象を与えることが多かったけれど、アラン・ランキンが加わるとそれがタイトになり、まるで伸び伸びとは歌わせまいとしているようなプロダクションに様変わりした。アソシエイツはそこが良かった。歌が演奏にのっているというよりも声と演奏が戦っているようなサウンドだったのである。まったくもって調和などという概念からは遠く、ビリー・マッケンジーがどれだけ気持ちよく歌っていてもアラン・ランキンのギターは容赦なくそれを搔き消し、いわば主役の取り合いだった。“Waiting for the Loveboat”も脱退前にアラン・ランキンが録っていたデモ・テープはぜんぜん緊張感が違っていた。アラン・ランキンはおそらくせっかちなのである。彼らの代表曲となった“Party Fears Two”がトップ10ヒットとなり、トップ・オブ・ザ・ポップスに出演した時もランキンは同番組が口パクであるのをいいことに鳴ってもいないバンジョーを弾いたり、ピエール瀧の綿アメみたいに客にチョコレートを食べさせるなどふざけまくっていたのは、たった1曲のために2時間以上も拘束されるため「飽きてしまったから」だと答えていた。『Fourth Drawer Down』も実はそれまでがあまりに狂騒状態だったので、少しは落ち着こうとしてつくった曲の数々だったというし、それがまた再び狂騒状態に戻ったのが『Sulk』だったから、あそこまで弾け飛んだということになるらしい。自分の人生を何倍にも巨大なものにしてくれる人との出会いがあるということはなんて素晴らしいことなのだろう。2人合わせて103歳の人生。短い。あまりに短いけれど、『Sulk』はこれから先、いつまでも聴かれるアルバムになるだろう。R.I.P.










