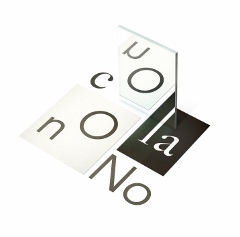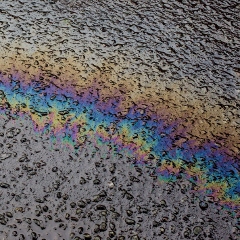 Laurel Halo / In Situ |
テクノがエクスペリメンタルなモードをまとうようになった時代……。それが2010年代初頭のエレクトロニクス・ミュージックの潮流であったと、ひとまずは総括できるだろう。
グリッチやクリック、ドローンなど00年代のエレクトロニカにおけるサウンドの実験が、ミニマル・ダブ以降のテクノの領域に流れてこんでいったことは、デムダイク・ステアやアンディ・ストットなどを擁する〈モダン・ラヴ〉、ビル・クーリガス率いる実験音楽レーベル〈パン〉、ルーシー主宰の〈ストロボスコピック・アーティファクツ〉の諸作品を思い出してみれば即座にわかる。
その結果、(アートワークも含め)、ノンアカデミックなエレクトロニクス・ミュージックは、よりアートの領域にシフトし、コンテクストとコンセプトと物語性が強くなった。エクスペリメンタルという言葉が頻繁に用いられるようにもなる。ビートは分断され、サウンドは複雑化した。

Laurel Halo / Quarantine
Hyperdub/ビート(2012)
ローレル・ヘイローは、待望の新作がリリースされるワンオートリックス・ポイント・ネヴァーやアルカ(新作『ミュータント』は前作を超える傑作!)などとともに、そのような時代を代表するアーティストといえよう。同時に孤高の存在でもあった。会田誠の作品を用いたファースト・アルバム『クアランティン』(2012)のアートワークなどを見ても分かるように、繊細・緻密な2010年代前半にあって、ほかにはない独自の感性であった。とはいえ、楽曲自体はどこか瀟洒で、それこそ「テン年代的」なエクスペリメンタル・アンビエントな質感を持っていた点も新しかった。
しかし、彼女の楽曲にはある種の「つかみどころのなさ」があったことも事実。声を存分に使ったトラックもあるが、ホーリー・ハーダン(新作『プラットフォーム』は90年代以降の音響学=ポップの領域越境のお手本のごときアルバム!)のキャッチーさとはまた違う「地味」なテイストがあったのだ。
いまにして思えば、その「つかみどころのなさ」こそ、テクノをルーツとする彼女のストイックさの表れだったのではないかと思う。テクノとアンビエントという領域のあいだでローレル・ヘイローの音は鳴っていた。実際、『アンテナ EP』(2011)や『アワー・ロジック』(2013)などを聴けば、彼女のストイックなテクノ感覚やアンビエント感覚をより理解できる。ある意味、『クアランティン』と『チャンス・オブ・レイン』は、やや異質な作品だったのではないかとも。この『イン・サイチュ』において、彼女は自分のルーツ=テクノへと素直に回帰している(『アワー・ロジック』的?)。1曲め“シチュエーション”の洗練されたビートメイクには誰しも驚くはず。この変化は彼女がベルリンというテクノの地に移住したことが大きいのかもしれないし、〈オネスト・ジョンズ〉からのリリースということもあるだろう。
ここから私はインダストリアル/テクノ、ジューク / フットワーク、グライム、近年のアンビエント・シーンとの関連性や交錯性もつい考えてしまう。

Jlin / Dark Energy
melting bot/Planet Mu(2015)
そこでまずジェイリン『ダーク・エナジー』(2014)をとり上げてみたい。類似性は3ビートメイキングではなく、独自の硬質感とファッションショーなどでも用いられるモードな雰囲気にある(とくに『イン・サイチュ』のM2)。
モード感覚は近年のエレクトロニック・ミュージックを考えていく上で重要な要素で、〈パン〉からリリースされたヴィジョニスト『セーフ』も同様だ。グライム文脈でありつつも、エレガンスでエクスペな音楽性は、アートワークにしても未来的。彫刻のような硬質なサウンドと鉱物的なビートがたまらない。そしてテクノ・フィールドからはドイツのヘレナ・ハフ『ディスクリート・ デザイアーズ』も併せて聴きたい。彼女のトラックはアシッドなビートが強調されているが、インダストリアルなダークさもある。
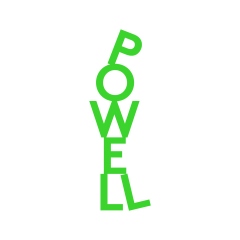
Powell / Insomniac /
Should Have Been A Drummer
XL(2015)
また、スティーヴ・アルビニにサンプリング許諾申請をして怒られ、結局、承認してくれたパウエル『インソムニアック/シュドゥヴ・ビーン・ア・ドラマー』もインダス以降の現代音響テクノの最先端として聴いておきたい。ここからエンプティセットの新作EP『シグナル』における過激で優雅な実験的なサウンドに繋げていくことも可能であろう。
個人的には〈ストロボスコピック・アーティファクツ〉からリリースされたシェヴェル『ブラーズ』と、〈オパール・テープス〉から発表されたインダストリアル・テクノとフリー・インプロヴィゼーションとアンビエントの交配を図るマイケル・ヴァレラ『ディスタンス』こそ、『イン・サイチュ』の横に置いておきたいアルバムだ。『ブラーズ』は最先端のインダストリアル・テクノで、そのストイックな感覚は『イン・サイチュ』とスムーズに繋がっていく。『ディスタンス』は、ジャンルと形式を越境していくストレンジな感覚の中に、ローレル・ヘイローの個性に近いものを感じる。
Chevel『Blurse』
Michael Vallera『Distance』
『イン・サイチュ』にはアンビエントなテクスチャーとジャズ的な和声感が見られる曲もある(M7とM8などにととまらず、ビート入りのトラックでもシルキーな上モノなどに彼女のアンビエント感覚を聴き取ることができる)。
そこでカラーリス・カヴァデール(Kara-Lis Coverdale)を聴いてみたい。彼女はクラシカルな感性と素養を持ったアンビエント・アーティストだが、讃美歌や宗教歌のようなエッセンスを感じる音楽家である。声を使ったり、ミニマルなフレーズによって曲を構築したりするなど、古楽のような音楽性と浮遊感のあるサウンドのテクスチャーが素晴らしい。LXVによるグリッチ・ノイズと、カヴァデールによる乾いた音と、弦のようなアンビエンスと加工されたヴォイスなどが交錯するコラボレーション作『サイレーン』も素晴らしいが、何はともあれ神話的なアンビエント『アフタータッチズ』をお勧めしたい。
Kara-Lis Coverdale『Aftertouches』
Kara-Lis Coverdale - "TOUCH ME & DIE" from Sacred Phrases on Vimeo.

Dasha Rush / Sleepstep
Raster-Noton(2015)
また〈ラスター・ノートン〉からリリースされたダーシャ・ラッシュ『スリープステップ』もアンビエントとテクノを20世紀初頭のモダニズムで越境するような優美なアルバムである。ジャズ/フュージョン的なコード感と今日的な電子音楽のという意味では、CFCF『ザ・カラーズ・オブ・ライフ』をピックアップしたい。架空のドキュメンタリー映画のサントラといった趣のアルバムだが、ピザールな感覚もありヘイローの諸作品と並べても違和感はない。
エクスペリメンタルかつ音響なテクノと幽玄なアンビエント/アンビエンス。そしてジャズ/フュージョン風味。ストイックでありながらローレル・ヘイローらしさもある。そのうえ2015年的な音楽的文脈すらも聴き取ることができる。今年も素晴らしい話題作・傑作が目白押しだが、『イン・サイチュ』も独自の存在感=鉱石のような光(まるでアートワークのごとき!)を放っているように思えてならない。
Note:
Jlin『Dark Energy』
Visionist『Safe』
Helena Hauff『Discreet Desires』
Powell『Insomniac/Should'Ve Been A Drummer』
Emptyset『Signal』
Chevel『Blurse』
Michael Vallera『Distance』
Kara-Lis Coverdale『Aftertouches』
Kara-Lis Coverdale/LXV『Sirens』
Dasha Rush『Sleepstep』
CFCF『The Colours of Life』