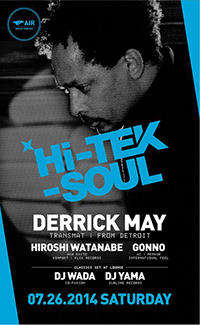8月突入ということで2014年上半期の書き損じを記させていただきたい夏真っ盛りな今日このごろ、みなさまはいかがお過ごしだろうか?
私は〈スカル・カタログ/スペンディング・ラウド・ジャパンツアー〉に全生命力を浪費し尽くし、一度ゲル状になり、再び人間らしい形を取り戻しつつある。そのなかでもとくにグッタリさせられたのがサウンド・チェックへ向かう車内や本番直前に必ずおこなっていたDJスカル・カタログ、というか彼のiPhoneのプレイリストを爆音で聴かされる儀式で、基本的にはメタルとビートの素晴らしい選曲ではあるのだけれど、おでこにサーチ・アンド・デストロイとか書いてある北斗の拳のキャラクターのようなノリノリの男を乗せて、そんなものを垂れ流しながらボロボロのハイエースを転がしていればつねに職質への警戒を怠ることはできぬし、イヴェント中に唐突にはじまる、「アイツの後でDJやるぜ!」みたいな対応に追われ溶けかけたりしていた。とはいえ自身のモチヴェーションを高めることを主としたミックスなのでそのアゲ作用も半端ではなく、とくにわれわれの話題にあがっていたのがコレであった。
活動歴15年、米国はロードアイランド州プロヴィデンスで結成され、現在はポートランド州オレゴンを拠点に活動するジ・ボディ(The Body)と、電子音楽・メタル・デュード最右翼、ハクサン・クローク(Haxan Cloak)による今年度もっともオサレだけども重い一枚。永久に存在しているんじゃないかと思うほど長きに渡ってストイック極まる独自のドゥーム/スラッジを追求してきたデュオ、ザ・ボディは、かつて〈アット・ア・ロス(At A Loss)〉などのクラスト~ドゥームの流れを汲む、遅くておっもい、ダーク・クラストな感性を持つレーベルに発掘され、2011年発表の『オール・ザ・ウォーター・オブ・ザ・アース・ターン(All The Water Of The Earth Turn)』では総勢24名の女性コーラス隊、アッセンブリー・オブ・ライトとのとんでもないコラボレーションでわれわれの度肝を抜いた。Youtubeでいま見ることのできるそれは、思わず笑ってしまうが。
これだけのインパクトをもった存在を、ゼロ年代以降のエクストリーム・ミュージックに対してインディへの架け橋を提示してきた〈スリル・ジョッキー〉が放っておくわけがない。コーラスやオーケストレーション、時にポスト・プロダクションによる大胆なインダストリアル的エディットを用いて孤高のサウンドを構築してきた彼らは、〈スリル・ジョッキー〉からの前作『クライスツ、レディーマース(Christs, Redeemers)』で、より大きなフィールドを得たのだ。そこに目を光らせたのが現在進行形インディ界随一の天才プロデュース・レーベル〈リヴェンジ・インターナショナル(RVNG Intl.)〉のマット・ウェルス(Matt Werth)である。彼はハクサン・クロークことボビー・ケリック(Bobby Krlic)をロンドンからニューヨークへ呼び出し、一週間スタジオに閉じ込めてジ・ボディのレコーディングのリミックスをおこなわせた。
リミックスという表現は的確ではない。それはハクサン・クロークの前作『エクスカヴェイション(Excavation)』で証明された彼の職人芸とも呼べる天才的なリ・エディット術を今回も我々に存分に堪能させてくれる。ローファイにフラット化されるザ・ボディの断末魔の叫び、スロッビング・グリッスルなベースライン、ブーストされた拷問ドラムのディケイと打ち込みビートの絡み合いは最高に心地よい。ギター・リフとわかる状態で並べた展開の一部だけはチョイダサいけども、そのあたりも自身のメタル・バックグラウンドをアピールしたいボビー・ケリックの思いととれば微笑ましいではないか。解体、再構築によって両アーティストの才能と経験が加算ではなく乗算された、近年まれにみる好例だ。
ザ・ボディを結成間もなくからつねに側で見守ってきた〈リヴェンジ・インターナショナル〉の敏腕プロデュースなくしては生まれなかった、最新型スタイリッシュ地獄絵図。「我ここに死すべし」にこめられた肉体の終焉と意識の宇宙的拡張を巡る漆黒の大スペクタクルにオサレ・ゴス・キッズも油ギッシュなノイズ/メタル・デュードも全員首と拳を振り下ろせ!
スカル・カタログが漏らしていたザ・ボディの乗り物恐怖症伝説──具体的にはある時ヨーロッパ・ツアーをブッキングされたが飛行機が怖すぎて船によって東海岸からヨーロッパへ渡ろうと試みたものの、出航後に恐怖で発狂。救命ボートで陸に引き返したというすさまじい逸話があるらしい。祈来日! ぜひともがんばって克服してほしい。