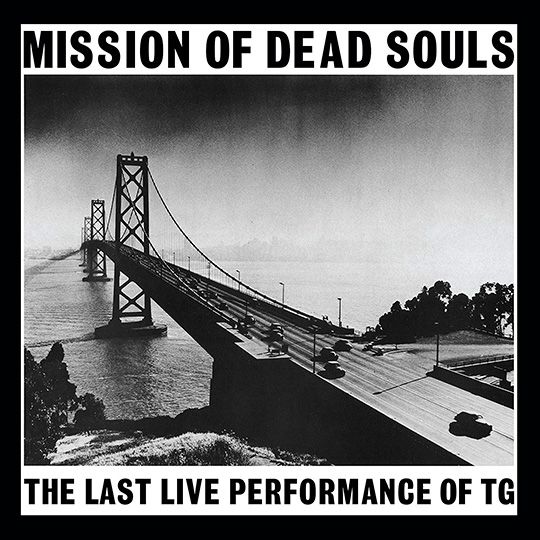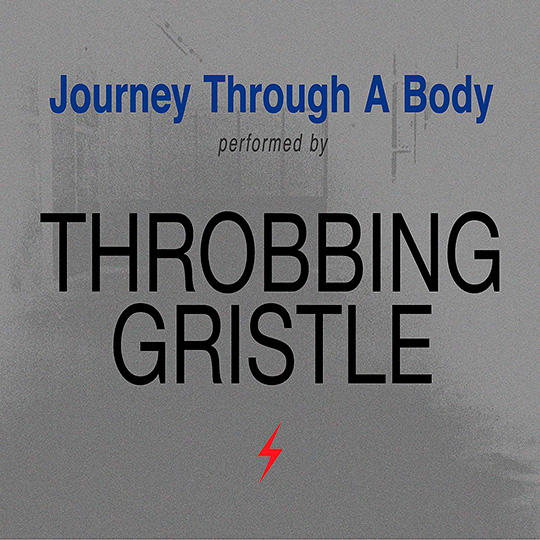怒濤の〈Brainfeeder〉祭り、続きます。かつて〈Stones Throw〉からデビュー・アルバムを発表し、マッドリブとのコラボや、エリカ・バドゥ、モス・デフ、ディーゴらの作品への客演で知られるLAのシンガーソングライター/マルチインストゥルメンタリストのジョージア・アン・マルドロウが〈Brainfeeder〉と契約、同レーベルより最新作をリリースします。国内盤CDとデジタルは10月26日に先行発売(輸入盤CD&LPは11月2日発売)。なお、10月24日発売予定の『別冊ele-king』には、彼女のインタヴューが掲載されます。そちらも合わせてご期待ください。
Georgia Anne Muldrow
現代のニーナ・シモンとも称される才媛、ジョージア・アン・マルドロウ、
フライング・ロータスをエグゼクティブ・プロデューサーに迎え、
設立10周年を迎えた〈Brainfeeder〉から待望の最新アルバムを発表!
アルバムから先行配信曲“Aerosol”が解禁!
彼女は本当に素晴らしいよ。ロバータ・フラックやニーナ・シモン、エラ・フィッツジェラルドを彷彿とさせる。特別な存在だよ。 - Mos Def
これからは彼女の時代だ。 - Ali Shaheed Muhammad(A TRIBE CALLED QUEST)
今年設立10周年を迎え、夏にはソニックマニアでステージをまるごとジャックしたアニバーサリー・イベントを大盛況のうちに終え、ますます勢いを増すフライング・ロータス主宰レーベル〈Brainfeeder〉。ロス・フロム・フレンズ、ドリアン・コンセプト、ルイス・コール、ブランドン・コールマンと怒涛のアルバム・リリース攻勢が続く中、フライング・ロータス自らがエグゼクティブ・プロデューサーを務めたジョージア・アン・マルドロウの〈Brainfeeder〉移籍第一弾アルバムが発売決定。
ケンドリック・ラマー、エリカ・バドゥ、ATCQ、ブラッド・オレンジ、マッドリブ、ビラル、ロバート・グラスパーら名だたるアーティストが支持する現代のニーナ・シモンとも称されるジョージア・アン・マルドロウにとって3年ぶりのオリジナル・アルバムとなる本作は、大半の楽曲を引き続き自らがプロデュースを行い、ピッチフォークでベスト・ニュー・トラックを獲得した先行シングルにしてタイトル曲“Overload”を含む4曲では、50セントからスヌープ・ドッグ、TDEやOFWGKTA諸作などを手がけてきた西海岸屈指のプロデューサー・デュオ、マイク&キーズ、共同エグゼクティブ・プロデューサーとしてフライング・ロータスに加え、アロー・ブラック、公私ともにパートナーであるダッドリー・パーキンスが参加した力作となっている。
アルバムからは2枚目となるシングル「Aerosol」が9月14日に公開。オランダ人ヒップホップ・プロデューサーのムーズを迎え、回顧的なリリックが映えるスローモー・ファンクを披露している。
Georgia Anne Muldrow - 'Aerosol'
https://youtu.be/nqGOU6d5pLA
「アルバム『Overload』は抑制の中での実験なの。私は、世界中の才能あるアーティストたちの力を借りて、できるだけ明瞭に自分自身を何らかの形に押し込めている。ライブはその解釈を実験する場になる。そこで私と(私のバンドである)ザ・ライチャスは、押し込めたその内容を楽しげな騒音に解放する。この二つのエネルギーがずっと私の中でバランスを取ろうとせめぎ合っていた。生まれたときから……あるいは何かをレコーディングしたいと思ったそのときから。そして、忍耐と規律と忠誠のおかげで、どこが力を入れるベストなポイントなのか、少しずつ明らかになってきた」
と本人が語る通り、彼女の偉大なキャリアにおいてもターニングポイントとなるであろうニュー・アルバム『Overload』は〈Brainfeeder〉より国内盤CDとデジタルが10月26日(金)に先行リリース(輸入盤CD/LPは11月2日発売)。国内盤CD歌詞対訳、解説書が封入され、ボーナストラックが追加収録される。またiTunes Storeでアルバムを予約すると、公開中の“Aerosol”、“Overload (feat. Shana Jenson & Dudley Perkins)”がいち早くダウンロードできる。
また、今回のリリースは〈Brainfeeder〉10周年キャンペーン対象商品となっている。
Brainfeeder10周年キャンペーン実施中

CAMPAIGN 1
対象商品お買い上げで、〈Brainfeeder〉10周年記念ロゴ・ステッカー(3種ランダム/商品に封入)をプレゼント!
CAMPAIGN 2
対象商品3枚お買い上げで、応募すると〈Brainfeeder〉10周年記念特製マグカップもしくはオリジナル・Tシャツが必ず貰える!
応募方法:
対象商品の帯に記載されている応募マークを3枚集めて、必要事項をご記入の上、官製ハガキにて応募〆切日までにご応募ください。
キャンペーン詳細はこちら↓
https://www.beatink.com/user_data/brainfeederx.php

label: BRAINFEEDER / BEAT RECORDS
artist: Georgia Anne Muldrow
title: Overload
国内盤CD BRC-583 ¥2,400+税
ボーナストラック追加収録 / 解説・歌詞対訳冊子封入
BEATINK.COM:
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=9857
Amazon: https://amzn.asia/d/eGBLizI
Tower Records: https://bit.ly/2xhrPvp
iTunes:https://apple.co/2Qo7axs
Apple Music:https://apple.co/2N6pJbz