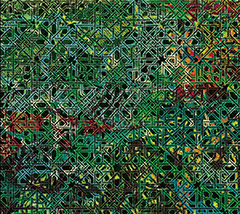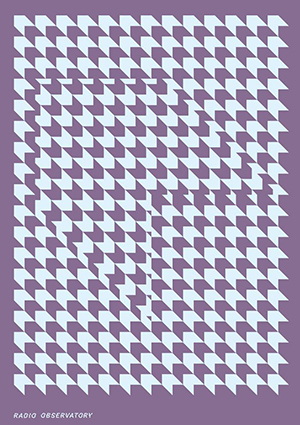キング・クルールは16歳でデビューしたが、ギターをかき鳴らしながら喚く皺がれて調子外れの歌声、シンプルなロックンロールを軸にブルースやフォークの香り漂うサウンドから、イアン・デューリー、トム・ウェイツといったアーティストを思い浮かべた人は多い。デューリーは身体障害者ということをさらけ出し、体を捩ってツバを吐きながらパフォーマンスした。ウェイツもアル中で浮浪者のような風体だけれど、そんなやさぐれたところが味だ。キング・クルールの歌はティーンエイジャーならではのナイフのような鋭さ、ガラスのような脆さを感じさせる一方、彼らのような汚いオッサンに通じる不格好さ、人生を諦観したような雰囲気があった。ウェイツとも親交が深かった酔いどれ詩人・作家、故チャールズ・ブコウスキーの作品を愛読するこの赤毛でソバカスだらけの青年は、その外見やサウンド、歌声からできるだけ装飾を排し、人間のいびつさやだらしなさ、弱さ、人生の不条理さを綴っているようだった。
キング・クルールことアーチー・マーシャルは、最初はズー・キッドやDJ JDスポーツといった名義を使い、その後キング・クルール名義で2011年にEP、2013年にファースト・アルバム『月から6フィート下(6 Feet Beneath The Moon)』を発表してきた。ジーン・ヴィンセントのようなロックンロール、ジョー・ストラマー(ザ・クラッシュ)、モリッシー(ザ・スミス)のようなパンク~ポスト・パンク、ジョイ・ディヴィジョン、コクトー・ツインズのようなニュー・ウェイヴ~ダーク・ウェイヴ、ジョン・ルーリー(ラウンジ・リザーズ)、ジェイムズ・ホワイト&ザ・コントーションズのようなパンク・ジャズ~ノー・ウェイヴ、ギャングスターにJ・ディラをはじめとしたヒップホップ、ルーツ・マヌーヴァからワイリーと連なるUKのラップ~グライム、さらにチェット・ベイカー、フェラ・クティからペンギン・カフェ・オーケストラなどいろいろな音楽の影響を受け、そのダウナーなサウンドにはトリッキーのようなブリストル・サウンド、ブリアルのようなダブステップも透けて見える。『月から6フィート下』はジェイミーXX、ジェイムズ・ブレイクら同時代のアーティストの作品と同じ土俵に並べられ、「新世代のビート詩人」というような評価を得た。そして、セカンド・アルバムとなる本作では初めて本名のアーチー・マーシャルを使っている。
本作は少し変わった体裁で、いままでもキング・クルール作品のアートワークを手掛けた実兄のジャック・マーシャルとの共同制作による208ページに及ぶアートブックが付けられ、そこに散りばめられたイラスト、写真、詩などから南ロンドンでの彼らの日常風景を垣間見ることができる。音楽はそれに対する一種のサウンド・トラックという位置づけだ(いまのところリリースはデジタル配信のみ)。SEやTVから取ってきたようなナレーションを随所に挟み、きっちりと作り込んだ楽曲集というより、いろいろな素材の断片を繋ぎ合わせたミックステープという色合いが強い。『月から6フィート下』は根本的にはシンガー・ソングライター的な資質を打ち出したロック・アルバムだったと思うが、本作のサウンドはよりダビーでエクスペリメンタルな傾向が強まり、“ダル・ボーイズ”などはディーン・ブラントの作品のようでもあるし、場面によってはアンディ・ストット、シャクルトンあたりを彷彿とさせるところもある。“アライズ・ディア・ブラザー”“アイズ・ドリフト”“エンプティ・ヴェッセルズ”のようにヒップホップ的なビート感覚がより前に出ている点も特徴だし、“ザ・シー・ライナー・MK1”のようにポスト・ダブステップ色が濃厚な曲もある。たしかに『月から6フィート下』にもそうした彼のサウンドの下地を匂わせる部分もあったが、それよりも前面に出た歌の強烈さが勝っていた印象だ。もちろん本作でもその独特の歌声は大きな要素となるが、それよりもちょっとしたノイズやSE、音響も含めたサウンド全体のコマのひとつとして表現する傾向が強い。そんな違いもあって、今回はキング・クルールではなくアーチー・マーシャルの名前で発表し、キング・クルールとしてはまた別の形でアルバムを作っていくのだろう。そう考えると、キング・クルールとはあるひとつの人格を借りて表現したプロジェクトであり、じつは本作の方がアーチーの素の部分が出ているという見方もできるが、果たしてどうだろうか。