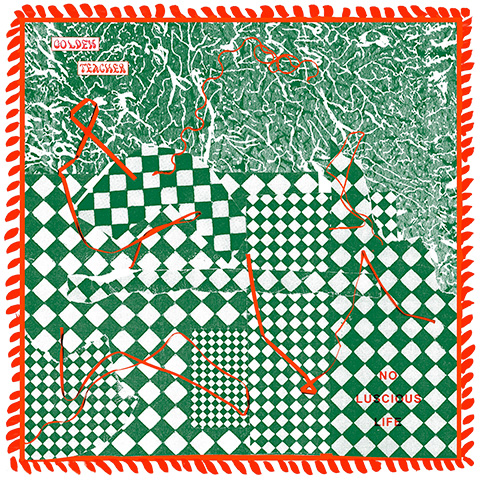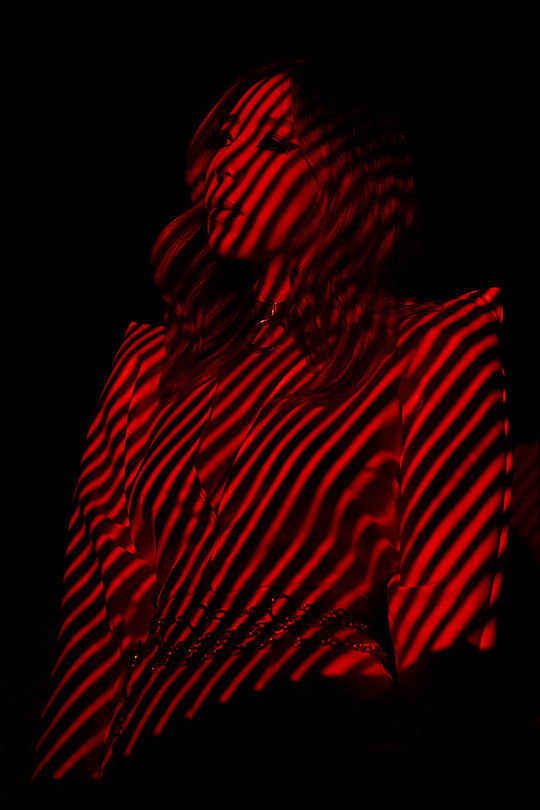おかげさまで好評をいただいております、田亀源五郎(著)『ゲイ・カルチャーの未来へ』ですが、その出版を記念したトーク・ショウが大阪にて開催されます。出演は田亀先生ご本人と、『ゲイ・カルチャーの未来へ』の編集を担当したele-kingでもお馴染みの木津毅! 日時は12月10(日)で、会場は難波のロフトプラスワンWESTです。当日は田亀先生によるサイン会も予定されており、嬉しいことに『ゲイ・カルチャーの未来へ』以外の田亀作品の持ち込みも可とのこと。詳細は下記またはこちらより。ぜひ足をお運びください!
『ゲイ・カルチャーの未来へ』出版記念
田亀源五郎スペシャル・トーク・ショウ in 大阪
日本を代表するゲイ・エロティック・アーティストであり、近年は初の一般誌連載『弟の夫』のヒットで知られる漫画家・田亀源五郎。
その初の語り下ろし本である『ゲイ・カルチャーの未来へ』の刊行を記念して、トーク・ショウを開催します。
日本のゲイ・アート・シーンのパイオニアであり、近年さらに多彩な活躍を見せる田亀氏独自の視点から、自身のキャリアやポリシー、日本における様々なゲイ・イシュー、そしてゲイ・カルチャーの現在と展望を語りつくします。
聞き手は同書の編集人であるライター・木津毅。
Q&Aやサイン会も予定していますので、貴重な来阪の機会をお見逃しなく!
※サイン会では、『ゲイ・カルチャーの未来へ』以外の田亀源五郎作品の持ち込みにも対応いたします。
ele-king Books「ゲイ・カルチャーの未来へ」
https://www.ele-king.net/books/005951/
■日時:12月10日(日)
12:00 OPEN/13:00 START
■会場:ロフトプラスワンWEST
https://www.loft-prj.co.jp/west/access
■入場料:前売¥2,000(飲食代別) / 当日¥2,500(共に飲食代別)
※要1オーダー¥500以上
Studio FATEのカレー販売もあります。
前売券はイープラス、ロフトプラスワンウエスト店頭&電話予約にて発売開始!
■購入ページURL(パソコン/スマートフォン/携帯共通)
https://sort.eplus.jp/sys/T1U14P0010843P006001P002244108P0030001
ロフトプラスワンウエスト電話→0662115592(16~24時)
※ご入場はプレイガイド整理番号順→ロフトプラスワンウエスト店頭&電話予約→当日の順となります。
--トーク出演者--
田亀源五郎 (たがめ・げんごろう)
1964年生まれ。漫画家、ゲイ・エロティック・アーティスト。
1986年よりゲイ雑誌に漫画、イラストレーション、小説などを発表。1994年から専業作家となり、ゲイ雑誌『G-men』の企画・創刊にも携わる(2006年に離脱)。『嬲り者』、『銀の華』、『PRIDE』、『外道の家』、『君よ知るや南の獄』、『冬の番屋/長持の中』、『エンドレス・ゲーム』、『奴隷調教合宿』など、多数のゲイ漫画を単行本で発表。同時に、日本の過去のゲイ・エロティック・アートの研究、およびその再評価活動を行い、『日本のゲイ・エロティック・アート』シリーズの編著を務める。また、アーティストとしてはパリ個展やニューヨーク個展をはじめ、アメリカ、イギリス、ドイツなどのアートブックへの作品掲載も多数。
2014年からは『月刊アクション』にて初の一般誌連載である『弟の夫』を開始、同作は第19回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞した。
WEB: https://www.tagame.org/
blog: https://www.tagame.org/jblog/
木津毅 (きづ・つよし)
1984年生まれ。ライター・編集者。映画、音楽、ゲイ・カルチャーなどについて執筆。ele-king、カジカジ、ミュージック・マガジン、the sign magazineなどに寄稿。田亀源五郎・著『ゲイ・カルチャーの未来へ』編集。
--フード出店--
StudioFATE
雁字搦めな既存のレシピからの逃亡。より安全で愛情のある食の彼方へ。しれっと日常に入り込みハッとさせる社会活動として俄カリー屋断続中。
空堀の裏路地の複合型アトリエ "StudioFATE" にて、持続可能で創造的な生活提案を実践中。
Blog: https://news.fatalbackground.org/
FBページ: https://www.facebook.com/fatalbackground/