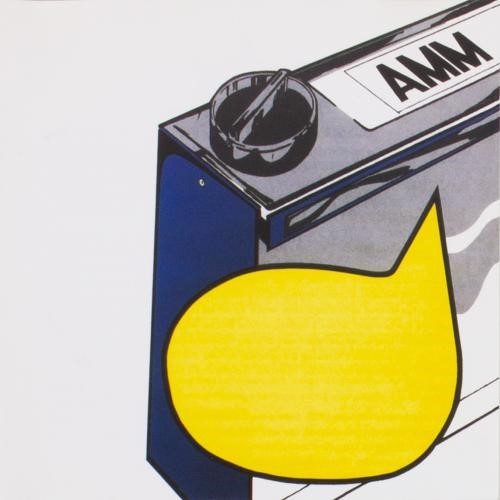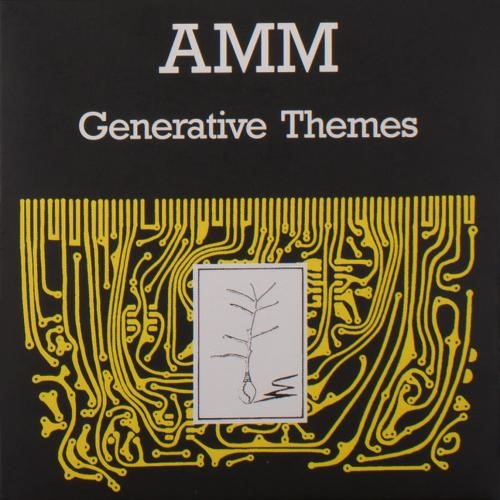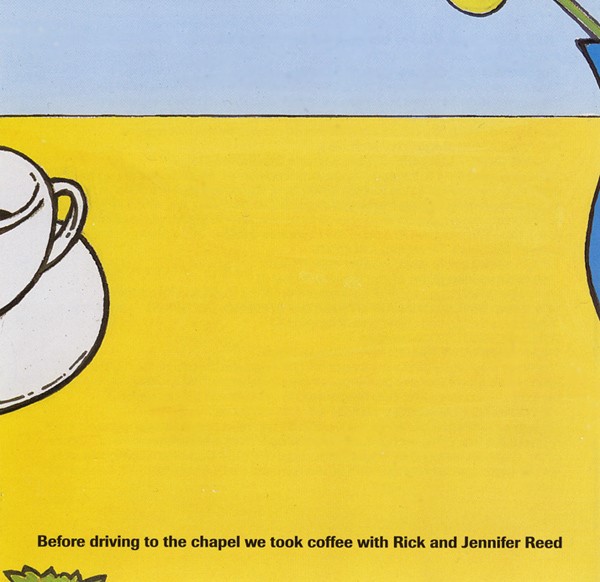イタリアのテクノ系プロデューサー、シェヴェル(シュヴェール?)ことダリオ・トロンシャンによるダブルパック『In A Rush And Mercurial』が興味深かった。これは4月にリリースされた彼の5thアルバム『Always Yours(いつもあなたを思っています)』がどのようにしてつくられたかを想像させる内容だったのである。彼は3年前までダブ・テクノにグライムを持ち込むことで大きな興味を引いた存在だった。その彼がマムダンスのレーヴェルに移り、さらにウエイトレスと呼ばれるジャンルにチャレンジし、またしても大きな飛躍を見せたのが『Always Yours』であった。個人的にはいまのところ今年のベスト・スリーに入る充実作である。2枚のEPから構成された『In A Rush And Mercurial』は一聴すると『Always Yours』よりも以前のスタイルに揺り戻したかのような印象を与える。実際にそうだったのかもしれない。しかし、『In A Rush And Mercurial』は『Always Yours』を作り上げる段階で捨てられた曲をまとめて出したと考えた方が得心のいく曲が多い。彼はダブ・テクノにもウエイトレスに通じる部分はあると考えているようだけれど、それまで彼の重心部分であったダブ・テクノの比重を減らし、グライムからウエイトレスを抽出して後者の方法論を肥大させていく過程でダブ・テクノから充分に脱却できなかったものを一度は捨てたのではないかというストーリーを勝手に組み上げてみたくなるのである。『In A Rush And Mercurial』もよくできてはいる。しかし、先に『Always Yours』を聴いてしまった耳には『In A Rush And Mercurial』は物足りなくなる部分があるし、逆に言えば『Always Yours』がどれだけ跳躍力が高かったかをあらためて実感できたともいえる。
マーラのDJがUKサウンドとの出会いだったというトロンシャンはウエイトレスに進路を定める上でとくに参考にした曲としてフランコ・バティアトーの6thアルバムから「Za」を挙げている。バティアトーは70年代のイタリアン・プログレッシヴ・ロックでもけっこうな異端児で、「Za」はとくにストレンジでコンセプチュアルな曲といえる(『アンビエント・ディフィニティヴ』P152)。そして、これとまったく同じ発想で作ったとしか思えない曲がローレル・ヘイローの5thアルバムにもフィーチャーされていた。“Quietude”である。スカしたタイトルはヴァンガード・ジャズ・オーケストラが60年代に録音していた曲と同じだけれど、それとは関係がないようで、バティアトーを飛び越えて、さらにその向こうにいるジョン・ケージやプリペアード・ピアノから着想を得たものなのだろう。トロンシャンでいえば『In A Rush And Mercurial』に収録された”Faded”にかなり近いものがあり、ふたりが同じところをウロウロしているのは間違いない。
『Raw Silk Uncut Wood』は、そう、オリヴァー・コーツのチェロをフィーチャーしたタイトル曲からしてモロだし、全体にミュジーク・コンクレートからのフィードバックが濃厚な1枚で、イーライ・ケッセラーのドラムを使い倒した“Mercury”ではフリー・ジャズ、“The Sick Mind”ではリュック・フェラーリのような名前がどうしても浮かんでしまう。あるいは例によって解体されたデトロイト・テクノのリズムにも強く注意が払われ、そのことによってトロンシャンとも同じく現在形の表現になっていることも保障されている(デリック・メイたちに“Mercury”の感想を訊いてみたい!)。テーマ的にはオランダのデザイン・スタジオ、メタヘヴンとアーシュラ・ル・グインが訳した道教の本からインスピレーションを得たそうで、音楽とイメージをどう結びつけるかはなんとでも言えるし、ああそうですかとしか言えないので、観念的な側面は省略。イージーにいえば瞑想的で静謐な曲が多い。
ローレル・ヘイローのサウンドはそれにしても完成度が高く、女子高生言葉でいうところの「雑味」がまったくない。だからといって息苦しいわけでもなく、冒険のセンスにもあふれている。リリース元はエナ『Distillation』や今年に入ってイヴ・デ・メイ『Bleak Comfor』をリリースしたフランスの〈レイテンシ〉。当初はシカゴ・ハウスやデトロイト・テクノを発していたものが、すぐにも実験的な作品ばかり扱うようになったレーベルである。『Raw Silk Uncut Wood』のエンディング、“Nahbarkeit(親しみやすさ)”をヴォルフガング・フォイト(マイク・インク)のガス名義に喩えたレヴューがいくつかあったので、たまたま同時期にリリースされたガス名義の6作目『Rausch(酩酊)』を聴いてみたら、まあ、確かにそうかなとも思いつつ、意外にもヘイローの方が快楽的だったので、クラブ・ミュージックの連続性も切り捨てられてはいないといえる。ちなみにトロンシャンも『Flowers From The Ashes: Contemporary Italian Electronic Music』でリュック・フェラーリを思わせる極上のアンビエント・チューンを聞かせくれる。