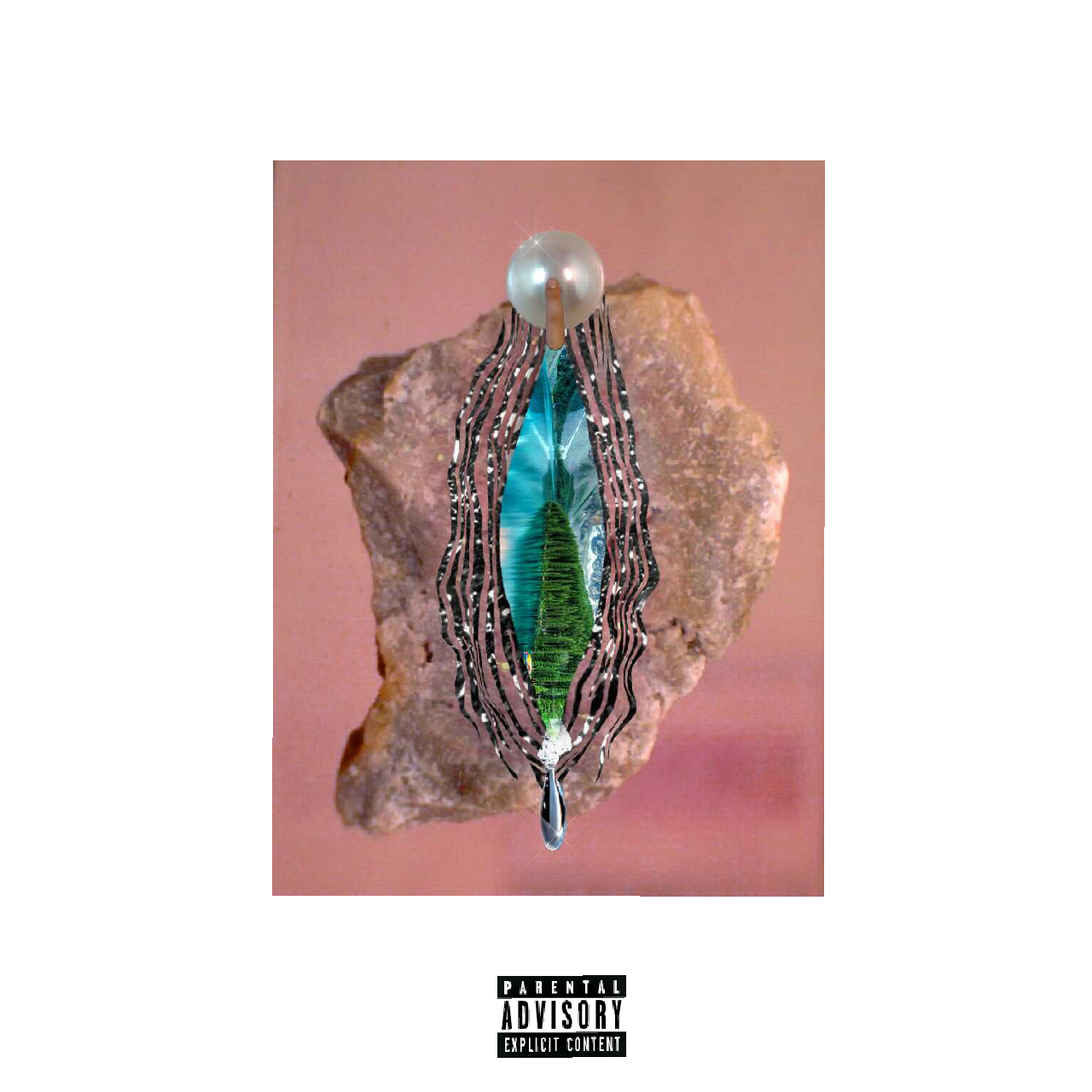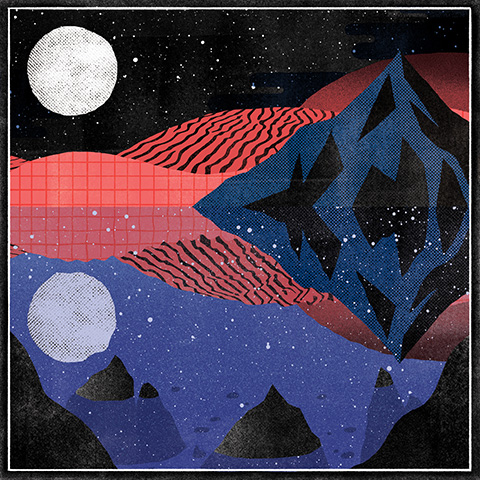10 records in my bag now (no particular order)
 |
LK - Keion - Shall Not Fade |
|---|---|
 |
YOU SPEAK WHAT I FEEL – My Good Friends Tell Me That - Boomkat Editions |
 |
A. GARCIA - Docile #27 - Docile |
 |
SECRET SOCIETY – EP - Secret Society |
 |
OL - Lada Passenger - Fit Sound |
 |
VINYL SPEED ADJUST – Passing Waves EP - Crystal Structures |
 |
ORANGE WATER - Lo Tek / Love Life - Archive |
 |
FUTURE BEAT ALLIANCE – Audio Photos - Delsin |
 |
TITONTON - The Explicit EP - Neroli |
 |
NUBIAN MINDZ – New World Chaos - Archive |
岡山県倉敷市在住。神戸UNDERGROUND GALLERYバイヤー。
- dates -
2017.5.7 (Sun) at 神戸troopcafe “20YEARS of RUSH HOUR in KOBE” w/ANTAL, SOICHI TERADA, SAN PROPER
2017.5.26 (Fri) at 浅草Pure’s “How High” w/KABUTO, ONO, RYOKEI
2017.5.27 (Sat) Somewhere in Tokyo
https://www.undergroundgallery.jp
https://www.facebook.com/djyukke