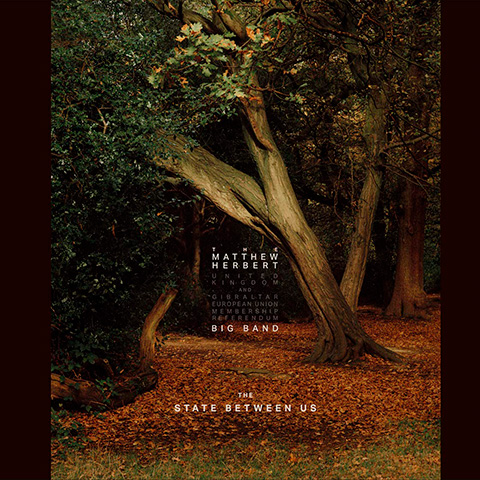世界で最初のハウスのレコードを作った男が綴るリアルな歴史
シカゴ・ハウスとは、どのように生まれ、どのように発展し、どのようにしくじり、どのように世界でもっとも愛される音楽スタイルになったのか
解説:西村公輝
自分のように、ハウス・ミュージック(とくにシカゴにおける)の成り立ちというものに少しでも興味を持っている者としたら、ハウス・ミュージック勃興期の出来事の大部分は想像/妄想を働かせる以外にない“ブラックボックス”と化しており、本書ではそれこそ目から鱗の剥がれ落ちるがごとくの貴重な証言が続々と飛び出してくることに感動する。 (解説より)
英「FACT mag」の“読むべきエレクトロニック・ミュージックの本10冊”のうちの1冊にも選ばれた、決定的なドキュメント
シカゴで生まれ世界で愛されているダンス・ミュージックの初期の物語
■著者
ジェシー・サンダース (Jesse Saunders)
1962年生まれ、シカゴ出身のDJ、プロデューサー。“ハウス・ミュージックのオリジネーター”と称されている。80年代、地元シカゴでハウス・ミュージックという新たな音楽ジャンルを発明し、1983年にハウス・ミュージック初のレコーディング作品となる“ファンタジー”を制作、1984年にはハウス・ミュージック初のリリース作品となるシングル「オン・アンド・オン」を発表する。その後、ハウス・ミュージックのクラシック、“ラブ・キャント・ターン・アラウンド”や、ハウス・ミュージックとしてはじめてビルボード・チャートにラインクインした“ファンク・ユー・アップ”といった初期ハウス・ミュージックの重要作品を次々と手がける。さらに、自身のレーベル〈Jes Say Records〉に加え、ラリー・シャーマンらとともに〈Trax Records〉を共同設立。〈Trax Records〉からは、数多くのハウス・ミュージックのクラシック作品がリリースされている。また、1986年には、ジェシーズ・ギャングとして、〈Geffen Records〉とメジャー契約し、アルバム『センター・オブ・アトラクション』をリリースしている。以降、現在まで、DJとして世界各国のさまざまなヴェニューでプレイし、プロデューサー、リミキサーとしても数多くの作品を手がけている。
https://www.jessesaunders.com/
■訳者
東海林修
青山学院大学大学院総合文化政策学研究科修士課程修了。青山学院大学総合文化政策学部附置青山コミュニティラボ(ACL)特別研究員。オンライン・ミュージック・マガジン「UNCANNY」を主宰、編集長を務める。またこれまで、A&Rとして様々な作品を手がけている。
市川恵子
エディンバラ大学大学院文学研究科中国文学専攻修了。国内広告代理店、音楽出版社にて、国内外のコンテンツビジネスを担当し、現在は主に、フリーの通訳者、翻訳者として活動する。
目次
プロローグ
第一章 サンダース家
第二章 ジェシー・ザ・DJ
第三章 ウェアハウス・ミュージック
第四章 ファンタジー──夢が現実になるとき
第五章 ハウス・ミュージック
第六章 不意打ちの痛み
第七章 新たな震源地
第八章 ファミリー・ツリー
第九章 間違った方向
第一〇章 終わり、そして、はじまり
第一一章 ハウス・ミュージックを愛するすべての人びとに
解説 世界はハウスの仮想庭園になった (西村公輝)