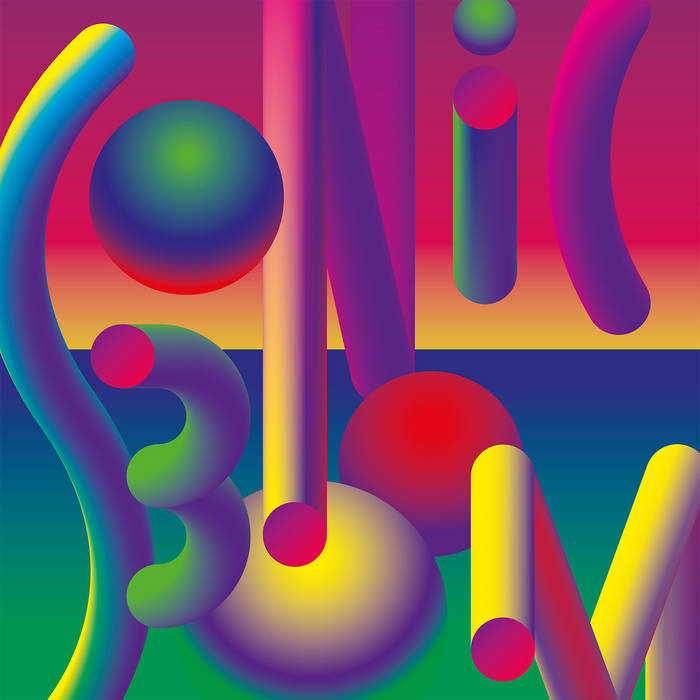家から15分ほど歩くと遠くから小さな悲鳴が聞こえてくる。そのまま「悲鳴」に向かって歩いていくと、どんどん悲鳴は大きくなり、複数の声になっていく。やがて視界にメリーゴーラウンドが飛び込んできて悲鳴の正体がジェットコースターだと判明する(ゴーよりヒヤアーの方が遠くまで聞こえるんですよ)。豆乳や野菜ジュースを買おうと後楽園のドンキホーテに向かって歩いていると、いつも経験することである。最初の頃はなんだかわからなくて気味が悪かったけれど、最近は悲鳴が小さいと少し物足りなく感じたり。夕方ぐらいに行くと東京ドームから「ドーン」という地鳴りが轟いてくることも。一拍遅れて「ワー」という歓声。野球だろうか。それともコンサートか。中日戦の時は試合が終わる前に帰らないと道が通れなくなってしまう。嵐のコンサートの時は「友だちの1人に加えてください」という札を持った少女がポツポツと道に並んでいる(多分「チケット売ってください」の意)。後楽園の周囲にはマンションも多いので、僕のように散歩ついでに悲鳴を聞くどころか、1日中、一定間隔で悲鳴を聞いている人もいるのだろう。いまは静まり返っているけれども。観覧車もピタッと止まったまま。
都会の喧騒や佇まいをテーマにして子熊ちゃん(Bearcub)はセカンド・アルバムをつくったという。子熊ちゃんことジャック・リッチーは映画のサウンドトラックをつくるために半年前からベルリンで暮らし、パブで働いていたロンドンとの違いをあれこれと噛み締めたものらしい。アルバム・タイトルの『Early Hours』というのは朝までクラブで遊び、そのあとの時間=午前中のこと。別な目で見た日常。もつれた日常や友だちと喧嘩して仲直りしたとか、そういう些細なことを歌詞にしたと本人は話している(基本的にはどうにでも取れるような書き方だという)。クラブからの朝帰りは確かに妙な体験である。同じ風景が同じ機能を果たしているようには思えない。牛丼屋が何のためにそこにあるのかもわからず、みんなで大笑いしてしまう(キマっているわけではありません)。会社に向かって行く人たちと逆方向に進んで行くことも、それだけでレッドピルを飲んだような気分になれた。誰かの家に転がり込んで、そのままグズグズと寝てしまうまでの時間。少しでも資本主義の外側に出た気分だろうか。
デビュー・アルバムはジェームス・ブレイクの下手くそな模倣という印象だったものが(本人はベリアルやフライング・ロータスに影響を受けたそうだけど)、2年ぶりとなる新作は格段の成長を遂げている。リズムが全体にしっかりとしてきたというか、マック・デ・マルコがエレクトロニック化したといえば細野ファンなどの関心を引けるだろうか(引かなくていいんだけど)。オープニングからもの悲しくてテンポのいいタイトル曲。淡々としてクールな“Diversions”へと受け継がれ、日常の隙間に溶けていくような淡いメランコリーが持続する。ザ・XXを思わせる“Même Langue”から、まさかのゴムを取り入れた“Everyplace Is Life”。ブレイクでゆっくりと曲の叙情性にひたらせるあたりは前作にはなかったスキル。セイント・エティエンヌやヴァンパイア・ウイークエンドのファンもこれは納得だろう。スティール・パンを取り入れた”Overthinking”は「考えすぎ」というタイトル通り、内省的なラテン・ポップスで控えめなアレンジはもう職人技の域。短いインストゥルメンタルを挟んで“Rubicon Guava”ではシクスティーズを思わせつつペイル・ファンテインズがトラップやUKガラージを取り入れたような展開に……残りはお楽しみということで。最後の最後までとてもいい。