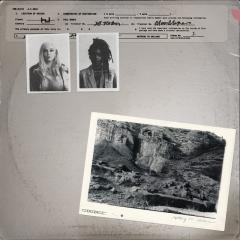一昨年に設立25周年を迎え、去る2021年もDJマニーやヤナ・ラッシュ、RP・ブーなど変わらず力作を送り出した〈Planet Mu〉。同レーベルを率いるマイク・パラディナス本人によるプロジェクト、ミュージック(µ-Ziq)名義の新作EP「Goodbye」が4月1日にリリースされる。
今年2022年は代表作『Lunatic Harness』の25周年にあたり、夏にリイシューが予定されているのだが、それを中心に展開される新作シリーズの一発目に当たるのが今回のEPだという。なんでも、『Lunatic Harness』のリマスタリング中に過去のアーカイヴに触れる過程でインスパイアされたのだとか。美しい和音とグリッチ、ジャングルのリズムが融合した表題曲が現在公開中です。

artist: µ-Ziq
title: Goodbye
label: Planet Mu
release: 1st April, 2022
tracklist:
1. Goodbye
2. Giddy All Over
3. Moise
4. Rave Whistle
5. Rave Whistle (Darkside Mix)
6. Rave Whistle (Jungle Tekno Mix)