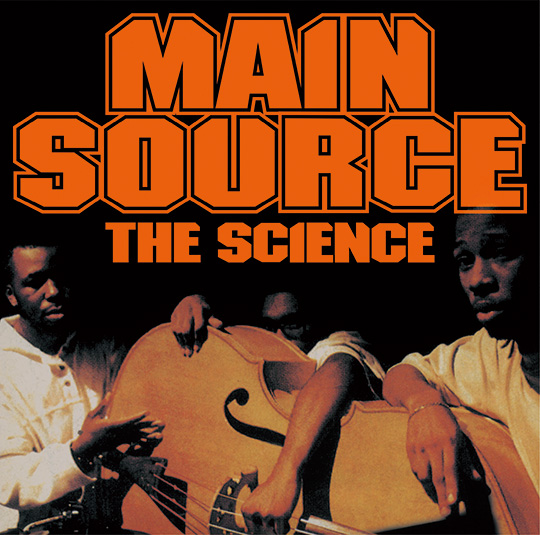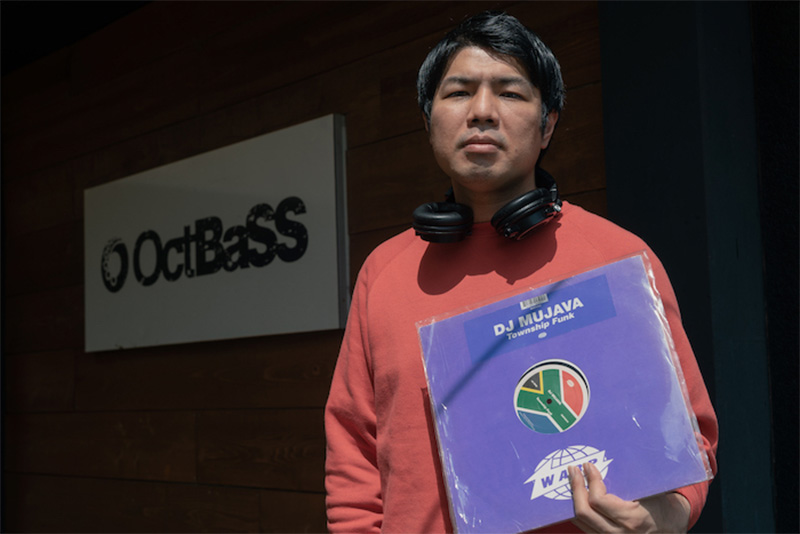家から一歩でも外に出ると、ふらふらと倒れそうになる。熱線そのものである日差しがあまりにも暑く、熱く、痛い。
2023年、日本の7月は、観測史上最高の暑さになったという。昨日、東京のある巨大ターミナル駅に仕事で行ったとき、エスカレーター付近でスーツ姿の初老の男性が気を失って倒れており、警察官などがその人を囲っていた。「気候変動の被害者だ……」と思ってしまった。
とはいえ、「酷暑」という言葉以上にふさわしい表現が見当たらない今夏においても、この夏の暑さを音楽とともに楽しもうじゃないか、と誘ってくるレコードがある。享楽的なダンス・トラックも、涼やかで内向きなチルアウトも収められているジェシー・ランザの4作め、3年ぶりのニュー・アルバム『Love Hallucination』だ。特に今回は、あまりにもオプティミスティックな椰子の木のカヴァー・アートが物語るとおりの楽しいレコードである。ジェシーが移り住んだLAは、東京よりは過ごしやすいのだろうか。
クラブにはあまり行かない、クラブ・カルチャーがルーツというわけではない、メロディのあるダンス・ミュージックが好き、とはこのアルバムについて本誌のインタヴューで語っていたこと。個人的にすごく共感してしまったのだけれど、それはともかくとして、彼女のそういう個性は、『Love Hallucination』の雑食性と、あくまでもレフトフィールドには振り切れないポジティヴなポップ・ヴァイブに表れている。
ジェシーの雑食性については、いまに始まったことではないものの、1曲めの “Don’t Leave Me Now” がハウスで、次の “Midnight Ontario” がUKガラージ/2ステップ調で……という取り留めのなさに明らかだ。『Love Hallucination』と同時期に制作していたという『DJ-Kicks: Jessy Lanza』(2021年)にしたって、自作のフットワークである “Guess What” から、ちょっとスピリチュアルなムードでスタートする。ジェシーのパレットは常にカラフルかつ賑やかで、彼女はそこからお気に入りのビートやテクスチャーを選び取り、それを煌びやかなダンス・ポップに仕立て上げてみせるのだ。野田努編集長は以前、これについて「ポストモダン的感性」と評していたが(https://www.ele-king.net/interviews/007776/)、つまりはなんでもありなのである。
とはいえ、その手つきは、『Pull My Hair Back』(2013年)や『Oh No』(2015年)など、かなりローファイでベッドルーム的だった初期の作品に比べると、ずいぶん洗練されている。前作の『All the Time』(2020年)と比較してみても、特にアルバムの心躍る前半部はもっとダンス・オリエンティドで、なおかつ朗らかでわかりやすいメロディ志向になった。たとえば、同時期にリリースされたジョージアの『Euphoric』やカーリー・レイ・ジェプセンの『The Loveliest Time』といった優れたダンス・ポップ・アルバムと並べて聴いてみても、『Love Hallucination』の華やかな力強さが感じられるだろう。
アルバムからのファースト・シングルだった “Don’t Leave Me Now” は、楽天的なムードに貫かれた、アッパーなハウスだ。プロダクションはシンプルではなく、練りこまれている。速いテンポで打ちこまれるキック、聴き手を急き立てるようなパーカッションとドラム・マシーンのビートにのせて、ジェシーは狂おしいR&Bヴォーカルを披露し、ファルセットで天上へと突き抜けていく。
続く “Midnight Ontario” は、世界を席巻中の NewJeans から、密かに盛り上がっているNYCガラージまで、UKガラージ/2ステップがちょっとしたリヴァイヴァルを起こしていることとの共振を感じさせる。この曲をジェシーとともに手がけているのはジャック・グリーンで、〈LuckyMe〉を拠点に〈Night Slugs〉や〈UNO〉からも作品を発表した経験がありつつ、R&Bヴォーカルの扱いにも長けている彼の手腕が発揮されていると言えるだろう。ピアソン・サウンド=デイヴィッド・ケネディが要所要所に参加していることもあって、『Love Hallucination』は、米国と英国の地下を繋げて歌ったダンス・ポップ・レコードだと言うこともできそうだ。
LPからのラスト・シングルになった、テンスネイクことマルコ・ニメルスキーとの “Limbo” は、初期ヒップホップを思わせるエレクトロ・ファンク。と、ここまでジェシーは、あっちに行ったりこっちに行ったりと、忙しない。
一方、ジャム・シティを思わせるUKベース的な “Big Pink Rose” やデトロイト・テクノっぽいムードを纏った “Drive” などが構成する中盤からは、踊りやすさやメロディを志向するというよりは実験に寄っていき、耳への刺激は驚きが心地よさを上回る。ここではヴォーカルも、トラックを織りなす素材の一部のような扱われかたである。細野晴臣風のエキゾティシズムが横溢した浮遊感たっぷりの “I Hate Myself”(ジェシーはYMOのファンでもある)は、リリックとの落差もあって、なかなかユニークだ。
ダニー・ブラウンやオボンジェイアーなどとのコラボレーションでも知られるポール・ホワイトと初めて制作した “Marathon” は、「クリスタル」と形容したい80年代的な雰囲気が濃厚である。サックス・ソロやシンセサイザーの音色は、手前の “Gossamer” と次のクローザー “Double Time” と結びついて、多分にニューエイジ風で瞑想的。このあたりからはLAの風土や文化が薫ってくる気がするし、それはジェシーの初期のレコードや彼女が好むR&Bとの接続が立ち上がってくる面でもある。
『Love Hallucination』の印象を決定づけ、新鮮なイメージを聴き手に植えつけるのは、見事なシングルを立て続けに叩きつける冒頭の鮮烈な3曲である。「このアルバムで『信頼』と『脆弱さ』というテーマを描いてみた」とジェシーが語っていることを踏まえると、ポップで踊れる挑戦的な前半部は彼女から他者(新たに手を組んだプロデューサーたち)への「信頼」を、次第に実験的かつ内省的になっていく中盤以降は彼女自身の「脆弱さ」を表しているのではないだろうか。
このアルバムは、エアコンが効いた部屋で聴いてもいいし、手元のデヴァイスにダウンロードして外で聴いてもいい。ただ、「外で」とはいっても、人命が危機にさらされそうな8月の日本の日中よりは、シングルの “Don’t Leave Me Now” のカヴァー・アートのような、涼しくなってきた夕方に水分を補給しつつ、適度に涼みながら、という条件つきではあるものの……。