幻の作品とされてきたゴッドスピード・ユー!ブラックエンペラーが1993年に録音したカセットテープ作品『all lights fucked on the hairy amp drooling』、すなわち彼らのもっとも初期の録音物が先日インターネット上に流出したことを受けて、バンドはbandcampにて正式にリリースすることにした。
なお、この売り上げはCanadians for Justice and Peace in the Middle Eastという慈善団体を通じて、ガザ地区への医療用酸素提供のために寄付される。
「K A R Y Y Nã€ã¨ä¸€è‡´ã™ã‚‹ã‚‚ã®
素晴らしい音楽や映画、あるいは書物というのは、思いも寄らなかったところに入り込み、硬直した視野を押し広げてくれるものだ。石橋英子の『The Dream My Bones Dream』には、いち個人が日本史の靄のかかった奥に潜り込んでいくという点において、村上春樹の『ねじまき島クロニクル』を彷彿させるところがあった。だからといって、彼女が濱口竜介監督の、傑出したこの映画のサウンドトラックを引き受けることになったわけではないだろう。ようやく時間が持てたので、ぼくは『ドライブ・マイ・カー』を観た。そして3時間後には、しばらく席から立てないほど打ちのめされた。エンドロールでかかる石橋英子の曲は、車がギアチェンジしたことさえわからない滑らさをもって、しかし映画の深い余韻をしっかりと引き受けている。
石橋英子は、このサウンドトラックを2曲に集約させている。表題曲“Drive My Car”、映画においてもっとも印象的なチェーホフからの引用を曲名とした“We'll Live Through The Long, Long Days, And Through The Long Nights(長い長い日々を、長い夜を生き抜きましょう)”。アルバムには、この2曲をもとにした合計10ヴァージョンが収録されている(*)。とはいえ、10曲といっても差し支えないくらいに、個々それぞれ違っている10作品でもあるのだが、日々ひっきりなしに往復する車と同じように、それぞれの楽曲にもアルバム全体にも反復性がある。また、劇中でかかっている多くは、おそらく楽曲の断片で(まだ一度しか観ていないので、正確なところはわからない)、石橋英子のサウンドトラックは映画の音をそのまま再現しているわけではなく、それらをもとにひとつの独立したアルバム作品として再構成しているようだ。
映画は静かにゆっくりと、一見なんの変哲もない日常のなかで、登場人物たちそれぞれが個々の悲しみを打ち明けていく。自分に何が起こっているのか理解することそのものが困難な、いつ日常がひっくり返っても不思議ではない不安定な(村上ワールドでたびたび描かれている)日々において、安定しているのは登場人物みさきの運転ぐらいなものとなっている。変わりない時間軸といっしょに、残酷なまでに変わっていく時間軸が併走し、ドライブする車がいつの間にか車線変更するように映画はそのどちらかを走っている。こうした微妙なニュアンス、さりげない場面の意味的な移り変わりを、石橋英子(そしてジム・オルークと山本達久をはじめとする演奏者たち)は、ゆったりとスウィングするリズムとさまざまな表情の小さなメロディ、効果的なサウンドコラージュと起伏に富んだストリングス、そして電子音による音数少ないテクスチュアによってじつに巧妙に表現したと思う。主人公の家福が演劇の稽古で、役者たちに台詞を(下手に感情を込めずに)棒読みにするよう徹底させるシーンがある。感情は自分が勝手に与えるものではなく、言葉のほうから与えられるものだということなのだろうけれど、この音楽も似ている。情緒を押しつけるのではなく、それは聴き手のうちなるところから生まれるべきだと、それが主張を控えたこの音楽の主張だろう。
石橋英子は特定のジャンル作家ではない。いろんなスタイルでたくさんの音楽を作っている。先鋭的な実験音楽から親しみやすいポップス、ジャズからアンビエントまで。そうした彼女の多彩なところも、本作ではうまくまとまっているんじゃないだろうか。優雅で美しいピアノが旋回する“Drive My Car”の(Misaki)、サウンドコラージュとサティ風のピアノによる同曲の(Cassette)。山本達久の趣あるドラムと茫洋とした電子ドローンをフィーチャーする“We'll Live Through 〜”の(SAAB 900)ヴァージョンは、実験音楽家としての石橋英子の面目躍如で、さらにドローンに徹した(Oto)ヴァージョンの寂しげな静寂もぼくには面白いし、ミニマルな“Drive My Car”の(The Truth, No Matter What It Is, Isn't That Frightening/真実はそれがどんなものであれ、それほど恐ろしいものではない)などはクラスター&イーノによるプロト・アンビエントを彷彿させる。
こうした抽象的な楽曲があるいっぽうで、小気味よいリズムとメロディを主体とした“Drive My Car”の(The Important Thing Is To Work/大切なのは仕事をすること)、そしてストリングスの音色を活かした“We'll Live Through 〜”のオリジナル・ヴァージョンは、ギリギリのところである種ロマンティックな雰囲気を引き起こしている。曲の後方でジム・オルークのギターがざわついている“We'll Live Through 〜”の(And When Our Last Hour Comes We'll Go Quietly/そしていつかその時が来たら、おとなしく死んでいきましょう)は、アルバムのクローザーに相応しい。昼も夜も休まることなく、クライマックスに向けて走り抜けていくようだ。が、しかし走っても走っても、カフカの『城』のように終着点はない。いや、ここはサミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』のように、と書くべきか。
本作は、2021年の夏に出たアルバムだが、ぼくが聴いたのはわりと最近で、レヴューを書くために映画を観に行こうと思い、ようやくそれが叶ったことでいまこうして書いている。映画を観た人と観ていない人では、このサウンドトラックの受け止め方が違うのは当たり前だ。これは観た人の感想文であって、観ていない人がこの音楽をどう聴くのかはわからない。ぼくはこのアルバムが気に入っているし、ここ最近は、ぼくが移動するときのサウンドトラックにもなっている。まあ、ぼくはもっぱら歩く人ですけど。
(*)つい先日発売されたCD版にはボーナストラックとして新たに2曲が追加されている。1曲は“Drive My Car”の(Hiroshima)、もう1曲は“We'll Live Through 〜”の(different ways)。前者はミニマルなピアノ演奏による曲で、後者は『ミュージック・フォー・エアポーツ』寄りの、複数の電子ドローンがそれぞれ循環する美しいアンビエント・ミュージックになっている。
デビュー・アルバムをリリースするポストパンク・バンド、もしかしたらみんなもうこの言葉を聞くのは飽き飽きしているかもしれない。しかしヤード・アクトは思い浮かぶそれらのバンドのどれよりも、はるかにポップだ。そして、それこそがきっとすべての違いなのだ。
早口でまくし立てられるヴォーカル、せき立てられて気持ちがせいで否が応にも事態に巻き込まれていく……。ヤード・アクトのアルバムのタイトル・トラックであり1曲目 “The Overload” ほどこのデビュー・アルバムの最初の曲にふさわしいものはない、そう思わせる程にキレがある。イングランド、リーズのバンド ヤード・アクト、サウス・ロンドン・シーンを尻目にリーズで結成されたこのバンドはポップなギャング・オブ・フォーのようでもありギャング映画とフォールにかぶれたフランツ・フェルディナンドのようでもあり、スタジアムのフットボール・プレイヤーではなくTVに映るフットボール解説者にキレるスリーフォード・モッズのようでもある。ギターは尖り、ベースは太くドラムはタイト、流行している例の喋るようなヴォーカルに圧倒的に足りなかったのはこのポップさだったのではないかという言葉がこのアルバムを聞く度に頭をよぎる(そしてそれらが出そろった2022年のこのタイミングでヤード・アクトのアルバムが出たことにも意味があるようにも思える。まったく違うものではないが、組み合わせるやり方が違う。それはショートカウンターとしてソリッドに機能する)。
僕が最初にヤード・アクトを知ったのは2020年の4月、イギリスの音楽誌 Dork がデビュー・シングル “The Trapper’s Pelts” をリリースするバンドを紹介する記事だった。Twitter のタイムラインにガレージの中にある薄汚れた車と共に写真に写る4人の男の姿が表示される。眼鏡をかけた3人の男とニット帽をかぶった2人の男(つまり一人はニット帽をかぶり眼鏡をかけている)の冴えないがしかし何やら雰囲気がある写真とビル・ライダー・ジョーンズがプロデュースしているという情報に惹かれて記事を開き、そしてその中の YouTube のリンクを踏むと「YARD ACT」の文字(つまりジャケットに描かれている例のマークだ)が回りはじめる。それで他の情報は全ていらなくなった。百聞は一見にしかず、音がなりはじめた瞬間に一発でわかるような種類の音楽というものがあって、ヤード・アクトは完全にそれだった。当然のようにあっという間に話題になり最初の7インチが出る前にはレコードを入手することが困難なバンドになっていた。もう誰もプロデューサーが誰なのか気にしなくなり、ただヤード・アクトがどんな音楽をリリースするかだけに関心が集まった(しかしちゃんと書いておく。アルバムのプロデューサーはドゥ・ナッシングやケイティ・J・ピアソンをプロデュースしたアリ・チャントだ。付け加えるなら8曲目の “Quarantine the Sticks” にはビリー・ノーメイツも参加している)。
そしてこのデビュー・アルバムもまさにそういう種類のアルバムだ。再生ボタンを押した瞬間に始まるタイトル・トラックの “The Overload” 「イェーイェーイェー」というジェームス・スミスの声がやる気なく聞こえてきたと思えば心構えも何もなく気がつけばもうヤード・アクトが巻き起こすこの事態の中に引き込まれている。“Dead Horse” はフランツ・フェルディナンドの最初の方のアルバムに入っていてもおかしくないほどムーディーで、“Witness (Can I Get A?)” はハードコアの曲を作ろうとしたがうまくいかず、スーサイドのドラムを試したらスロウタイやムラ・マサみたいな曲になったと彼らは言う(しかし1分と少しのこの曲はギターを効かしたスリーフォード・モッズのようにも聞こえる)。
このアルバムで白眉なのが9曲目の “Tall Poppoeis” で、この曲は同時代の他のポストパンク・バンドにはちょっとみられない曲だろう。イラついていないときのマーク・E・スミスみたいな語り口で語られる物語、クラスでいちばんハンサムだった男、村でいちばんフットボールが上手かった奴、クルー・アレクサンドラのスカウトが見にきて関心があるとかなんとか言う(クルー・アレクサンドラはイングランドの3部にあたるリーグ1に所属しているクラブだ)。だが彼はフットボールの道に進まなかった。16歳の時に決断し、村で不動産の仕事について、結婚して、犬を飼って、子供が生まれ、そうして年を取り死んでいく。彼は夢を追うことをしなかった。グレート・マンチェスターにはもっとハンサムな男がいて、信じられないくらいフットボールが上手い奴がいる、だから彼は村を出ずに平凡な幸せな中に死んでいくことを選んだ。そんな男の一生が音楽に乗せた説話として描かれ、そのあとにこの話を受けて現代を生きる人間の思いが語られる。この国では16歳になるまでにどんな大人になるのか決めなければならない。そうやってみな選択した自分の人生を生きる。そのことに精一杯で、どこかの国で爆弾が落とされ子供が死んでいくことを知っていたとしても、その利益を受けて生きていくしかない。この曲ではそうした人生の選択や不条理さ、無常観が描かれている。体制にただ牙をむくのでもなく、怒りをぶつけるのでもない。誰かを諭そうともせず意見を押しつけず、ヤード・アクトは自分の見た世界の現状を提示して、どう思う? と笑顔を浮かべ皮肉じみた質問を投げかけるのだ。
「近頃のガキは自分が苦労しているって思っている / 俺みたいに鉄の肺を味わったわけでもないだろうに」 “The Overload” でそう唄われているようにヤード・アクトはいわゆるサウス・ロンドン・シーンのバンドとは違う世代に属している。ヴォーカルのジェームス・スミスは31歳で結婚していて子供がいて、その相棒、ベースのライアン・ニーダムは彼より10歳年上で、メンバーチェンジを経て加入したギタリストのサム・シップストーンやドラムのジェイ・ラッセル(この二人は地元リーズのバンド、ツリーボーイ&アークのメンバーと交代で入った二人だ)にしてもヤード・アクトの前に違うバンドで活動しており、メンバー全員がこれまでに他のバンドで音楽活動をしていた。ジョン・クーパー・クラークからその名がとられたであろうジェームス・スミスのバンド、ポスト・ウォー・グラマラス・ガールズはゴシックの香りが漂う陰鬱なギターバンドで、ライアン・ニーダムのメネス・ビーチも『Black Rainbow Sound』というアルバム・タイトル通りの暗さがある。そうした時代を経てのヤード・アクトだ。ヤード・アクトはこれまでのバンドと同じようなエッジを持ちながら、それよりもずっとポップで親しみやすく、そしておそらく大きな場所で響きやすい。
ソー・ヤング・マガジンのサム・フォードが言うように、いまのロンドンで音楽をしようと思うのならば学生時代の3年間を有効活用するしかないのだろう(つまりジェントリフィケーションの問題だ)。サウス・ロンドンの多くのバンドはそれを利用し連帯しシーンを形作っていった。だがそれらのバンドの大半は成功し売れるということにあまり興味を示さなかった。情熱を持って活動し自分たちの音楽を気に入ってくれる誰かに届けば良い。そうしてお互いに刺激を受けて、それがまた音楽を作る原動力になる。それは素晴らしいものなのだが、もしかしたらそれが少なからず頭でっかちの音楽になってしまった原因なのかもしれない(あるいは “Tall Poppoeis” で描かれたフットボールの話はこうした状況にもかかっているのかもしれない)。しかしヤード・アクトは違う。生活のための音楽、もしくは音楽のための生活を経験している彼らは目標をしっかりと掲げはっきりと大きなステージを目指した(この点でもフランツ・フェルディナンドを彷彿とさせる)。
その上で彼らは同時に信念を持ち続けている。人気を集めた “Fixer Upper” や “Dark Days” などアルバム以前に発表された曲を1曲も収録しなかったというのがおそらくその証拠になるだろう。ただ売れればいいというものではなく波風が立つようなエッジがなければ意味がない、この姿勢がヤード・アクトをヤード・アクトたらしめる。切れ味鋭いポップな楽曲に乗せた社会風刺、人気ゲーム「FIFA22」のサウンドトラックに収録された “The Overload” がジェントリフィケーションの問題を取り扱った曲であるように、“Dead Horse” ではBrexit時代の政治の現状が嘆かれ、“The Incident” ではキャンセル・カルチャー世界の健全さが、そして “Rich” や “Payday” では社会格差や資本主義のねじれがユーモアと皮肉を交えて描かれている。こうしたメッセージが込められた曲を大きな場所で響かせようとしているのがヤード・アクトなのだ。サウス・ロンドン・シーンのバンドとの共通点と差異、エッジを持ちつつポップでもあるということ、ヤード・アクトのこのアルバムはやはり巻き起こったシーンに対してカウンターとして機能するのだ。
そして物事にはタイミングというものがある。おそらくこの 1st アルバムは10年前では同じように作れなかっただろうし、同様に響くこともなかっただろう。時代と場所と流れ、様々なものが噛み合って音楽は生まれ、受け入れられていく。だからこそヤード・アクトのアルバムがいまこのタイミングで出たことに意味があるとこのアルバムを聞いてそんなことを考えてしまう。
Madegg名義で作品を発表していた小松千倫による、Kazumichi Komatsu名義のアルバム『Emboss Star』のリミックス盤が先週リリースされた。リミックス担当は、堀池ゆめぁ、Takao、荒井優作、土井樹といった若手注目の面々。アナログ盤と配信のリリースとなる。
Kazumichi Komatsu
Emboss Star Remixes
FLAU
https://smarturl.it/EmbossStarRemixes
https://flau.bandcamp.com/album/emboss-star-remixes
tracklist:
1. Umi Ga Kikoeru (feat. Dove & Le Makeup) (Extremely Raw Version)
2. Lipsynch (堀池ゆめぁ Remix)
3. Followers (feat. Cristel Bere) (Takao Remix)
4. Umi Ga Kikoeru (feat. Dove & Le Makeup) (荒井優作 Remix)
5. Emory (土井樹 Remix)

なお、『Emboss Star』のアナログ盤も絶賛発売中。
こちらは収録曲“Followers feat. Cristel Bere“のMV(shot by Maho Nakanishi)。
以下、レーベル資料から。
Madeggとして活動を行なっていた小松千倫がKazumichi Komatsu名義で昨年リリース、Visible Cloaksがミックステープに楽曲をフィーチャー、柴田聡子が昨年のベストアルバムの1枚に選ぶなど、多方面で注目を浴びたアルバム「Emboss Star」が1年越しにLP化。本作は、過去4年の間に作業されたEP、インスタレーション作品、映像作品、ファッションショー、パーティー、レイヴ等の実験の中から、将棋の棋譜を読み返すようにして見つけ出されたものを基礎としている。全体で30分にも満たない本作は、再生とともに現象してしまう音源のファンダメンタルな側面を強調しつつ、情報やイメージのヴェイピングに対する様々な反応を、身体において再構成することが意図されている。ハウスやアンビエントが誘き寄せる半意識的な状態への契機とともに、抵抗が意図されており、インプットへのある種の免疫を作り出そうとする。コミュニケーションの戯図のなかで、フィクションはハッシュタグやジャーゴンといった冗長に圧縮されていく。それらはフォークロアの話素にもなる。ルドンダンスを組み合わせたフォークソング集。シングル「海がきこえる」にはアルバム「微熱」が注目を集めるDove & Le Makeup、「Followers」ではPure VoyageからCristel Bereをフィーチャー。マスタリングは注目のレーベルRecitalを主宰するSean McCannが担当。
Kazumichi Komatsu
小松千倫は1992年生まれ、トラックメイカー Madeggとしても知られる。これまでにFLAU、Angoisseなど様々な国のレーベルよりアルバム、 EPをリリースするが、その表現領域は音楽、映像、インスタレーションと多岐にわたる。原初的な経験的感覚やイメージを基点としながら、ジャンルによる規定性を迂回するように街や自然、メディアや記憶の内外にある微細な現象や変化を重ね合わせることで、抽象的なイメージが固有のシーケンスへと転化していくかのような作品制作を行っている。
4年前に急逝した Fla$hBackS のラッパー/プロデューサー、FEBB。生前手がけていたという幻のサード・アルバム『SUPREME SEASON』がなんと陽の目を見ることになった。残されたPCから発見された全16曲を収録、アナログ2枚組とCDのフィジカル限定で、デジタルでのリリースは予定されていない。これは要チェックです。
FEBBが生前に最後まで手がけていた幻の3rdアルバム『SUPREME SEASON』が完全限定プレスの2枚組アナログ盤、CDのフィジカル限定でリリース。
2018年2月15日に急逝したFEBBが生前に最後まで手がけていた幻の3rdアルバム『SUPREME SEASON』がリリース。デジタルでリリース済みの“SKINNY”や“THE TEST”の7インチにカップリングされた"FOR YOU”など一部既出の楽曲やGRADIS NICEとの『SUPREME SEASON 1.5』でリミックス・ヴァージョンが収録されたりしているものの、これが本人が纏めていたオリジナル音源での3rdアルバム。
FEBB自身のパソコンから発見された全16曲のオリジナルデータにマスタリングを施し、ご家族と協議の上リリースすることとなりました。客演としてMUD(KANDYTOWN)が唯一参加となっています。(本来は全17曲ですが"DROUGHT"はMANTLE as MANDRILLのアルバムに収録されたため本作には未収録)
アートワークは名盤『THE SEASON』と同じくGUESS(CHANCE LORD)、マスタリングはNAOYA TOKUNOUが担当。
本作はアルバムとしてのデジタル・リリースは予定しておらずフィジカル限定となり、アナログ盤は帯付き見開きジャケット/完全限定プレスで一般販売。同じく完全限定プレスのCDやTシャツ等のマーチャンダイズはP-VINE
SHOP限定での販売となり、詳細は追ってアナウンスになります。
(Photo: Shunsuke Shiga)
[商品情報]
アーティスト: FEBB
タイトル: SUPREME SEASON
レーベル: WDsounds / P-VINE, Inc.
発売日: 2022年5月25日(水)
仕様: 2枚組LP(帯付き見開きジャケット仕様/完全限定生産)
品番: PLP-7778/9
定価: 4.950円(税抜4.500円)
[TRACKLIST]
A-1 SUPREME INTRO
A-2 DRUG CARTEL
A-3 THUNDER
A-4 FOR YOU
B-1 CITY
B-2 DANCE
B-3 RUSH OUT
B-4 $AVAGE
C-1 F TURBO
C-2 FOR REAL THO
C-3 ELOTIC
C-4 NUMB feat. MUD
D-1 REALNESS
D-2 LIFE 4 THE MOMENT ( SKIT )
D-3 MOTHAFUCK
D-4 SKINNY
現代の日本のダークサイドを風刺しているともっぱら評判の遊佐春菜のアルバム『Another Story Of Dystopia Romance』、1曲目の“everything, everything, everything”が配信を開始した。彼女の〝ディストピア・ロマン〟をぜひ聴いてみてください。
Apple Music | Spotify
アルバムはCD2枚組で、1枚はオリジナル・ミックス盤、もう1枚はリミックス盤になる。リミキサー陣は、DJ善福寺、SUGIURUMN、Yoshi Horino、Eccyといった〈kilikilivilla〉レーベルでお馴染みのベテラン勢が担当。アルバムは4月20日に発売予定。
遊佐春菜 / Another Story Of Dystopia Romance
KKV-120
4月20日発売予定
CD2枚組
税込3,300円
https://store.kilikilivilla.com/product/receivesitem/KKV-120

Disc 1 : Another Story Of Dystopia Romance
1. everything, everything, everything
2. ミッドナイトタイムライン
3. Faust
4. Night Rainbow
5. Escape
6. 巨大なパーティー
7. everything, everything, everything (beat reprise)
Disc 2 : Another Story Of Dystopia Romance Remixes
1. everything, everything, everything (beat reprise)(SUGIURUMN Remix)
2. 巨大なパーティー(DJ善福寺from井の頭レンジャーズ Remix)
3. Escape(ReminiscenceForest Remix)
4. Night Rainbow(House Violence & Yoshi Horino remix )
5. Faust(Satoshi Fumi Remix)
6. ミッドナイトタイムライン(XTAL Remix)
7. everything, everything, everything(Eccy Remix)
以下、レーベル資料から。
Remixerについて by 与田太郎
このアルバムが伝えようとする物語はクラブやパーティーが重要な舞台となっている。野外レイヴやパーティーで踊ることはこの行き詰まる日常からの解放だ、そして様々な場所からそこに集まる人々とのオープン・マインドなコミュニケーションは人生に大きな出会いをもたらしてくれる。
Have a Nice Day!のライブでフロアがモッシュピットだったことは偶然ではなく、そこに集まった人々による1時間にも満たない熱狂は彼らにとって日々を生きる糧だったはずだ。2020年以降消えてしまったパーティーやフロアの熱気がようやく今年取り戻せるかもしれない。
今作のプロデューサーである僕は90年代からパーティー・オーガナイザーとして、またDJとしてその熱気を求め続けてきた。Another Story Of Dystopia Romanceが90年代以降のダンス・カルチャーが生み出したサウンドから作られているのはそういう理由による。ならばそれぞれの楽曲のフロア向けのリミックスを作る必要があるだろう、というアイデアはすぐに実行された。
everything, everything, everything (beat reprise)(Sugiurumn Remix)
数々のパーティーを20年以上共に駆け抜けてきた盟友であり、変化の激しいシーンを生き抜いたベテランらしくないベテランSUGIURUMNは静かな熱気をきらめくようなエレクトロ・ビートの結晶に封じ込めた。
巨大なパーティー(DJ善福寺from井の頭レンジャーズ Remix)
90年代のワイルド・ライフを共に過ごした高木壮太は普段なら引き受けないリミックス、ダブの制作を2021年8月に亡くなったリー・ペリーの追悼ということで特別に引き受けてくれた。そのDJ善福寺from井の頭レンジャーズ名義のダブ・リミックスからは彼がいかに深く音楽に精通しているかを物語る。
Night Rainbow(House Violence & Yoshi Horino remix )
東京のハウス・シーンのライジング・スターHouse Violenceとワールド・ワイドなレーベルUNKNOWN SEASONをオーガナイズするYoshi Horinoがタッグを組んだリミックス、パーティーの現場に即した構成とシカゴ・テイストなビートとニューヨーク・マナーな展開は彼らが日々のパーティーで培ってきたダンス・ミュージックそのもの。
FAUST(Satoshi Fumi Remix)
90年代からプログレッシヴ・ハウスを追いかけてた僕にとってジョン・ディグウィードにフックアップされたSatoshi Fumiは特別な存在と言っていい。2022年現在、リアルタイムでワールド・クラスのプロデューサーが織りなす展開は見事としか言いようがない。彼の最新アルバムはディグウィードのBEDROCKからリリースされた。
ミッドナイトタイムライン(XTAL Remix)
Traks Boysとしても活躍するXTAL、近年の作品同様に流れで聴かせるのではなく瞬間を切り取るようなスタイルは歪み成分がまるで音の粒子のように広がるって聞こえてくる。バレアリックかつシューゲイズなタッチは彼ならではの作品となった。
everything, everything, everything(Eccy Remix)
かつてSLYE RECORDSを共に率いたトラック・メイカーは今またコンスタントに作品を発表している。オリジナル・アルバムのオープニング・ナンバーは現代の日本を見つめるインターネットの視点から歌われているがEccyのビートはそのディストピアのダークサイドを見つめている。
私はあなたを愛したくない
なぜなら私はあなたを知っているから
ベティ・デイヴィス“反ラヴソング”
時代の先を走りすぎたという人がたまにいるが、ベティ・デイヴィスはそのひとりだ。彼女については、かつてのパートナーだったマイルス・デイヴィスが自伝で語っている言葉が的確に彼女を説明している。「もしベティがいまも歌っていたらマドンナみたいになっていただろう。女性版プリンスになっていたかもしれない。彼女は彼らの先駆者だった。時代の少し先を行っていた」(*)
ベティ・デイヴィスは女ファンクの先駆者というだけではない。彼女は、セックスについての歌をしかもなかば攻撃的に、鼓膜をつんざくヴォーカリゼーションと強靱なファンクによって表現した。公民権運動時代のアメリカには、ローザ・パークスやアンジェラ・デイヴィスをはじめとする何人もの革命的な女性がいた。音楽の世界においてもアレサ・フランクリンやニーナ・シモンらがいたが、ベティ・デイヴィスは彼女たちがやらなかったことをやった、それはセクシャリティの解放であり、家父長社会に対する性的な挑発だ。男性が伝統的に当然としてきた性的自由を享受する権利を声高く主張すること。だが、そのあまりにも放埒でラディカルな性表現は、1970年代当時、公民権運動の主体の一部であった全米黒人向上協会(NAACP)からもボイコットされたほどだった。
1944年7月16日、ノースカロライナ州ダーラムで生まれたベティ・デイヴィスが、2月9日に77年の生涯を終えたことを先週欧米のメディアはいっせいに報じ、彼女にレガシーに言葉を費やしている。
16歳のとき、ファッション・デザインを学ぶためにニューヨークにやってきた彼女は、その街の文化——グリニッジヴィレッジやフォークなど——を思い切り吸収した。モデルとしても働くようになったが、モデル業よりも音楽への情熱が勝り、1967年にはザ・チェンバース・ブラザーズのために曲を書いている。それが昨年ヒットした映画『サマー・オブ・ソウル』でも聴くことができる“Uptown (To Harlem)”だ。そして、マイルス・デイヴィスが、おそらくはほとんど一目惚れして、1969年のアルバム『キリマンジェロの娘(Filles De Kilimanjaro)』のジャケットになり、収録曲の1曲(Miss Mabry)にもなった。マイルスにスライ&ザ・ファミリー・ストーンとジミ・ヘンドリックスを教えたベティは、彼の二番目のパートナーとなり、かの『ビッチェズ・ブリュー』へと導いたことでも知られている。「音楽においても、これから俺が進むべき道を切り拓いてくれることになった」とマイルスは語っている(*)。
そしてベディ・デイヴィスはマイルスとの短い結婚生活を終えると、わずか3枚の、しかし強烈なファンク・アルバムを残した。ぼくが所有しているのは『They Say I'm Different』(1974)の1枚だが、このジャケット写真を見れば、どれだけ彼女がぶっ飛んでいたかがわかるだろう。彼女はグラム・ロッカーであり、サン・ラーやジョージ・クリントンと肩を並べることができるアフロ・フユーチャリストでもあった。

しかしながら、1970年代前半のアメリカで、黒人女性がファンクのリズムに乗って、自分の性欲や別れた男=マイルスのことを面白おかしく歌うこと(He Was A Big Freak)は、あまり歓迎されなかった。だがいまあらためて聴けば、先述の『They Say I'm Different』はもちろんのこと、ファースト・アルバム『Betty Davis』(1973)もサード・アルバム『Nasty Gal』(1975)も、その素晴らしいファンクのエネルギーに圧倒される。ベティの散弾銃のようなヴォーカリゼーションは、因習打破の塊で、まだまだ保守的だった時代においては恐れられてしまったのだろう。彼女の前では、ジェイムズ・ブラウンの“セックス・マシーン”でさえもお上品に聴こえると書いたのは、ガーディアンやクワイエタスに寄稿するジョン・ドーランだ。「彼女は、揺るぎない勇気とリビドーをストレートに感じさせる強さをもっていた」

ベティは結局、早々と音楽業界から身を引かざるえなかった。ドーランは、ベティが無名性に甘んじたのは、明らかな性差別だったと断言しているが、21世紀の現在では、エリカ・バドゥやジャネール・モネイのように、彼女からの影響を公言するアーティストは少なくない。カーディBやニッキー・ミナージュだってその恩恵を受けているだろうし、もっと前には、それこそマイルスが言ったように、マドンナとプリンスにもインスピレーションを与えているという。テキサスのサイケ・パンク・バンドのバットホール・サーファーズだってベティへの賞賛を表明しているし、彼女はいま、ようやく時代が自分に追いついたことに安堵していることだろう。
人は私が変わってるって言うけれど
だって私はサトウキビで芯まで甘い
だからリズムがある
曾祖母は社交ダンスなんて好きじゃなかった
そのかわり
エルモア・ジェイムズを鼻歌で歌いながらブギったものさ人は私が私は変わってるって言うけれど
だってチットリンを食べるから
生まれも育ちもそうなんだから仕方がない
毎朝、豚を屠殺しなければ
ジョン・リー・フッカーの歌を聴いて帰るんだ人は私が私は変わってるって言うけれど
だって私はサトウキビで
足で蹴ればリズムが出る
曾祖父はブルース好きだった
B.B.キングやジミー・リードの曲で
密造酒をロックしていたのさ
“They Say I’m Different”
※サトウキビは長い円筒形の管のなかに甘い液体が入っていて、その管を口に入れて汁を吸う。
(*)『マイルス・デイヴィス自叙伝』(中山康樹 訳)。原書は1989年刊行
どの年もどの日も特別な時間であると思う。コロナ禍が続くなかでもそれが変わらないことを私たちは知っている。2021年を振り返りそのTHE BESTを自らの言葉で綴ることはその時間を少しだけ自分のものにしてくれると思う。そんな「THE BEST 2021」。
・RIVERSIDE READING CLUB
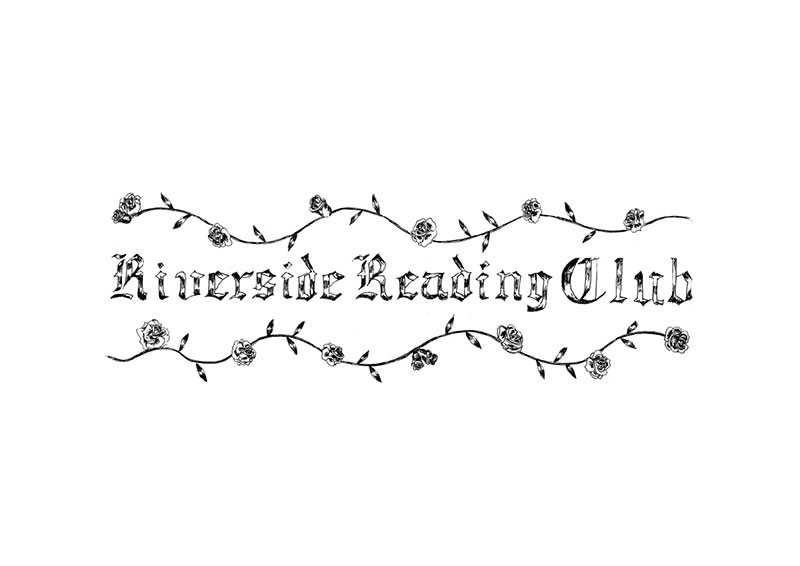
* 保坂和志『残響』
去年いちばん繰り返し読んだ一冊。これは世界を小説にしか出来ないやり方で描いた作品だ。という考えに2回目の途中くらいでたどり着いたのだけど、その後に読んだ作者の“創作ノート”には全然そんなことは書かれていなくて、ぶちあがると同時に、別の文脈で書かれていた「だって、世界ってそういうものだからだ」という一文に完全に納得した。そこまで含めて、Best読書2021。 ( ikm )
* CHIYORI × YAMAAN “MYSTIC HIGH”
2021年。前年に続きとにかく大変な1年だったけれど、どんな状況下でも『パーティー』はそこにあり続けた。決して楽な環境ではなかった中で「それを今やる意味」。その意味は各々で消化され、細胞となり、それはどんなウィルスにも侵食することはできない精神の強力な抗体となった。
そして、個人的にはそれを象徴するかのような曲が「Mystic High」収録の「I'm So High」。第五波で緊急事態宣言真っ只中の夏、BUSHBASHで行った自主企画でCHIYORIが「新曲です!」と言ってYAMAANとの共作を披露したときからすでにアンセムだった。透明感のあるボーカル、柔らかな上音に浮かび上がるハットの軽快さ、さまざまな音の重なりがゆらゆらと波が起こし体全体を包んでいくような感覚。あぁ、ここはもうすでに水の中なのかもしれない。母のお腹で眠る赤ちゃんはこんなあたたかくてきもちいいのだろうか。重力から解放されてふわふわと永遠に踊っていられるような、そんな感じだった。
そして、パーティー明けに惨劇の森から大絶賛され、瞬速でBushmindはremixを製作。心地よいゆるやかな波はremixによって化け物のような大波に進化した。どちらも良さがありまくる。それからremixがパーティーで流れようになると、どこの場所でもその日一番の盛り上がりとなり、キラキラと魔法がかかったように輝き出した。フロアは一瞬で波に飲み込まれ、引き込まれていく感覚にゾワゾワと鳥肌が立つ。このような感覚は今まで味わったことがなく、やはりこの曲こそ2021年の私が体験したダンスフロアの象徴に他ならなかった。
※一曲についてしか書けませんでしたが「Mystic High」は全編を通して衝撃的に素晴らしいアルバムです ( Mau Sniggler )
* rowbai “Dukkha”
HYDRO BRAIN MC’s加入以降、ほんの幾つかのバースとほんの数回のライブで一躍チームのエース格に躍り出た我らがKuroyagiによる客演が圧倒的に素晴らしい。
取り分け事態を本邦だけに限定するとたかだかスキルの話にしても、ほとんどのラッパーが彼のちょっとしたおふざけにすら足元にも及ばない状況の中、本作で繰り広げられるゴン攻めに至り、俺も含めてここに展開されたラップアートを正確に理解できている人が果たしてどれだけいるのか? 取り分け2曲目の「Gōma」に於ける今更初期のLil Yachty的バブルガム感を引用しつつ、その背後に1977年のSuicideの幻影さえもがチラつく白昼の落雷のようなすっとぼけた覚醒感で"ぶっ殺死!!"(© 冨樫義博先生)をパフォームする、このコロナ禍のディストピアにこそ相応しい破格のエンターテイメントにとりあえず一回全員蹴散らされたらいい。また、本作のオーナーrowbaiが自身で手がける、透過性と不透過性とその裂け目を縫うようにして這い進むヒビ割れた磨りガラスのようなbeatとあくまで静謐なボキャブラリーの中に"激痛"("激情"ではなく)を宿したwordは、"ポスト〇〇"的なタームでは解析しきれない明らかなる切断面を開陳し、現在、SSWという言葉が置かれた位置座標を立体的に浮かび上がらせている。同二人のコンビネーションによる前作、rowbai & Kuroyagi / "nothing"と併せて普通に必聴。
まるで逆境を跳ね返すかのように友人たちが傑作を量産した2021年の中でもBESTの一つ。この作品の所為で暫く他のが聴けなくなって超迷惑でした! ( Phonehead )
・.daydreamnation.( iiirecordings )
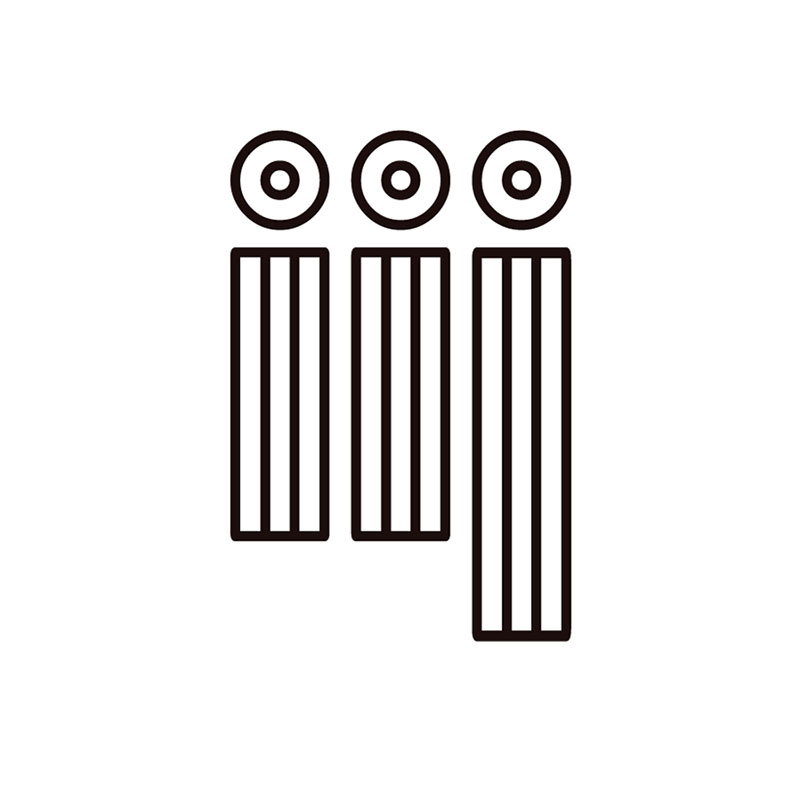
1. SPECTRE “THE LAST SHALL BE FIRST (CD)”
SPECTREをBGMに自分が好きなことをする。有限の時間の中で聴く音楽、最高のものをききたい。2021年この音楽に乗りながら色々なことをやりました。ヒップホップでありながら完全にそれを超えていて、説明不可能な領域まで振り切ったビートにしびれました。WORDSOUNDはミュータント。ミックスがSCOTTY HARDさん、マスタリングはTURTLE TONE STUDIO NYC.で音最高。ぜひCDで。 DJKATAWAからの贈物。ZOZNT PROBLEMDUBBERS CLASSIC. ありがとうございます。
2. NECESSARY (Necessary Intergalactic Cooperation) “VOLDSLOKKA (CD)”
夜に何か作業をする時に聴いていました。NICはバンドサウンドの枠をこえたリズム・演奏・ダブすべてがかっこよくてミックスもキレキレです。SWANS/PRONG/teledubgnosisのTed Parsonsさんのドラムビートがくらいます。大好きなグルーブ感。ミックスはGodflesh/JesuのJustin K. Broadricさん、マスタリングがTURTLE TONE STUDIO NYC.で音質最高です。ぜひCDで。
3. 吉村弘 “PIER & LOFT (VINYL)”
再生して終わるまでの間に、今までの自分ぜんぶを包み込んで許されたような気持ちになりました。やわらかくて、やさしくて。聴く度にたいせつなことを思い出しています。シンセサイザーのやさしい音と演奏。この作品に出会えてうれしいです。レコードのマスタリングをしたSinkichi君(KOZA BC STREET STUDIO)からの贈物。ありがとうございます。
・HANKYOVAIN

1. J.COLUMBUS feat.ERA “BEST COAT”
本作の最後でPHONEHEADが登場した事は私にとって2021年最大の衝撃であり、目白と守口が確実に繋がっていると実感した特別な出来事となった。
楽曲の素晴らしさについては、リリース時に添えられたikm君の愛を感じる解説文を読んでみてほしい。
2. SATO “トワノアス”
本作の7インチ・レコード化計画に携われたことは私にとって2021年の貴重な経験となった。京都で音楽活動を続けるSATOが「高瀬川」と「永遠の二人」について歌う本作は、瑞々しく輝く普遍性と、それと相反するような愛の儚さや危うさを感じさせる名曲である。
3. HIRANO TAICHI “BLINDING LIGHTS”
今1番アルバムの発表を待ち焦がれているシンガーソングライターの名曲。
この曲を初めて聴いた時、演奏が始まって歌声が入ってきた瞬間に「この人本物や」と感動してすっかり心を打ち抜かれてしまった。
・BUSHBASH

柿沼実(BUSHBASH)
* MEJIRO ST. BOYZ “BLOWING BUBBLE FOREVER”
J.COLUMBUS,Phonehead,HANKYOVAINで構成される"MEJIRO ST. BOYZ"が11月にリリースしたBLOWING BUBBLE FOREVER。
この曲によってBUSHBASHの行ってきた事を新しいフェーズに移動させる事ができたと思う。悩みや存在し続ける問題や壁のようなもの、それらがなんでありどう向かっていくかという事。希望や一時的な逃避ではない確実な揺るぎない"現実"が歌われる事で足元を再確認し、抽象的でない"未来"を生み出す一端になる広がり続ける大気の様な、そして果てしない強靭さを兼ね備える音楽。
時代が変わり続けても何処かに射し続ける光みたいに在り続けるCLASSIC。一音目からの音、聴こえるリリック、そして結成の経緯と皆の佇まいや会話、存在。全てがMSBでとてつもなくEMPOWERしてもらってます。LIFETIME BEST。シャボン玉を吹き続けよう。
* RAMZA ”Pure Daaag” AIWABEATZ ”pearl light - Rain”
BUSHBASHのレーベルからリリースさせて頂いたRAMZA君のMIX CDとAIWABEATZ君の7inch。リリースという行為の中にある一つひとつのやりとり、多くの人の協力などが積み重なってできた素晴らしい作品。
2020年3月からの出来事や交差していく人や物事の中で自然/必然というような流れでスタートできたBUSHBASH LABELは狭くなっていた視野を壊してくれるものでした。その中でもこの2作品はなるべくしてなったというか極自然な流れで形作られていったものであり、どちらもこの時代性を反映しつつも左右されない芯が通った内容で、BUSHBASHとして考える大切な物事を忘れず、地に足をつけるという意志を紡いでくれているような気がしています。
この2作品から生みでたイメージが繋がって今後もリリースしていく予定の最高の作品がありますので楽しみにしていてください。
喉元を過ぎて熱さを忘れた後は熱さを感じる喉元すらなくなると思います。
* 惨劇の森 "緊急事態新年会 + 歳末大感謝無礼講大祭"
2021年の始まりと暮れに執り行って頂いた2大祭。期せずしてこちらもずっと考え続けた場所としての在り方や考えを体現してもらえた夜。どらちも悪化の一途を辿る世の中の状況の中で行われましたがプリミティブであり美しい、笑顔が絶えない時間で、"音楽"ってものを考えた時に最初に受けた衝撃からこれから朽ち果てるまでの間に何がしたい/できるか、という疑問の答えに身をもって提示してくれたような惨劇の森(DJ Abraxas / Bushmind / Ko Umehara / Phonehead)とACID EXILE、そして集まって頂いた皆さんに敬意を表します。
物凄くシンプルに音楽の最高さ/カッコよさを感じさせてくれて新しい楽しみ方やワクワクする事が増えて行くと共に、惨劇の森による大祭で挟み込まれた2021年という年に感じた希望や手応えは身体に刻み込まれて突き動かしていく。
2022年も多くの人が集まりそれぞれの尊厳を奪われず、自由な楽しみ方で過ごせる場所と時間を創っていきたいと思います。
新たな変化と少しずつ明けていく夜の確信として此処に記します。
・DISCIPLINE

* Scowl “How Flowers Grow”(SHV(KLONNS))
* Team Rockit “Bahamut Zero”(LSTNGT )
* Ellen Arkbro ”Sounds while waiting”(Keigo Kurematsu)
* Sozorie “Paper Ruins”(1797071 (Ms.Machine))
* OPERANT “Traumkörper”(Golpe Mortal)
* セーラーかんな子 “Kanna-chan/Hachi-chan”(CVLTSL4VE (#SKI7))
* Sega Bodega “Romeo”(Ray Uninog (#SKI7))
* George Crumb - Music For a Summer Evening :The Advent(TIDEPOOL (IN THE SUN))
* Telematic Visions 2 “watch?v=7QklmysU_o4Ku”(富烈)
こういう機会を頂いて改めて振り返ってみると、2021年もコロナ禍によって生活の色々を縛られ続けた1年だったけど、そんな中でも各地で新しい物語が絶え間なく紡がれていたと思う。バラバラに散らばっていた点と点が邂逅を果たし、そして同時に永遠に捨て去るべきものが何なのかも分かった。
Disciplineは根底にHARDCORE PUNKの精神を持ちつつも特定のジャンルや言説に依拠しない(或いは出来ない)個人の集合体。それぞれがそれぞれの視座を持ちつつも、同じMOODと怒りを共有していると思う。メンバーのみんながそれぞれ選んだ曲たちはジャンルも世代も国籍も異なるけど、それぞれの「2021年」を映し出す鏡。大きな潮流としての「時代」ではなく、引き裂かれながらも「今」という切断面まで持続させてきた個人史。全部通して聴いてみると、世界がどんなに酷くなってもまだ少し明日を楽しみに出来る、ような気がする。( tSHV )
・CHIYORI × YAMAAN

YAMAAN
* Hegira Moya audio visual set at Curiosity Shop “Hidden Meadow” 29th May 2021
5月の明け方5時くらいにライヴ配信されていたHegira Moyaさんの映像作品。
Hegiraさんが旅先や日常の中で撮りためた映像と音を夜明け前の時間帯に配信で見るのは、不思議で印象的な体験でした。
* CHAMO TEU VULGO MALVADÃO “MC Jhenny (Love Funk) feat MC GW, DJ KOSTA22”
偶然聴いたこの曲をきっかけに現行のバイレファンキにはまりました。
「ンチャチャ」の基本的なリズムを変わった音で置き換えていたり、音数が極限まで少なかったり、斬新な音遊びをしている曲が多くて面白いです。
この曲はどことなくDJ FUNKなどに通ずる感じもします
* Mio Fou ”Mio Fou”
ムーンライダーズの鈴木博文さんと美尾洋乃さんのアンビエント感あるポップスのユニット。
84年の盤なのですが、昨年の夏頃にとてもはまって繰り返し聴いていました。素晴らしい作品です。
CHIYORI
2021年は旦那との初アルバム、CHIYORI × YAMAAN「Mystic High」のリリースができました。多くの時間を制作に費やしましたが、その間に起きた熱い思い出やハマったものを選りすぐりました。きっと間接的に制作にも活かされていたと思います。
* ポータブルスピーカーレイヴ
コロナ禍による時短営業で行くあてが無くなった時用に、ポータブルスピーカーをいつでも持ち歩いておいて、広場、川辺や海岸などでスピーカーを鳴らして友達と踊りまくったり、曲について語り合う、という遊び方にハマりました。スピーカーがボロかったので友人が誕生日に新しいのをプレゼントしてくれたのも嬉しかったな。また暖かくなったら始めよう。
* ドキュメンタリー映画「寛解の連続」ツアー
スタッフとして東京や関西3館の映画館上映を光永惇監督や主人公の小林勝行、他スタッフや配給さんたちと回りました。皆んな快楽主義な所があるのでノリが合うし、その反面、社会福祉への高い意識や強い想いに、とても影響を受けました。人間味溢れるこの映画と、幅広い文脈でのトークショーや様々な出会いによって、随分心が自由になれたし視野が広がったと思います。その小林勝行の3rdアルバムも2021年マストな衝撃作でした。
* OGGYWEST
2021年1番ハマったラップグループは、西荻を拠点とし2016年結成後コンスタントに作品を発表し続けているOGGYWEST。
オギーの魅力に気付いてしまった日から、全作品隈なく聴き込みました。クオリティの高い心地良いトラップな上、よく歌詞を聴くと生活感や妄想癖に溢れた絶妙なユーモアセンスがツボ過ぎて中毒になりました。ファンが高じてリリパでDJさせもらえたのはとても光栄でした。粗悪ビーツさんとの新作「永遠」も最高!
・MASS-HOLE

2021年よく聞いたアルバム。
* Benny The Butcher×Harry Fraud “The Plugs I Met 2”
すごく聞きました。佐井さんのクリアランス話を聞いて、地球が丸いことを知りました。salute WDsounds、P-VINE!!
* All Hail YT×Cedar Law$ “Player Made”
let me rideのカヴァーから気になってて、cedar君とつながってんだーってびっくりした。
albumはなんていうかラグジュアリーな感じが最高に気持ち良い。誰か全曲翻訳頼みます。dj shoe曰く、次はVICASSOがクルらしい。
* Issugi×Dj shoe “Both Banks”
82s屈指のhardest mcとgroove mixing masterのalbum。
近くにこういう音楽があるってことは幸せなことだ。これからも曲を作って遊んで行きたい。
2022年はまずbeat tapeを。そして、自分のepを仕込んでます。dirtrainとしてはbomb walker,mac ass tigerの作品とrandy young savageというコンピalbumを出します。あと、松本に店開きます。
・今里 ( STRUGGLE FOR PRIDE / 不死身亭一門 / LPS )

敷居を高くしていないとご飯が食べられない人達のお茶碗を、夜な夜な割っていく作業に従事しています。
1. NAKATANI “HUNGRY&ANGRY ”
どのような状況下でも、人は学べるという事を教わった。
2. LRF “THE ANTI-VAX PUNK SONGS E.P “
LRFは常に、「説得力」という言葉の意味と強さを体現してくれている。
3. “IT LOOKS TO A LIFE FORWRD 12/4 “
修正ペン界の巨匠による名言と、悪意に満ちたセレクトの出演者の紹介写真を用いたフライヤーで知られる、毎年末に行われる好企画。a.k.a. 大阪大忘年会。
みんなが口を揃えて「RIGIDが素晴らしかった」と言っていた。定期的に開催されている “ JUICYちゃん “ と併せて、機会があったら是非、足を運んでみるべきだと思う。
2021年が始まって間も無く、金山さんに呼んで頂いてSOCORE FACTORY でレコードをかけた。たくさんの英雄達にお会いして、多くの逸話とずっと知りたかった問い(大洞さんWORKSについてや、当時どうやってSTA-PRESTを入試していたのかetc. ) の答えを手に入れて、様々な最高級の音楽を耳にして完璧な時間を過ごした。だから2021はとても良い年。昨年お世話になった皆様、本当にどうもありがとうございました。2022も毎日レゲイの話しようぜ!!
ミュージックのなかにはマジックがある──以下のインタヴューで、そうまっすぐに話す人物がプロデュースを務めていることは、間違いなくこのアルバムの美点であるだろう。異なるパーソナリティを持つ人間たちが集まって、それぞれの音を重ねていくことの喜びや興奮を「魔法」と呼んでいること自体が、ビッグ・シーフというバンドの魅力をよく表している。
もはや現在のUSインディ・ロックを代表するバンドと言っていいだろう、ビッグ・シーフの5作目となる『Dragon New Warm Mountain I Believe in You』は、もともとエンジニアでもあったドラムのジェイムズ・クリヴチェニアが全編のプロデュースを務めた2枚組全20曲のアルバムだ。ニューヨーク州北部、コロラドのロッキー山脈、カリフォルニアのトパンガ・キャニオン、アリゾナ州ツーソンとレコーディング場所を4か所に分けて録音されたが、2019年の『U.F.O.F.』『Two Hands』のように音楽性を分けてリリースすることはなく、それこそビートルズのホワイト・アルバムのように雑多な音楽性が一堂に集められた作品になっている。ベースはフォーク・ロックにあるとは思うが、アメリカの田舎の風景が目に浮かぶような長閑なカントリー・ソングから、空間的な音響を効かせた静謐なアンビエント・フォーク、シンセとノイズを合わせたアブストラクトなトラック、パーカッションが耳に残るクラウトロック風の反復、そしてギターが荒々しく鳴るロック・チューンまで……曲のヴァリエーションそれ自体が面白く、なるほどビッグ・シーフというバンドのポテンシャルを十全に発揮したダブル・アルバムとまずは位置づけられるだろう。
だが特筆すべきは録音である。まるで4人が間近で演奏しているかのような生々しいタッチがふんだんに残されており、呼吸の震えを伴うエイドリアン・レンカーの歌唱もあって、アンサンブルがまるで生き物のような温度や振動を携えているのである。アコースティック・ギターの弦の細やかな震えが見えるような “Change”、ノイジーなギターが奔放に咆哮し歌う “Little Things”、ドラムのリズムの揺れが不思議な心地よさに変換される “Simulation Swarm”……オーガニックという言葉では形容しきれない、揺らぎが生み出す迫力がここには存在する。
そしてそれは、ビッグ・シーフがタイトな関係性によって成り立っているバンドだから実現できたものだと……、どうしたって感じずにはいられない。そもそもエイドリアン・レンカーとバック・ミークという優れたソングライター/ギタリストを擁するバンドであり、実際、ふたりは見事なソロ作品をいくつも発表している。けれども、サウンド・プロダクションにおいて重要な最後の1ピースであったジェイムズ・クリヴチェニア(彼もアンビエント/ノイズ寄りのソロ・アルバムを発表している)がいたことで、ビッグ・シーフはソロではないバンドが生み出しうる「マジック」を明確に目指すことになったのだ。このインタヴューでクリヴチェニアは技術的なこと以上に感覚的な説明を多くしているが、そうした抽象的なものを追求することがこのバンドにとって重要なことなのだろう。
エイドリアン・レンカーが描く歌詞世界はどこか空想がちで、だから社会からは少し離れた場所で4人のアンサンブルは成立している。そこで見えるのはアメリカの自然の風景だけではない。動物たちが生き生きと動き回れば、想像のなかでドラゴンだって現れる。そして彼女は生や死、愛について考えて、仲間たちとそっと分かち合う。
だからきっと、重要なのは魔法が存在するか/しないかではない。ビッグ・シーフは、魔法がこの世界にたしかに存在すると感じる人間の心の動きを音にしているのだ。
僕たちは全員リズムが大好きだし、リズムにグルーヴして欲しいと思ってる。それくらい、リズムには敏感なんだ。
■『Dragon New Warm Mountain I Believe in You』を聴きました。バンドにとっても現在のシーンにおいても今後クラシックとなるであろう、本当に素晴らしいアルバムだと思います。
ジェイムズ・クリヴチェニア(以下JK):(笑)わあ、素敵だな。ありがとう! 感謝!
■(笑)。まずは制作のバックグラウンドについてお聞きしたいです。日本でのライヴを本当に楽しみにしていたのでパンデミックによってキャンセルされたのは残念だったのですが──
JK:うん。
坂本(以下、□):まあ、仕方ないことではあります……。
JK:(苦笑)
■ただ、ツアーがなくなったことで制作に集中できた側面もあったのでしょうか?
JK:そうだね、僕たちからすればあれは本当に……自分たちだけじゃなく多くのミュージシャンにとっても、あの状況には「不幸中の幸い」なところがあったな、と。あれで誰もが一時停止せざるをえなくなったし、でもおかげで自分たちが過去5年ほどの間やってきたことを振り返ることができた。で、「うわあ……」と驚いたというのかな。じつに多くツアーをやってきたし、すごい数の音楽をプレイしてきたわけで、要するに、いったん立ち止まってじっくり考える余裕があまりなかった(笑)。それが今回、少し落ち着いて理解することができたっていうね、だから、「……ワオ、僕たちもいまやバンドなんだ。れっきとした『プロのミュージシャン』じゃん!」みたいな(照れ笑い)? とんでもない話だよ。それもあったし、あの時期の後で──だから、この状況はそう簡単には終わらない、長く続きそうだぞ、と僕たちがいったん悟ったところで、「みんなで集まろう。この間にいっしょに何か作ろうよ」ってことになったというかな。完全に外と接触を断ち、各自のウサギの穴にこもったままじっと待つのではなくてね。この時期が過ぎるまでただ待機していたくはなかったし、とにかく自分たちにやれることを利用しよう、少なくとも僕たちはバンドとして集まれるんだし、みんなで顔を合わせて音楽を作ろうよ、と。携帯画面をスクロールして、破滅的なニュースを眺めながら「ああ、なんてこった……」と滅入っているよりもね。というのも、パンデミックとそれにまつわるすべてに関しては、僕たち自身にコントロールできることにも限界があるわけだし、だったら音楽を作ろうじゃないか、と。
■この2年には、エイドリアン・レンカーさんの『songs / instrumentals』とバック・ミークさんの『Two Saviors』と、メンバーの素晴らしいソロ・アルバムがリリースされています。『Dragon New Warm Mountain I Believe in You』の制作に影響を与えることはあったのでしょうか。
JK:うん、絶対にそうだろうと僕は思う。とは言っても、それは必ずしも直結した影響であったり、言葉で簡単に言い表せる類の因果関係ですらないのかもしれないよ。ただ、バンド以外のところで誰もがそのひと自身の何かをやれるスペースを持っているということ、そしてバンド側にも彼らに対する信頼、そして自由を容認する余裕がじゅうぶんにあることは……そうだな、たとえばエイドリアンがソロ作を作りたいと思うのなら、イエス、彼女はやるべきだろう、僕もぜひ聴きたい、と。要するに、(パニクった口調で)「えっ、そんなぁ! 彼女がビッグ・シーフのアルバムを作りたくないって言い出したらどうしよう??」ではなくてね。僕もビッグ・シーフというバンドが好きでケアしてくれる人と同じで、レコードでとある楽曲を発表して、「これを彼女がソロ作でやっていたとしたら?」なんて考えるわけだけど──でも、そこでハタと気づくっていうのかな、それでも構わないじゃないか、と(苦笑)。これらの、僕たちがそれぞれにバンド以外の場で個人として重ねる経験は、じつのところバンドにとって非常にいい肥やしになっている、みたいな。おかげで、このバンドのスペシャルなところにも気づかされるし、かつ、たぶんバンドではやれなさそうなことを実践する柔軟性ももたらされるんだろうね。(苦笑)それでもOKなんだよ、だって、僕たちがお互いの音楽人生におけるあらゆる役割を果たすのはどだい無理な話だから。その点を受け入れるってことだし……うん、僕たちはいっしょにバンドをやっているけれども、と同時に個人でもある。それはいいことだ。
■『Dragon New Warm Mountain I Believe in You』はまず、ジェイムスさんが全体のプロデュースを務めたことが大きなトピックかと思います。前作までと今回で、あなたの役割や行動で大きく変わった点は何でしょう?
JK:そうだな……今回僕がこうプロデュースしたいと思った、「たぶん僕たちはこんな風にやれるんじゃないか?」というアイデアを抱いた、その理由の多くは、こう……自分たちの前作レコーディングでの経験を理解・吸収していってね。そうやって、「このやり方は自分たちには効果的みたいだ」、「こうすれば自分たちは気持ちよく作業できる」、「これくらい時間をかければいいらしい」といった具合に状況を眺めていたし、そうした自分のリアクションの数々はクリエイティヴ面で実りあるもののように思えた。で、そんないわば「舞台裏」の知識、僕自身がバンドの一員として現場で目にしたあれこれがあったおかげで、「あ、たぶん自分には、僕たち全員がいい気分でやれる場をセットアップできるぞ」って手応えを感じた。かつ、フレッシュで新しくも感じられる状況をね。というのも、誰もがちょっと脇道に逸れていろいろと探りたがっているのは僕も承知していたし、でも、これまで時間の余裕がなかった。それだとか、やりたい曲があっても「いや、それはちょっと……」とダメ出しが出たりね。他と比べて異色だからとか、カントリー過ぎるとか、ヘヴィ過ぎるなどなどの理由で。だから、ヘヴィな曲はここ、カントリーな曲はあそこ、という風にそれらの分のスペースをとっておくのはどうかな? と考えた。とにかく場所を作り、エイドリアンのいつもとは違う曲の書き方だったり、僕たちがいっしょに演るときの様々なプレイの仕方、それらのもっと幅広いレンジを捉えてみよう、と。と同時に、ちょっと失敗しても大丈夫なくらいの余裕も残そうとしたよ(苦笑)。及第点に達さなくても気にしない、とね。
□レコーディング・セッションを4か所に分けたのは、実験的だと思いますし、エンジニアとウマが合わない危険性だってありましたよね?
JK:(苦笑)ああ、うん。
■でも、この制作スタイルをとったのは、録音する土地から何か影響を与えられるからでしょうか?
JK:うん、間違いなく……そこだろうね。実験的な側面がたしかにあった。とは言っても、何も「奇妙な音楽を作ってみよう」って意味での「実験」ではないけどね!
□(笑)ええ、もちろん。
JK:ただこう、これは実験だし、うまくいかないかもしれないって感覚はあった。どうなるか試してみたい、と僕たちは好奇心に駆られていたんだと思う。録る場所、そして各エンジニアの作る異なるサウンドには、こちらとしても非常に反応させられるものだから。で、そこで起きるリアクションのなかに実際、バンドとしての僕たちの強みのひとつ、自分たちのやっていることにちゃんと耳を傾けられるって面があるんじゃないかと僕は思ってる。僕たちは自分たちの音楽が好きだし、だから何が共鳴するのか分かるっていうのかな、内的な反応が生じる。「おっ! このひとがレコーディングすると、僕たちの音はこんな風になるんだ。面白い!」とか、「興味深いな、たぶんもっとこれを掘り下げられるんじゃない?」と。で、それを4人の人間がそれぞれにやれるのは、バンドとして様々なリアクションがある、ということでね。たとえば、メンバーの誰かは「フム、これは生々しい(raw)、うん、エキサイティング!」って感じるし、一方で別のひとはもっとこう、そこで音響面で違和感を覚えて「ここはもっと探っていかないと……」と感じる、みたいな。とにかくそうやって、僕は異なるリアクションを引き出そうとしていった。というのも、僕たちは各自が好き勝手にやっていて、「あー、他の連中も何かやってるな」と看過するんじゃなく、お互いにとても反応するバンドだからね。しっかり耳を傾けている。だから、いい箇所があると「そこ、気に入った! いいね!」ってことになるし、逆に「この曲はうまい具合に進んでない。何か他のものが必要じゃないか」ってときもあって。

楽曲をぶつかり合わせ、コントラストを生むことである種の深みを作りたい、と。古典的な、「アルバム」に必要とされるひとつの一貫したソニック体験というか──「完璧で破綻のない35分くらいの経験」みたいなもの、それにさよならする、という。
■カリフォルニア、ニューヨークなど、多彩なロケーション/環境で制作されましたが、どのような影響をレコーディングした土地から受けましたか?
JK:大きく影響されたと思う。でも、たぶん……「ここではこれを」といった具合に、それぞれの土地環境に特定の狙いを定めてはいなかったんじゃないかな? 僕たちにとってはそれよりも、各地に違いがある、それ自体がいちばん重要だった。だから、実際に違うわけだよね──砂漠に囲まれた暖かな土地で、いままでと違う相手とレコーディングしたこともあったし、一方で、たとえば(コロラドの)山岳地帯に行ったのは冬で、おかげでものすごく外部から隔離されていた。だから、各地におのずと備わった違いの方が、「これはここで録らなくちゃいけない。あれはあそこじゃないとダメだ」的な考えよりも大事だったんじゃないかと。ある意味、僕たちに新鮮と感じられる場である限り、どこでやってもよかったっていうかな? というのも、レコーディング作業に取り組んでいる間だけじゃなく、僕たちはその場に溶けこんで暮らしていたわけだし──たとえばニューヨーク上州で録っていた間は、朝起きると散歩に出かけ、その日の空模様に反応したり。だから、確実に場所/環境には強く影響されたと思うけど、それは具体的に「ここにこう作用した」と指摘しにくい何かだ、みたいな?
□はい。
JK:と言っても、僕たちが求めていたのもそこだったんだけどね。だから、寒いし、表も暗いっていうレコーディング環境と、対してすごく暑くて、全員シャツを脱ぎ捨てて汗だくでプレイする、そうした対照的な状況下では、自分たちのプレイだって確実に変化するだろう、と(笑)。
□(笑)暑いと、もっとリラックスできるでしょうしね。
JK:(笑)うんうん。
■本作のコンセプトを提案したのはジェイムスさんだそうですが、なぜ今回のアルバムでは多様な音楽性をひとつのアルバムに集約することが重要だったのでしょうか? たとえば『U.F.O.F.』と『Two Hands』のように、音楽性で分けることは選択肢になかったのでしょうか。
JK:ああ、なるほど(笑)。そうだな……僕は個人的にぜひ、自分たちの音楽に備わった異なるスタイル、それらがすべて等しく共存したものをひとつの作品として聴いてみたいと思っていた。だから、僕たちはバンドであり、かつエイドリアンはこれらのいろんなムードを備えたソングライターでもある、その点をもっと受け入れようってことだね、何かひとつのことに集中したり、「これ」というひとつの姿を追求するのではなく。それよりも、それらを丸ごと捉えることの方にもっと興味があったし、そうやって楽曲をぶつかり合わせ、コントラストを生むことである種の深みを作りたい、と。それによってある意味……んー、いわゆる古典的な、「アルバム」に必要とされるひとつの一貫したソニック体験というか──「完璧で破綻のない35分くらいの経験」みたいなもの、それにさよならする、という。それよりもっとこう、とにかくごっそり曲を録ってみようよ、と。結果、もしかしたら3枚組になるかもしれないし、1枚きりのアルバムになるのかもしれない。ただ、作っている間はどんな形態になるかを考えずに、僕たちはやっていった。それよりもとにかく、たくさんプレイし、たくさんレコーディングしようじゃないか、その心意気だった。その上で、あとで編集すればいいさ、と。4ヶ月の間、あれだけ努力すれば、そりゃきっと何かが起きるに違いない(苦笑)、そう願っていたし、その正体が何かはあまりくよくよ気にせずとにかく進めていった。何であれ、自分たちがベストだと思う組み合わせを信じよう、そこには僕たちを代弁するものが生まれるはずだから、と。
■本作はロウ(raw)な音の迫力が圧倒的なアルバムですよね。たとえば先行曲 “Little Things” の野性的なギター・サウンドが象徴的かと思いますが、このアルバムにおいて、ある種の音の生々しさや激しさはどのようなアプローチで追求されたのでしょうか?
JK:思うに、ああしたロウさ、そして自然な伸びやかさの多くはほんと、練習のたまものだというか、長年にわたり培ってきたものなんじゃないかな。自分たちがこつこつ積み重ねてきたものだっていう感覚があるし、じょじょに気づいていったというか……だから、アルバムを作るたびに「うおっ、これだよ、最高じゃん!」みたいに思うんだ(苦笑)。要するに、過去に作ってきたアルバムのなかでも自分たちのいちばん好きなものっていうのは、少々……何もかもがこぎれいにまとまった、オーヴァーダブを重ねて完璧に仕上げた、そういうものじゃなくて、少々ワイルドな響きのものが好きでね。“Little Things” だと、あの曲でのバックのギターの鳴りはクレイジーだし、どうしてかと言えば──実際、ある意味クレイジーな話だったんだよ。というのもあのとき、彼はまだあの曲をちゃんと知らなかったから。エイドリアンが書いたばかりのほやほやの曲だったし、彼はそれこそ、曲を覚えながら弾いていたようなもので、そのサウンドがあれなんだ! だからエキサイティングな、違った響きになったし、いつもなら彼はちゃんと腰を据えて(落ち着いた口調で)「オーケイ、わかった、こういうことをやるのね、フムフム」って感じだけど、あのときはもっと(慌てた口調で)「えっ、何? この曲をいまやるの?」みたいなノリだったし(笑)、僕が惹かれたのもそういうところだったっていうか。ずさんさやミスも残っているけど、と同時に自由さが備わっている、という。
□なるほど。その話を聞いていて、ニール・ヤングのレコーディングのアプローチが浮かびました。たしか彼もよく、きっちりアレンジを決め込まずに録音したことがあったそうで。ある意味、最終型がわからないまま、レコーディングしながらその場で曲を探っていくっていう。
JK:(苦笑)ああ、うんうん!
□ただ、その探っていく過程/旅路が音源にも残っていて、そこが私は好きです。
JK:うん、すごくこう、「(他の音に)耳を傾けながら出している」サウンドだよね。その曲をまだちゃんと知らなくて、しかも他の連中がどんな演奏をするかもよくわからない、そういう状態だと──やっぱり、自動操縦に頼るわけにはいかないよ(笑)。次にどうなるかつねに気をつけなくちゃいけないし、お互いに「次のコースが近づいてる?」、「だと思うけど?」、「あっ、そうじゃない、違った!」みたいに(苦笑)確認し合うっていう。
□自分の音楽的な反射神経・筋肉を使って反応する、という感じですね。
JK:うん、そう。
□そうやって他のメンバーの音をしっかり聞きながら、いろんなヴァイブをクリエイトしていく、と。
JK:イエス、そうだね。

想像力を働かせることで、物事は何もかもディストピアンなわけじゃないんだ、と思うことは大事なことじゃないかと思う。この世の終わりだとしても、そこでイマジンできるようにならなくちゃ。
■資料によると、はじめ制作が難航するなか “12000 Lines” が突破口になったとのことですが、その曲のどのような点が、あなたたちにインスピレーションを与えたのでしょうか?
JK:ああ。思うに……まあ、あの曲自体が実に、とても美しいものだしねえ……。ただ、僕が思うのは、今回のアルバム向けにおこなった複数のレコーディング・セッション全体のなかで、はじめて何かが起こったのがあの曲だった──というのも、あの曲を録ったのは最初にやったセッションでのことだったし──からじゃないかと。僕たち全員があの曲を高めている、そんな手応えがあった。だから、録り終えた音源を聴き返すまでもなく、プレイしたあの場で即座に、自分たちには……「いまの、すごかったよね? 絶対なんか起きたよ、かなりやばくない?」とわかっていたっていう(笑)。だから、僕たちはあのときやっと、フィジカルな面での正しい状態──各人がどこにポジションを占め、同じ空間でどんな風にお互いの音を聴けばいいのか、そこを発見したっていうかな。だから、あの曲はある意味突破口になったんだね、あれをプレイバックしてみたとき、みんなが(驚いたような表情を浮かべつつ)「……うん、素晴らしい響きじゃん! これ、すごくいい!」と思った(笑)。
□(笑)。
JK:(笑)いや、でもさ、最初の段階だと、そういう風に自信を与えてくれる要素って必要なんだよ、はじめのうちはいろいろと試すものだから。ドラムの位置をあれこれ変えたり、エイドリアンの立ち位置を取っ替え引っ替えしたり……そういう技術面での、エンジニア系の作業のすべてを経てみるし、ところが、いざ出た音を聴いてみると──「まだ『音楽』に聞こえないなぁ……」(苦笑)みたいな気がしたり。
□(笑)。
JK:(笑)要するに、まだレコードになっていないし、いずれなんとか形になってくれますように、と願いつつやっていく。だから、あれ(“12000 Lines”)は、はじめて「うん、これはグレイトな響きだ」と思えた1曲だったっていうか。
■“Time Escaping” や “Wake Me Up To Drive” のように、ユニークなリズムを持った曲が目立つのも本作の面白さだと思います。このようなリズムの工夫は、どのように生まれたのでしょうか?
JK:その多くは、たぶん……このバンドのメンバーは誰もが、音楽的な影響という意味で、いろんなヴェン図を描いているからじゃないかな? もちろん、4人全員が好き、というものもちゃんとあるんだよ。だけど、全員の好みが重なる領域は狭いし、だからある意味、この4者がピタッと一致した中央のエリア、そこにビッグ・シーフが存在する、みたいな(笑)?
□ああ、なるほど。
JK:(笑)それが主要部であって、そこでは全員が「ビッグ・シーフが好き!」ってことになる。でも、全員がそれぞれに、個人的に好きなものもたくさん含まれている。そこには被っているものもあるよ。だけど、たとえばバック、彼の背景は……ジプシー・ジャズにあるんだよ、ジャンゴ・ラインハルト系っていうかな。だから、バックは彼なりにとてもリズミックな音楽家だし、非常に独特なスウィングを備えている。一方でマックス(・オレアルチック/ベース)は、とんでもないリズム・キープをやってくれるひとで、彼もジャズ・ベース奏法をルーツに持っている。だからあのふたりはどちらも、テンポの維持っていう意味では、僕よりもはるかに腕がいいっていうのかな(苦笑)、ビートにジャストに乗っていくって面では、あのふたりはドラマーだよ。
□(苦笑)。
JK:その一方で、エイドリアンについて言えば、彼女のタイミングの感覚は彼女の運指のパターンに、フィンガー・ピッキングに多くを依っていて。だから、この4人はそれぞれが異なるリズム感覚を備えているってことだし、僕が思うに今回のアルバムでは、僕たちはそれらをごく自然に溶け合わせた、そういうことじゃないかと。だから、たとえば「これこれ、こういうことをやってみない?」って場面もあるわけ。言い換えれば、自分にもおなじみのフィーリングを追求するっていうか、過去の作品を参照することがある。「これはニール・ヤングっぽくやった方がいいんじゃない?」とか、「リーヴォン・ヘルム(※ザ・バンドのドラマー)っぽくやったらどう?」って具合にね。でも、今回のアルバムでは、僕はそれよりも「ここは、『僕たちならでは』でやってみるべきじゃないかな?」と示唆したっていう。うん……僕たちは全員リズムが大好きだし、リズムにグルーヴして欲しいと思ってる。それくらい、リズムには敏感なんだ。
「これは自分には不自然だ」と思うことって、おのずとわかるものだ、というか。で、それはオリジナリティがあるか否かではなく、自分が本当にやろうとしていることは何なのか、ということなんだよね。
■ビッグ・シーフの音楽の魅力は、そのアンサンブルの濃密さによって4人の関係の緊密さ、ミュージシャン/友人同志としてのタイトさが音から強く伝わってくるところだと思います。何か、特別なことがここで起こっているぞ? みたいな。
JK:うん。
■ただ、あなたたち自身はそのことを意識しているのでしょうか?──もちろん、そうは言っても、いわゆるニューエイジ的な「神がかった」スペシャルさ、という意味ではないんですけどね。
JK:(苦笑)うんうん、わかる。
□意図的にやっているものではないにせよ、自然に生まれるこのケミストリーを、あなたたち自身は自覚しているのかな? と。
JK:確実にあるね、うん。だから……僕たちも、そういうことが起きているのは感じてる。そうは言っても、必ずしも四六時中いっしょにプレイしている、ってわけじゃないけれども。ただ、それでもつねに感じてきたというのかな。バンドの初期の頃ですら、自分たちはある意味気づいていたんだと僕は思うよ……「このバンドには何かが宿っているぞ」と。だから、僕たちが演奏していて互いにガチッと噛み合ったと感じるときには、何かクールなことが起きている、みたいな? 要するに、「ジェイムスはいいドラマーだし、マックスも優秀なベース奏者。エイドリアンはグレイトなソングライターであるだけじゃなくギターも達者だし、バックも上手い」的な、単純に各人の才能を足した総計、「ビッグ・シーフは全員優秀だよね!」という以上に大きい何かがある。いやいや、それだけじゃなくて、ビッグ・シーフにはちょっとした、特別なケミストリーが働いているんですよ、と。だから、いっしょにプレイすればするほど、僕たちはそのケミストリーをもっと感じることができる。そのぶんそこにアクセスしやすくなるし、化学反応が起きている/逆にそれが起きていないかも、すぐわかる。それは、録音音源からも聴き取れると思う。だから、たとえその曲にダラッとしたところやミスが残っていても、聴き手は「おーっ、ちょっと待った、これは……!?」と気づくんじゃないかな。それらのミスは、たとえば歌詞が間違っていたら直すし、ヘンなドラムのフィルもすぐに修正できるって類のものだよ。けれども、この演奏には他の楽曲以上に「僕たちならではの何か」がしっかり宿っているってこと、そこは聴き手にもわかるだろうし……(苦笑)第六感みたいなものだよね。だから、もちろん、それは言葉では表現しにくいわけで──
□(苦笑)ですよね。
JK:要するに、これは一種の、「サムシング」だからね(苦笑)、僕たちの間に走っている、何らかのエネルギーなんだし。だけど、間違いなくリアルなものでもあるんだよ、ってのも、そのエネルギーが発生していないと、それも僕たちにはわかるから。たとえば、とある音源を聴き返してみたら、誰もがお互いに対してイライラして怒っているように聞こえるんだけど、どうしてだろう……? と思ったり(苦笑)。
□(笑)。
JK:で、「そうか、たぶん自分たちには休憩が必要だな!」と悟るっていう(笑)。

■エイドリアンさんの書く歌詞は感覚的なものも多いですし、パーソナルな感情や体験を出発点にしているように思えます。バンドのなかで、彼女の書く歌詞の感情や主題はどのようなアプローチでシェアされるのでしょうか?
JK:うん……主題がデリケートになることもあるよね。そこに対する僕たち全員のメインのアプローチの仕方というのは、言葉と歌とをサポートしようとする、かつ、それを通じて人間としてのエイドリアンをサポートすることじゃないかと思う。これは特別だというフィーリング、あるいは傷つきやすい何かだというフィーリングが存在するし、それによってこちらも歌に対して一定の敬意を払わなくてはいけないな、という気持ちになる。なぜかと言えば、このひとはそれだけ覚悟して自分自身をさらけ出してくれているんだってことがわかるし、本当に、そのパフォーマンスを、そのひとが何を言わんとしているのかをしっかり感じ取ろうとするようになる。だから、その面をサポートしたい、それに向けてプレイしたいと思う、というか。それもあるし、そうすることで自分自身に対しても少しオープンになるってところもあるだろうね。僕たちはとにかくあれらの歌に惚れこんでいるわけだけど、いくつかの歌に至ってはもう、僕たちそれぞれが「うっわあ……この曲は『宝石』だ!」と感じるっていうのかな、だから、その曲の歌詞が僕個人にとってすごく特別な意味を持って迫ってくる、という。そんなわけで、うん、(歌詞/主題等)はデリケートなこともあるけれども、それもまた、歳月のなかで僕たちが育んできたリスペクトみたいなものの一部なんだと思う。エイドリアンは、僕たちは彼女の歌と歌詞とに心から気を遣っている、そう信頼してくれているし……だから、僕たちが歌を真剣に捉えずにふざけていたりして、そのせいで彼女が孤島にひとりっきりで疎外された気分にさせるつもりは僕たちにはない、というか? リードしているのは彼女だし、彼女の強烈さだったり、目指す方向性、僕たちはそこについていこうとしているから。
□お話を聞いていると、あなたたちの関係は「トラスト・ゲーム」みたいなものですね。みんなが受け止めてくれるのを信じて、後ろ向きに倒れる、という。
JK:(笑)ああ、うんうん、トラスト・フォールね!
□はい。それをやれるだけ、エイドリアンもあなたたちを信じているし、あなたたちもそれを受け止める、それだけ絆が強いバンドなんだなと思います。
JK:うん、その通り。
■(カントリー/フォーク・ミュージシャンの)ジョン・プラインが亡くなったとき、バンドが追悼を捧げていたのが印象的でした。
JK:ああ、うん。
■実際、あなたたちの音楽を聴くと、様々な時代の様々なアーティストの影響が豊かに入っていると感じられます。少し大きな質問になってしまうのですが、ビッグ・シーフはアメリカの音楽の歴史の一部であるという意識はありますか? ある意味、未来に向けてその松明を運んでいる、というか……。
JK:うん、言わんとしていることはわかる。そうだな、僕の見方としては……その「対話」の一部として参加している、という感じかな。僕たちの受けてきた影響ということで言えば、ジョン・プラインは本当に大きな存在だし……だから、ジョン・プラインはすでに世を去ったわけだけど、いまもなお、僕たちの音楽は彼の音楽と対話を続けているし、それに強く影響されている、みたいな? そうあってほしい。でも、と同時にそれは、彼の音楽に対する反応でもある、っていうのかな。たとえば、「ああ、あなたのその表現の仕方、好きだなあ!」とか。自分も同じことを言いたいと思ってるけど、あなたが表現するとこうなるんですね! みたいなノリで、一種の、クラフト(技術)とアイデアの交換が起きているっていう。で……うん、いろんなレコードとの間で、ある種の対話が起きているなと僕は感じているし──じつに多彩な人びとが、様々なやり方でいろんなことをまとめ、音楽的な合成をおこなっているわけだし、いまやクレイジーで手に負えないっていうか(苦笑)、とんでもない量だからいちいちフォローすることすら無理、みたいな。けれども、一種のスレッドみたいなものは存在するよね……様々な影響を取り入れるというか、自分の気に入ったもの、あるいは霊感を与えてくれる何かを取りこんで、そこから何かを作り出そうとする、というスレッドが。僕たちはそれをやるのがとても気持ちいいし、っていうか、自分たちがオリジナリティ云々に強くこだわったことって、これまでなかったんじゃないかと思うよ(笑)? 要するに、自分が「これだ、こう言うのが正しい」と感じる、あるいは逆に「これは自分には不自然だ」と思うことって、おのずとわかるものだ、というか。で、それはオリジナリティがあるか否かではなく、自分が本当にやろうとしていることは何なのか、ということなんだよね。
■ビッグ・シーフはリアルな感情や人間関係を描きながら、同時に、本作でも宇宙やドラゴン、自然や動物、魔法といったファンタジックなモチーフが登場するのが面白いと思います。
JK:(笑)たしかに。
■なぜこの世界にファンタジーが必要なのか問われたら、ビッグ・シーフはどのように答えるとあなたは考えますか?
JK:なるほど。思うに、このアルバムのタイトルに僕たち全員がとても強く惹きつけられた、その大きな要因は──はじめから、僕たちがこのレコードを作る前から、あのタイトルは存在していたんだ。だから、あのタイトルがレコードに影響を与えたっていうのかな、「これは、『Dragon New Warm Mountain I Believe in You』って感じがする音楽だろうか?」みたいな……あれはいろんなものを意味するフレーズだろうけれども、思うに、こう……あれはとにかく、世界にはこの「マジック」が存在するってこと、音楽(ミュージック)のなかにはマジックがあるんだ、そこを認めようとすること、というのかな。ほんとに……ロジックだの、物事の基本の仕組みが通用しない何かであって、それよりもずっと、ずっと大きなものだ、と。だから、たんに「ドラム、ベース、ギターがあって、そこで誰かが歌ってる」程度のものじゃないし──いや、たしかにそうなんだけれども、たんにそれらを足しただけじゃなくて、それとはまた別の何かが起こっているんですよ、みたいな(笑)。だから、僕たちのプレイの仕方、そして音楽への耳の傾け方のなかでは、何かが起きている、と。で、うん……この世界において、そういった抽象的というのか、空想的/突飛のないコンセプトなんかを想像力を通じて鍛える、それによって試されるのって、大事なことじゃないかと思う。そうやって想像力を働かせることで、物事は何もかもディストピアンなわけじゃないんだ、と思うことはね(苦笑)。この世の終わりだとしても、そこでイマジンできるようにならなくちゃ、みたいな。いまの世のなかはリアルじゃないし、そこに向かっていくのではなく、むしろ想像力を働かせていこう、と。というわけで、うん、とにかくそうしたマジカルな要素を持つのって、大事だと思う。というのも、僕たちだってみんな、音楽のなかにマジックが宿っているのは知っていると思うし──ただし、それって「これ」と名指しするのが難しいものであって。でも、僕たちとしては、「いや、たしかに何かが存在しているし、それはスペシャルなものなんです」ってところで。でも、たぶん……「それは何ですか?」と問われても、はっきり形容しがたい、というね、うん。
□質問は以上です。今日は、お時間いただき本当にありがとうございます。
JK:こちらこそ、質問の数々、ありがとう。
□近いうちに、あなたたちがまたツアーに出られることを祈っていますので。
JK:僕たちもそう思ってるよ、ありがとう!
■ビリー・ホリデイ、死の真相
2020年5月、アメリカ・ミネソタ州ミネアポリスで白人警官に殺害された黒人男性ジョージ・フロイドの死によって、1939年に録音されたビリー・ホリデイの名曲“奇妙な果実”が脚光を浴びている。「南部の木には奇妙な果実がなる。血が葉を濡らし、根にしたたる。黒い体が揺れている、南部のそよ風に」。リンチで殺害され木に吊るされた黒人の死体を描写したこのプロテスト・ソングは、ブラック・ライヴズ・マター(BLM)運動の時代に新たな重要性を発揮し、2020年上半期には200万回以上ストリーミング再生されている。
この曲は1965年にジャズ歌手で公民権運動の活動家でもあったニーナ・シモンがカヴァーした。シモンは「私がこれまでに聞いた中で最も醜い曲だ。白人がこの国の同胞にしてきた暴力的仕打ちとそこから生まれた涙という意味で、醜い」と語った。厳粛なピアノの音色に乗って深い悲しみを表現したシモンの曲は2013年にカニエ・ウエストが、2019年にはラプソディがサンプリングしている。ラプソディは「80年も経っているのに、あの曲は今の時代を物語っている」と振り返っているが、黒人がリンチで殺害されることが当たり前だった時代にビリーが歌った“奇妙な果実”は21世紀の人種問題や社会問題とも共鳴し続けているようだ。
歴史学者の研究によると、1883年から1941年までの間にアメリカでは3000人以上の黒人がリンチを受け殺されているという。ボブ・ディランの“廃墟の町”は「やつらは吊るされた死体の絵葉書を売っている」という歌詞で始まるが、南部で普通に見られた〝奇妙な果実〟は当時、絵葉書として出回っていたというのだ。
こんな時代に“奇妙な果実”を定番曲として歌ったビリーが一体どのような仕打ちを受けたのかはあまり知られていない。リー・ダニエルズ監督の最新作『ザ・ユナイテッド・ステイツVS.ビリー・ホリデイ』は、米連邦麻薬局が仕掛けた巧妙な罠によって死に追いやられたビリーの死の真相を描きだしている。
映画の原作はヨハン・ハリの『麻薬と人間 100年の物語』(作品社)。ハリは、『ル・モンド・ディプロマティーク』紙や『ニューヨーク・タイムズ』紙などで健筆をふるう英国出身のジャーナリストだ。アムネスティ・インターナショナルの「ジャーナリズム・オブ・ザ・イヤー」に2度選ばれている。同書は、1930年に連邦麻薬局の初代局長に任命され、フーバーからケネディまで5代の大統領の下で32年間「麻薬局の帝王」として君臨したハリー・アンスリンガーに着目し、彼が書き残した記録などを基に、彼が麻薬と黒人ジャズ・ミュージシャンへの怒りをビリーに集中していった経緯を見事に暴いている。

■奴らを牢屋にぶち込め!
禁酒法時代の取締官だったアンスリンガーはカリブやアフリカの響きが入り混じったジャズを「黒人にひそむ生来の衝動」と考え、「真夜中のジャングル」と評した。「ジャズの演奏家の多くはマリファナを吸っているおかげで素晴らしい演奏をしていると思い込んでいる」という部下の報告もあった。マリファナは時間感覚を損ねるので「(即興演奏の)ジャズが気まぐれな音楽に聞こえるのはそのせいだ」とも語っている。いずれにせよ、ハリによるとアンスリンガーは「チャーリー・パーカー、ルイ・アームストロング、セロニアス・モンクといった男たち全員を牢屋にぶち込みたくて仕方がなかった」というのだ。
というのも、「(薬物依存症の)増加はほぼ100%、黒人によるもの」と考えたからだ。アンスリンガーが薬物戦争を遂行できたのはアメリカ人が感じていた恐怖に負うところが大きい。『ニューヨーク・タイムズ』紙は「黒人コカイン中毒者、南部の新しい脅威に」と書いた。「これまでおとなしかった黒人がコカイン中毒で暴れている。……署長は拳銃を抜いて銃口を黒人の心臓に向け、引き金を引いた。……射殺するつもりだったが、銃弾を受けても男はびくともしなかった」。コカインは黒人を超人的な存在に変えてしまい、銃弾を浴びても平気なのだと噂されていた。そのため南部の警察で使われる銃は口径が大きくなった。ある医療関係者は「コカイン依存症のニガーを殺すのは大変だよ」と語っている。
「黒人が怒るのは白い粉が原因だ。白い粉を一掃すれば黒人はおとなしくなり、再び服従する」と考えたアンスリンガーは、部下を使ってミュージシャンを尾行させ、「ジャズをやるやつら」を一網打尽にしようとした。だが、ジャズメンには堅い団結があった。密告者をひとりとして見つけることができなかった。仲間がひとりでも逮捕されると彼らは資金を募って保釈させた。米財務省はアンスリンガーの連邦麻薬局が時間の無駄遣いをしていると批判しはじめた。やむなく、彼は当時、ニューヨーク・ダウンタウンの人種差別のないカフェ・ソサエティで“奇妙な果実”を歌い、人気上昇中だったジャズ・シンガーのビリーに狙いを定めることにした。
アンスリンガーはビリーがヘロインを使っているという噂を聞きつけ、ジミー・フレッチャーという職員を「覆面警官」としてビリーの元に送り込み、監視させた。ジミーは薬物を売る許可を持っており、自分が警官ではないことを証明するために客と一緒にヘロインを打つことも認められていた。ビリーを逮捕するために送り込まれた捜査官を信用したビリーは、彼を部屋に招き入れ、麻薬所持で逮捕された。その時、身体検査した女性警官とジミーの目の前で、ビリーは真っ裸になり「見てごらん」と放尿した。

■パパを殺したものすべてが歌い出されている
“奇妙な果実”はそのカフェ・ソサエティで生まれた。作詞作曲は共産党員の教師エイベル・ミーアポール(ペンネームはルイス・アレン)だが、ビリーは自伝(油井正一・大橋巨泉訳『奇妙な果実 ビリー・ホリデイ自伝』晶文社)の中で「彼(ミーアポール)は、私の伴奏者だったソニー・ホワイトと私に、曲をつけることをすすめ、三人は、ほぼ三週間を費やしてそれをつくりあげた」と書いている。これに対してミーアポールは沈黙を守った。「レイシストたちにビリーを攻撃する材料を与えたくなかった」というのがその理由だ。
ビリーはこの歌詞に「パパを殺したものがすべて歌い出されているような気がした」と語っているが、ギタリストだった父クラレンスは巡業先のテキサス州で肺炎に罹り、黒人であるがゆえに病院をたらい回しにされた挙げ句、39歳で「白人専用病院」で亡くなった。ビリーは「テキサス州のダラスが父を殺した」と叫んだ。差別の激しい南部でリンチを受け、木に吊るされた黒人の姿を、自分の父親の死に重ね合わせたのだ。
ビリーは自伝の中で、カフェ・ソサエティで初めてこの曲を歌った晩をこう書いている。「私は客がこの歌を嫌うのではないかと心配した。最初に私が歌った時、ああやっぱり歌ったのは間違いだった、心配していた通りのことが起った、と思った。歌い終わっても、一つの拍手さえ起らなかった。そのうち一人の人が気の狂ったような拍手をはじめた。次に、全部の人が手を叩いた」
それからは毎晩、ステージの最後の曲として歌った。感情をすべて出し切って歌ったので、歌い終わると立つのがやっとになった。ビリーが歌い出す瞬間、ウェイターは仕事を中断し、クラブの照明は全て落とされた。こうして黒人へのリンチに対するプロテスト・ソングはビリーの十八番になった。この曲のレコーディングは大手の〈コロンビア〉には断られたが、インディー・レーベルの〈コモドア・レコード〉によって実現し、ビリー最大のベスト・セラーになった。
ビリーが歌う“奇妙な果実”は多くの黒人の心を奮い立たせると同時に、レイシズムを嫌う白人の間にも感動の輪を広げた。黒人解放運動はカフェ・ソサエティの晩に始まったと数年後に言われるようになった。連邦麻薬局が「その歌を歌うな」と禁じたにも関わらず、ビリーが勇気を奮って歌い続けたからだ。

■あいつらはあたしを殺す気なのよ
当時、連邦麻薬局は財務省の奥の薄暗い場所に置かれていた。かつては酒類取締局だったが、1933年に禁酒法が廃止されたため、即刻取りつぶしになっても仕方のないような弱小組織だった。それをアンスリンガーは「地上からすべての薬物を一掃する」ことを誓い、一大組織に育て上げた。アンスリンガーが残した記録によると、彼はジャズ界で唯一ビリーにこだわり、手を緩めなかった。
薬物所持で逮捕され、女性刑務所で8ヶ月の服役を終えた後も、ビリーを執拗に追い回した。ビリーのヒモを脅して彼女のポケットにヘロインを忍ばせ、麻薬所持で現行犯逮捕したこともあった。ビリーを破滅に追い込むため、アンスリンガーはありとあらゆる罠を仕掛けた。
最初に薬物所持でビリーを逮捕したジミーは「アンスリンガーに話をつけてやる」とビリーに約束し、その後もビリーに接近し続けた。母親から「あんな素晴らしい歌手はいない」と諭されてこともあった。それから、捜査官と麻薬依存者がクラブで一緒に踊る姿が見られるようになった。そのうち愛し合う関係になった。ビリーが薬物所持で再逮捕された時には裁判所でビリーに有利になる証言をしてアンスリンガーの怒りを買った。だが、アンスリンガーはビリーの情報を得るため捜査官としてジミーを使うことを厭わなかった。
裁判が終わった後もビリーは“奇妙な果実”を歌い続けた。周囲の誰もが当局から睨まれるのを恐れて「歌わないように」とビリーを説得したが、「これは私の歌だ」と誰の忠告にも従わなかった。ビリーの友人は「彼女はどこまでも強い人だった。誰にも頭を下げなかった」と語っているが、その強さは黒人と麻薬を憎むアンスリンガーには通じなかった。
その後もビリーは薬物とアルコールに溺れる生活を続け、1947年に解毒治療を受けるが失敗している。その数週間後にまたもや麻薬所持で逮捕され、懲役一年の刑に処せられた。度重なるスキャンダルのせいでニューヨークでの労働許可を取り消され、地方巡業に出るようになったビリーは経済的にも追い詰められ、麻薬とアルコールをやめることができなくなった。この間、カーネギーホールでのコンサートや欧州ツアーを一応は成功させたが、疲労や体重の減少による心身の衰えは隠しようがなかった。パリ公演を観たフランソワーズ・サガンは「(ビリーは)痩せほそり、年老い、腕は注射針の痕で覆われていた」「目を伏せて歌い、歌詞を飛ばした」と書いている。
1959年、44歳になったビリーは、自宅で倒れ、病院に入院したが、既にヘロイン離脱症状と重度の肝硬変を患っており、心臓と呼吸器系にも問題があった。「長くは生きられない」と医者に言われた。それでもまだアンスリンガーはビリーを許そうとはしなかった。ビリーの方も友人に「見てなよ。あいつらは病室までやってきて、あたしを逮捕しようとするから」と吐き捨てるように言った。その言葉通り麻薬局の捜査官がやって来てアルミ箔に包まれたヘロインを見つけたと言って寝たきりのビリーを訴追した。ヘロインの包みはビリーの手の届かない病室の壁に貼ってあった。これも罠だった。
警官2人が病室の入り口で警備に当たり、ビリーはベッドに手錠で拘束された。ビリーの友人らが「重病患者を逮捕するのは違法だ」と主張すると、警官はビリーの名前を重病人名簿から削除した。こうしてメタドン投与が打ち切られ、ビリーの体調は日に日に悪化した。ようやく面会を許された友人に向かってビリーは「あいつらはあたしを殺すつもりなのよ」と叫んだという。
ビリーが病院のベッドで亡くなった時、警察は病室の入り口を封鎖し、彼女の死が公表されないようにした。手錠をかけられたビリーの足には50ドル札が15枚くくりつけてあった。ビリーを世話してくれた看護師たちにお礼として渡すはずだった。これが彼女の全財産だった。葬式の時に参列者が暴動を起こすことを恐れた警察はパトカーを数台出動させた。ビリーの親友は周囲の人たちに「ビリーは、彼女をめちゃくちゃにしてやろうという陰謀に殺された。麻薬局が組織をあげてそう画策したんだ」と怒りをぶつけた。

■ビリーは真のヒーローだ
この映画で歌も雰囲気もビリー・ホリデイになりきったアンドラ・デイはスティーヴィー・ワンダーに見出された黒人ジャズ・シンガーだ。BLM運動のデモ行進でも歌われた“ライズ・アップ”の曲でグラミー賞にノミネートされたことがあるが、演技の経験はなかった。心配したリー・ダニエルズ監督が彼女に演技指導をつけたところ、その変身ぶりに驚いたという。監督は「彼女は演じているのではなく、ビリーそのものだった。神の声を聞いたような気がした」と語っている。
当初、監督はビリーの曲に合わせてデイに口パクで演じさせる意向だった。だが、予定を変更しデイにはライヴで歌わせることにした。映画の中で“奇妙な果実”をフル・ヴァージョンで歌うシーンは圧巻だ。ビリーの深い悲しみと怒りが臨場感を持って伝わってくる。聞く者の心の琴線を強く揺さぶるシーンだ。まるでビリーがデイに憑依しているようで鳥肌が立った。
このシーンについてデイはこう語っている。「ビリーとして、そして私自身として“奇妙な果実”を生で歌うことは、痛みのある体験だった。同時に不思議なことだけれど、カタルシスでもあった」
ダニエルズ監督は1980年代後半のニューヨーク・ハーレムを舞台にした映画『プレシャス』で、母親から虐待を受けた黒人の少女がフリースクールの女性教師との出会いで「学ぶことの喜び」を知り、成長していく姿を描いた。1919年にヴァージニア州の農場で生まれた黒人の人生を描いた『大統領の執事の涙』(2013年)では、公民権運動やブラックパンサーの活動などを通して黒人から見た歴史を見せてくれた。
今回の映画について監督はこう語っている。「政府がビリーを止めるただ一つの方法は、彼女を死の床に追い込むことだけだった。だから、ビリーは真のヒーローだ」。ヨハン・ハリによると、同じ麻薬中毒者でも白人歌手のジュディー・ガーランドや、「赤狩り」で知られる共和党上院議員ジョセフ・マッカーシーはアンスリンガーから良質な麻薬を渡され、逮捕されることもなく擁護されていたという。黒人はもちろん、共産党員や密売ルートとして中国やタイを槍玉に上げたアンスリンガーのグローバルな「麻薬戦争」は、自らが麻薬の “売人” になるという汚い戦争でもあった。
結局のところ、彼の政策は麻薬密売シンジケートのギャングと取締当局をお互いに持ちつ持たれつの関係にしただけだったともいえる。アンスリンガーは終生、黒人差別と「地上から麻薬を一掃する」というパラノイア(偏執狂)に取り憑かれていた。ビリーはその犠牲者だが、“奇妙な果実”の歌声はデイによって模倣(ミメーシス)され、社会変革を求める「神の声」として現代に蘇った。

予告編


