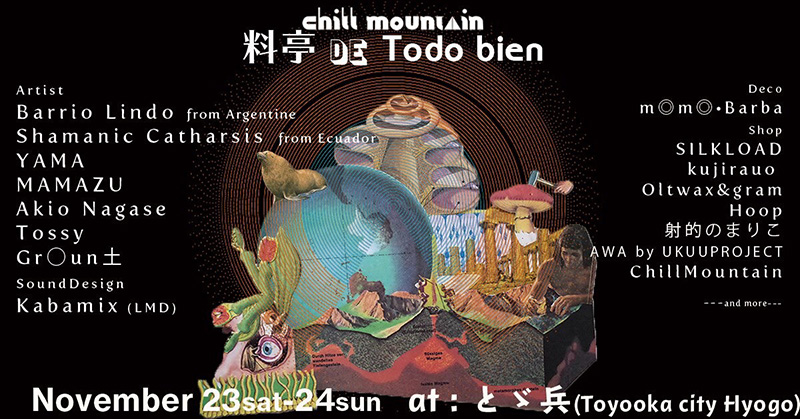アナ・ロクサーヌはサンフランシスコ出身のアジア系のニューエイジ音楽家だ。アナの生みだすドローン音楽には、北インドの古典音楽のヒンドゥスターニ音楽の響きがあり、同時に西カトリックの聖歌隊のような響きもある。西欧のクラシックとアジア音楽のエッセンスがアンビエントやアナの声やドローンの中に溶け合っている。アナの出自も大きく関係しているかもしれない。
移民の両親によって育てられアナは、ジャズ、クラシック、合唱音楽を学び、その神聖さを知った。2013年、インドのアターカンドで過ごしたとき、アナは人生を左右するほどに重要な声/歌の教師に出会い、共に生活し、勉強をした。彼女はアナに古典的なヒンドゥスターニの歌を教えた。この体験はカリフォルニア州オークランドにある実験的なミルズカレッジで音楽研究を終了することになる大きなきっかけになった。2018年、アナは自身がインターセックスであるということも公表した。自身の性別とアイデンティティの探求が、アナの音楽には深く込められている。その意味で近年流行のニューエイジのリヴァイヴァルのような「見捨てられた20世紀音楽の再発見」のようなコンテクストからアナの音楽は遠く離れている。正式な音楽教育、民族性が混じり合う歴史を背景とした複雑な出自、自身の性別に関するアイデンティティの探究から社会正義への問題に至るという複雑な文脈を内包しているのだ。加えて母親のCDコレクションであった80年代/90年代のR&Bからも影響を受けているという。
そうした状況から生まれたアナの音楽は攻撃性からは遠いものである。2019年に〈Leaving Records〉からリリースされたファーストアルバム『~~~』を聴けば、即座に分かる。たしかに辛い現世だ。不平等と差別に満ちている。しかしそこにある幸福を慈しみ、希求するような感覚も重要であり、それも音楽の力ではないか……。そんなことを思わせるような安らかなアンビエント/ドローンなのだ。現世を慈しみつつも、同時にこの世ではない天国を目指すような、ふたつの感覚が共存している。生命と臨死体験を経由したような音響とでもいうべきか。あらゆるカテゴライズを拒みつつも、自由に、端正に、静かに語りかけるような極めて独創的な新世代ニューエイジ、アンビエント音楽である。
『~~~』は、まずカセットで発売され、即座に売り切れた。次いでレコードもリリースされた。マスタリングはマシューデイヴィッドがストーンズ・スロウ・スジタオでおこなった。ニューエイジとヒップホップ・カルチャーとの結びつきも感じられて興味深い。『~~~』には全6曲が収録されている。どの曲も声、電子音、環境音などが安らぎの中で交錯し、聴き手の心と体に深いところに「効く」アンビエント/ドローン音楽に仕上がっている。インド音楽と聖歌隊の音楽が交錯するような美麗な M1 “Immortality”と M4 “Nocturne”、ミニマルな電子音と声と持続音がミックスされる M2 “Slowness”、M5 “I'm Every Sparkly Woman”、ノイズが雨のように空間に満ちていく M3 “It's A Rainy Day On The Cosmic Shore”を経て、最終曲 M6 の“In A Small Valley”に至るとき、そこから聴こえてくるのは幸福な記憶のような話声や笑い声だ。人の真の安らぎとは何かと思わずにはいられない。
「ジェンダー/とアイディンティティ」というテーマを持ったこのアルバムが希求するのは、互いの差異を認め、平等に、人と人が語り合い、笑うような世界かもしれない。そう考えると「天国」は意外とこの世界にも「ある」。本作の柔らかく、空気のような透明なアンビンスを浴びていると、思わずそんなことを考えてしまった。