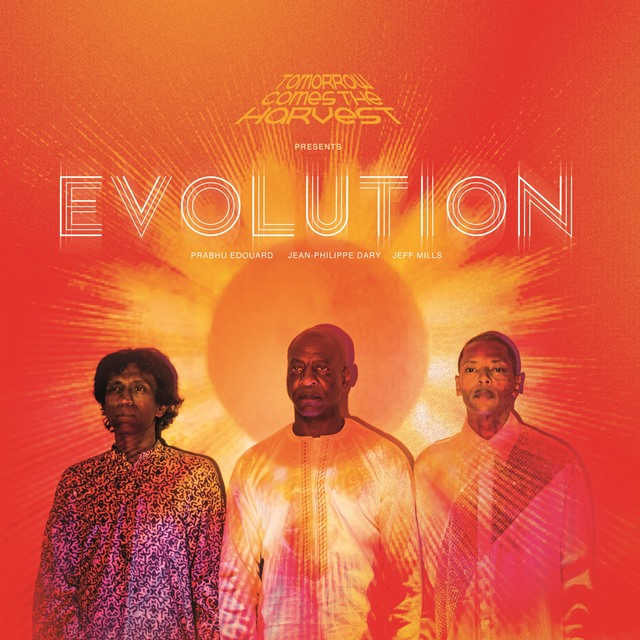2017年の『Fly Or Die』で注目を集め、その野心的なスタイルで将来が期待されていたものの、昨年亡くなってしまったジェイミー・ブランチ。才あるこのジャズ・トランぺッターが生前ほぼ完成させていたというアルバムがリリースされることになった。パンクやノイズからアフロ・カリビアンの要素までが含まれる作品に仕上がっているようだ。CDの発売は9月6日。注目しよう。
Jaimie Branch『Fly or Die Fly or Die Fly or Die』
2023.09.06(水)CD Release
2022年8月22日39歳という若さで亡くなった、ダイナミックなジャズ・トランペット奏者/作曲家ジェイミー・ブランチによる、瑞々しく、壮大で、生命力に溢れた遺作となるアルバムが完成。メンバーには、チェリストのレスター・セントルイス、ベーシストのジェイソン・アジェミアン、ドラマーのチャド・テイラーが参加。
ジェイミー・ブランチが亡くなった時、彼女が率いたフライ・オア・ダイの新作はミキシングを残すのみで、ほぼ完成していた。遺族と共に完成までこぎ着けたこのアルバムは、デビュー作『Fly Or Die』から変わらないメンバーと制作されたが、その音は随分と遠いところへと我々を導く。パンク・ジャズのダイナミズムとノイズから、アフロ・カリビアンの陽気なポリリズムまでがここには刻まれている。かつてないほどにフィーチャーされているジェイミーのヴォーカルは、ハードコアとソウルの間を深く揺れ動く。美しいという形容こそが相応しいアルバムだ。(原 雅明 ringsプロデューサー)
ミュージシャン:
jaimie branch – trumpet, voice, keyboard, percussion, happy apple
Lester St. Louis – cello, voice, flute, marimba, keyboard
Jason Ajemian – double bass, electric bass, voice, marimba
Chad Taylor – drums, mbira, timpani, bells, marimba
with special guests-
Nick Broste – trombone (on track 5 & 6)
Rob Frye – flute (track 5), bass clarinet (track 5, 6 & 7)
Akenya Seymour – voice (track 5)
Daniel Villarreal – conga and percussion (track 2, 5, 6 & 7)
Kuma Dog – voice (track 5)
[リリース情報]

アーティスト名:Jaimie Branch(ジェイミー・ブランチ)
アルバム名:Fly or Die Fly or Die Fly or Die
リリース日:2023年09月06日(水)
フォーマット:CD
レーベル:rings / International Anthem
品番:RINC109
価格:2,700円+税
販売リンク:
https://ringstokyo.lnk.to/WQEQcd
オフィシャル URL :
http://www.ringstokyo.com/jaimie-branch-fly-or-die-fly-or-die-fly-or-die-world-war/