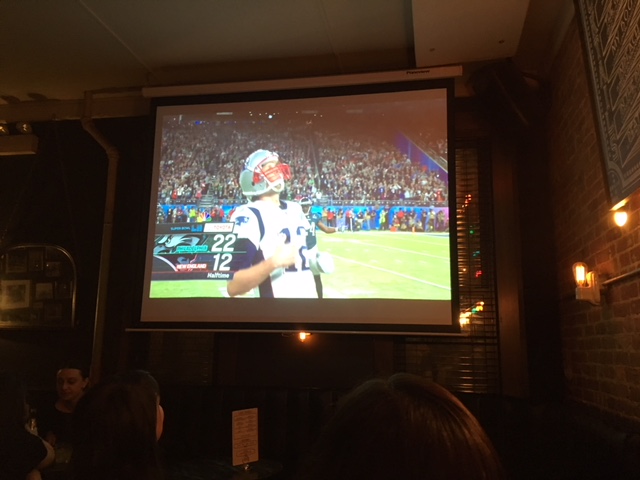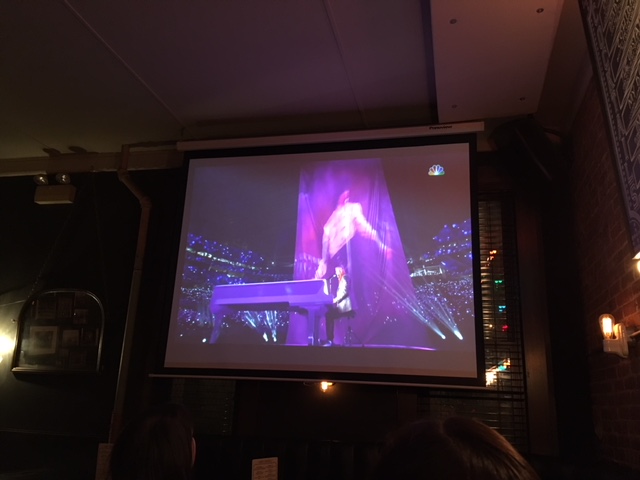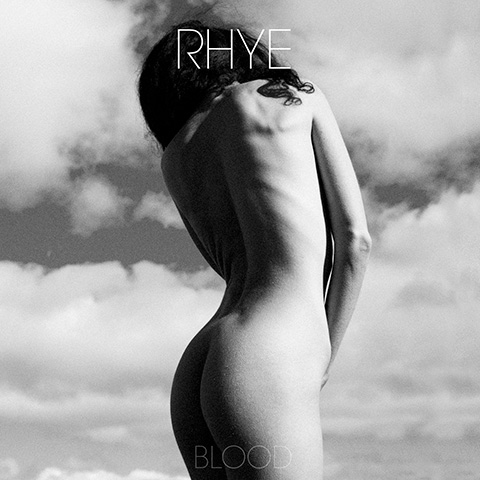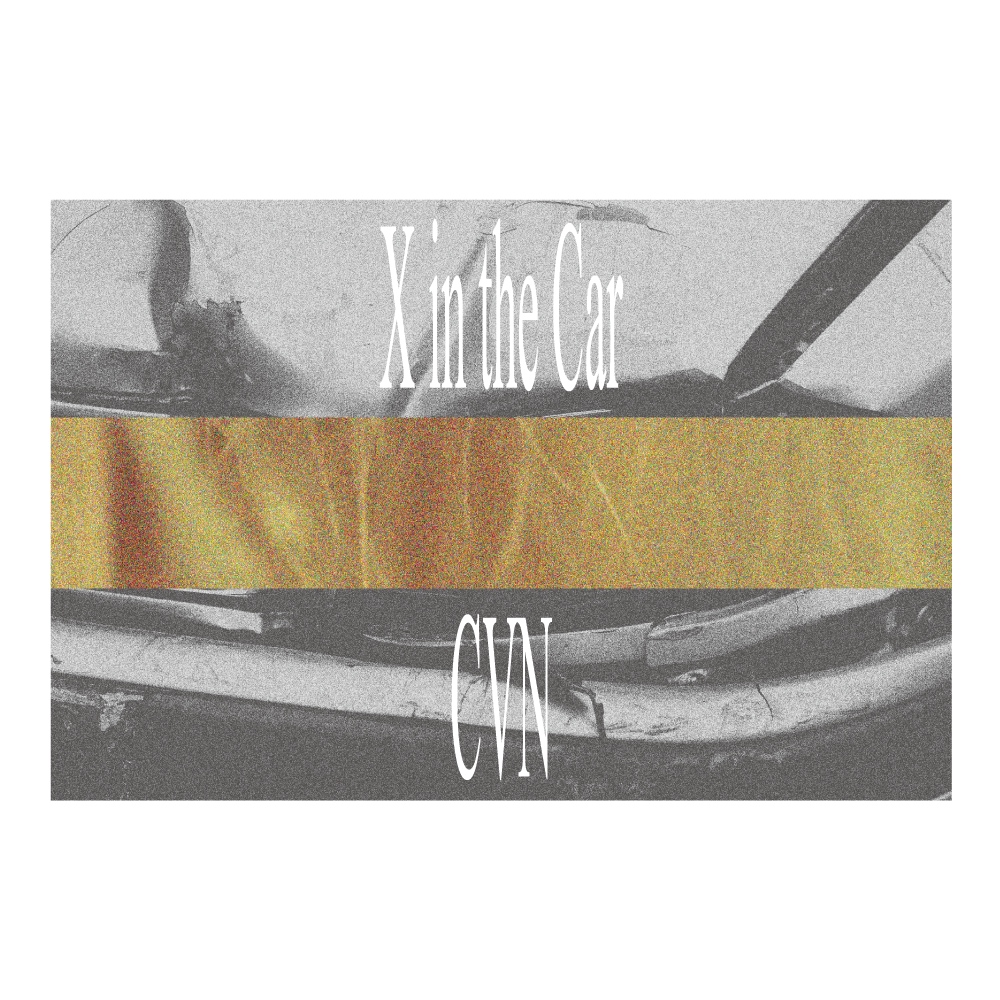ブルックリンのレコード屋はグリーンポイントやブッシュウィックに多いのだが、家賃の高いウィリアムスバーグにお店を構えるのがUKのレコード店兼音楽会場のラフ・トレード。2013年にオープンしてから騒音問題でクローズしたこともあったが、その後は順調に運営し、最近では中古レコードも置いている。

場所柄、UKからの観光客が多く、昼はカフェとしても機能していて、2Fはアート本やグッズがあり、Sonos
の音響システムが楽しめる部屋もある。私が行ったのは夜9時頃だったが、中古レコードを10枚くらい購入している人がいた。以前インタヴューしたマネージャーのジョージもレジスターにいた。
相変わらず、圧倒的にレコードが多かったが、ラフトレのオススメ・コーナーは見る価値ありで、カセット・テープやカセット・デッキも沢山増えていた。ショーはスーパーチャンク、ジョアン・アズ・ポリスウーマン、クリスティン・ハーシュ、モービーなどの中堅バンドから、アンバー・マーク、ガス・ダッパートンなどのニューアーティストまで、全体的にシュッとしている感じのラインナップが揃う。バワリープレゼンツがオーガナイズしているので、どうしてもそうなる。ちなみに今回見たバンドは、リグレット・ジ・アワー。
https://www.roughtrade.com/events/teen-girl-scientist-monthly

まだ20代前半の、アップステート出身の若いバンドだが、久しぶりに、U2やナショナルなどのバンド・サウンドを地でいっている。目を瞑って聞くと2018年の音とは思えないが、新世代の冷めた感覚で、熱いギターをかき鳴らしているのを見ると応援したくもなる。だってアルバムタイトルが『Better Days』なのだ。20代前半で!
オーディエンスは、彼らの両親や従兄弟、友たちでいっぱいだった。同窓会みたいだったが、こういうライヴ・バンドが健在なのを確認したのは今夜の収穫だった。ラフトレードで隣にいた男の子と話していると、彼はロンドンから観光で来ていて、することもないからここに来たと言っていた。バンドでなく、ラフトレードが目的だったらしい。見たバンドも、結構好きだと言っていた。
ラフトレードは安全なバンドのショーケースで、DIYスペースのように様々なハプニングや感情を剥き出しにする生々しさはほとんどない。至ってクールなのだ。それでも$20を知らないバンドに難なく払うお客さんがいるし、暇な時間には、レコードも買ってくれもする。ちなみにDIYショーはほとんどフリー、もしくは$5ー$10。


Regret the hour @rough trade
ラフトレの後、違法なブッシュウィックDIYスペースに行ってたくさんのDIYバンドを見て、勝手にブーズを持ち込んで大騒ぎしている人たちを見て、ホッとしている自分もいる。最近のDIYスペースは減っているばかりかすぐに摘発されるので、オンラインで住所を公開していない。外の見張りもかなり徹底しているので、一見が入るのは難しい。それゆえこのシーンを閉鎖的にしているのだが、DIYコミュニティは健在。
NYは、DIYバンド/会場に優しくなるように、2017年末から少しずつ動き出している。Dr.マーティンやハウス・オブ・ヴァンズのような企業もDIYバンドを使って自分たちの商品をプロモートしているし、DIYバンドがもっと日の目を見るときがくるのではと、いろんなショーを見ながら考える。近い将来ラフトレで、彼らを見ることもあるのかもしれない。

Grace kelly all day @DIY space