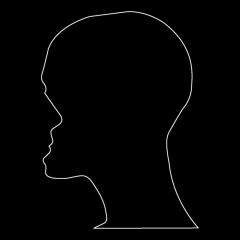カリブーの音楽の真骨頂は(Manitoba時代も含めて)ドリーミーであることだ。いろんな音楽によく使われる形容詞だが、カリブーはそのハイクオリティー・ヴァージョンである。〝ドリーミー〟であることは何も幻覚剤のみを意味しない。甘くメロウでメロディアスな音楽であることも意味し、未来に対するウキウキとしたオプティミスティックな気分のことも含有する。日々の暮らしのなかの喜びとか。
クラウトロックをやろうがフォークをやろうがIDMをやろうがハウスをやろうが、カナダ出身の元数学者にして音楽プロデューサーである彼の音楽は、優雅にしてドリーミー、メロディアスにして刺激的、ソフトにして機知に富んでいる。また、いっきに彼の名声を高めた『Swim』(2010)がスウィミングプールに通っていたことが契機となったように、そして前作『Our Love』(2014)の主題に娘の誕生があったように、作品の動機は私的で、素朴極まりない。が、作り話よりも実話が優位であるこの時代においては、それもまた彼にとっての追い風だろう。「僕の場合は音楽が僕についてで、歌詞がまずパーソナルだし、サウンドも僕なんだ」と彼は語り、カリブーらしさとは何かと訊かれることは、自分の人生とは何かと訊かれることに等しいとも語っている。
ひとつ面白いのは、彼のその〝ドリーミー〟で〝私的〟で〝感じの良い〟ただしひと工夫のある音楽は、ハウス・ミュージック(meではなくweの音楽)を取り入れたことで開花していることだ。先に挙げた『Swim』のことだが、そもそもブラック・ハウスには暗い面もあるし、間違っても私的ではない。しかしそれを自由に自分なりに解釈するプロデューサーはすでにたくさんいる。そうしたハウス解釈組のなかにおいて、彼=ダン・スナイスは抜きんでたひとりという話である。『Swim』以降の彼は、Daphni名義でよりフロア向けのダンストラックを作っているし、『Our Love 』もその路線の延長にあった。新作『Suddenly』もまた彼の家族の記録であり、そして変わらずハウスを根幹としている。が、ほぼすべての曲が歌モノであり、何曲かはハウスから離れてもいる。簡単にいえば、フォークやR&Bやラップの要素も取り入れてたポップな出来で、またしても懲りに凝った作りの質の高いアルバムだ。
ぼくはいちどだけダン・スナイスに対面取材したことがある。見るからに誠実そうで、良い人柄の人物だった。その感じの良さが、彼の音楽にも滲み出ているような気がする。で、そのとき彼が言ったのは、アーサー・ラッセルこそ我がヒーローということだった。
『Suddenly』を聴いていると、彼は本当にアーサー・ラッセルのようになってきていると思う。実験音楽からフォークやポップソング、そしてダンス・ミュージックまで自分が好きな音楽であればなんでもやってしまうその縛りのないアプローチの自由さが似ている。それが創意工夫をもって自分だけのユニークなサウンドに仕上げてしまうことも。
音楽をやりはじめた頃はボーズ・オブ・カナダが好きだったというダン・スナイスは、その時代その時代に応じて自身のスタイルを変化させていった。セオ・パリッシュからの影響が『Swim』の原動力だという話しは有名だが、『Suddenly』にはより広範囲に渡る彼の影響が散りばめられている。もちろんハウスは彼の基盤だし、“You And I”のような美しいメロディとアイデアの盛り込まれたハウシーな曲は出色の出来だと思う。そのいっぽうで、エリック・サティとミニマル・テクノを掛け合わせラッパーの声をまぶしたかのような“Sunny's Time”、R&Bとブレイクビーツとペット・ショップ・ボーイズを滑らかに融合させた“New Jade”、ガラージのリズムをジャズ・ギターの甘いメロディに混ぜ合わせた“Like I Loved You”といった新境地も見事な仕上がりを見せている。ファンクのリズムにディスコのストリングスが交わる“Home”、フュージョン・ハウスの“Lime”、もっとも真っ当なハウスに近い“Never Come Back”や“Ravi”、ソフト・ロックの“Magpie”……はっきり言うが、ぼくはこのアルバムは『Swim』以上だと思う。カリブーは確実にアップグレードしている。
世界はいまたいへんな局面を迎えている。アメリカにはいま良からぬ緊張感が生まれていると、かの地に住む旧友から聞いている。彼はつい先日東京にやって来たところだが、万が一を思ってぼくとはすぐには会わないという。日本は欧米ほど感染者数が急激に増えていないためか欧米の先進国にくらべて政府の対応はゆるい。日本人は清潔好きだから助かっている面もあるのかもしれないし、海外メディアからバッシングされているように検査数が少ないからかもしれない。いずれにしても、漠然とした不安をみんなが抱えながら暮らしているのがいまだ。困窮している人たちのために毅然とリーダーシップを取れる政治家はいないし、もう何週間も週末のサッカーの試合もない。まさに〝突然〟やって来たこんな難しい時代では、ますます音楽は贅沢なひとときとなっている。家でカリブーの愛らしい音楽を聴くというささやかな幸せ。ドリーミーであること、上等じゃないか。読者のみなさんも音楽を楽しみつつ、そしてまずはくれぐれも気をつけてください。














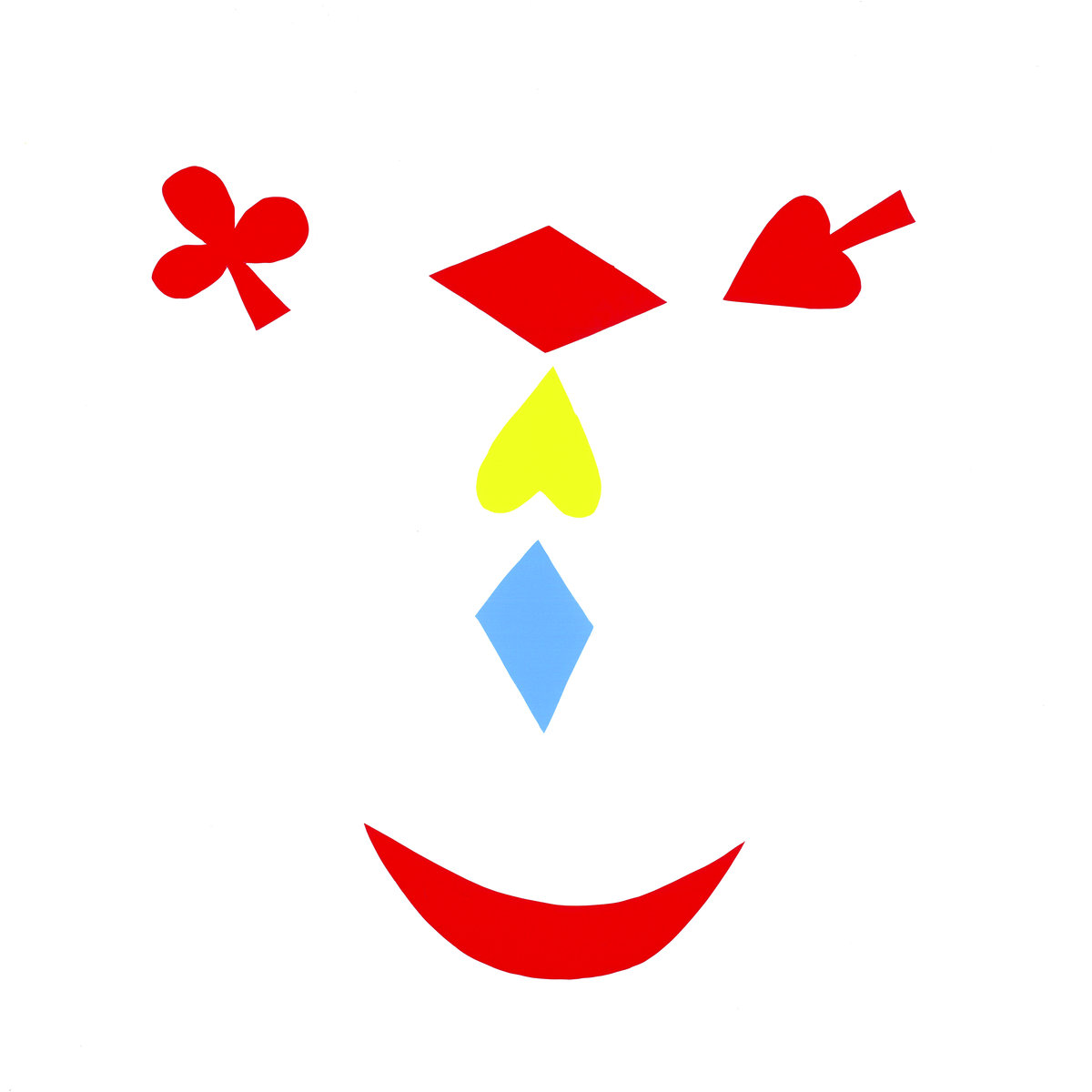 DJ Nigga Fox / Cartas Na Manga
DJ Nigga Fox / Cartas Na Manga
 Tunes Of Negation / Reach The Endless Sea
Tunes Of Negation / Reach The Endless Sea
 Sequoyah Murray / Before You Begin
Sequoyah Murray / Before You Begin
 Ultramarine / Signals Into Space
Ultramarine / Signals Into Space
 Caterina Barbieri / Ecstatic Computation
Caterina Barbieri / Ecstatic Computation
 Tenderlonious / Hard Rain
Tenderlonious / Hard Rain