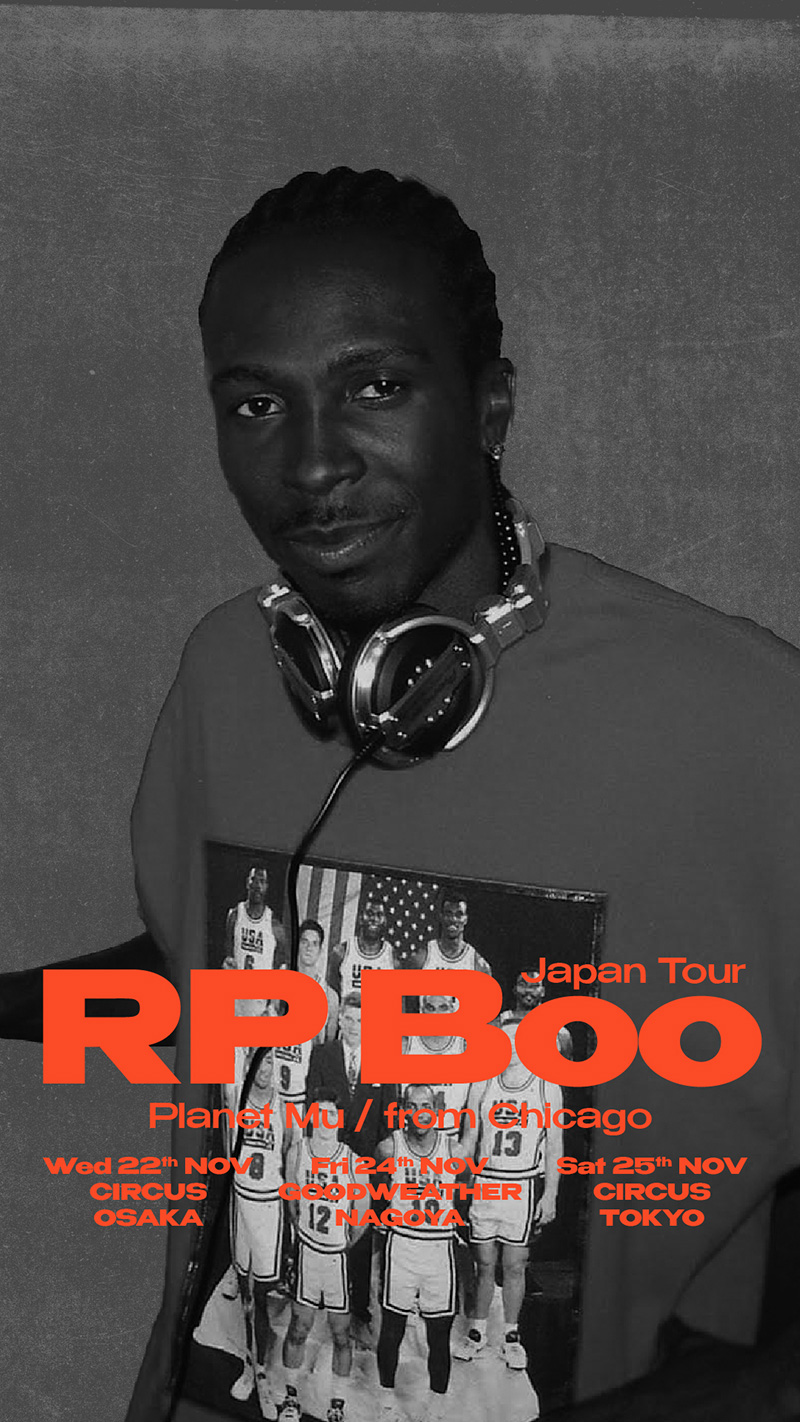今年精力的にパーティを開催してきたファッション・ブランドの〈C.E〉。その2023年最後のパーティの内容が発表されている。〈The Trilogy Tapes〉から作品をリリースするメルボルンのCS + Kremeは今回が初来日。
今年充実のアルバムを送り出したカッセム・モッセ。さらにそこに〈C.E〉のパーティには初出演となるlivwutang、YPYの2組が加わる。全4組中3組がライヴでの出演とのことで、新しい試みに満ちた〈C.E〉のパーティを堪能しよう。会場はおなじみの表参道VENTです。
[11月27日追記]
新たに追加出演者が発表されました。ロンドンをベースに活動するDJのCõvcoが登場。また、会場のみ限定で販売されるTシャツについても告知されています。


C.E presents
CS + Kreme -Live-
Kassem Mosse -Live-
livwutang
YPY -Live-
開催日時:2023年12月1日金曜日 午後11時30分
会場:VENT http://vent-tokyo.net/
料金:Door 3,000 Yen
Advance 2,000 Yen (11月30日木曜日 午後11時59分 販売終了)
https://t.livepocket.jp/e/vent_20231201
Over 20's Only. Photo I.D. Required.
20歳未満の方のご入場はお断り致します。年齢確認のため顔写真付きの公的身分証明書をご持参願います
■CS + Kreme
CS + Kremeは、コンラッド・スタンディッシュとサム・カーメルの2人による音楽プロジェクト。ナーム/メルボルン周辺を拠点に活動する2人は、数年前に知り合い、スタジオ・ジャムを経て、今に至る。
ここ数年、CS + Kremeは、Total Stasis、Wichelroede、Efficient Space、Reel Torque、The Trilogy Tapes(TTT)といった、彼らの理念を共有するレーベルから、レコードをリリースしており、TTTのウィル・バンクヘッドとのコラボレーションが最も多く、TTTは本デュオにとって非公式なホームとなっている。2018年にEP『Cold Shoulder』、2020年に『Howwouldyoufeelwithoutthatthought』、そして『Snoopy LP』をリリースし、高い評価を得た。2022年、彼らは前述したTTTより最新作となるアルバム『オレンジ』をリリースした。『スヌーピー』が「静かに魅惑的で、深くロマンチックで、こっそりと病みつきになる」ものだったのに対し、『オレンジ』は、スキッターのようなドラム・プログラミング、呼びかけるような声、ダブワイズ的な処理で構成された、それまでとは異なるレコードである。このLPは、デュオが完全にゼロから再出発し、未知の世界へと自分たちのために別の道を切り開いたかのような、深いオリジナリティに満ちている。このアルバムには、イギリスの伝説的フォーク・ミュージシャン、ブリジット・セント・ジョンや、『スヌーピー』へ参加したオーストラリア出身のコンポーザー/パフォーマー、ジェームス・ラッシュフォードがゲストとして参加している。
経験豊富なミュージシャンであるスタンディッシュとカーメルは、共に実験的なグループとして成功した豊かな歴史を持っている。例えば、F ingers、Bum Creek、Standish/Carlyon、Devastationsなどである。近年では、ヴォーカリストのブリジット・セント・ジョン、『スヌーピー』と『オレンジ』でオルガンを演奏したジェイムズ・ラッシュフォード、『Howwouldyoufeelwithoutthatthought』の "April Fools Day "においてチェロを担当したジュディス・ハマンらとコラボレーションしている。
2020年、マンチェスターのザ・ホワイト・ホテルでの公演を終えた後、CS + KremeはRewire Festival(オランダ)とBerliner Festspiel(ドイツ)へ出演した。2022年には、イギリス、ヨーロッパ、北米で27日間もの期間に及ぶツアーを行った。同年後半、NTSにおいてラジオ・レジデンスを開始。
2023年現在、彼らは新曲を書き、パリの権威あるBourse de CommerceやハーグのRewire Festivalなど、ヨーロッパにおける一連の公演に向け準備を進めている。
https://soundcloud.com/cs-kreme
https://twitter.com/csandkreme
https://www.instagram.com/csandkreme/
■Kassem Mosse
Kassem Mosseは、2006年にクィア・コレクティブ・レーベルMikrodiskoからデビューし、その埃っぽく、モヤモヤとした霧のようなプロダクションでシーンに驚をあたえた。絶賛された3枚のアルバム、Workshop 19(2014年)、Disclosure(2016年)、そしてChilazon Gaiden(2017年)において、自身のスタイルを進化させてきた。
モッセは自身のレーベルであるOminiraを運営するほか、Workshop、Honest Jon's、The Trilogy Tapes(TTT)といったレーベルからリリースを行っている。
モッセの最新のコラボレーションは、TapesとMix Mupの3名によるZigtrax、それにFit Siegel とのプロジェクトFIT+KMである。また、Mix Mup とのMM/KM、Lowtec とのKolorit、Beatrice Dillon とのDillon Wendel、といった実験的デュオの一員でもある。
Kassem Mosseとしての活動に加え、様々な別名義でソロ・リリースをおこなっており、代表的なものにDJ Residue(TTT)、Seltene Erden(Youth)がある。
https://soundcloud.com/kmos
https://twitter.com/KareemMoser
https://www.instagram.com/kassemmosse/
■livwutang
livwutangは、特定のスタイルやジャンルに収まらない現代的なDJの流れの中に位置する一方で、高揚した運動性、内省的な力強さ、混沌とした巧妙さなど、明らかに折衷的な要素をダンスフロアへと届けている。
シアトルにおいてパイレーツ ラジオの解放された周波数とDIYレイヴのサイケデリックな抱擁の中で始まったDJという彼女の表現活動は進化を続け、彼女の内なる世界を周囲の人々と結びつけてきた。
彼女のスタイルは、ダブの統一された空間認識とダンス・ミュージックのレネゲード・サウンドの楽しさの中に根ざしたものだが、彼女の音楽的な生い立ちから生涯影響を受け続けてきたものが、彼女の魅惑的な音楽的ビジョンに注ぎ込まれている。それは、中央・西部アフリカのリズム、ブラック・アメリカン・ミュージックの革新的な勢い、そして過去60年のポピュラー・ミュージックから生まれた時代を超越したヴォーカルの華やかさと耳に残るメロディーを巧みに操る魅惑的な音のパレットである。
2021年からニューヨークを拠点に活動する彼女は、dweller、Honcho Campout、Sustain-Releaseにおいてそのセットを披露している。
Dekmantel、Truants、Animalia、Dimensions Festivalに提供したミックスの数々で世界中のエアウェイブを魅了した彼女はその国際的な知名度を今後さらに飛躍させていくだろう。
https://soundcloud.com/livwutang
https://twitter.com/livwutang
https://www.instagram.com/livwutang/
■YPY
日野浩志郎によるソロプロジェクト。
国内外のアンダーグラウンドミュージシャンのリリースを行うカセットレーベル「Birdfriend」、コンテンポラリー/電子音楽をリリースするレーベル「NAKID」主宰。
「goat」、「bonanzas」というバンドのプレイヤー兼コンポーザーであり、これまでの主な作曲作品は、クラシック楽器や 電子音を融合させたハイブリッドオーケストラ「Virginal Variations」(2016)、多数のスピーカーや移動する演奏者を混じえた全身聴覚ライブ「GEIST(ガイスト)」(2018-)の他、サウンドアーティストFUJI|||||||||||TAと共に作曲・演奏した作品「INTERDIFFUSION A tribute to Yoshi Wada」(2021-)等。佐渡を拠点に活動する太鼓芸能集団 鼓童とは2019年以降コラボレーションを重ねており、中でも延べ1ヶ月に及ぶ佐渡島での滞在制作で映像化した音楽映画「戦慄せしめよ/Shiver」(2021、監督 豊田利晃)では全編の作曲を日野が担当し、その演奏を鼓童が行った。
https://soundcloud.com/koshiro-hino
https://twitter.com/po00oq
https://www.instagram.com/po00oq/