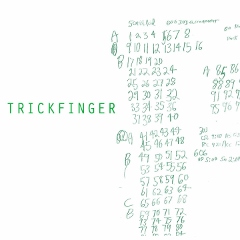White Men Are Black Men Too.とはまたポリティカルな。というのは誰しも思うところだが、うちの連合いと隣家の息子の反応は、「ほんなん聞いたらブラックの男どもが怒るだろ」だった。「なんで?」と言うと、「一緒にすんなって言うぜ。あいつら自分たちのことすげえクールだと思ってるから」「そうそうそう」とか言って頷き合ってるので笑ったが、ガーディアン紙が「UKのアイデンティティ・ポリティクスとブラック・マスキュリニティを想起させるタイトル」と書いていた後述の部分がその辺だろう。
昨年10月、かのFKAツイッグスを押さえて「番狂わせ」で彼らがマーキュリー賞を受賞したとき、個人的には「スコットランド出身だからじゃないのか」と思った。英国中を騒然とさせたスコットランド独立投票は9月だった。あれから半年が過ぎ、またなぜかスコットランドが英国総選挙の主役に躍り出るというシュールな状況になっているが、「スコッツにUKを支配させてたまるか」という感情が皆無のわたしのような外国人にすれば、いまスコットランドがおもしろい。右傾化と緊縮でノー・フューチャーな英国に揺さぶりをかける力が、意外なところから出現した。リベラルや左派で当たり前のUK音楽メディア界にも、スコットランドに夢を感じている人は少なくない筈だ。
そのスコットランドは昨年の独立投票で、在住外国人には投票権を与えたが、仕事の関係で国境の外に住んでいるスコットランド人には投票権を与えなかった。White Men Are Black Men Too. という言葉がそうした場所から出てきていると思えば、これはプログレッシヴ・ポリティクスをも想起させる。
*******
彼らがマーキュリー賞を獲った1stは所謂オルタナティヴ・ラップだったので、昨今の風潮からすればスコットランド→ポリティカル→ラップという構図は非常にわかりやすいので「ブリット・アワードのオルタナティヴ」を自称するマーキュリー賞が彼らに賞をやりたくなった気持ちもわかるが、2枚目は一転してポップ・ソング・アルバムになっている。
で、これがやけにいい。ラジオから聞こえてくる懐かしいポップ・ソングの肌触りがするのだ。音楽性は全く違うが、わたしがこの肌触りから思い出したのは、ザ・スペシャルズの”Ghost Town”だ。ガーディアン紙に「UKチャート史で最も重要なポップ・ソング」と評され、いまでも史上最高の流行歌と呼ばれるあの名曲は、ロンドン暴動後に再評価された。
ポップ・ソングとは、好いたのはれたのふられて泣いただのいうことを歌うだけのものじゃない。ということを十代のわたしに教えてくれたのはUKだった。政治や社会や時代のムードを鋭く抉ったポップ・ソングが普通にチャート1位になり、幼い子供たちがそれを口ずさみながら育つというポップの伝統が英国にはあった。
が、いつしかその伝統は途絶えた。UKチャートは公開オーディション番組出身のボーイバンドや、白人の兄ちゃんや姉ちゃんたちが黒人の声を真似た歌い方で好いたのはれたのふられて泣いただのいうことを歌っているばかりで、”Ghost Town”のようなポップ・ソングが聞こえなくなった。ここは本当にUKなのか。
白人を責めるのは飽きた
彼の軽率さは本心じゃない
黒人だって彼のように振る舞うことがある
白人には黒人でもある奴らがいる
奴らはニガー
君たちはジェントルマン
白人には黒人でもある奴らがいる
ニガー
ニガー
ニガー
目を覚ませ ‟Old Rock’n Roll″
“Old Rock’n Roll”のシンプルな歌詞と歌いやすさは、むかし子供たちが歌っていたオールド・ポップ・ソングを思い出させる。本作のレヴューを読むと、エレクトリック、クラウトロック、ゴスペル、ロック、ソウル、ヒップホップ、グライム、ミニマリズム等々、ありとあらゆる音楽のジャンルや、ビーチ・ボーイズからレディオ・ヘッドまで、ボ・ディドリーからアウトキャストまで節操がないほど広範な人々の名前が「like(〜のような)」という言葉の後に使われている。が、個人的には「like」の後につけたいのはザ・スペシャルズの”Ghost Town”だ。彼らがやろうとしたのはきっとその現代版だ。何よりもこのアルバムは、UKのポップ・ソングが先鋭的で政治的でユーモラスでクールだった時代を思い出させる。
英国全土を揺るがすスコットランドのSNPが掲げるマニフェストの一つがスコットランド沖の核兵器トライデント撤廃だが、科学者や芸術家によるトライデント撤廃運動Time to Move On Tridentのテーマ曲に使われいてるのが本アルバム収録の‟Rain or Shine″だ。
僕に力をくれ 僕に痛みをくれ
永遠なんてすべて同じこと
未知のものを探し続けて
力をつけても救いにはならない
力をつけても救いにはならない ‟Rain Or Shine″
スコットランドには昔の英国にあった気骨のようなものが残っている気がする。その古臭さがいま進歩的と注目されているとすれば、それは時代が動く兆しだろう。
「White Men Are Black Men Too」は、プログレッシヴ・ポリティクスの地から出て来たプログレッシヴ・ポップだ。