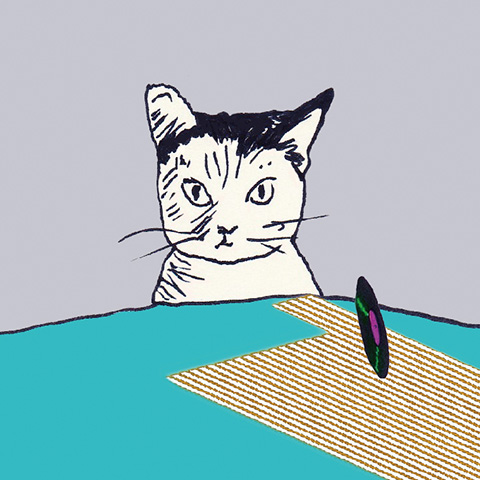大久保祐子
小さな子供がいる家庭ならわりとどの家でも朝と夕方はNHKの教育テレビ番組(Eテレ)を当たり前のように毎日つけている。教育テレビ、賢くなりますように! というのは表向きの理由で、各番組自体の面白さに加えてそれぞれのキャスティングのセンスの良さに、ぜひとも子供に見せたい(いやむしろ自分が見たい)と親の方が積極的にテレビに夢中になっている場合が多い。古くはトータス松本やクレイジーケンバンドなどの曲に加え、大人計画や片桐仁、サケロック時代の星野源などTVブロス的サブカル人が旬のお笑い芸人に混じって参加していたり、さらに最近は水曜日のカンパネラ、ナカコー&ミキやカジヒデキまで出演しているのだから、私も朝から目が離せない。そしてEテレのクリエイティヴ且つ遊び心のある大人向けな人選の最たる番組がこの『デザインあ』で、僅かな時間とはいえほぼ毎朝コーネリアスの音楽がテレビから流れるという贅沢が日常化してから、かれこれもう7年も経とうとしていることに驚く。残念ながら子供のほうはたいして興味を示してくれないのだけれど。
青葉市子や坂本真綾にアート・リンゼイ、昨年活動停止を発表したチボ・マットなどの近年のコーネリアス・ファミリーや、本物のいとこにあたるハナレグミなど、豪華なゲスト・ヴォーカルを迎えた番組のサウンドトラックのシリーズ第2弾。収録されている曲は既にTVで何度も流れているお馴染みのものばかり。ミニマル・ミュージックでありながら控えめなコラージュ作品のようであったり、クラシックのようにも聴こえたり、童謡のようなカジュアルさもあり、堅苦しさは全くない。楽曲は番組内での文字や絵を使った映像に基づいているので『Point』以降のコーネリアスのMVのように、もしくはそれ以上に視覚と音をより密接にシンクロさせている。なのでいつも観ていたはずの番組の映像の部分がばっさりなくなると、人生の折り返し地点を過ぎて退化に向かいつつある中年は、登っていたはしごを外されたように音の小宇宙に取り残され、歌詞カードを裏返しながら「ええっと、この曲は10曲目だから……」ともたもたする。するとすかさず向こうから「○○の曲だ。さっきから『デザインあ』の曲ばっかり聴いてるね」と幼い声で鋭い指摘が入る。反応がないのであまり好きじゃないように見えたのに、ちゃんと聴いていて覚えていた。子供の耳って、よくわからない。
そもそも「好き」ってなんだろう。好きになるのには理由が見える。元気で踊れる、とかこのメロディがいい、とか歌詞に共感するぅ、とかドラムの音が変態、だとか。そして「好き」は「嫌い」の裏側に潜んでいて、あるとき強烈な自我によってあっという間に翻ったりもする。なんかうるさいとか、このメロディはありきたりだ、とか歌詞が凡庸だ、とかオリジナリティがない、だとか、自分勝手な言葉を付けて、見えるところにいちいち姿を現す。では言葉にならない「好き」はどこにあるのか? 「好き」に理由がつかないと成り立たないのか? 感情というものは言葉を獲得すればするほど適当なものを探してうまく当てはめ、表に引き出され出ていこうとする。子供はそれを無理にやらないので、傍から見ている者は楽しそうに踊ったり、歌ったりする「好き」だけを受け取ってしまうけれど、内側に潜んでいる気持ちには様々な種類があり、きっと無限の可能性が広がっているのだろう。子供が自分で好きな曲を選ぶ場面で意外な回答をして周りを驚かせたりするのは、つまりそういうことなのかもしれない。
たしかに音楽を聴いていると情動的になりすぎるきらいがある。自分が普段好んで聴いている音楽家のなかでも特に実験的なコーネリアスにですら、やれ11年ぶりのオリジナル・アルバムで、この歌詞はこれを意味していて、このような表現意図がある、と思いを巡らせ、感情を上乗せしたり、付加価値をつけたりしてしまう。好きな理由を言葉で探さないと落ち着かなくなってしまっているのだ。その固い頭のままでこのアルバムの"かんがえていない"や"うらおもて"や"おれがあいつであいつがおれで"や"なんやかんや"などの収録曲をじっと眺めていると、なんだかとても意味深に見えてくる。けれど並べられたタイトルは番組のコーナー名であって、意味はない。代わりにそこにはリズムを持ったデザインがある。「こどもたちにデザインの面白さを伝え、デザイン的な視点と感性を育む一歩となることを目指しています」と番組概要に記されているように、音楽もあくまでミュージックというスタンスを崩さず、素っ気ない位にアートで、洒落ている。現在、東京オペラシティで開催されている谷川俊太郎展の一角の、コーネリアスと中村勇吾とのコラボレーションによるギャラリーでも、視覚と聴覚のあいだを言葉が自由に弾んで刺激的な空間を作っていて、非常に面白かった。アイディアによって整えられたスタイリッシュなそのスペースに、もっともらしい感情を美しく詰め込むことは難しい。この際コーネリアスの人物像は余計な感情はさっぱり忘れて、身近な音のデザインとして気軽に楽しむことが正解だろう。そしてこのアルバムを何回も聴いた耳で『Mellow Waves』を改めて聴き返してみると、新たな音の発見があるはずなので是非オススメしたい。
そういえば昨年「コーネリアスのファンのすべて」というファンサイトを勝手に設けた時に、コーネリアス好きとして話を伺った趣味の良い高校生の男の子が、NHKの「テクネ 映像の教室」という番組でコーネリアスが音楽を手掛けていた回を見たことがコーネリアスの名前を知るきっかけだったと話していて、なんだか嬉しかった。日常的にコーネリアスの音を耳にしていた子供たちがこの感覚を持ってこれから様々な分野に浸透していくことを思うと、未来が楽しみで仕方ない。一方で感情に苛まれたままの人間は、小山田圭吾が歌う曲をもっと聴きたい、レオ今井の歌う"Shoot&Edit"も入れてほしかった、などと、やはり余計なことばかり考えてしまう。ああ、煩悩とは!
[[SplitPage]]野田努
のちにキング・オブ・テクノとさえ呼ばれることになる作曲家のブルース・ハークは、60年代初頭に感熱式シンセサイザーを作ると、エスター・ネルソンとともに1963年から子どもたちのためのダンス音楽を発表する。1978年に、テキサス・インスツルメンツ社は子供用教育用玩具としてスピークアンドスペルを発売。クラフトワークをはじめとする多くのテクノ・アーティストたちに使用される。エイフェックス・ツインとして成功したリチャード・D・ジェイムスは、同胞のマイケル・パラディナスと一緒にマイク・リッチ名義で極めて幼稚な作品を1996年にリリースする。コーネリアスを名乗り、かつて『ファンタズマ』を作ったロック・ミュージシャンの小山田圭吾は、2011年から「子供たちのデザイン的な視点と感性を育むこと」を目的としたNHK教育テレビジョンの番組「デザインあ」の音楽ディレクターを担当する。
TVはニュースとスポーツ番組、そしてピエール瀧のしょんないTVぐらいしか見ないぼくは、当然「デザインあ」を見たことがない。以下、その立場で音楽を聴いた感想を書こう。
『デザインあ2』は前作『デザインあ』同様に、小山田圭吾の無邪気なサウンド・デザイン/コラージュ、遊びの世界である。で、参加アーティスト:青葉市子、アート・リンゼイ、坂本真綾、ショコラ、チボ・マット、ハナレグミ、原田郁子、jan and naomi、環ROY×鎮座DOPENESS。まあ、このメンツで子供のための音楽を作るというのがミソで、もし音楽が文化として/趣味として衰退することがなければ、おそらく20年後の世界から見たとき「あの時代はこんなものがあったのか」ということになるのだろう。
昨年の『Mellow Waves』の悲しげな響きとは、もちろん一線を画している。とはいえこれも確実にコーネリアス・サウンドだ。ロック的な陰影はなく、そしてリラックスした雰囲気や言葉遣い、その無邪気さが、この音楽を子供っぽい音の遊技性のなかに定義しようとしているが、一枚皮を剥がせば、むしろ実験的で、ときおりシド・バレット的なサイケデリック・ポップな側面も垣間見せる。子供モノというのは、歴史的に見れば、ときに大人の実験場にもなり得るのだ。
子供はギミックが好きだ。サンプラーが好きだし、エフェクターが大好きだ。コアなYMOのファンというのは、だいたいが小学生のときに聴いた世代に多い。ぼくは世代的にクラフトワークのほうが先だった。感性が開かれるときの喜びとはああいう体験を言うのだろう。コーネリアスのポップな側面が、ヒットチャートではなくNHKの教育番組を通じて子供に伝播するというのは、現代的というかポストモダン的というか、なんとも感慨深い話である。