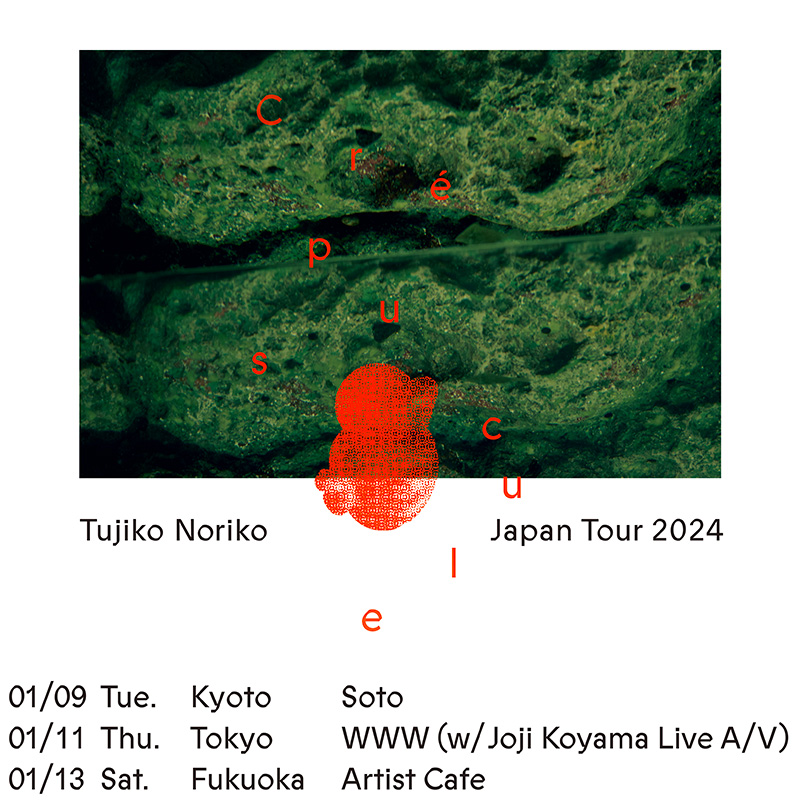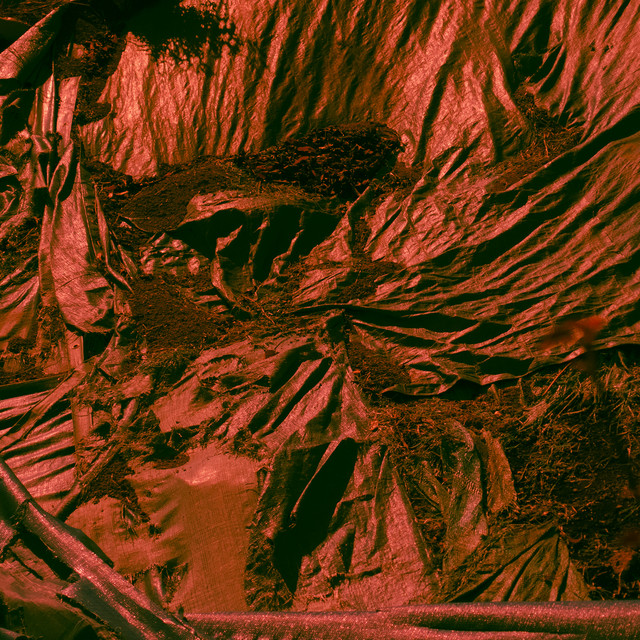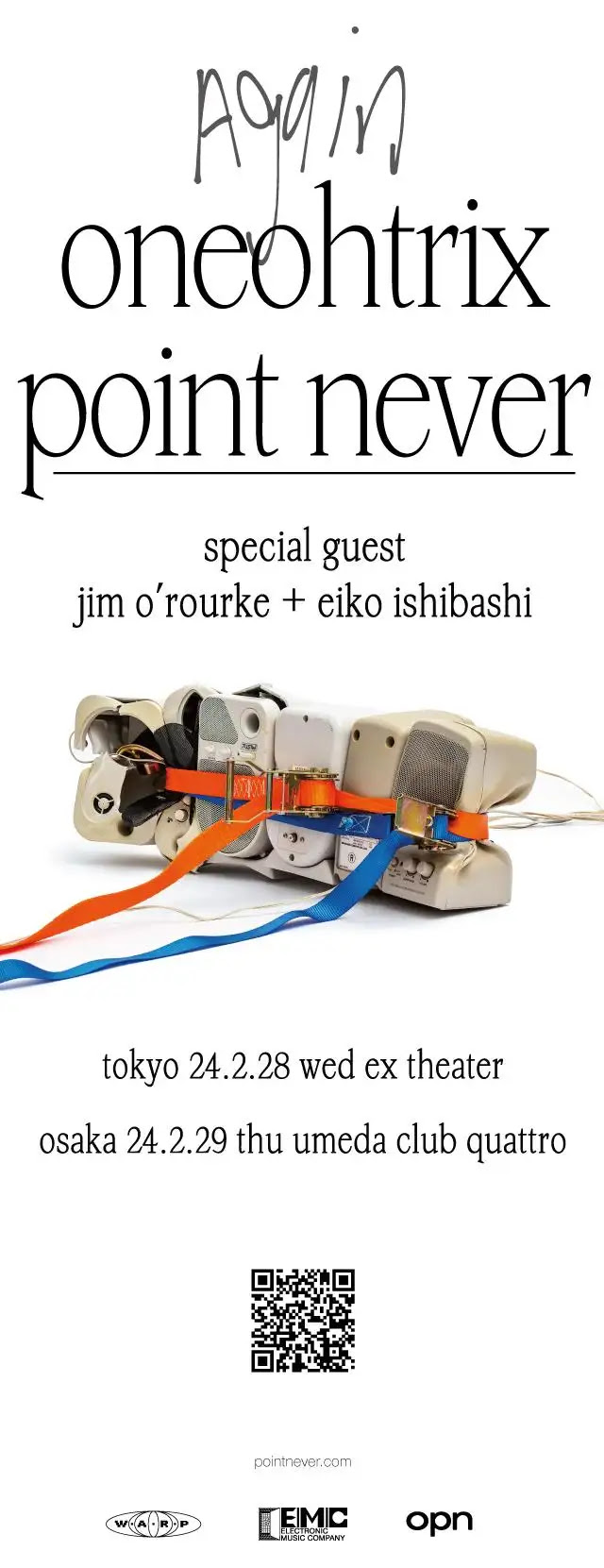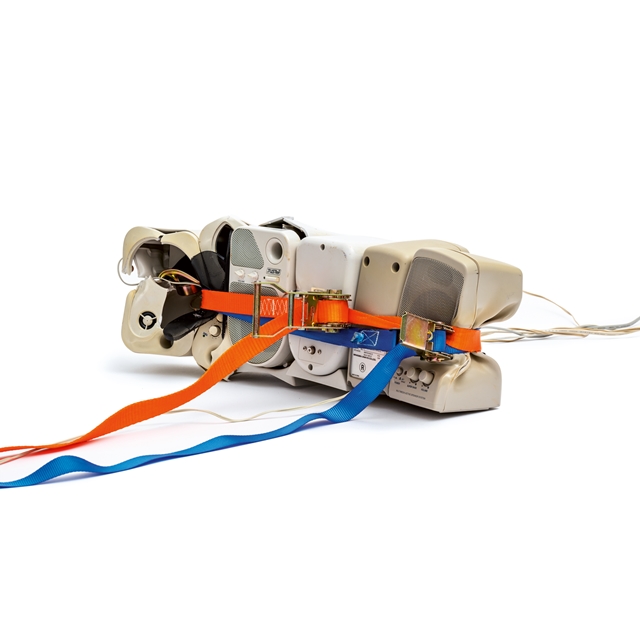これは冬のためのアルバムだ。ローラ・キャネル自らがそう説明している。地球の北半球の、ここ日本でもまさに今週からはじまった寒い冬。12月1日にリリースされた、彼女にとって8枚目のアルバムは『真冬の行列』と名付けられている。
これはいかにも英国風の、宇宙的だが土のにおいがする音楽だ。牧歌的だが厳しさがある。馬車に乗って、森のなかでたき火をしよう。ノーフォークの900年の歴史を持つノリッジ大聖堂内でレコーディングされたその本作について、キャネルは次のようにコメントしている。「大聖堂の内部からの残響を捉え、真冬の世俗的な行列を想像させるシンセサイザーのレイヤーと組み合わせたいと思った。長い音色はステンドグラスや石壁に跳ね返り、長い小島や彫刻の施された柱を通り抜け、トランセプトへと霧のように消えていく」
すでにキャネルの音楽に親しんでいる人は、この発言に「おや」と思うはずだ。そう、本作には、いつものヴァイオリンとリコーダーのほかにシンセサイザーが使われている。それだけで、興味をそそられるのではないだろうか。アルバム・タイトルもさることながら、“星の記憶” “太陽の行列” “大聖堂のこだま” “夜明けまでの月光を追って” “真冬の鐘” といった曲名もじつにいい。
ローラ・キャネルの音楽は、ぼくにとって2010年代の喜ばしい出会いのひとつだった。社会のものごとはスマホやネットありきが前提となっている今日において、液晶画面が告げる未来から逃げるように、削除された記憶や歴史の残滓が混在する荒れ地と共振しようとする音楽が生まれ、小さいながらも広く注目されることになるのは必然だ。2023年のベスト・アルバムの1枚がランクムであることと、キャネルのようなアーティストに一目置かれることとは無関係ではない。
「醜悪な町の広がりを忘れ、むしろ下りの荷馬車を思い浮かべよ」と書いたのは、都市化がすすむロンドンを嘆いた19世紀後半の、後世にもっとも影響を与えたデザイナーであり情熱的な社会主義者であったウィリアム・モリスだったが、古くは詩人ウィリアム・ブレイクや作曲家グスタフ・ホルスト、そして大衆文化の分野ではザ・ビートルズやレッド・ゼッペリン、ケイト・ブッシュにザ・KLF、エイフェックス・ツインやボーズ・オブ・カナダ等々もそうだったように、イギリスの夢想的な文化はことあるごとに、未来を志向するとき田舎道を選ぶところがある。SF的なタイムトラベルが中世ロマンに通じることは、ウィリアム・モリスの『ユートピアだより』にも見て取れよう。キャネルの音楽の基礎はクラシック音楽にあるが、彼女はそのエリートコースから脱し、かつてのセシル・シャープのように農村を訪ねて歌を集めていたわけではないが、先駆者デイヴィッド・マンロウようにアーリー・ミュージックの旋律をもとめて過去を調査した。
彼女の目的はしかし、中世の旋律の収集ではなかった。キャネルの試みは、古き建造物固有の音の鳴りを捉えること、時空を超えたサウンドの探求であり、前作『Antiphony of the Tree』のように鳥たちとの対話から生まれたサウンドであったりもする(エレキングvol.29のインタヴューを参照)。『真冬の行列』は、高さ69フィートのノリッジ大聖堂の中央で即興演奏したときの録音をもとに作られている。「私の多くのレコーディングと同様、今作も、その瞬間に自分がどう感じるかをたしかめるために、決まったプランなしに臨んだ」と彼女は明かしている。「演奏すること、そして自分には言いたいことがあるのだと信じること、サウンドがどこに行きたいのかを見つけること。私は、教義に基づいて、高度に設計された建てられた美しい空間の神聖なるものに対する葛藤した感情を押し通すことができるだろうか。私は、その瞬間に判断するのではなく、突き進み、演奏を続け、家に帰ったら空間との対話から何が生まれたのかを確認することを学んだ」
ぼくのような彼女のファンのために付け加えると、なかば神秘的ともいえる旋律をもった“星の記憶” には、彼女の音楽には珍しく、少しだけビートが刻まれている。もちろん今作にも、ローラ・キャネルのヴァイオリンとリコーダーによるヴィジョナリーな旋律が演奏され、そして編まれているわけだが、先にも書いたように、今作には彼女にとって初の試みといえるシンセサイザーの伴奏もあって、いままでにないポスト・プロダクションが施されている。今作のひとつの聴きどころとしては、彼女の説明にもあったが、大聖堂内部における反響音とシンセサイザーの抽象音との調和にある。いわばエレクトロニカの時代のフォークで、ひとりの演奏者が作品ごとにコンセプトを変えて、これだけのアルバムを発表するのは並大抵のことではないが、そんな風に、ここでも新たなアイデアが具現化されているのである。
キャネルが住んでいる英国ノーフォークの美しい田舎町は、ぼくが住んでいる人工的な東京よりもずっと季節の厳しい変化に晒されているはずだ。ゆえに、自明のことだが、ぼくよりも深く自然を感じることができているのだろう。そうしたライフスタイルすべてが彼女の、真冬の冷たく澄んだ空気に溶け込み、白い月や吐息と共鳴する演奏に影響していることは想像に難くない。リコーダーが反響する “大聖堂のこだま” や “真冬の鐘” といった曲からは、彼女が演奏した場のアトモスフィアさえも伝わってくる。
サウンドのゆらめきと幽玄さは、彼女のすべての作品の特徴ではあるが、ことに今作では突出しているのかもしれない。あるいは、東京も本格的な真冬を迎えているから音楽がより鮮明に聴こえるのかもしれない。なんにせよ、この季節にどんぴしゃりの、これは嬉しいリリースだ。型にはまった音楽に飽き飽きしているあなたが、さらに冬の冷気を愛することができる人でもあるならば、『真冬の行列』もきっと好きになれる。
 ファースト・プレスプロモ盤
ファースト・プレスプロモ盤 ファースト・プレス市販盤
ファースト・プレス市販盤 セカンド・プレス FULLERSOUND盤
セカンド・プレス FULLERSOUND盤 セカンド・プレス・スローダウン盤
セカンド・プレス・スローダウン盤 ファースト・プレスプロモ盤
ファースト・プレスプロモ盤 ファースト・プレス市販盤
ファースト・プレス市販盤 セカンド・プレス FULLERSOUND盤
セカンド・プレス FULLERSOUND盤 セカンド・プレス・スローダウン盤
セカンド・プレス・スローダウン盤