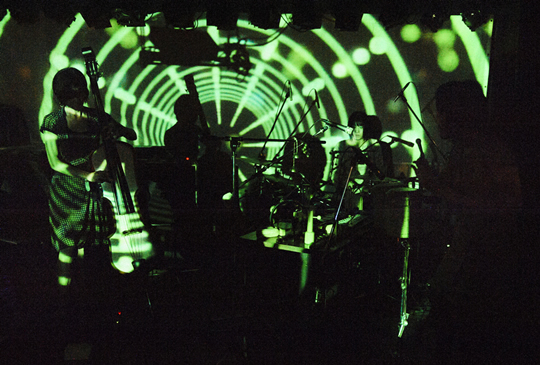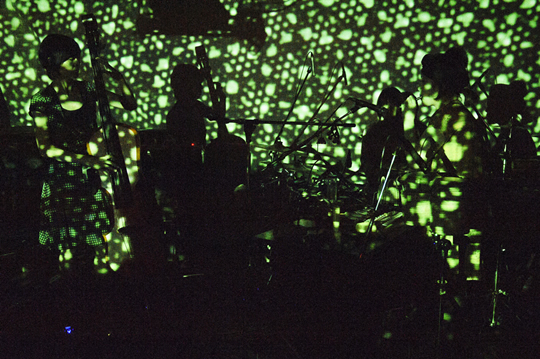「TRANS ARTS TOKYOは、神田の街に『神田コミュニティアートセンター』をつくるためのプロローグ」......10 月21 日(日)から旧東京電機大学校舎11 号館などで開催されるアート・プロジェクト「TRANS ARTS TOKYO」。公式サイトにはそう謳われているが、実際に相当に楽しいごった煮カルチャー体験が期待できそうである。旧東京電機大学11号館の地下2Fから17Fまでをフルに使い切って、アート、建築、ファッション、デザイン、地域の歴史、インターネットのユーザー参加型コンテンツ等々をめぐるさまざまな展示や発表会、研究会が行われる予定だ。「あらゆるものを超えて立ち上がってくるもの。それこそが私たちの目指す『コミュニティアート』です」。
さてその一角で広げられる、こんなバザールの噂はご存知だっただろうか?
「インターネット ヤミ市」
インターネットの明るいヤミを目指して
自由の国インターネットとは名ばかり、ほらリジェクトだとか、ほら違法化だとか、
あんまり自由じゃなくなって来ている今日このごろ。
そこで、あえて人と人とが直接プロトコルする、そんなフリマを開催します!
インターネットに病み(ヤミ)続けるぼくらに、手と手の触れ合う生あたたかいデータを直リンク!!
※違法なもの、危険なものは扱わない、明るいヤミ市です!
出店者のひとり、カセットレーベル〈ダエン〉主宰氏からは開催趣旨に関してこのようなコメントをいただいた。
「リジェクトされたiPhoneアプリとか、もちろん普通にTシャツとか、自分の作品とかでもOK。データとか、リンク集みたいな形のないもの......フォロー権、RT権とかの権利ものなど、インターネットに関連するものを何でも売り買いできるマーケットです。さすがに法に触れるものは売れません。グレーはいいけどブラックはダメ!!」
ご本人はブース内でのミニ・ライヴを敢行予定とのこと。その他のブースでもいろいろなハプニングが楽しめそうだ。
伊藤ガビンや庄野祐輔、古屋蔵人らがキュレーションするスリリングなフロアで、多彩でダイナミックな買い物を楽しもう。タナカカツキ氏、渋家を始めクリエイター系の参加者が多数エントリーしている模様である。
■IDPW presents インターネット闇市
日時:11月4日(日)14:00-18:00
会場:17F
https://idpw.org/fest/blackmarket/
■神田コミュニティアートセンタープロジェクト『TRANS ARTS TOKYO』
日時:2012 年10 月21 日(日)~11 月25 日(日)12:00-19:00 (火曜日休み)
会場:旧東京電機大学校舎11 号館ほか(東京都千代田区神田錦町2-2)
主催:東京藝術大学(美術学部 絵画科 油画専攻)
共催:神田コミュニティアートセンター構想委員会(委員長:佐藤一郎(東京藝術大学美術学部絵画科長))
運営:一般社団法人非営利芸術活動団体コマンドN(東京都千代田区外神田6-11-14)
協賛:住友商事株式会社 他
参加料:500円(期間中何度も使えるパスポート制です)
https://www.kanda-tat.com/