1996年に〈Mo' Wax〉からリリースされたDJシャドウのファースト・アルバム『Endtroducing.....』は、既存の音源のみで構築されたサンプリング・ミュージックの金字塔として、いまなおポップ・ミュージックの歴史に燦々と輝いている。
同作は来る11月19日をもってリリース20周年を迎えるが、このたび、それを記念したリミックス盤の企画が進行中であることが明らかになった。DJシャドウは9月12日に放送された「トークハウス・ミュージック・ポッドキャスト」の最新回でクラムス・カシーノと対話をおこなっているが、そこで『Endtroducing.....』のリミックス・アルバムの計画について言及している。リリースの日程やトラック・リストなどはまだ明らかにされていないが、リミキサーとしてクラムス・カシーノやハドソン・モホークが参加しているとのことである。
ちなみにDJシャドウは、去る7月27日にロンドンのエレクトリック・ブリクストンにておこなわれたライヴで、自身のクラシック "Midnight In A Perfect World" のハドソン・モホークによる未発表リミックスを披露している。その音源が計画中のリミックス・アルバムに収録されることになるのかどうか、注目である。
ファンが撮影した映像




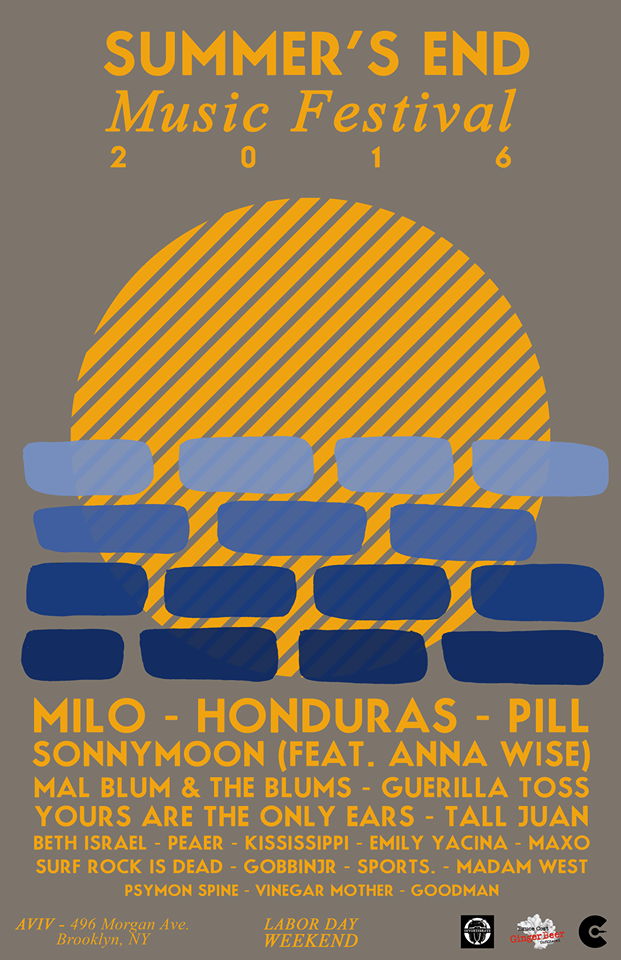




 Guerilla Toss merch
Guerilla Toss merch 




