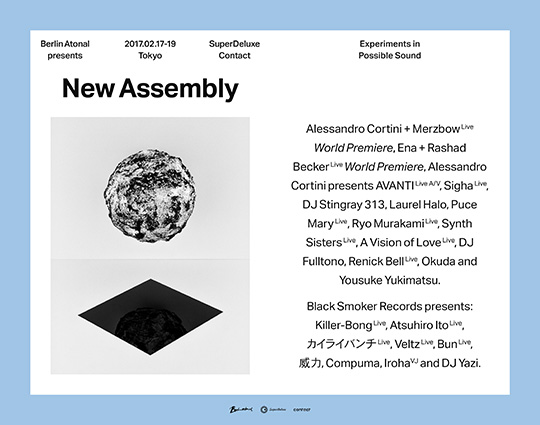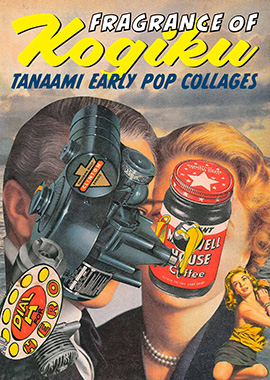親がすべてを駄目にする。そういう話だったと思う。親というものはどうしても子の「幸せ」を願ってしまうがゆえに、必然的に子のやることなすことにケチをつける。子が熱心に芝居に取り組んでいればそんなものはやめてしまえとくさし、海外公演が決まろうものならパスポートを隠匿して子の行く手を阻む。それがもとになって子の友人関係が歪みはじめたとしても、自らにその原因があるなどと思い至ることはない。結果、若き才能たちはぐしゃぐしゃに引っかき回され、表現活動は阻害される。そんなふうに親世代の価値観が若者の未来を押し潰すという話それ自体は、それこそ親が子だった時代から、さらにその親が子だった時代から脈々と存在し続けてきたものではあるが、その舞台が現代イランとなると事情は込み入ってくる。長回しが印象的なこのベーナム・ベーザディの『ルールを曲げろ』という映画を知っているか、とアッシュ・クーシャに問うてみたところ「監督の名前には聞き覚えがある」との答えが返ってきたが、演劇にせよ音楽にせよかの地で表現活動をおこなうことはいまでもやはり困難なのだろう。
ハンブルクに生まれテヘランとサンフランシスコを往復しながら活動を続けている電子音楽家、アタ・エブテカール。2002年にソート名義で発表された「Electric Deaf」が素晴らしかったので、その後もちょいちょい気にしてはいたのだけれど、彼からの便りはあまり多くなく、もしかしたらもう音楽活動はやめてしまったのかもしれない、と少し心配になったこともあった。しかし2014年の『Architectonic』から彼は再びソート名義で作品を発表するようになり、2016年は一気にアルバムとEPとシングルをリリースしている。1972年生まれの彼はもはや若者ではなく、どちらかといえば子の邪魔をする親の世代に近いが、その彼があえてテヘランという地でエクスペリメンタルな試みを継続していることについて、僕たちはあれこれと想像をめぐらす必要があるだろう。
『Hardcore Sounds From Tehran』には長尺のトラックが2曲収録されている。ビートがダンスを要求したかと思えば急にそれがつき崩されていったり、ノイズが宙を舞ったりインダストリアルな針が耳を突き刺したりと、“Hardcore Sounds From Tehran A”も “Hardcore Sounds From Tehran B”も、おそらくはいくつかの録音をもとに編集・構成されたものなのだろう、次々とアヴァンギャルドな展開がぶち込まれてきて聴き飽きない。ある瞬間はラッセル・ハズウェルのように、ある瞬間はオウテカのように、ある瞬間はAFXのように、ある瞬間はクラークのように、このアルバムではUKをはじめとする欧米各国で育まれてきたテクノやIDMの分子たちが、ひとつのトラックのなかで動的に対抗したり調和したりしている。それはよりダンス志向のEP「Hyper-urban 20 30」でも同様で、こちらは4分前後の短いトラックが4曲収録されている。
トラディショナルな音楽との融合を試みる本人名義の作品とは異なり、ソート名義の作品は決して異国趣味を誘発するものではない。『Hardcore Sounds From Tehran』にせよ「Hyper-urban 20 30」にせよ、そのアートワークとは裏腹に特に民族音楽的な要素が散りばめられているわけではなく、ソートはあくまで純粋に「エレクトロニック・ミュージック」としての完成度の高さを追究している。しかしそうであるからこそかえって僕たちリスナーは、その音楽制作の舞台がイランであることに意識を向けざるをえない。
アッシュ・クーシャがテヘランを去ってから少しだけ状況は好転したようで、若いミュージシャンが政府の許可を得ることは比較的容易になったという話もある。しかし許可が必要な時点で、依然としてかの地の文化や表現を取り巻く状況が厳しいものであることに変わりはないのだろう。ソートの鳴らす動的な音の展開には、そういったイランの困難な文化的状況がこだましている。おそらく『Hardcore Sounds From Tehran』というタイトルはメッセージなのだ。逮捕されるかもしれないと思いながら音を奏でること。摘発されるかもしれないと思いながら音を聴くこと。そういう状況への想像力こそが重要なのだ、とソートの音楽は告げているのではないか。