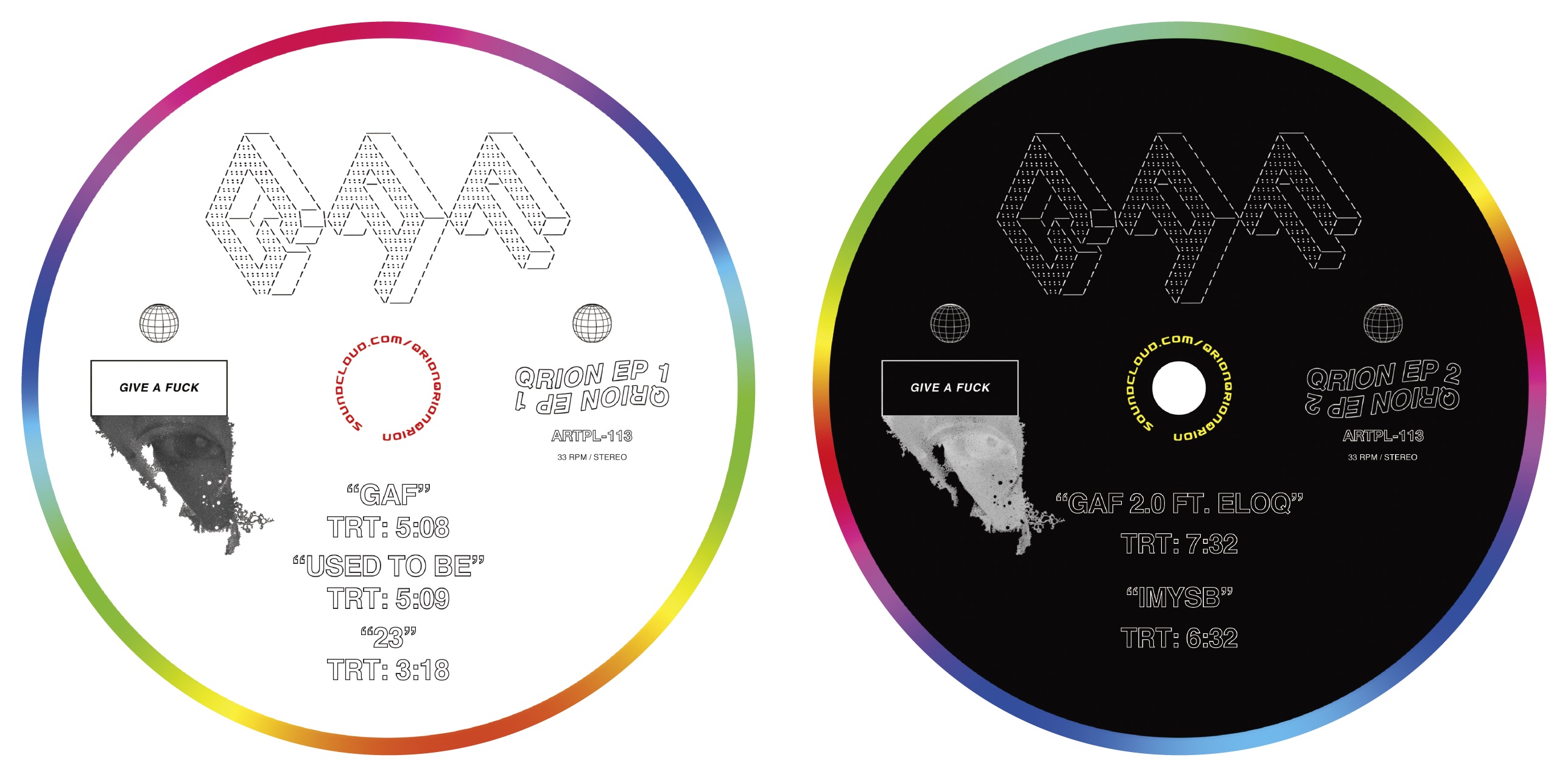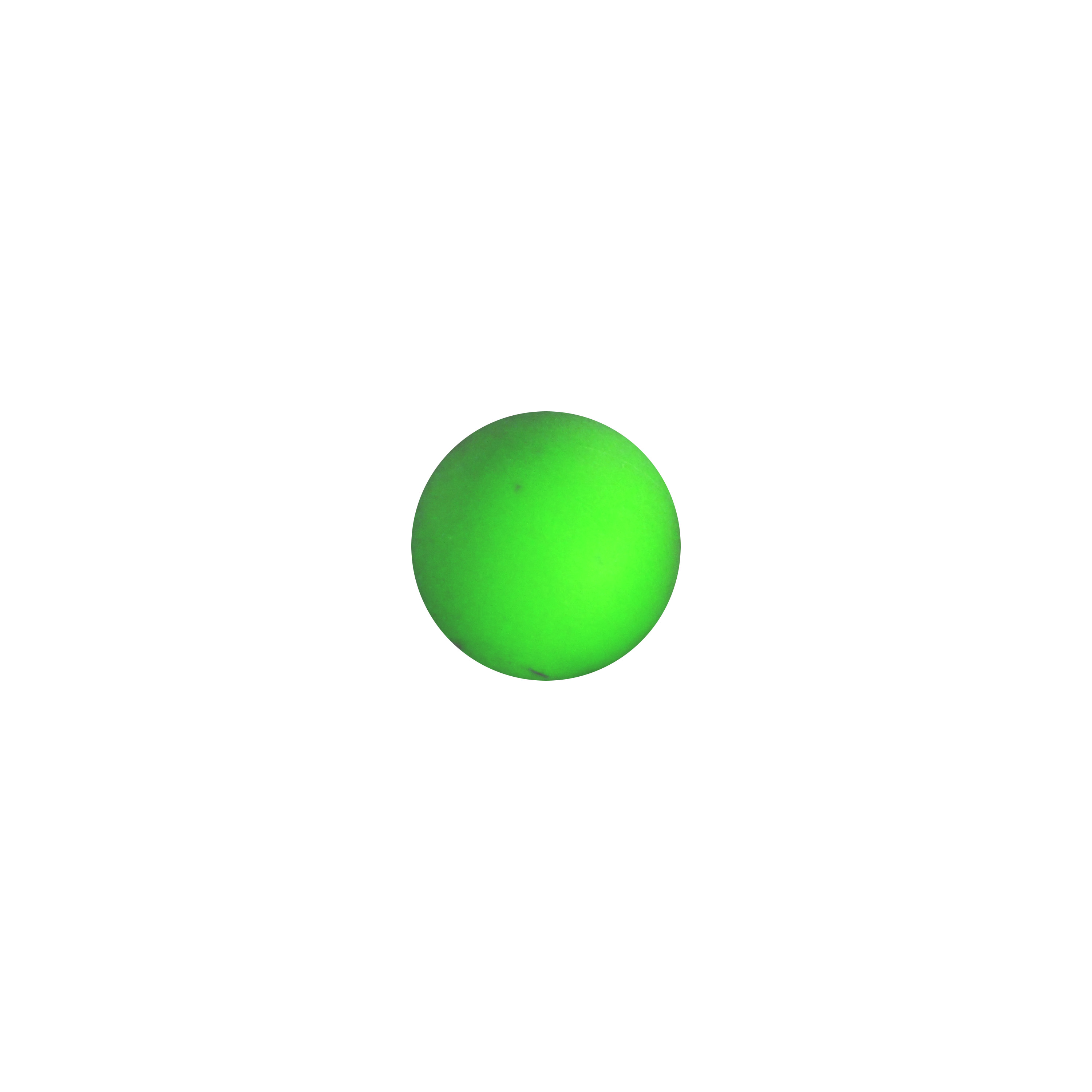これはビッグ・ニュースだ。去る2月、デヴィッド・ファースによるWebアニメ・シリーズ『Salad Fingers』の新作に音楽を提供していることが話題となったばかりのフライング・ロータスだけれど、なななんと、渡辺信一郎による最新アニメ『キャロル&チューズデイ』にもコンポーザーとして参加していることが明らかとなった。さらに同作には、フライローの盟友たるサンダーキャットまで参加しているというのだから驚きだ。ほかに G.RINA、マイカ・ルブテ、☆Taku Takahashi が参加していることも発表され、音楽好きとして知られる渡辺総監督の気合いがひしひしと伝わってくる。
また今回の発表にあわせ、ナルバリッチとベニー・シングスが手がけるOP・ED曲(ヴォーカルはナイ・ブリックスとセレイナ・アン)を収録したシングルが5月29日にリリースされることも決定、現在OP曲“Kiss Me”のMVが公開されている。ボンズ20周年×フライングドッグ10周年記念作品として送り出される『キャロル&チューズデイ』、放送開始は1週間後の4月10日(フジテレビ「+Ultra」、NETFLIXほか)。モッキーが劇伴を担当し、総監督みずからが音響監督を務める同作、けっして見逃すことなかれ。
[4月24日追記]
本日、フライング・ロータスやサンダーキャットらが手がける劇中挿入歌を収録したヴォーカル・アルバム『VOCAL COLLECTON Vol.1』のリリースがアナウンスされた。発売日は7月10日。アニメ好きとして知られるフライロー&サンダーキャットだけれど、まさかの本人アニソン・デビューである。いったいどんな曲に仕上がっているのやら。続報を待とう。
[4/24更新]
TVアニメ『キャロル&チューズデイ』
フライング・ロータス、サンダーキャットらが手掛ける劇中挿入歌(1クール分)を収録したアルバム『VOCAL COLLECTON Vol.1』 7/10発売決定!!
■TVアニメ『キャロル&チューズデイ』VOCAL COLLECTION Vol.1
7月10日(水)発売
VTCL-60499 / POS: 4580325328639 / ¥3,000+tax
※配信
iTunes Store、レコチョク、moraほか主要ダウンロードサイト及びストリーミングサービスにて5月29日(水)より配信スタート
(収録内容)
TVアニメ「キャロル&チューズデイ」を彩るキャラクターが歌唱する約20曲の劇中歌を収録。
※2019年4月から連続2クール(半年間)放送となるTVアニメ『キャロル&チューズデイ』の1クール分(12話分)の劇中歌をまとめたヴォーカルアルバム
・キャロル&チューズデイ (Vo. Nai Br.XX & Celeina Ann) / 「The Loneliest Girl」
作詞/作曲/編曲: Benny Sings
・キャロル&チューズデイ (Vo. Nai Br.XX & Celeina Ann) / 「Round&Laundry」
作詞/作曲/編曲: 津野米咲
・DJアーティガン / 「Who am I the Greatest」
作曲: ☆Taku Takahashi (m-flo)
他、20曲収録予定
総監督:渡辺信一郎、アニメーション制作:ボンズ、キャラクター原案:窪之内英策ら強力なスタッフ陣が挑む
全世界の音楽を愛する人に捧げる、2人の少女が起こした奇跡の物語。
『キャロル&チューズデイ』
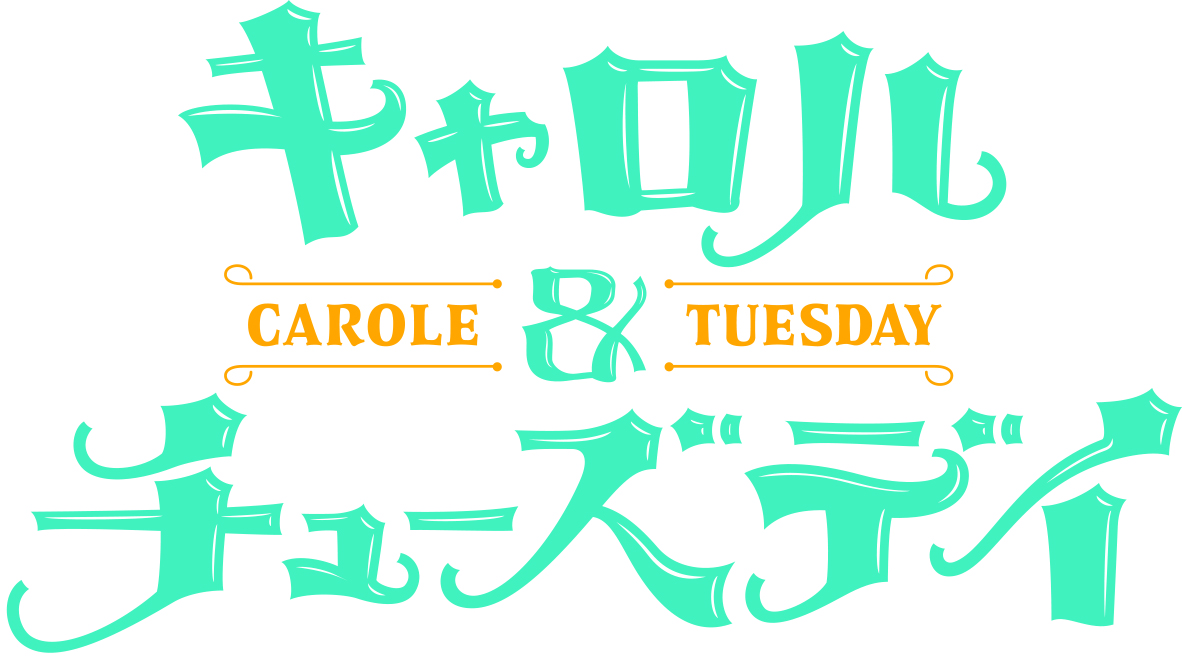
☆オープニングテーマ「Kiss Me」ミュージックビデオ公開!!
☆オープニング&エンディングテーマ
「Kiss Me/Hold Me Now」5/29リリース決定!!
☆第3弾参加コンポーザー
(フライング・ロータス、サンダーキャット等)発表!!
☆『キャロル&チューズデイ』劇中ボーカル曲参加コンポーザー
ラインナップ映像公開!!
きっと忘れない。
あの、永遠のような一瞬を。
あの、ありきたりな奇跡を。
ボンズ20周年×フライングドッグ10周年記念作品として総監督・渡辺信一郎、
キャラクター原案・窪之内英策を迎えアニメ史を塗り替える、全世界に向けた音楽作品
TVアニメ『キャロル&チューズデイ』。
本日、番組オープニングテーマ「Kiss Me」のミュージックビデオが公開となった。
出演は『キャロル&チューズデイ』のシンガーボイスを担当しているNai Br.XX(ナイ・ブリックス)&Celeina Ann(セレイナ・アン)。この2人は全世界オーディションによって選ばれたシンガー。
オープニングテーマ「Kiss Me」は先日、ミュージックステーションにも初出演し、現在男女問わず
絶大な人気を誇るNulbarich(ナルバリッチ)によるプロデュース楽曲。この「Kiss Me」にのせてギブソン(ハミングバード)を弾きながら歌うセレイナ・アンとナイ・ブリックスが向かいあって歌うシーンはまさに『キャロル&チューズデイ』を象徴しているようなミュージックビデオになっている。
「Kiss Me」Music Video(short ver.)
URL: https://youtu.be/k45EpgweT9o
またこのオープニングテーマ「Kiss Me」とオランダを代表するポップの才人・Benny Sings(ベニー・シングス)プロデュースによるエンディングテーマ「Hold Me Now」を収録したシングルCD、配信、アナログ盤が5/29にリリースすることが決定した。
そして、劇中ボーカル曲第3弾参加コンポーザーも同時に発表となった。
LAビートシーンを先導する存在であり、現在の音楽シーンのカギを握る最重要人物であるFlying Lotus(フライング・ロータス)。
超絶技巧のベーシストでもあり、ここ数年のブラックミュージックの盛り上がりにおいて、誰もが認める立役者の一人にでもあるThundercat(サンダーキャット)。
日本の女性シンガーソングビートメーカー/DJで土岐麻子やNegiccoなどへの楽曲提供からtofubeats、鎮座DOPENESSなどとのコラボなど、幅広い領域で活動しているG. RINA(ジーリナ)。
Shu Uemuraやagnès bなどの 数々のファッションブランドやCM音楽を数多くプロデュースしている気鋭のシンガーソングライター/トラックメーカーのMaika Loubté(マイカ ルブテ)。
m-floのトラック・メイカーとしての活動はもちろんのこと、音楽プロデューサーとしても向井太一や加藤ミリヤなどを手がけ、アニメ「Panty&Stocking with Garterbelt」などのサントラも担当しており、渡辺信一郎監督作では「スペース☆ダンディ」にも楽曲提供している☆Taku Takahashi (m-flo)といった超豪華な面々。
合わせて現時点で参加している全てのコンポーザーのラインナップ映像も公開となった。
参加コンポーザーラインナップ映像
URL: https://youtu.be/jJ6QCaqCC5g
このメンツを見るだけでも胸アツラインナップだが、今後もさらに参加コンポーザーが発表されるようなので
今からこちらも楽しみに待ちたい。
いよいよ第1話放送まで1週間に迫った他に類を見ない本作に是非ご期待ください!!
------------------------------------
INFORMATION
OPテーマ「Kiss Me」/ EDテーマ「Hold Me Now」
キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX & Celeina Ann)
5月29日(水)発売
<収録曲>
1. Kiss Me (作詞/作曲/編曲:Nulbarich)
2. Hold Me Now (作詞/作曲/編曲:Benny Sings)
3. Kiss Me TV size ver.
4. Hold Me Now TV size ver.
※シングルCD
VTCL-35302/POS:T4580325 328578
¥1,300+tax
※アナログ盤
VTJL-2 /T4580325 328622
¥2,000+tax
※配信
iTunes Store、レコチョク、moraほか主要ダウンロードサイト及びサブスクリプションサービスにて5月29日(水)より配信スタート
------------------------------------
渡辺信一郎監督の新作「キャロル&チューズデイ」に楽曲を提供するアーティスト第3弾。
フライング・ロータスは正真正銘、現在の音楽シーンのカギを握る最重要人物だ。彼は本名をスティーヴ・エリソンというプロデューサーで、83年にロサンゼルスで、お婆さんのお姉さんがアリス・コルトレーンという家系に生まれた。06年にビート・メイカーとしてデビュー。08年には自らのレーベル=ブレインフィーダーを立ち上げ、ヒップホップやテクノ、ジャズなどを包括するLAのビート・シーンを先導する存在となった。今のところの最新作『ユーアー・デッド!』にはラッパーのケンドリック・ラマーやハービー・ハンコックなども参加している。昨年8月には“ソニックマニア”出演のために来日し、3D映像と融合したDJステージを展開、そこでもゲームや『攻殻機動隊』サントラなどをプレイしたが、「カウボーイ・ビバップ」なども好きだったようで、渡辺信一郎監督の『ブレードランナー ブラックアウト2022』の音楽を監督からの要望で担当してもいる。
そんなフライング・ロータスと楽曲を共作するのがサンダーキャット。ブレインフィーダー・レーベルに所属するロータスの盟友の一人だ。彼は本名をスティーヴン・ブルーナーといい、84年にLAで生まれた。ベーシストとしてスラッシュ・メタルのスイサイダル・テンデンシーズから、R&Bのエリカ・バドゥ、ラップのケンドリック・ラマーまで、様々なアーティストと共演してきたが、そんな経歴を詰め込んだようなハイブリッドな音楽性で11年にソロ・デビューした。シンガー・ソングライター的な側面を強めた『ドランク』(17年)はそんな彼の決定版で、マイケル・マクドナルドなどを迎えた「ショウ・ユー・ザ・ウェイ」はAOR再評価の波と相まって、大きな話題となった。
☆Taku Takahashiは日本のDJ、音楽プロデューサー。98年からm-floのトラック・メイカーとして活動、99年にメジャー・デビューしてからヒット曲を連発した。音楽プロデューサーとしても向井太一や加藤ミリヤ、MINMIなどを手がけ、最近では韓国のセクシー・グループ、EXIDの日本オリジナル曲もプロデュースした。また、アニメ「Panty&Stocking with Garterbelt」などのサントラも担当しており、渡辺信一郎監督作では「スペース☆ダンディ」にも楽曲提供している。
G.RINA(ジー・リナ、グディングス・リナ)は日本の女性シンガー/ビートメイカー/DJ。03年にすべてセルフ・プロデュースで作り上げたアルバムでデビューした。ディスコ/ソウル/ヒップホップを始め、広くダンス・ミュージックにこだわった音楽性で、07年にはビクターからメジャー・デビューしたが、同時にインディ・レーベルも主宰するなど、独自の活動を続けている。土岐麻子やNegiccoなどへの楽曲提供から、tofubeats、鎮座DOPENESSなどとのコラボなど、幅広い領域で活動している。
Maika Loubté(マイカ ルブテ)は日本人の母とフランス人の父の間に生まれた女性シンガー・ソングライター/トラックメイカー/DJ。10代まで日本・パリ・香港で過ごし、14歳で作詞/作曲を始めた。小山田圭吾、鈴木慶一、菊地成孔などとの共演を経て、14年にアルバム・デビュー。ヴィンテージなアナログ・シンセから最新電子楽器までを駆使した宅録女子として独自の世界を作り上げている。CM音楽や劇中歌なども数多く手がける気鋭のクリエイターだ。
Text: 高橋修
------------------------------------

・Flying Lotus(フライング・ロータス)
LA出身のプロデューサー、フライング・ロータスことスティーヴン・エリソン。大叔父にモダンジャズの名サックスプレイヤーのジョン・コルトレーン、そしてその妻でありジャズミュージシャンのアリス・コルトレーンを大叔母に持つ。LAビートシーンの最重要人物にして、サンダーキャットやテイラー・マクファーリン、ティーブスらを輩出した人気レーベル〈Brainfeeder〉を主宰。2010年の『Cosmogramma』、2012年の『Until The Quiet Comes』、そして世界各国で自己最高のセールスを記録し、その年を代表する名盤として高い評価を受けた2014年の『You're Dead!』などのアルバムを通して、その評価を絶対的なものとする。2017年には、自ら手がけた映画『KUSO』の公開や、渡辺信一郎監督の短編アニメーション『ブレードランナー ブラックアウト 2022』の音楽を手がけるなど、その活躍の場をさらに広げている。

・Thundercat(サンダーキャット)
フライング・ロータス諸作を始め、ケンドリック・ラマー、カマシ・ワシントンらの作品に参加する超絶技巧のベーシストとしてシーンに登場し、ここ数年のブラックミュージックの盛り上がりにおいて、誰もが認める立役者の一人にまで成長したサンダーキャット。2011年の『The Golden Age Of Apocalypse』、2013年の『Apocalypse』でその実力の高さを証明し、2017年の音楽シーンを象徴する傑作として高く評価された最新作『Drunk』ではケンドリック・ラマー、ファレル・ウィリアムス、フライング・ロータス、マイケル・マクドナルド、ケニー・ロギンス、ウィズ・カリファ、カマシ・ワシントンら超豪華アーティストが勢揃いしたことでも話題となり、その人気を決定づけた。

・G.RINA (ジーリナ)
シンガーソングビートメイカー・DJ
近作アルバム『Lotta Love』『LIVE & LEARN』では80年代 90年代へのオマージュとともに、日本語歌詞のメロウファンク、ディスコ、モダンソウルを追求している。英国、韓国アーティスト、ヒップホップからアイドルまで幅広くプロデュース、詞/楽曲提供、客演など。2018年、ZEN-LA-ROCK、鎮座ドープネスとともにヒップホップユニット「FNCY」を結成。
https://grina.info

・Maika Loubté (マイカ ルブテ)
Singer song writer / Track maker
SSW/トラックメーカー/DJ。近所のリサイクルショップでヴィ ンテージアナログシンセサイザーを購入したことをきっかけに、ドリームポップとエレク トロニックミュージックを融合させたスタイルで音楽制作を始める。 日本とフランスのミックスであり、幼少期から十代を日本・パリ・香港で過ごす。
2016年夏、アルバム『Le Zip』(DIGITAL/CD+42P PHOTO BOOK)をリリース。
のち2017年3月にリリースしたEP『SKYDIVER』がJ-WAVE「TOKIO HOT 100」に選出され、
番組にも出演。2017年5月、Underworldがヘッドライナーを務めた バンコクの音楽フェス
「SUPER SUMMER SOUND 2017」に出演。 SUMMER SONIC 2017出演。同年7月、Gap“1969 Records”とのコラボレーションによりMVが制作された「Candy Haus」を、配信と7インチLPでリリース。
インディペンデントな活動を続けながら、Shu Uemuraやagnès bなどの 数々のファッションブランドやCM音楽をプロデュースし、これまでに自主盤を含め2つのアルバムと3つのシングルEPを発表。
2017年、米Highsnobietyが企画・制作したMercedes BenzのWeb CMに出演し、
未発表曲がフィーチャーされた。台湾・中国・韓国・タイ・フランスでのライブパフォーマンスも成功させ、活動の幅を広げている。2019年、新作フルアルバムをリリース予定。元Cibo MattoのMiho Hatoriらを客演に迎え、PhoenixやDaftpunkなども手がけるAlex Gopherがマスタリングを務めた。
Official web www.maikaloubte.com
Twitter https://twitter.com/maika_loubte
Instagram https://www.instagram.com/maika_loubte/

・☆Taku Takahashi (m-flo)
DJ、プロデューサー。98年にVERBAL、LISAとm-floを結成。
ソロとしてもCalvin Harris、The Ting Tings、NEWS、V6、Crystal Kay、加藤ミリヤ、MINMIなど国内外アーティストのプロデュースやRemix制作も行うほか、アニメ「Panty&Stocking with Garterbelt」、ドラマ・映画「信長協奏曲」、ゲーム「ロード オブ ヴァーミリオン III」など様々な分野でサウンドトラックも監修。2010年にリリースした「Incoming... TAKU Remix」は世界最大のダンスミュージック配信サイト“beatport”で、D&Bチャートにて年間1位を獲得。また同曲で、過去受賞者にはアンダーワールドやファットボーイ・スリム、ジャスティス等、今や誰もが知っているスーパースター達が名を連ねる『beatport MUSIC AWARDS 2011 TOP TRACKS』を獲得し、日本人として初めての快挙を成し遂げ、名実ともに世界に通用する事を証明した。
国内外でのDJ活動でクラブシーンでも絶大なる支持を集め、LOUDの“DJ50/50”ランキング国内の部で3年連続1位を獲得し、日本を牽引する存在としてTOP DJの仲間入りを果たした。2011年に自身が立ち上げた日本初のダンスミュージック専門インターネットラジオ「block.fm」は新たな音楽ムーブメントの起点となっている。2018年3月7日には、15年ぶりにLISAが復帰しリユニオンしたm-floのNEW EP「the tripod e.p.2」をリリース。m-floの最新シングル「MARS DRIVE」「Piece of me」「epic」も好評配信中。
https://twitter.com/takudj
https://block.fm/
------------------------------------
《キャロル&チューズデイとは?》
ボンズ20周年×フライングドッグ10周年記念作品。
総監督に『サムライチャンプルー』・『カウボーイビバップ』・『アニマトリクス』・『ブレードランナー ブラックアウト2022』ほかを手掛け国内外においてカリスマ的な人気を誇る、渡辺信一郎。
キャラクター原案に、日清食品カップヌードルCM「HUNGRY DAYS 魔女の宅急便篇」、「HUNGRY DAYSアルプスの少女ハイジ篇」などのキャラクターデザインで人気を博している窪之内英策。
この強力タッグのもと、アニメーション制作は『COWBOY BEBOP 天国の扉』・『鋼の錬金術師』・『交響詩篇エウレカセブン』・『僕のヒーローアカデミア』など数多くのヒット作品を世に送り続けるボンズ、物語の主軸となる音楽は『カウボーイビバップ』・『マクロス』シリーズなど数々のヒットアニメーション音楽を作り出すフライングドッグが担当する。
劇中音楽はカナダ出身のアーティストMockyが手掛け、主題歌は全世界オーディションによって選出されたNai Br.XX(ナイ・ブリックス)、Celeina Ann(セレイナ・アン)がキャロル・チューズデイのWキャストとして曲を歌唱する。音楽にも強い拘りがある本作は海外アーティストからの楽曲提供が多く、さらに劇中歌及び主題歌は全て外国語で歌唱される。
オープニングテーマ「Kiss Me」は現在、男女問わず絶大な人気を誇るNulbarich(ナルバリッチ)。エンディングテーマ「Hold Me Now」はオランダを代表するポップの才人・Benny Sings(ベニー・シングス)が担当。また、劇中ボーカル曲参加コンポーザーとして、ノルウェー出身の音楽プロデューサー・ミュージシャンのLido、オランダを代表するポップの才人・Benny Sings、エレクトロポップデュオ《The Postal Service》への参加でも知られるUSインディー界の歌姫・JEN WOOD、女性4人によるロックバンド・《赤い公園》でギターを担当する津野米咲、ビヨンセやリアーナ、ジェニファーロペスなど超大物アーティストに楽曲を提供しているEvan "Kidd" Bogart、現在活動停止中ではあるがロック・ファンにはなじみの深いKeane(キーン)のTim Rice-Oxley、コーネリアスやファイストなどとのコラボも話題となったノルウェー出身のグループ、Kings of Convenience(キングス・オブ・コンビニエンス)のEirik Glambek Bøe等といったこちらも早々たる面子が音楽で本編を彩る。
2019年4月10日からのオンエアに向けて本編、音楽ともに絶賛鋭意制作中!
他に類をみない本作品に乞うご期待!!!
☆新プロモーション映像
URL: https://youtu.be/CBak9m0bcB0
☆ドキュメンタリー映像
・Story of Miracle (vol.1)
URL: https://youtu.be/hzxqk2dVvf4
・Story of Miracle (vol.2)
URL: https://youtu.be/K8X10gdWz-A

《あらすじ》
人類が新たなフロンティア、火星に移り住んでから50年になろうという時代。
多くのカルチャーはAI によって作られ、人はそれを享楽する側となった時代。
ひとりの女の子がいた。
首都、アルバシティでタフに生き抜く彼女は、働きながらミュージシャンを目指してい
た。いつも、何かが足りないと感じていた。
彼女の名はキャロル。
ひとりの女の子がいた。
地方都市、ハーシェルシティの裕福な家に生まれ、ミュージシャンになりたいと思ってい
たが、誰にも理解されずにいた。世界でいちばん孤独だと思っていた。
彼女の名はチューズデイ。
ふたりは、偶然出会った。
歌わずにいられなかった。
音を出さずにいられなかった。
ふたりなら、それができる気がした。
ふたりは、こんな時代にほんのささやかな波風を立てるだろう。
そしてそれは、いつしか大きな波へと変わっていく───
■メインスタッフ
原作:BONES・渡辺信一郎
総監督:渡辺信一郎
監督:堀 元宣
キャラクター原案:窪之内英策
キャラクターデザイン:斎藤恒徳
メインアニメーター:伊藤嘉之、紺野直幸
世界観デザイン:ロマン・トマ、ブリュネ・スタニスラス
美術監督:河野羚
色彩設計:垣田由紀子
撮影監督:池上真崇
3DCGディレクター:三宅拓馬
編集:坂本久美子
音楽:Mocky
音響効果:倉橋静男
MIXエンジニア:薮原正史
音楽制作:フライングドッグ
アニメーション制作:ボンズ
公式HP: https://caroleandtuesday.com/
Twtter: @carole_tuesday
Instgram: @caroleandtuesday
Facebook: https://www.facebook.com/caroleandtuesdayofficial/
©ボンズ・渡辺信一郎/キャロル&チューズデイ製作委員会
《主題歌情報》
オープニングテーマ「Kiss Me」
作詞・作曲・編曲:Nulbarich
歌:キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX & Celeina Ann)
エンディングテーマ「Hold Me Now」
作詞・作曲・編曲:Benny Sings
歌:キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX & Celeina Ann)
■メインキャスト
キャロル:島袋美由利
チューズデイ:市ノ瀬加那
ガス:大塚明夫
ロディ:入野自由
アンジェラ:上坂すみれ
タオ:神谷浩史
アーティガン:宮野真守
ダリア:堀内賢雄
ヴァレリー:宮寺智子
スペンサー:櫻井孝宏
クリスタル:坂本真綾
スキップ:安元洋貴
■シンガーボイス
Nai Br.XX(キャロル)
Celeina Ann(チューズデイ)
Alisa(アンジェラ)
■本作参加コンポーザー
Mocky / Nulbarich / Benny Sings / Lido / JEN WOOD / 津野米咲(赤い公園) / Evan "Kidd" Bogart / Tim Rice-Oxley (Keane) / Eirik Glambek Bøe (Kings of Convenience) / Flying Lotus / Thundercat / G.RINA / Maika Loubté / ☆Taku Takahashi (m-flo)
・・・and more
《タイアップ》
ノード、ギブソンとのタイアップ決定!!
世界のトッププレイヤーたちが愛用するシンセサイザー/キーボードの“Nord”ブランドと世界的老舗ギターメーカー“ギブソン” (Hummingbird)とのコラボレーションが決定!
キャロルのキーボード、チューズデイのギターにはそれぞれNord、ギブソンのロゴが入り、
リアルな音楽作品としてよりいっそう本タイトルを盛り上げます。
協力:株式会社ヤマハミュージックジャパン(日本国内におけるNordブランド製品の輸入・販売元)
《放送情報》
2019年4月10日よりフジテレビ「+Ultra」にて毎週水曜日24:55から放送開始(初回は25:05~)
NETFLIXにて4月10日配信開始。2話~毎週木曜日配信(日本先行)
ほか各局にて放送 (関西テレビ/東海テレビ/テレビ西日本/北海道文化放送/BSフジ)
・テレビ西日本 4月10日(水)25:55~26:25
・東海テレビ 4月13日(土)25:55~26:25
・北海道文化放送 4月14日(日)25:15~25:45
・関西テレビ 4月16日(火)25:55~26:25
・BSフジ 4月17日(水)24:00~24:30