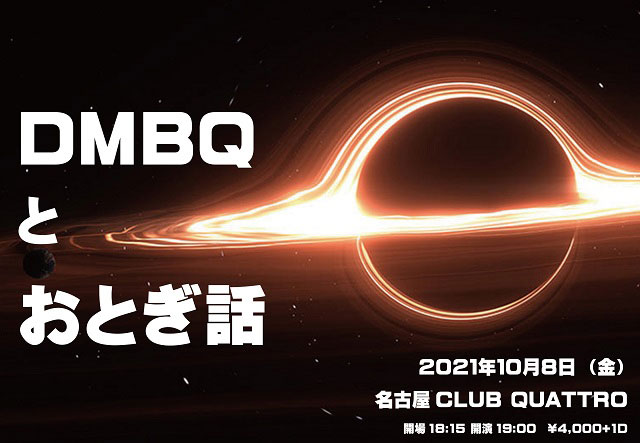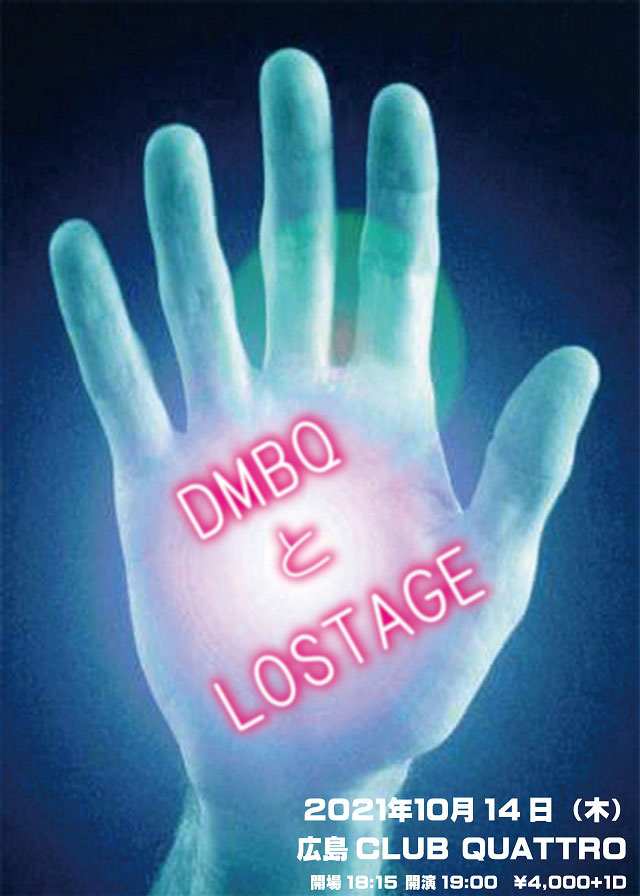ロンドンで活動する注目の若手ジャズ・ミュージシャン/作曲家のナラ・シネフロが、なんと、まさかの〈Warp〉からデビュー・アルバムをリリースする。
同作には、サンズ・オブ・ケメットのドラマー、エディ・ヒックをはじめ、マイシャのジェイク・ロング、ヌバイア・ガルシア、シャーリー・テテーといった今日のUKジャズ・シーンを支える強力な面々が参加。現在、収録曲 “Space 3” が先行公開されている。フィジカル盤はLPのみのようなので、なくなる前にチェックしておきたい。
NALA SINEPHRO
UKジャズ・シーン期待の新鋭、ナラ・シネフロが〈WARP〉と契約!
レア化必至のデビュー・アルバム『Space 1.8』を9月3日にリリース!
カリブ系ベルギー人の作曲家でミュージシャンのナラ・シネフロが〈Warp〉と契約を果たし、デビュー・アルバム『Space 1.8』を9月3日にリリースすることを発表! 合わせてアルバムからリード曲 “Space 3” を解禁した。
Nala Sinephro - Space 3
https://nalasinephro.ffm.to/space-3
“Space 3” は、サンズ・オブ・ケメットのドラマー、エディ・ヒックと、スチーム・ダウンのメンバーで、ウォンキー・ロジックとしても活躍するプロデューサー/マルチインストゥルメンタリストのドウェイン・キルヴィングトンとの3時間に及ぶ即興セッションの一部を切り取ったもので、シンセサイザーの粒子が飛び散るような歓喜に満ちたサウンドとなっている。
瞑想的なサウンド、ジャズの感性、フォーク音楽やフィールドレコーディングを融合させ、独特の世界観を築き上げたナラ・シネフロ。デビュー・アルバム『Space 1.8』は、シネフロが22歳のときに作曲、制作、演奏、エンジニアリング、録音、ミキシングを行い完成させている。本作ではモジュラーシンセやペダルハープを演奏し、友人のジェイムス・モリソン、シャーリー・テテー、ヌバイア・ガルシア、エディ・ヒック、ドウェイン・キルヴィングトン、ジェイク・ロング、ライル・バートン、ルディ・クレスウィックらが参加している。
ロンドンでの精力的なライブ活動を経て、UKジャズ・シーンにその名を轟かせてきたナラ・シネフロは、ガーディアン紙が選ぶ「2020年に注目すべきアーティスト」の一人に選ばれ、ジャイルス・ピーターソンからも熱烈な支持を受けている。
ナラ・シネフロのデビュー・アルバム『Space 1.8』は9月3日に数量限定のLPとストリーミング/デジタル配信で世界同時リリース。NTSのレジデントDJとしても人気を集めている彼女が、革新的レーベル〈Warp〉に加わり、ここからさらなる飛躍に期待が集まっている。

label: WARP RECORDS
artist: NALA SINEPHRO
title: Space 1.8
release date: 2021.09.03 fri
WARPLP324 / 輸入盤1LP
商品情報はこちら:
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=12050
Tracklisting
A1. Space 1
A2. Space 2
A3. Space 3
A4. Space 4
A5. Space 5
B1. Space 6
B2. Space 7
B3. Space 8